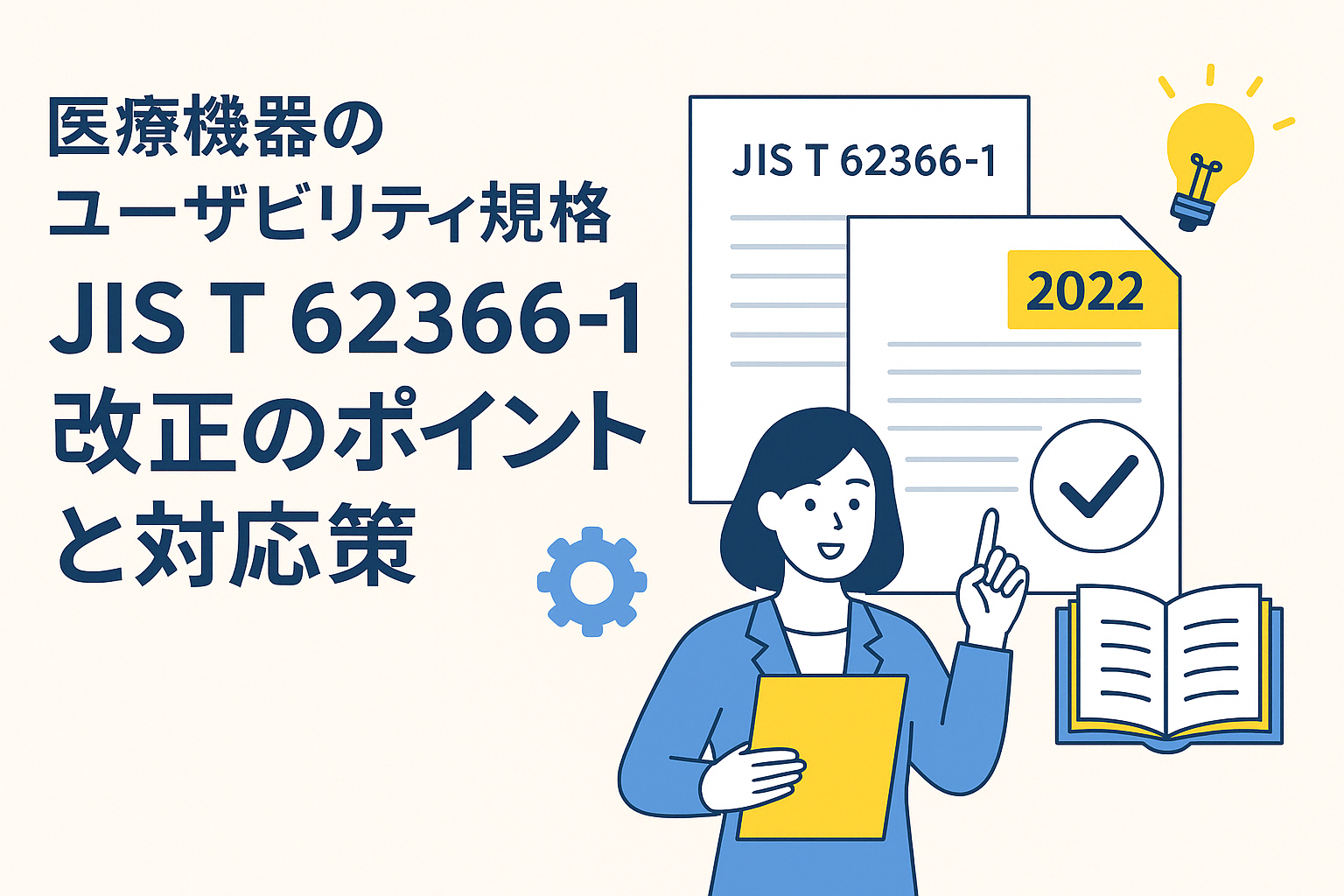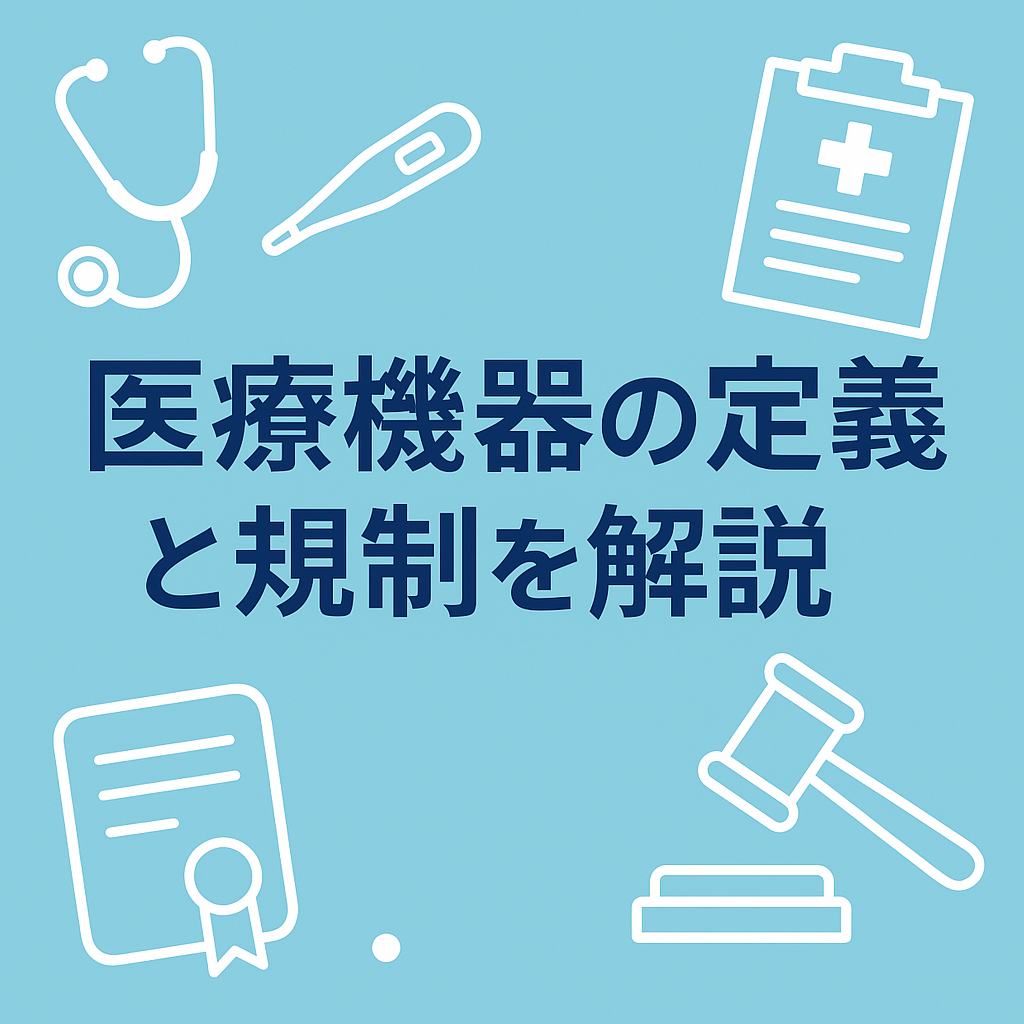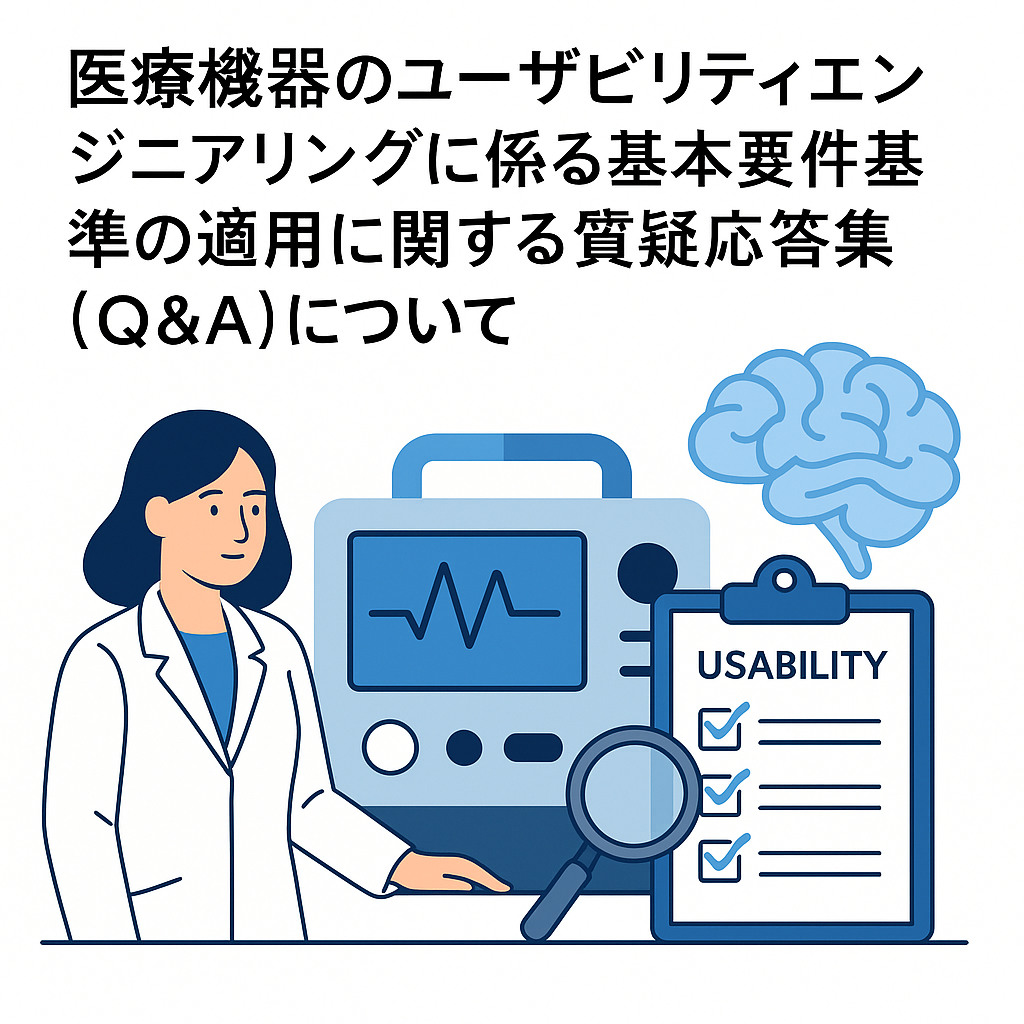概要
令和4年9月30日付けで厚生労働省より「医療機器のユーザビリティエンジニアリングに係る要求事項に関する日本産業規格の改正の取扱いについて」という通知が発出されました。この通知は、医療機器のユーザビリティエンジニアリングに関する日本産業規格「JIS T 62366-1:2019」から「JIS T 62366-1:2022」への改正に伴う取扱いを示すものです。本改正では、引用規格である「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」(JIS T 14971)においてユーザビリティ等の分野への適用を明確化した改正が行われたことを受けて更新されています。これにより、医薬品医療機器等法における医療機器の取扱いが定められ、令和4年10月1日より適用開始となります。
1. 改正の背景と目的
1.1 ユーザビリティエンジニアリングの重要性
医療機器のユーザビリティエンジニアリングは、医療機器の安全性と有効性を確保するための重要な要素です。医療機器の使用に関連するエラーを減少させ、使用者が適切に機器を操作できるようにすることで、患者の安全性を向上させる役割を担っています。近年、医療機器の複雑化に伴い、ユーザビリティの問題に起因する医療事故も報告されており、その重要性はますます高まっています。
1.2 規格改正の経緯
「医療機器のユーザビリティエンジニアリングに係る『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準』(平成17年厚生労働省告示第122号、以下「基本要件基準」という。)」の適用については、令和元年10月1日付け薬生機審発1001第1号・薬生監麻発1001第5号(以下「令和元年課長通知」という。)により、JIS T 62366-1:2019の取扱いが示されていました。
今般、JIS T 62366-1の引用規格である「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」(JIS T 14971)において、ユーザビリティ等の分野への適用を明確化した改正が行われたことを受け、JIS T 62366-1:2022(以下「改正後のJIS」という。)へ改正されました。これに伴い、医薬品医療機器等法における取扱いが改めて定められました。
2. 基本要件基準への適合性確認に関する要件
2.1 製造販売業者等の対応期限
製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「製造販売業者等」という。)は、令和6年3月31日(以下「経過措置期間終了日」という。)の翌日以降に製造販売される医療機器に対して、改正後のJISへの適合をもって基本要件基準第9条、第16条等で規定するユーザビリティに係る事項への適合の確認を行う体制を整備する必要があります。
なお、経過措置期間終了日までに改正後のJISに適合するよう手順書改訂など、必要な措置を講ずることが求められています。
2.2 国際的に用いられている規格の取扱い
改正後のJIS以外に、国際的に用いられている適切な規格等がある場合には、それらの規格等への適合性を確認することをもって基本要件基準第9条、第16条等への適合を確認したものとして差し支えないとされています。ただし、新規の承認申請又は認証申請(承認事項一部変更承認申請及び認証事項一部変更認証申請を含む。以下「承認申請等」という。)に際しては、それらの規格等を用いることの妥当性を説明する必要があります。
2.3 経過措置期間終了後の承認申請等における対応
経過措置期間終了日の翌日以降に、高度管理医療機器又は管理医療機器の承認申請又は認証申請を行う製造販売業者等は、当該医療機器について上記2.1で整備した体制で適合性を確認することが求められています。また、承認申請等の添付資料において改正後のJISへの適合性を説明する必要があります。
2.4 製造販売届の取扱い
経過措置期間終了日の翌日以降に製造販売届出を提出する場合についても、上記2.1で整備した体制で適合性を確認することが必要です。
3. 品質管理システムにおける対応
3.1 QMS省令に基づく対応
製造販売業者等は、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)第26条で規定する製品実現及び第30条から第36条で規定する設計開発等において、改正後のJISに基づく活動を行い、その適合に関する確認等を適切に記録し保管することが求められています。
3.2 調査対応
法第23条の2の5第7項又は第23条の2の23第4項の規定による調査の調査権者の求めなどに応じて資料を提示し、適切な説明を行わなければならないとされています。
4. 実務上の影響と対応策
4.1 製造販売業者等が取るべき具体的なアクション
- 体制整備: 令和6年3月31日までに改正後のJISに適合するための体制を整備する。
- 手順書改訂: 必要に応じて社内手順書を改訂し、ユーザビリティエンジニアリングのプロセスを更新する。
- 教育訓練: 設計開発担当者や品質保証担当者などの関係者に対して、改正内容に関する教育訓練を実施する。
- 文書体系の見直し: 既存の技術文書や設計開発文書を見直し、改正後のJISに適合していることを確認する。
- 記録保管: ユーザビリティエンジニアリングに関する活動とその適合性確認の記録を適切に保管する。
4.2 経過措置期間中の注意点
経過措置期間中(令和4年10月1日から令和6年3月31日まで)は、旧JIS(JIS T 62366-1:2019)と改正後のJIS(JIS T 62366-1:2022)のいずれを適用しても差し支えないとされていますが、経過措置期間終了後は改正後のJISに適合していることが求められます。そのため、新規開発製品や変更計画中の製品については、早期に改正後のJISへの適合を検討することが望ましいでしょう。
4.3 国際的な規格との整合性
医療機器は国際的な流通が多いため、JISだけでなく、国際規格(ISO/IEC)との整合性も考慮する必要があります。JIS T 62366-1:2022は国際規格IEC 62366-1:2020を基に作成されていますが、自社製品が複数の市場で販売されている場合は、関連する国際規格との整合性も確認することが重要です。
5. まとめ
JIS T 62366-1の改正(2019年版から2022年版への移行)は、医療機器のユーザビリティエンジニアリングに対する要求事項をより明確にし、使用エラーの低減と患者安全の向上を目的としています。令和6年3月31日の経過措置期間終了までに、製造販売業者等は改正後のJISに対応した体制の構築や手順の見直し、記録管理の整備などを進める必要があります。
今回の改正にあたり、「どこから手をつければ良いのか分からない」「既存のプロセスがJIS T 62366-1:2022に適合しているか不安」といったお声も多く聞かれます。当社では、規格対応に関するご相談から実務レベルでのサポートまで、ニーズに応じた柔軟な支援をご提供しています。
ユーザビリティエンジニアリングの対応に少しでも不安や疑問がある方は、ぜひ一度、当社までお気軽にご相談ください。