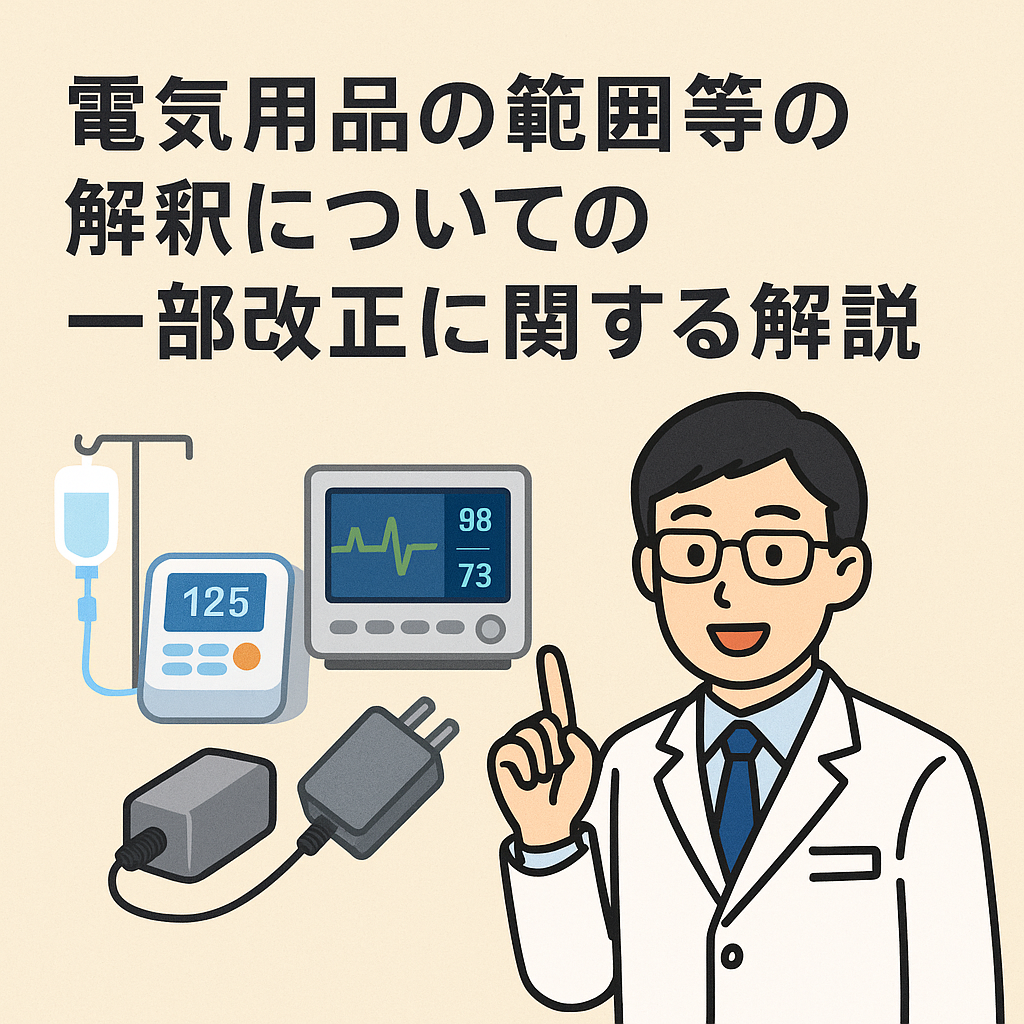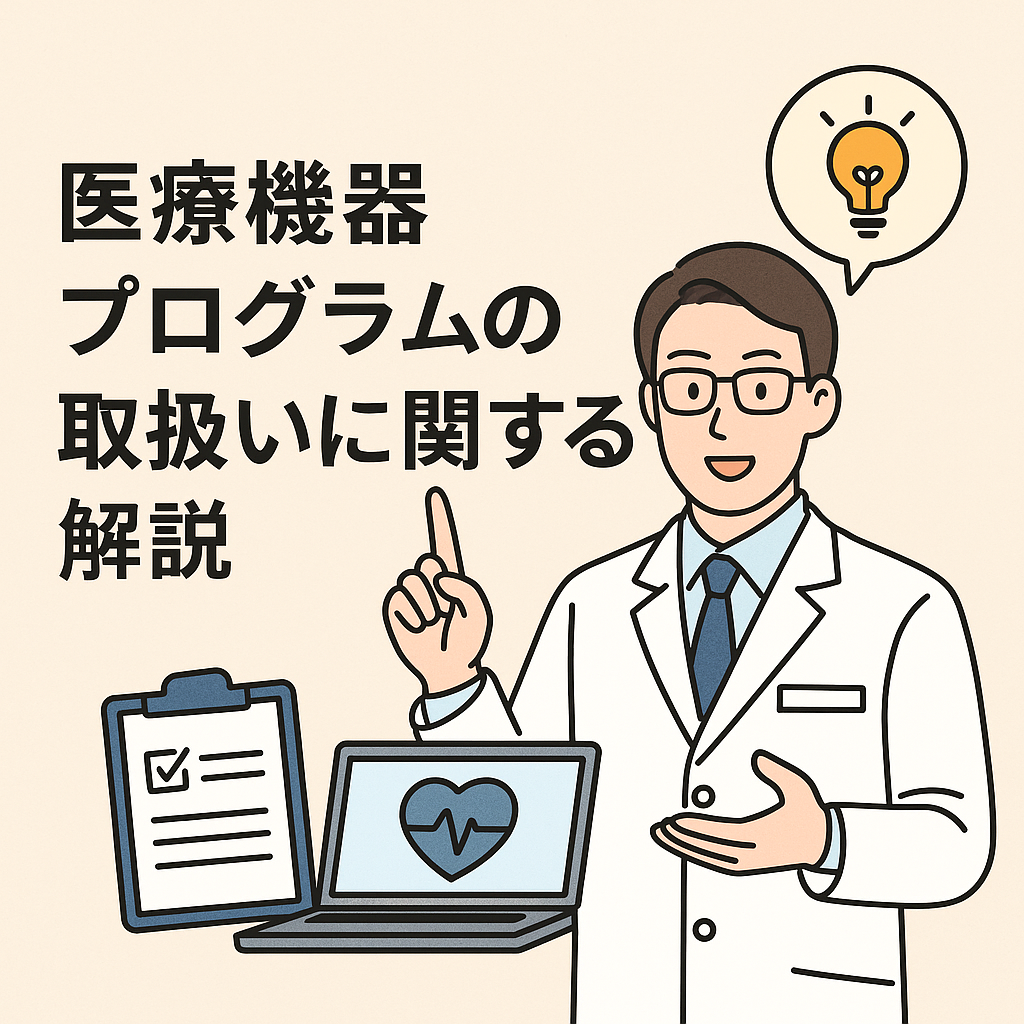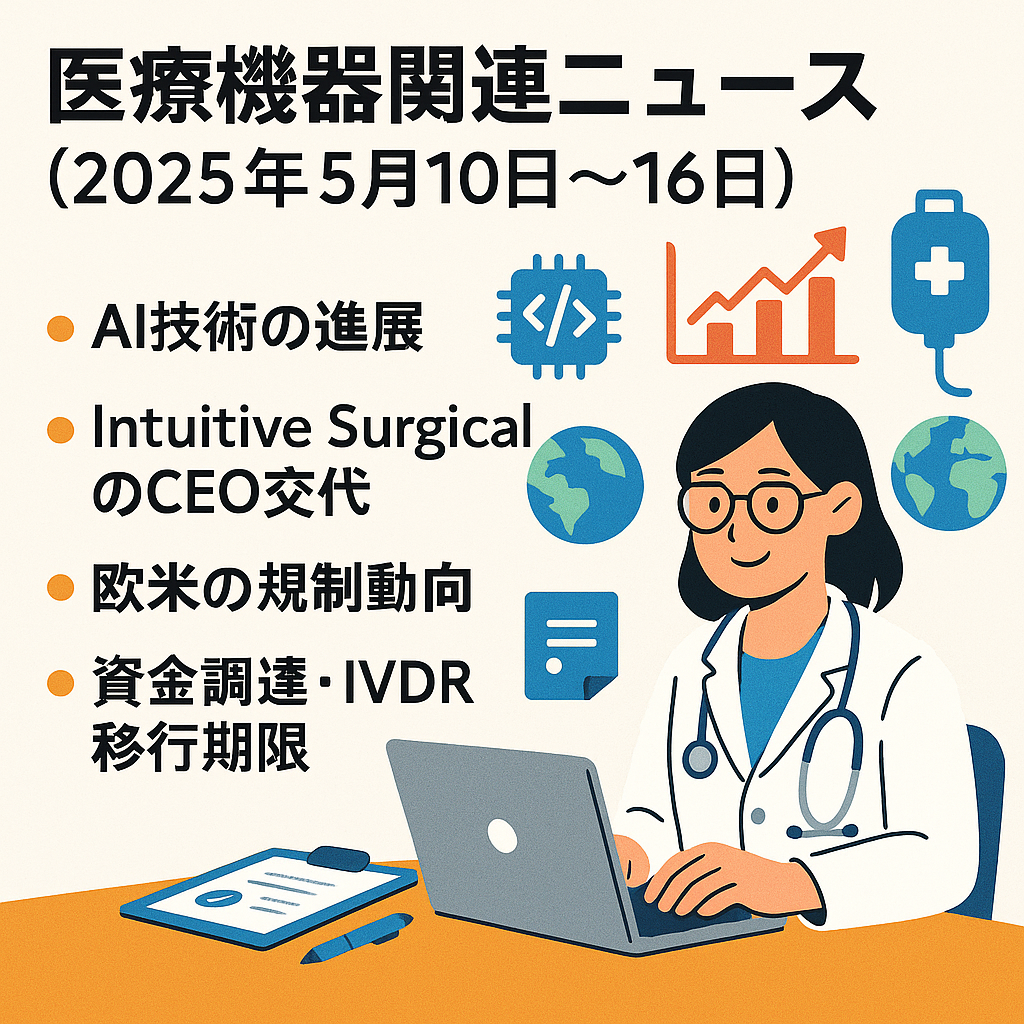概要
平成27年1月、経済産業省商務流通保安グループ製品安全課は「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正を行いました。この改正は、医用電気機器の部品である直流電源装置に関する規制の合理化を目的としています。従来、医用電気機器として一体で用いるために設計・製作された直流電源装置は、電気用品安全法と医薬品医療機器等法(旧薬事法)の両方の規制を受けていました。本改正により、高度管理医療機器または管理医療機器として一体で用いるために設計・製作される直流電源装置については、電気用品安全法の規制対象から除外されることになりました。この措置は規制改革の一環として実施され、医療機器メーカーの負担軽減と医療機器開発の促進に寄与するものです。
1. 規制の現状と背景
1.1 電気用品安全法による規制
直流電源装置は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)により特定電気用品として指定されています。この法律は電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的としており、直流電源装置の製造業者や輸入業者には以下の義務が課せられています。
- 製造または輸入の事業の届出
- 製品の技術基準適合及び検査
- 登録検査機関が行う適合性検査の受験
- PSEマーク表示
これらの規制により、市場に流通する直流電源装置の安全性が確保されてきました。
1.2 医薬品医療機器等法による規制
一方、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号、旧薬事法)は、医用電気機器に対して独自の規制体系を持っています。具体的には以下のような規制が行われています。
- 製造販売の許可
- 製造業の許可
- 高度管理医療機器等の厚生労働大臣による承認
- 管理医療機器の登録認証機関による認証
- 一般医療機器の厚生労働大臣への届出
- 性状・品質・性能の適正を図るための基準に適合しないものの販売、製造等の禁止
これらの規制は医療機器の品質、有効性および安全性を確保するために設けられています。
1.3 医用電気機器の技術的進化
電気電子技術の進歩に伴い、医用電気機器は高性能・高機能化と同時に小型軽量化が進んでいます。その過程で、比較的容量と重量がかさむ電源部を独立させ、直流電源装置を用いる医用電気機器が増加しています。医用電気機器として一体で用いるために設計・製作された直流電源装置については、当該医用電気機器の一部として医薬品医療機器等法の規制を受けています。
しかしながら、このような直流電源装置は電気用品安全法と医薬品医療機器等法の両方の規制を受けることになり、メーカーにとって二重の負担となっていました。
2. 規制改革の経緯
2.1 規制改革会議の設置と検討
平成25年1月に設置された規制改革会議において、医用電気機器の部品(ACアダプタ等)に対する薬事法と電気用品安全法による重複した安全確認が検討テーマとして取り上げられました。この背景には、医療機器メーカーからの規制の合理化を求める声があったと考えられます。
2.2 規制改革実施計画の閣議決定
平成25年6月5日の規制改革会議の答申を受けて、同年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画には、次のような内容が記載されました。
「電気的に作動する医療機器に使用される部品(ACアダプタ等)について、薬事法に基づく承認や認証において求める電気的な安全基準及びその適合性認証の手続きに関して、電気用品安全法が求めるものと同等以上の水準が確保できた場合は、電気用品安全法に基づく検査を省略する等の簡素化を検討する。」
この計画に基づき、経済産業省と厚生労働省が協力して具体的な措置を検討することになりました。
3. 安全性確保の仕組みの比較
3.1 医薬品医療機器等法における電気的安全性の確保
医薬品医療機器等法では、高度管理医療機器等の承認や管理医療機器の認証において、電気的安全性についてJIS T 0601-1(医用電気機器―第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項)等の規格への適合性を証明するよう求めています。
これらの規格は、それぞれの医用電気機器に対応する国際規格に日本独自の要求事項を加えたJIS規格であり、その技術的要件は非常に厳格なものとなっています。
3.2 電気用品安全法との関係
注目すべき点として、医薬品医療機器等法で適用される上記のJIS規格は、電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)に定める技術的用件を満たすものとして、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)」別表第12に掲げられている規格と同じものまたは同系列に属するものであることが挙げられます。
つまり、医薬品医療機器等法によって確保される安全性のレベルは、電気用品安全法によって確保されるレベルと同等以上であると考えられるのです。
3.3 規制体系の比較
また、医薬品医療機器等法における高度管理医療機器等の承認または管理医療機器の認証の手続きは、その比較的厳格な規制体系を鑑みれば、電気用品安全法の特定電気用品と同等以上の水準が確保されると判断されました。
具体的には、医薬品医療機器等法に基づく承認・認証プロセスでは、製品の設計から製造、販売後の監視に至るまでの包括的な品質管理システムが要求されており、電気用品安全法の要求事項を包含するものとなっています。
4. 改正の内容と意義
4.1 改正の具体的内容
これらの検討結果を踏まえ、経済産業省は「電気用品の範囲等の解釈について(平成24・03・21商局第1号)」の必要な改正を行いました。
改正の内容は、高度管理医療機器または管理医療機器として一体で用いるために設計・製作される直流電源装置を電気用品安全法の規制対象から除外するというものです。これにより、該当する直流電源装置については、医薬品医療機器等法の規制のみが適用されることになりました。
4.2 改正の意義
この改正には、以下のような意義があります。
- 規制の合理化:二重規制が解消されることで、医療機器メーカーの負担が軽減されます。
- 医療機器開発の促進:規制負担の軽減により、医療機器の開発・改良が促進されることが期待されます。
- 国際競争力の強化:日本の医療機器産業の国際競争力強化に寄与する可能性があります。
- 安全性の確保:医薬品医療機器等法による規制だけでも十分な安全性が確保されるため、消費者の安全は維持されます。
4.3 実務への影響
この改正により、医療機器メーカーは以下のような実務上のメリットを享受できるようになりました。
- 電気用品安全法に基づく届出や検査の省略
- PSEマーク表示の不要化
- 開発・製造プロセスの効率化
- コスト削減と開発期間の短縮
ただし、この除外規定が適用されるのは、あくまでも「高度管理医療機器または管理医療機器として一体で用いるために設計・製作される直流電源装置」に限定されています。一般用途の直流電源装置や、一般医療機器用の直流電源装置については、従来通り電気用品安全法の規制が適用されることに注意が必要です。
5. まとめ
経済産業省による「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正は、医療機器分野における規制の合理化を実現する重要な施策です。高度管理医療機器または管理医療機器として一体で用いる直流電源装置について、電気用品安全法の適用が除外されたことで、医療機器メーカーにとっては規制負担の軽減や製品開発の効率化が期待されます。
ただし、適用範囲や要件には明確な線引きがあり、誤った運用はリスクにもなり得ます。
弊社では、本改正の具体的な運用に関するご相談や、医薬品医療機器等法への対応支援を行っております。対象製品の規制該当性や手続き等に不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。