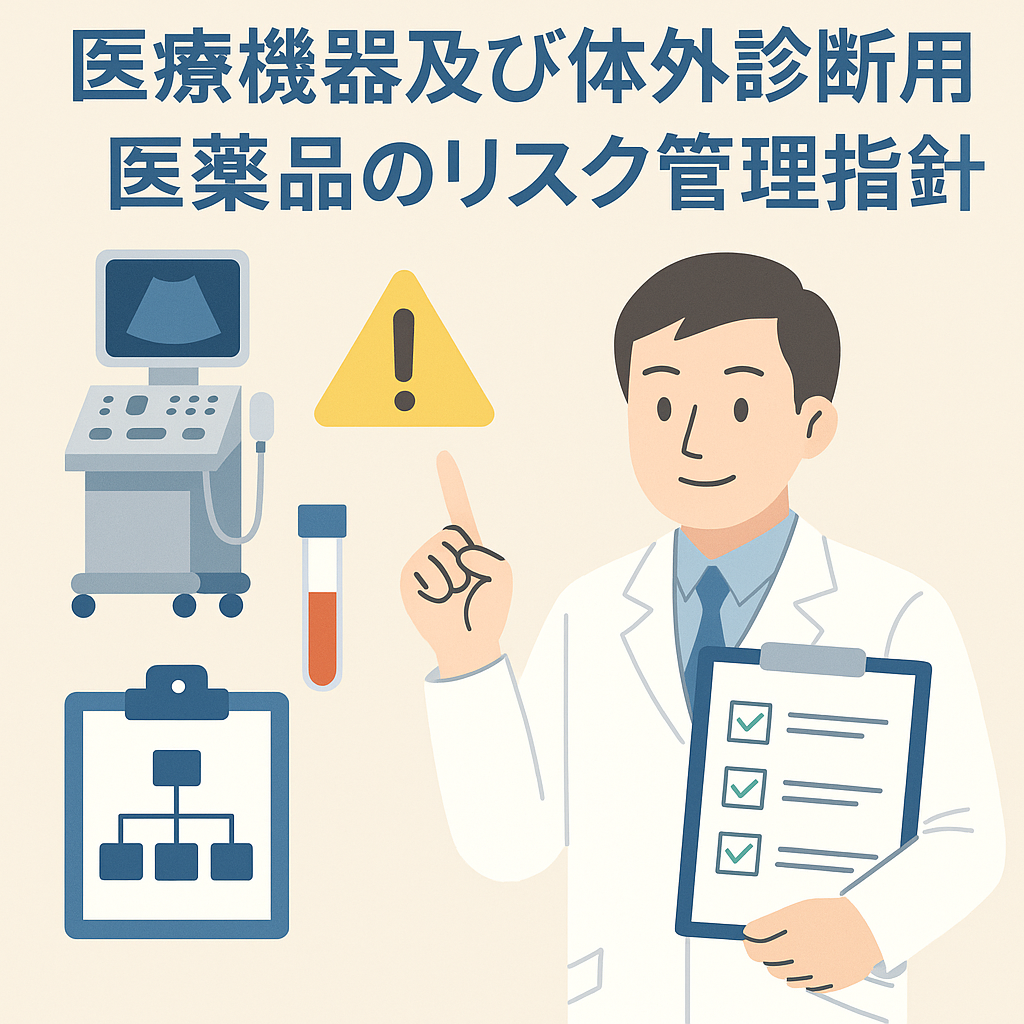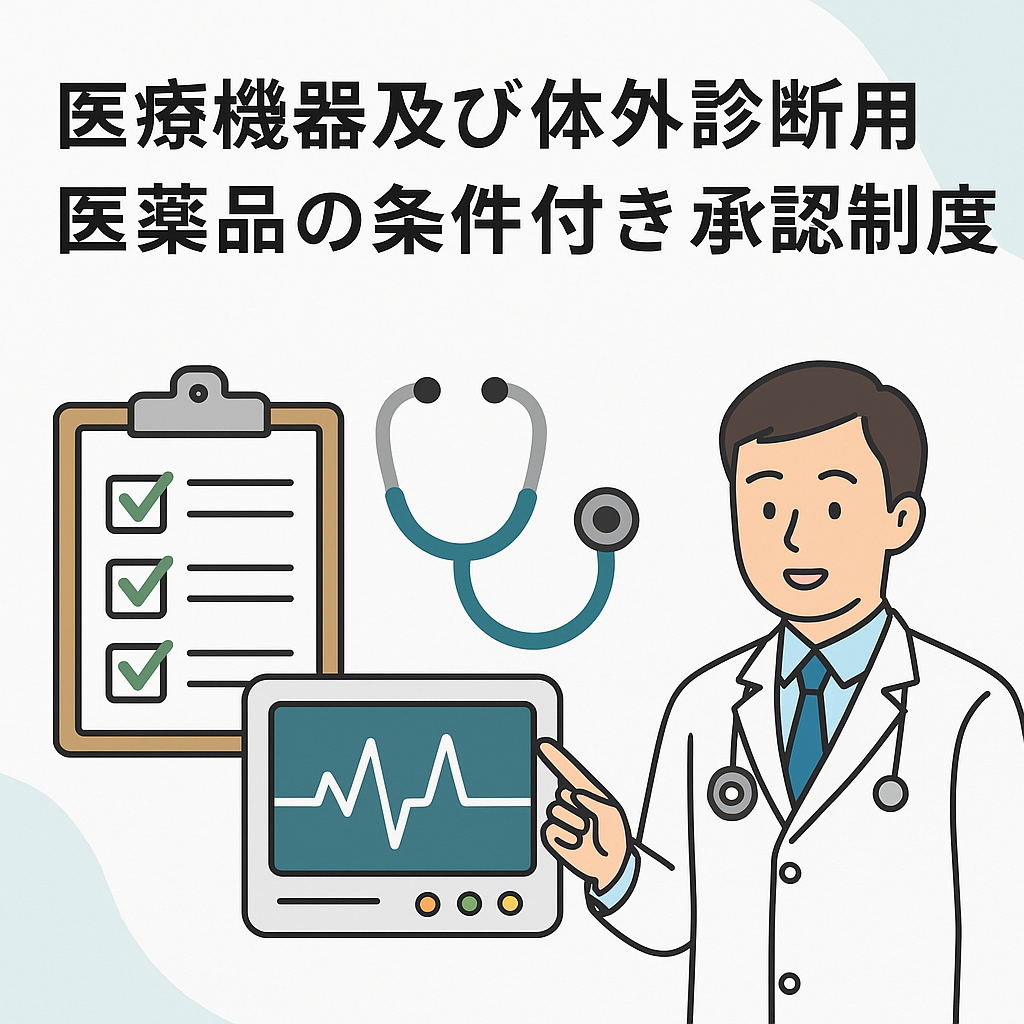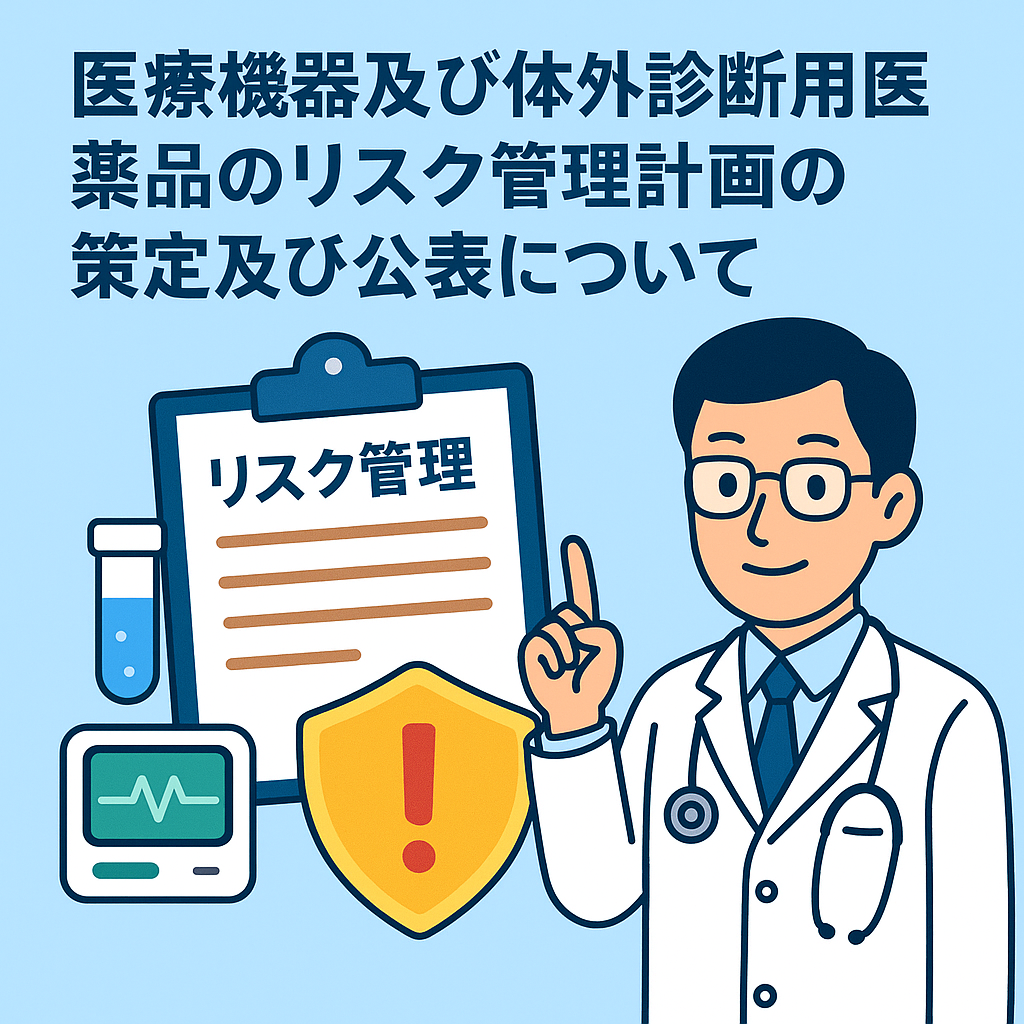概要
令和2年8月31日付けで厚生労働省より発出された本通知は、医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」)の製造販売後リスク管理計画を策定するための指針を示したものです。医薬品医療機器等法の改正により創設された「医療機器等条件付き承認制度」の施行に伴い、承認申請前の限られた臨床データでは明らかにならないリスクへの対応を慎重に行うため、市販後のリスク管理を開発段階から計画する必要性が生じました。
本指針はJIS T 14971に示されているリスクアセスメント及びリスクマネジメントの概念を踏まえ、医療機器等のリスク低減を図るための適正使用管理を含めた医療機器等リスク管理計画の策定について基本的な考え方を示しています。市販後に得られたデータは実施施設の拡大等の計画見直しだけでなく、今後の医療機器等の改善や将来の承認申請にも活用されることが期待されています。
1. 医療機器等リスク管理計画の基本的枠組み
1.1 医療機器等リスク管理計画の構成要素
医療機器等リスク管理計画は、製造販売業者又は製造販売承認申請者が医療機器等の適正使用を図り、ベネフィット・リスクバランスを適正に維持するために策定するものです。計画は以下の3つの主要な要素から構成されます。
第一に安全性検討事項の特定です。医療機器等のハザードを特定し、推定されたリスクのうち重要なものを「重要な特定されたリスク」「重要な潜在的リスク」「重要な不足情報」として整理します。
第二に医療機器等安全性監視計画の策定です。通常の安全性監視活動に加え、必要に応じて追加の監視活動を計画し実施します。
第三にリスク最小化計画の策定です。通常のリスク最小化活動(添付文書による情報提供等)に加え、必要に応じて追加のリスク最小化活動を実施します。
1.2 計画策定における留意事項
医療機器等リスク管理計画の策定にあたっては、推定使用患者数、使用方法、特定されているリスク集団、対象疾患の重篤性、不具合等がベネフィット・リスクバランスに及ぼす影響の大きさ等を考慮する必要があります。
承認審査の過程において計画の妥当性が検討されることから、審査報告書の記載内容との整合性を図って整備することが重要です。また、通常の医療機器等安全性監視活動として法第68条の10に基づく不具合等情報の収集・報告等、通常のリスク最小化活動としての添付文書等による情報提供は義務付けられていることに留意が必要です。
2. 安全性検討事項の特定と管理
2.1 重要な特定されたリスク
特定されたハザードから推定されたリスクのうち、臨床データでも十分に確認された重大な危害となるものを指します。具体的には、非臨床試験等において医療機器等との因果関係が十分に明らかにされており、臨床データにおいても確認されている重大な不具合等、製造販売後に多くの自発報告があり使用状況等から因果関係が示唆される不具合等が該当します。
2.2 重要な潜在的リスク
特定されたハザードから推定された重大なリスクのうち、臨床データからの確認が十分でないものです。非臨床データから安全性の懸念となりうる所見が示されているが臨床データ等では認められていない事象、類似の医療機器等で認められているが臨床データ等では認められていない事象、医療機器等の形状・構造及び原理等の特質から推定される重大なリスクが含まれます。
2.3 重要な不足情報
医療機器等リスク管理計画を策定した時点では十分な情報が得られておらず、製造販売後の安全性を予測する上で不足している重要な情報です。これまでの臨床での使用経験がほとんどないが使用が想定される患者集団での安全性の検討に必要となる情報等が該当します。
3. 医療機器等安全性監視計画
3.1 通常の医療機器等安全性監視活動
製造販売業者において実施している通常の医療機器等安全性監視活動及びその実施体制について要約します。これには法令に基づく不具合等情報の収集、報告等が含まれます。
3.2 追加の医療機器等安全性監視活動
安全性検討事項を踏まえて、追加の医療機器等安全性監視活動の必要性、その理由、手法等について検討します。製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した場合、使用状況により使用者の拡大を図る時期、医療機器等リスク管理計画で設定している節目となる時期、法令に基づく又は総合機構から指示されている定期的な報告の時期、医療機器等の使用成績評価申請を行う時期等に見直しが必要となります。
3.3 追加の医療機器等安全性監視活動の実施計画
各医療機器等安全性監視活動について、実施計画書の表題、安全性検討事項、実施計画(案)、目的、実施計画の根拠、結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の決定基準、評価又は総合機構への報告を行う節目となる予定の時期及びその根拠を含んだ概要を簡潔に記載します。
4. リスク最小化計画
4.1 通常のリスク最小化活動
医療機器等の形状・構造及び原理、使用目的又は効果、使用方法等の製造販売承認事項並びに使用上の注意を記載した添付文書を作成し、必要に応じて改訂し、その内容を医療関係者に対して情報提供することが通常のリスク最小化活動となります。
4.2 適正使用管理活動
追加のリスク最小化活動として、関連学会による適正使用基準の策定があります。医療機器等の特性や対象疾患の性質等に鑑み、適正使用による安全性の確保を目的として、関連学会と協力の上、適正使用基準を作成します。
適正使用基準には、実施医、実施施設等の要件を規定するほか、使用に当たって特に注意が必要な症例や合併症への対応方法、講習、トレーニング、プロクタリング等の実施計画、実施施設を拡大する場合の考え方等が含まれます。関連学会としては日本医学会又は日本歯科医学会の分科会が考えられ、当該品目の使用及び使用に当たって発生しうる合併症の治療に関連の深い学会が関与することを基本とします。
4.3 その他のリスク最小化活動
適用患者の慎重な選定、適用に際しての患者への説明の実施、特定の検査等の実施、表示・容器・包装等の工夫などが追加のリスク最小化活動として実施される場合があります。
患者の状態、既往歴、治療歴、併用医薬品等を含む状況を勘案した条件を設定し、特に注意を要する場合には患者の条件への適合性に係る事前確認の確保やモニタリングの実施、製造販売業者における使用患者の登録等を求めることがあります。
5. 医療機器等リスク管理計画の評価と報告
各医療機器等安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク最小化活動に関し、医療機器等リスク管理計画に基づく実施状況及び得られた結果についての評価を、その節目となる時期に適切に行います。
使用成績評価期間中の医療機器等については、法第23条の2の9第6項の規定又は法第23条の2の10第2項前段の規定による報告に係る医薬品医療機器等法施行規則第114条の43に規定する報告の際に、その評価内容を要約して報告します。この報告の際には医療機器等リスク管理計画を見直し、その検討結果を報告することとされています。
計画の変更を行う場合には必要に応じて事前に総合機構と相談を行います。報告の内容については総合機構において確認を行い、何らかの対策が必要と判断された場合には製造販売業者に対する指示が行われます。
まとめ
本指針は、医療機器および体外診断用医薬品の市販後リスク管理を体系的に実施するための基本枠組みを示しています。安全性検討事項の特定からリスク最小化計画まで、製造販売業者が自社製品のベネフィット・リスクバランスを適正に維持するための実務的指針として活用できます。
また、リスクマネジメントの国際規格であるJIS T 14971の考え方を踏まえた計画策定や学会との連携による適正使用基準の整備など、承認後も継続的に安全性を確保するための実践的な手法が求められています。これにより、条件付き承認制度における市販後データの活用や、製品改良へのフィードバックが可能となります。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、医療機器リスク管理計画書(RMP)の作成支援、PMDA協議対応、適正使用基準策定支援などを行っています。自社製品への具体的な適用や体制構築に関してご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。