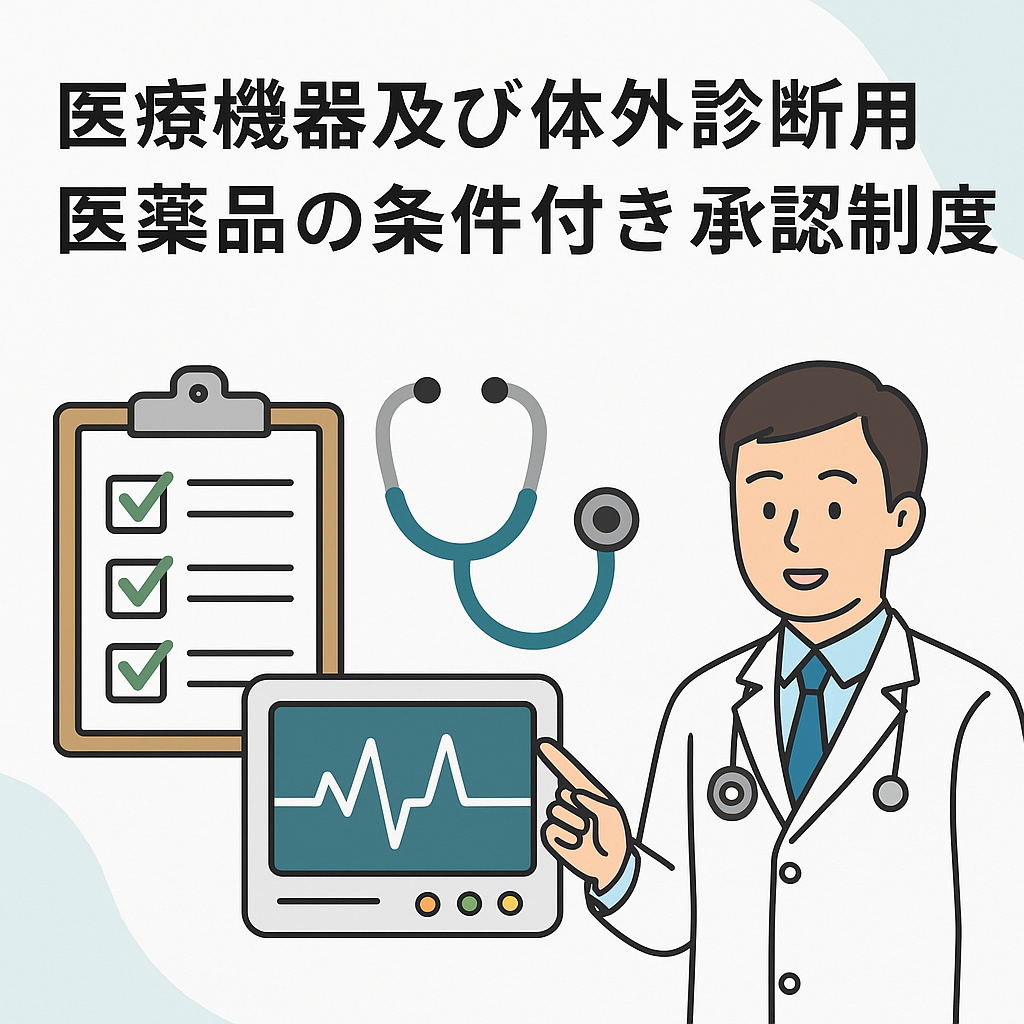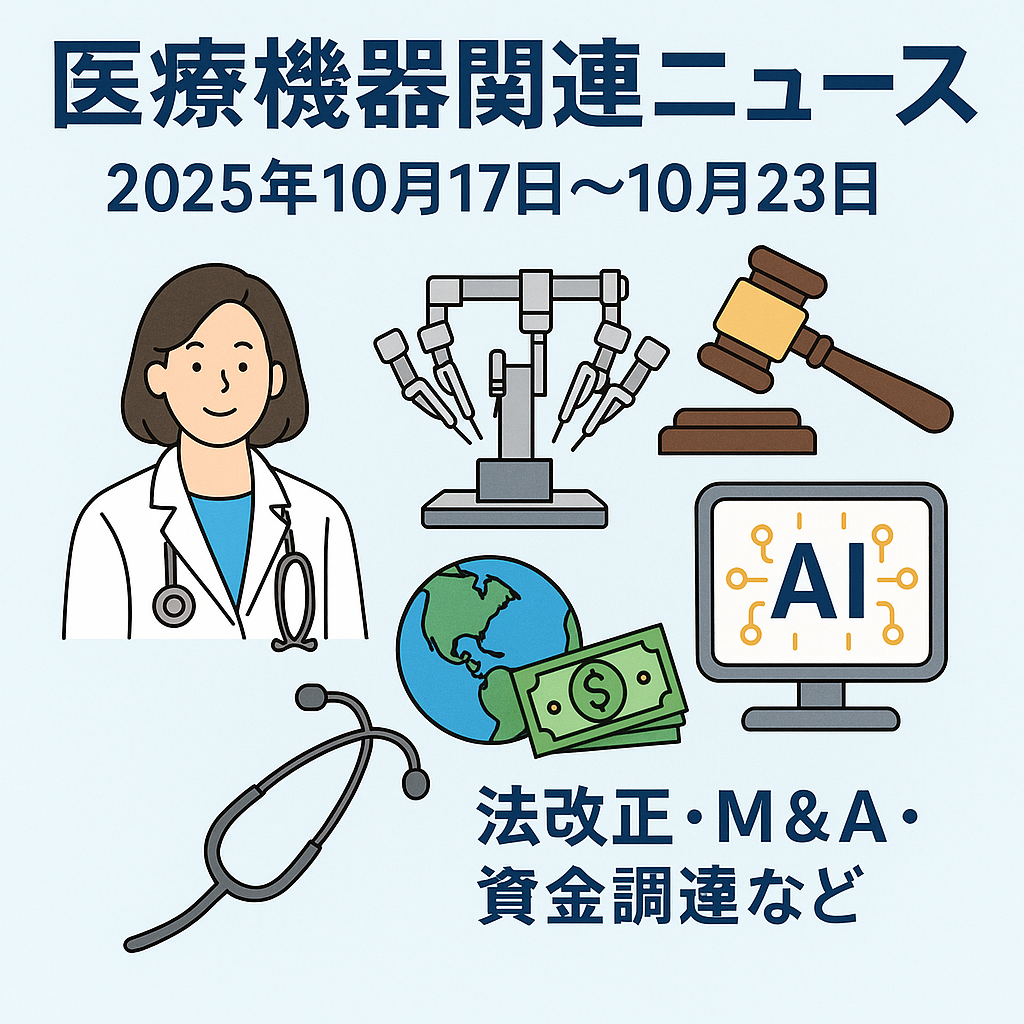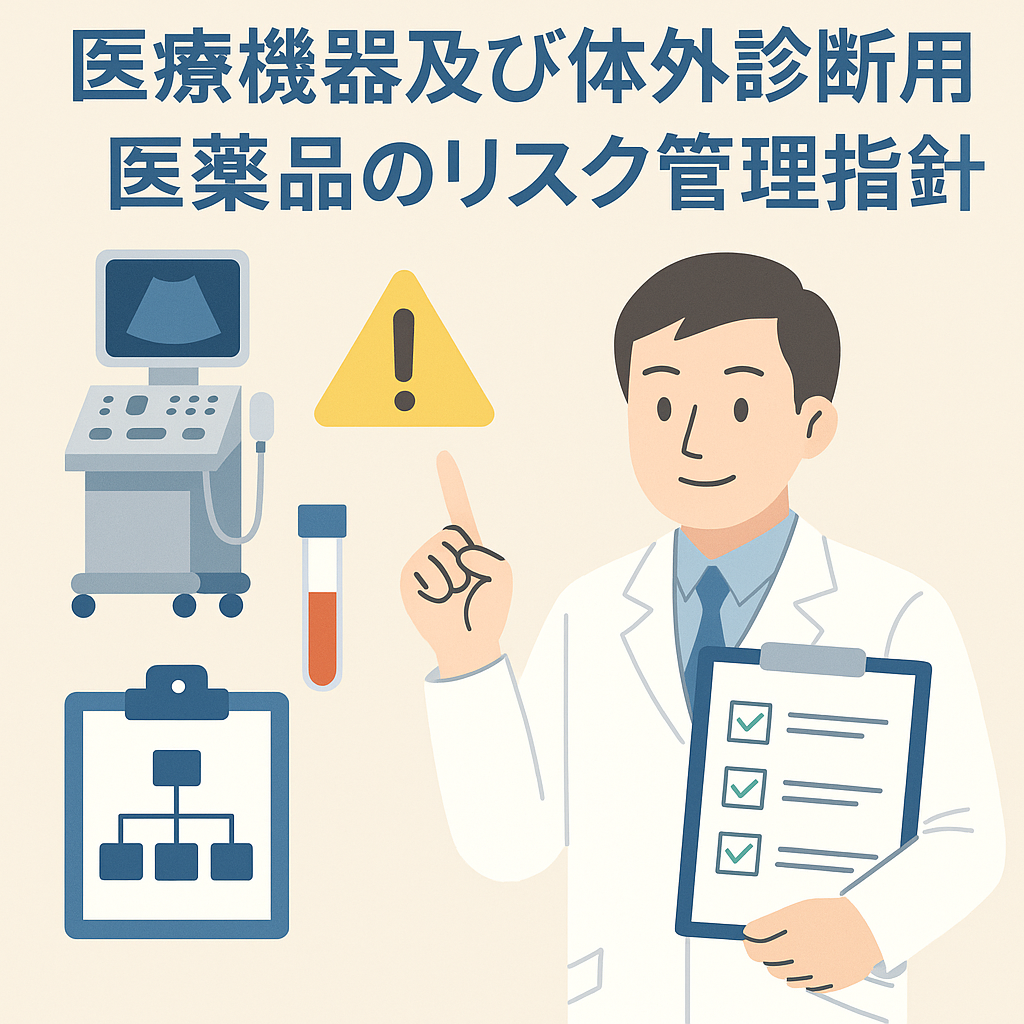概要
令和2年9月1日より、革新的な医療機器や体外診断用医薬品の早期実用化を促進するための新たな制度が施行されました。この制度は、生命に重大な影響を与える疾患を対象とする医療機器等について、限られた臨床データでも条件を付して承認を可能とするものです。
従来の「革新的医療機器条件付早期承認制度」が法令上明確化され、医薬品医療機器等法第23条の2の5第12項の規定に基づく制度として位置付けられました。患者数が少ない疾患や臨床開発に長期間を要する医療機器等において、市販後のリスク管理を厳重に行うことを前提に、早期の承認を可能とする仕組みです。
本制度により、医療現場で必要とされる革新的な医療機器等を、適切なリスク管理のもとで迅速に患者さんへ提供することが可能となります。申請者は関連学会と連携して適正使用基準を作成し、市販後のデータ収集計画を具体的に提示することが求められます。
1. 対象となる医療機器等の要件
1.1 類型1(革新的医療機器等)
類型1では、以下のすべての要件を満たす医療機器等が対象となります。
第一に、対象疾患が生命に重大な影響がある疾患、または病気の進行が不可逆的で日常生活に著しい影響を及ぼす疾患であることが必要です。重篤な疾患への対応が本制度の主要な目的となっています。
第二に、既存の治療法や診断法がないこと、または既存の方法と比較して著しく高い有効性や安全性が期待されることが要件となります。医療上のアンメットニーズに応える革新性が求められます。
第三に、一定の評価を行うための適切な臨床データを提示できることが必要です。探索的な治験データ、海外の臨床試験成績、先進医療や臨床研究のデータなども活用可能です。
第四に、新たな臨床試験の実施に相当の困難があることを合理的に説明できる必要があります。患者数の少なさや疾患の特性により、通常の臨床開発が困難な場合が想定されています。
第五に、関連学会と緊密な連携の下で適正使用基準を作成し、市販後のデータ収集及び評価の計画を具体的に提示できることが求められます。
1.2 類型2(適用拡大型)
類型2は、焼灼その他の物的な機能により人体の構造又は機能に影響を与える医療機器等が対象となります。医療上特にその必要性が高いと認められるものに限定されます。
既存の臨床データでは直接的に評価されていない適用範囲について、一定の外挿性をもって評価を行うための適切な臨床データの提示が必要です。物理的な作用機序に基づき、新たな臨床試験を実施せずとも適正使用を確保できることを合理的に説明することが求められます。
類型1と同様に、関連学会との連携による適正使用基準の作成と、市販後のデータ収集計画の具体的な提示が必要となります。
2. 申請手続きと審査の流れ
2.1 開発前相談による該当性の確認
本制度の適用を希望する申請者は、まず独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の開発前相談を申し込む必要があります。この相談において、申請予定の品目が本制度の対象となるかどうかについて、厚生労働省及びPMDAと意見交換を行います。
相談では、別紙様式の医療機器等条件付き承認制度該当性概要を提出し、要件への適合性について検討します。必要に応じて、「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」での評価も行われます。
希少疾病用医療機器等の指定を受けている品目や、先駆的医療機器等の指定を受けている品目については、開発前相談を経ずに本制度の対象となる場合もあります。
2.2 臨床試験要否相談の実施
本制度の対象となることが確認された品目については、承認申請前に医療機器臨床試験要否相談または体外診断用医薬品評価相談を受ける必要があります。
この相談では、入手可能な臨床データの評価、医療機器等リスク管理計画案の内容の適切性、適正使用基準案などについて、必要に応じて医学専門家を交えて検討します。既存の臨床データでリスクベネフィットバランスを適切に評価できるかどうか、製造販売後のリスク管理やデータ収集の内容について助言を受けます。
2.3 承認申請と審査
承認申請時には、臨床試験成績に関する資料の一部として医療機器等リスク管理計画の案を添付します。申請書の備考欄には、開発前相談や臨床試験要否相談の実施済みである旨と、相談日時及び受付番号を記載する必要があります。
審査では、医療機器等リスク管理計画案の妥当性を確認し、その適切な実施を前提として安全性や有効性の確認を行います。本制度の対象品目は原則として使用成績評価の対象となり、適正使用基準などの製造販売後のリスク管理が法第23条の2の5第12項に基づく承認条件として付されます。
3. 市販後の管理体制
3.1 医療機器等リスク管理計画の実施
承認後は、販売開始予定時期の1か月前までに医療機器等リスク管理計画書をPMDAに提出する必要があります。この計画に基づき、市販後の情報収集、医療関係者や患者への情報提供、その他必要な対策を実施します。
使用成績調査については、関連学会の症例登録(レジストリ)等を活用することも可能です。その場合、データの管理や利用に係る責任関係を明確にしておくことが重要です。
3.2 使用成績評価と定期報告
本制度で承認された品目は、原則として法第23条の2の9に規定する使用成績評価の対象となります。使用成績調査の期間中は、使用の成績に関する調査結果を1年ごとにPMDAへ報告する必要があります。
定期報告では、医療機器等を使用する医師等と最新の情報を共有することも考慮されます。収集されたデータは、リスク管理内容の見直しだけでなく、将来の改良や新たな承認申請にも活用することが期待されています。
3.3 適正使用基準の運用と更新
関連学会と連携して作成された適正使用基準は、実施医や実施施設の要件、特に注意が必要な症例、合併症への対応方法、講習やトレーニングの実施計画などを含みます。
市販後の不具合等の発生動向やデータの蓄積を踏まえて、適正使用基準を含む製造販売後のリスク管理計画の内容を変更する場合や、実施施設の拡大等を行う場合は、事前にPMDAへの相談が必要です。
4. 制度活用における留意事項
4.1 他の制度との関係
「適応外使用に係る医家向け医療機器の取扱について」に示される場合や、「希少疾病用医療機器等に関する臨床試験データの取扱いの明確化について」に示される場合には、本制度によらない承認申請が適切な場合があります。個別の事案については、厚生労働省医療機器審査管理課への相談が推奨されています。
4.2 既存制度からの移行
従前の「革新的医療機器条件付早期承認制度」に基づいて承認申請された品目については、引き続き従前の取扱いが適用されます。新制度は令和2年9月1日以降の申請から適用となります。
4.3 データ活用の重要性
本制度では、市販後に収集されるデータが極めて重要な役割を果たします。使用成績調査やレジストリ等によるデータは、リスク管理の見直しだけでなく、医療機器等の改善や将来の承認申請にも活用されることが期待されています。PMDAの相談を活用し、データ収集計画と活用方法を十分に検討することが推奨されています。
まとめ
本制度は、革新的な医療機器や体外診断用医薬品を早期に患者へ届けるための仕組みとして位置づけられています。限られた臨床データでも、厳格なリスク管理と市販後のデータ収集を条件に承認を可能とし、医療現場で求められる革新的技術の実用化を加速します。
特に、患者数が少ない疾患や臨床試験が困難な領域での開発支援を目的としており、適正使用基準の策定や関連学会との連携が重要な要素となります。承認後も継続的なデータ収集と評価を通じて、安全性と有効性を高めることが求められます。
弊社では、条件付き承認制度の適用判断、PMDA相談の準備支援、リスク管理計画書や適正使用基準の作成支援まで、一貫した薬事サポートを提供しています。制度活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。