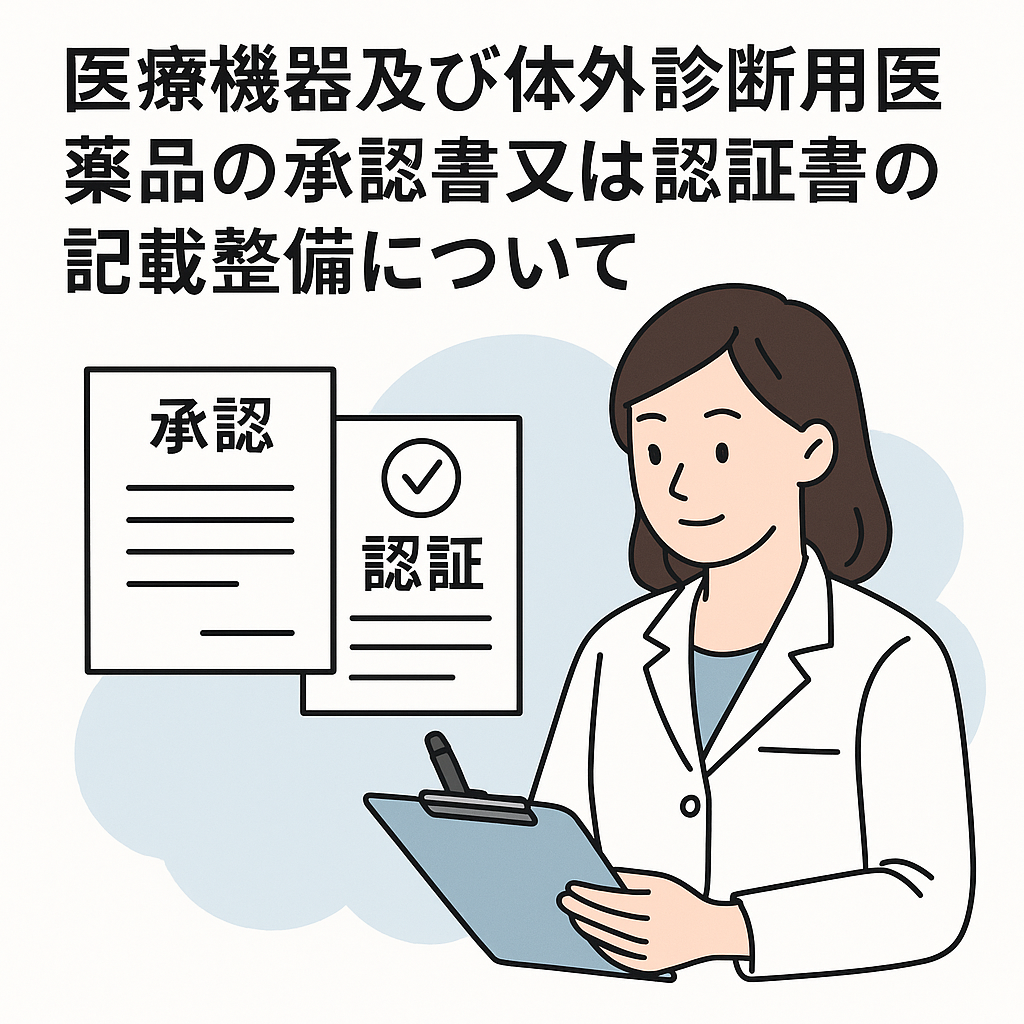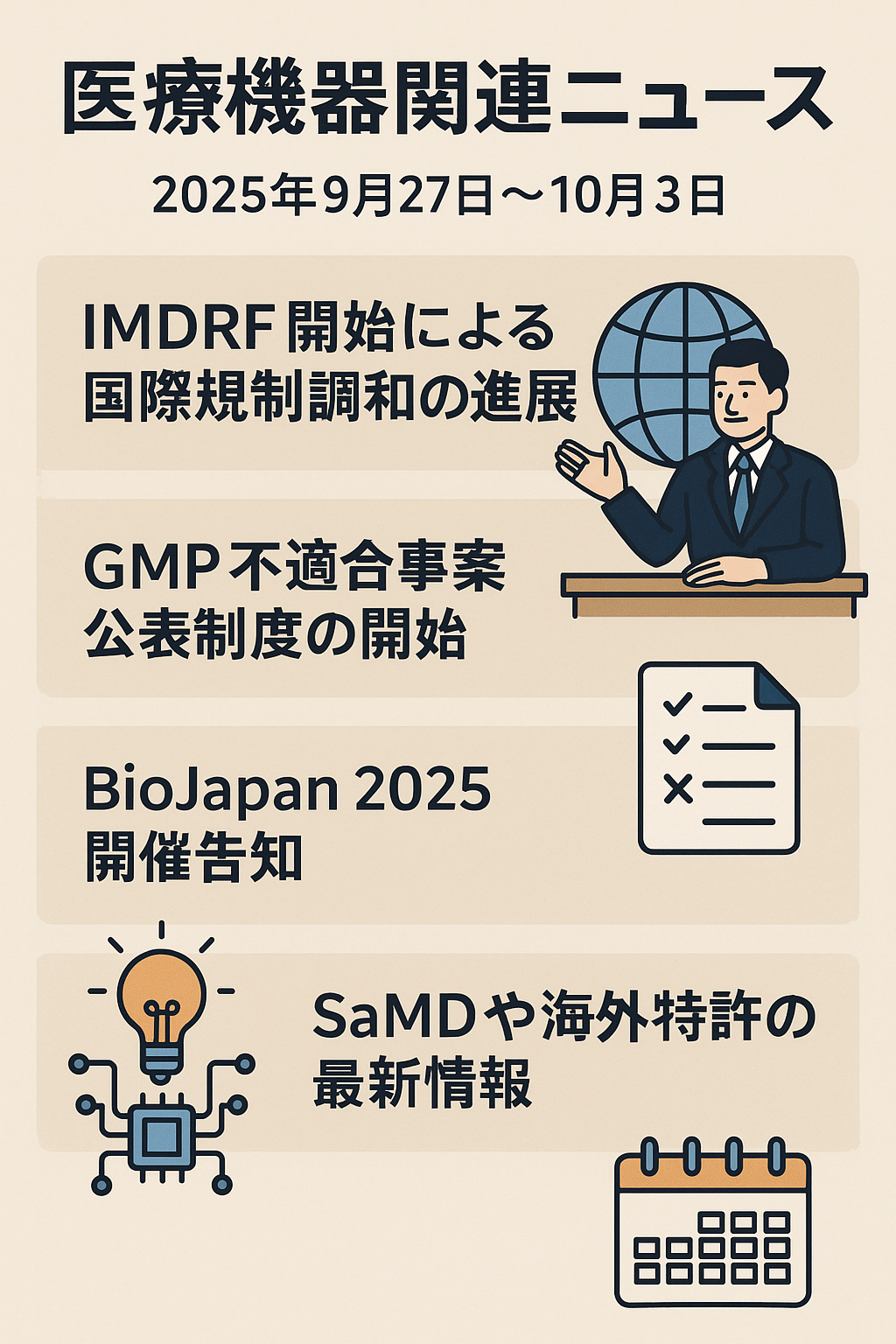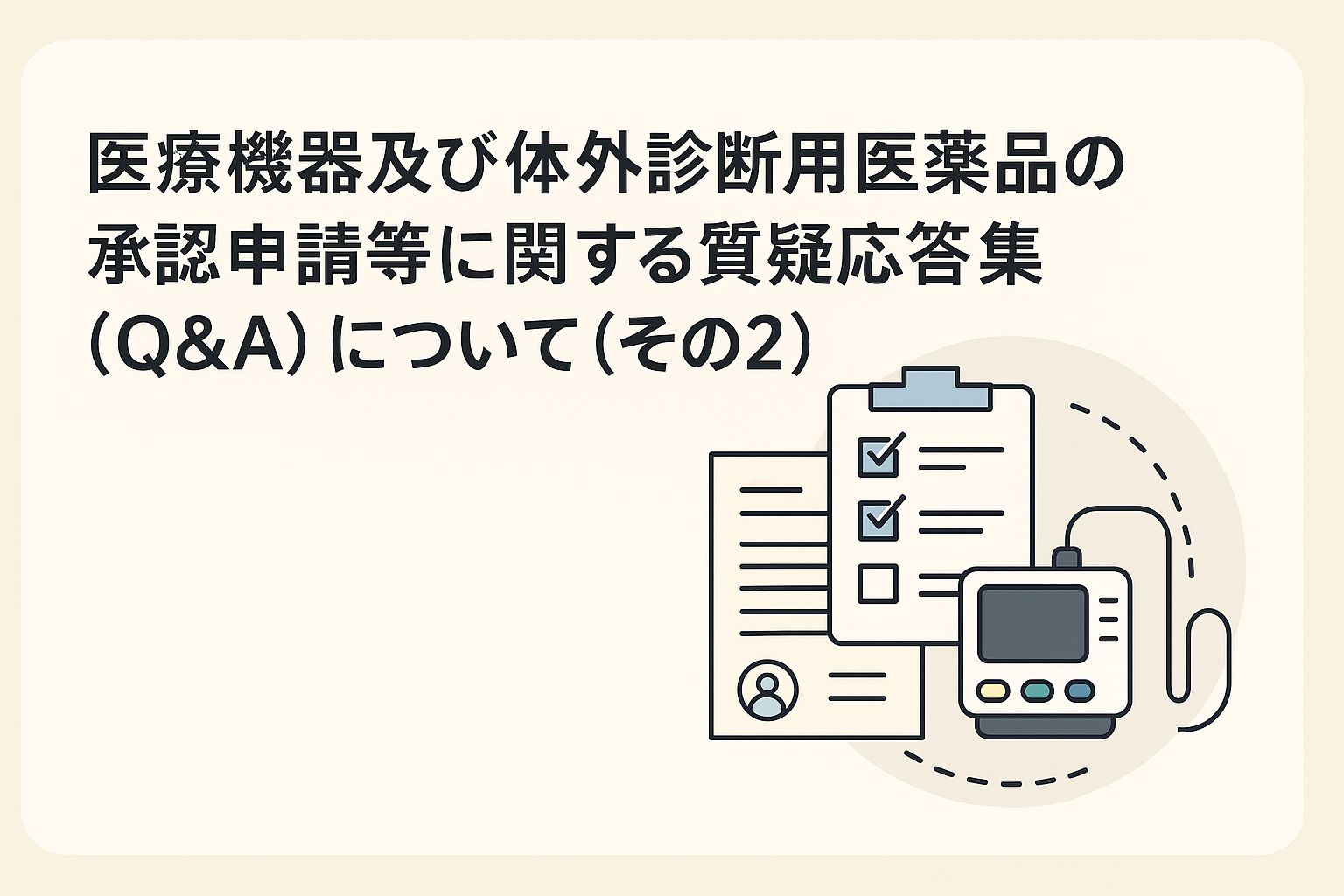概要
平成26年9月29日、厚生労働省から医療機器及び体外診断用医薬品の承認書又は認証書の記載整備に関する重要な通知が発出されました。これは、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、医療機器及び体外診断用医薬品の製造業が許可制から登録制へ移行することに伴うものです。
本通知は、すでに承認又は認証を取得している医療機器及び体外診断用医薬品について、新法である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に対応した承認書又は認証書の記載内容への整備方法を明確にしています。製造販売業者にとっては、保有する全品目の承認書又は認証書を適切に整備することが求められており、その具体的な手順と期限が示されています。
1. 記載整備が必要となる対象品目
1.1 対象となる品目の範囲
改正法施行前の承認申請又は認証申請に基づき承認又は認証を取得した医療機器及び体外診断用医薬品すべてが記載整備の対象となります。具体的には、旧薬事法施行規則の以下の様式により申請された品目が該当します。
医療機器については、様式22(3)、様式53(2)又は様式53(3)、様式64の(1)から(4)の申請書に基づくものです。体外診断用医薬品については、様式22(2)、様式53(2)又は様式53(3)、様式64の(1)から(4)の申請書に基づくものが対象となります。
1.2 記載整備が必要な項目
記載整備すべき事項は、主に製造方法欄及び製造販売する品目の製造所欄です。これらの欄については、新法に対応した記載内容に整備する必要があります。一方、使用目的又は効果欄(旧「使用目的、効能又は効果欄」)、原材料欄(旧「原材料又は構成部品欄」)などの名称変更のみの欄については、従来どおりの記載で差し支えないため、記載内容の整備は不要です。
2. 製造方法欄の記載整備内容
2.1 医療機器の製造方法欄
医療機器の製造方法欄については、新法に対応して記載を簡素化することが可能となりました。各工程に係る登録製造所が単一である場合など、各工程の関係について誤認が生じない場合においては、工程ごとの記載や工程フロー図等は原則として記載不要となります。
ただし、組合せ医療機器については、構成品の滅菌状況等の確認が必要であることから、従来どおり工程フロー図等の記載が必要です。製造条件、滅菌方法、ウイルス等の不活化・除去方法の処理等に関する記載は従来どおり必要です。
外部試験検査施設の記載は不要となり、主たる設計を行った事業者の氏名又は名称の記載も不要となりました。なお、設計を行う施設については、製造販売する品目の製造所欄で設計を行う製造所として記載することになります。
2.2 体外診断用医薬品の製造方法欄
体外診断用医薬品についても、医療機器と同様に製造工程に関する記載が簡素化されました。各工程に係る登録製造所が単一である場合等においては、工程ごとの記載や工程フロー図等は原則として記載不要です。
外部試験検査施設の記載及び主たる設計を行った事業者の氏名又は名称の記載は不要となりました。製造工程に関する詳細な情報については、承認申請又は認証申請時の添付資料やQMS調査の申請資料等において必要に応じ提出を求められることになります。
3. 製造販売する品目の製造所欄の記載方法
3.1 記載すべき内容
製造販売する品目の製造所欄には、登録を受けた製造所ごとに、製造所の名称、製造業登録番号、製造工程を記載します。製造工程については、新施行規則第114条の8の各号に基づき、明確に区分して記載する必要があります。
医療機器の場合、製造工程は「設計」、「主たる組立て」、「滅菌」、「保管」の別を記載します。滅菌については、さらに放射線、EOG(エチレンオキサイドガス)、湿熱、その他の別を製造所ごとに記載します。
体外診断用医薬品の場合、製造工程は「設計」、「充填」、「充填工程以降」、「保管」の別を記載します。
3.2 記載例の活用
通知には具体的な記載例が示されており、製造工程ごとに製造所が異なる場合、一つの製造所で複数の製造工程を有する場合、同一工程の登録製造所が複数ある場合など、様々なパターンに対応した記載例が提供されています。
特に重要な点として、設計を行う施設が製造販売業者の主たる事務所と同一の場所である場合は、登録番号欄に製造販売業許可番号(88AAA88888の形式)を記載することが明記されています。
4. 記載整備の手続きと期限
4.1 記載整備の方法
記載整備は、新施行規則様式63の10(1)、様式63の10(2)、様式63の24(1)又は様式63の24(2)、様式66(1)から(4)の軽微変更届出により行います。変更年月日欄には「届出年月日」を、変更理由欄には「整備届」と記載します。
同一の製品群区分で全ての製造所が同一である品目について、既に新法下でのQMS調査を受け有効な基準適合証が交付されている場合は、備考欄に当該基準適合証の番号及び交付年月日を記載し、必要に応じて基準適合証の写しを添付します。
4.2 届出先と提出方法
届出先は、承認品目については独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、認証品目については認証を受けた登録認証機関となります。品目ごとに届け出る必要があり、記載整備のため記載する欄は製造方法欄及び製造販売する品目の製造所欄のみとし、他の欄の記載は変更しないことが重要です。
承認品目については、FD申請様式等を用いることで電子的に記載を整備し、届け出ることが推奨されています。
4.3 記載整備の期限
改正法施行時において、製造販売業者が保有する品目のうち、新法第23条の2の5第6項又は第23条の2の23第3項に基づく承認又は認証の取得後5年ごとに受けるべきQMS調査について、当該期間の残存期間が最も長い品目のQMS調査を受けるべき日から30日後までに、当該製造販売業者が保有する全ての承認品目又は認証品目の記載整備を完了させる必要があります。
医療機器又は体外診断用医薬品に関して複数の製造販売業許可を有する場合の記載整備期限は、複数の許可に係る全ての品目のうち最も残存期間が長い品目のQMS調査を受けるべき日から30日後までとすることができます。
5. 実務上の留意点
5.1 早期対応の推奨
記載整備期限前であっても、新法に基づくQMS調査を行った品目については、調査後に当該品目を含めた関連品目の記載整備を行うなど、可能なものは速やかに記載整備することが望ましいとされています。
記載整備期限の前に製造方法欄又は製造販売する品目の製造所欄の承認(認証)事項を一部変更承認(認証)申請又は軽微変更届出により変更する場合は、変更の機会に併せて該当する欄を記載整備する必要があります。この際、両方の欄の記載が整備された場合は、あらためて記載整備期限までに記載整備のための軽微変更届出を行う必要はありません。
5.2 製造販売届出品目の取扱い
改正法施行前に製造販売届書により届出された品目については、製造方法欄又は製造販売する品目の製造所欄に変更が生じない限り、新法に対応した記載整備は必要ありません。ただし、当該欄の変更が生じた際には、その変更にあわせて記載を整備する必要があります。
記載整備をしていない場合であっても、必要に応じて規制当局から新法に基づく記載内容の照会等があった場合には、新法に対応した情報を説明する必要があることに留意が必要です。
まとめ
薬事法改正に伴い、医療機器・体外診断用医薬品の承認書・認証書の記載整備は、全製品を対象とした重要な対応事項となっています。特に、製造方法欄の簡素化や製造所欄の新たな記載要件、そしてQMS調査の期限を踏まえた計画的な届出対応は、製造販売業者にとって実務上の大きなポイントです。
これらの手続きは一見シンプルに見えても、製造所区分の正確な整理や届出書類の書き方など、細部に注意が必要です。誤った記載や対応の遅れは、今後のQMS調査や承認更新に影響を及ぼす可能性もあります。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、承認書・認証書の記載整備対応や軽微変更届の作成支援、製造所区分の整理など実務支援を専門的に行っています。自社での対応に不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な薬事専門スタッフが迅速にサポートいたします。