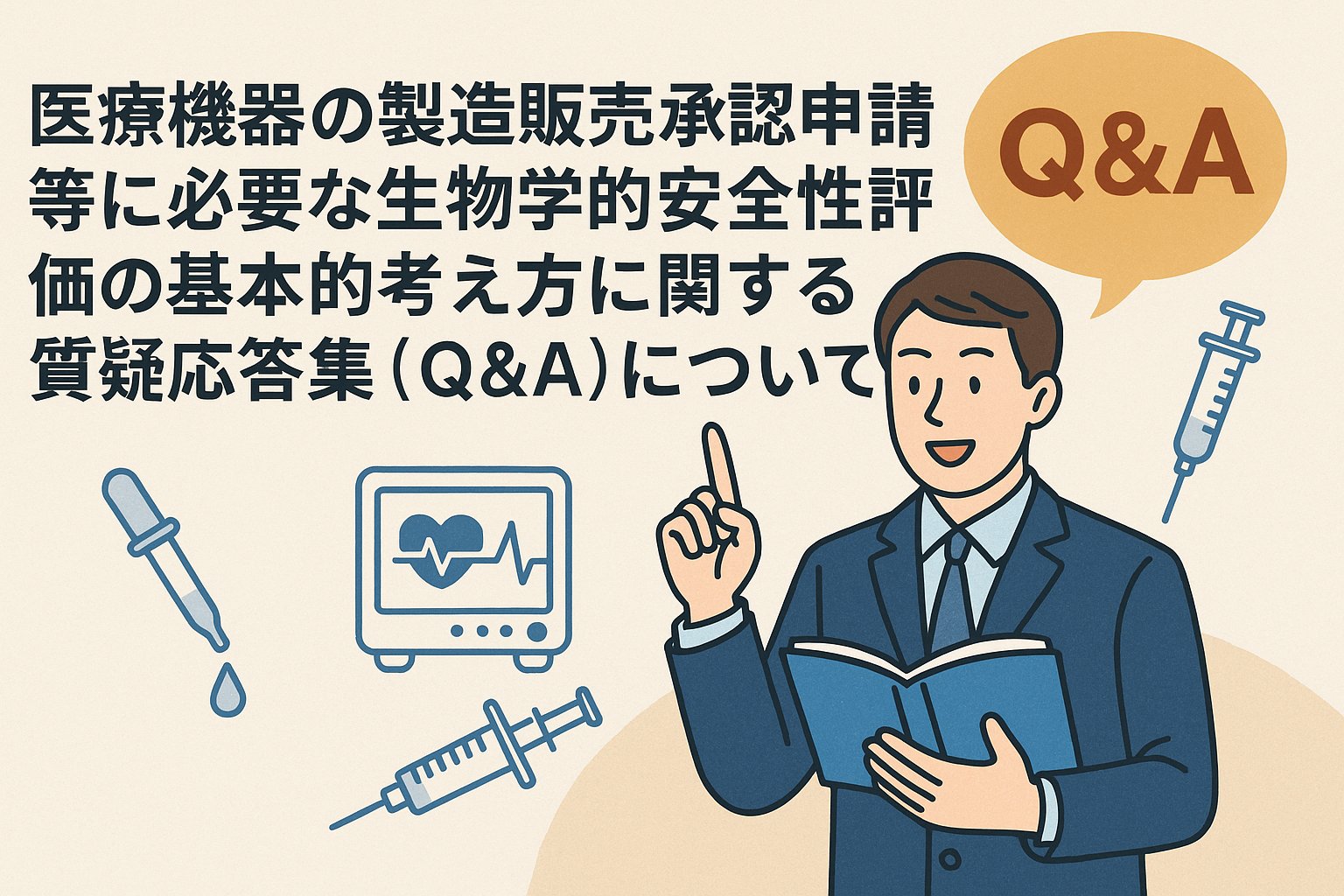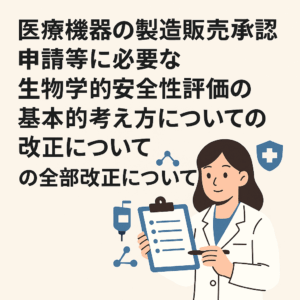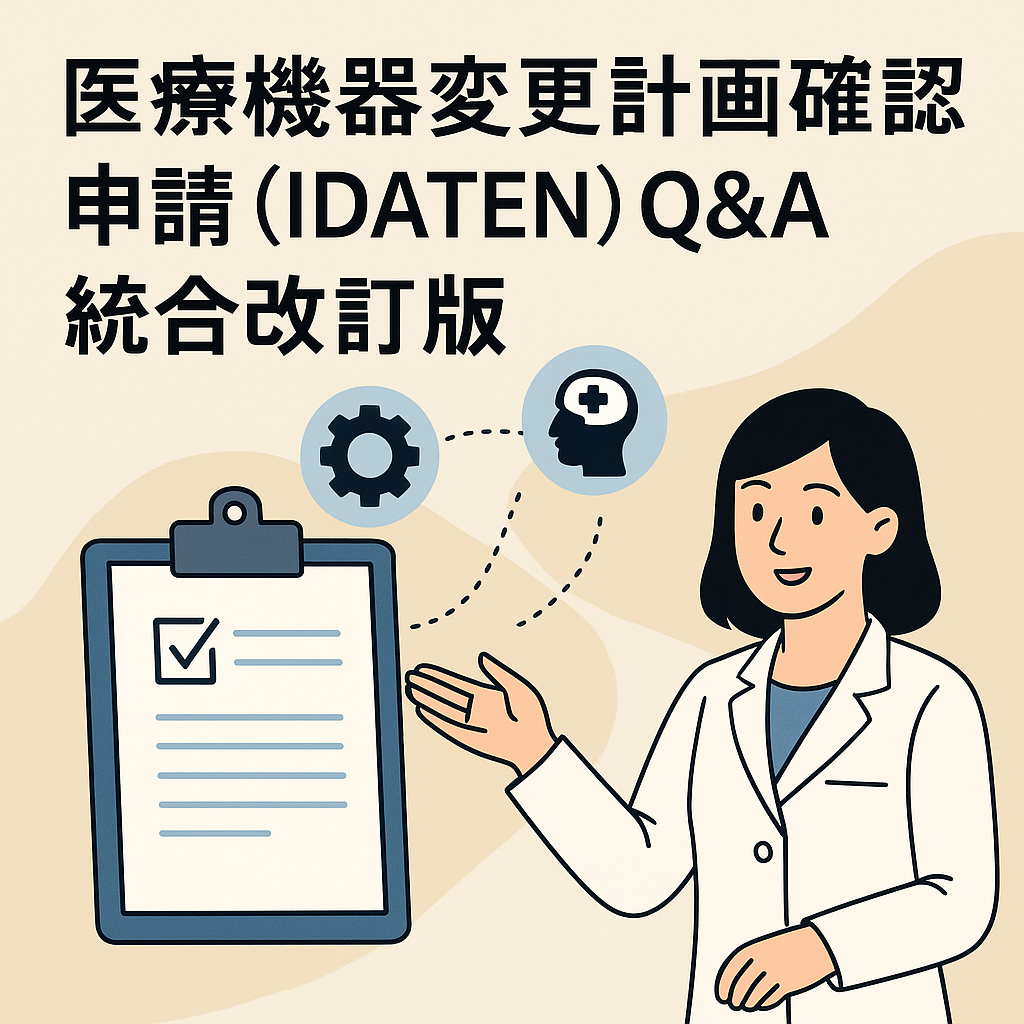概要
令和7年3月11日、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課より、医療機器の生物学的安全性評価に関する質疑応答集が発出されました。本通知は、同日付で全部改正された「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について」を補完するものとして位置づけられています。
医療機器の製造販売において、生物学的安全性評価は患者の安全を確保する上で極めて重要な要素です。しかし、規格の更新や評価方法の複雑さから、実務においては様々な疑問や課題が生じることがあります。本Q&A集は、製造販売業者や開発担当者が直面する具体的な課題に対して、明確な指針を提供するものです。
今回発出されたQ&A集では、最新規格の適用時期、試験実施における規制要求、既存製品との同等性評価、特殊な医療機器の取り扱いなど、実務上重要な6つの質問に対する回答が示されています。これらの内容を理解し、適切に実践することは、効率的な承認申請と確実な薬事対応を実現するために不可欠です。
1. 生物学的安全性評価における最新規格の適用
1.1 最新規格の参照と適用時期
生物学的安全性評価試験の必要性を判断する際、最新の関連公的規格等を参考とすることが求められています。Q&A集では、これらの規格として主にISO(国際標準化機構)やJIS(日本産業規格)が該当することが明確化されました。
重要な点として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページでは、本通知に合わせて生物学的安全性評価に関連したSTED記載項目および審査ポイントが公開されています。これらの情報は、申請書類の作成において重要な参考資料となります。
ただし、正式にISOやJISが制定されるまでの移行期間においては、現在発行されている規格に基づいて生物学的安全性評価試験の必要性を判断することが認められています。これにより、規格改定の過渡期においても、業務の継続性が確保されます。
1.2 規格更新時の対応方法
申請資料において旧規格に従って実施した試験結果を添付する場合、特別な配慮が必要です。まず、どの規格に従って試験を実施したのかを明確に記載することが求められます。さらに、最新の規格とのギャップ分析を行い、安全性評価として問題がないことを説明する必要があります。
この取り扱いは、申請時点において既に試験が終了しているものや、新規の試験が不要であるものを想定しています。最新の規格が制定された後に新たに試験を実施する場合は、必ず最新の規格に従って実施することが原則となります。
2. 試験実施および申請資料作成における実務的留意点
2.1 機能性試験と化学分析の規制要求の違い
生物学的安全性評価に必要となる試験には、機能性・有効性試験と化学分析があります。Q&A集では、これらに対する規制要求の違いが明確化されました。
機能性・有効性試験については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第114条の22の規定の順守が要求されます。これは、試験の信頼性を確保するための重要な要件です。一方、化学分析に対しては、この規定の適用は求められないことが確認されました。
この区別を正確に理解することで、試験計画の立案や外部委託先の選定において、適切な判断が可能となります。過剰な規制対応を避けつつ、必要な品質保証体制を構築することができます。
2.2 既承認品等との生物学的同等性評価
生物学的同等性評価は、新規申請品の安全性を効率的に証明する重要な手法です。Q&A集では、既承認品、既認証品、既届出品との同等性情報の収集について、その範囲と考え方が示されました。
一般的には、日本国内において承認、認証、届出実績がある製品との同等性評価が想定されています。これは、国内の規制要求事項との整合性を確保する観点から重要です。
ただし、日本以外の国における承認品等の情報を利用することも可能です。その場合、対象となる製品や原材料の接触リスクの程度、市販後の毒性情報の有無なども含めて、総合的に判断することが求められます。単純な材料の同一性だけでなく、使用実績や安全性プロファイルを包括的に評価する必要があります。
3. 認証基準と規格の移行措置
3.1 JIS T 0993-1引用認証基準の取り扱い
認証基準においてJIS T 0993-1を引用している場合、特別な移行措置が適用されます。引用されるJISの最新版への適合性確認については、「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る日本工業規格の改正に伴う薬事法上の取扱いについて(その3)」に基づいて行うことが示されました。
この通知では、経過措置期間が原則3年間と定められています。製造販売業者は、この期間内に最新規格への対応を計画的に進める必要があります。移行期間中は旧規格での対応も認められますが、早期の対応が推奨されます。
3.2 規格リストの発行年の取り扱い
「生物学的安全性試験に関連する公的規格リスト」には規格の発行年が記載されていません。これについて、Q&A集では承認または認証申請する段階で最新の規格を参照することが基本原則であることが確認されました。
申請資料において旧規格による試験結果を使用する場合は、実施した規格の版を明確にし、最新規格とのギャップ分析および安全性評価上の問題がないことの説明が必要です。これにより、審査の透明性と効率性が確保されます。
4. 特殊な医療機器における評価の考え方
4.1 歯科用医療機器の生物学的安全性評価
歯科用医療機器については、独自の評価指針が存在します。「歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について」(令和3年5月31日付け薬生機審発0531第5号)に基づいて評価することが確認されました。
歯科用医療機器は、口腔内という特殊な環境で使用されるため、一般的な医療機器とは異なる評価の観点が必要です。材料の溶出特性、唾液との相互作用、長期間の口腔内滞在による影響など、特有の考慮事項があります。
4.2 眼科用医療機器等の基本要件適合性
基本要件適合性チェックリストの第7条第1項において、JIS T 0993-1以外のJISを引用している医療機器があります。例えば、眼底カメラ基準が適用される医療機器では、JIS T 15004-1が適用されます。
このような場合、申請資料においては当該JISのみを引用して確認した結果を添付することで良いことが明確化されました。これにより、医療機器の特性に応じた適切な評価基準の適用が可能となります。重複した評価を避けることで、効率的な申請資料の作成が実現できます。
5. 実務における適用のポイント
5.1 規格移行期の対応戦略
規格の改定や新規制定は継続的に行われており、製造販売業者は常に最新の動向を把握する必要があります。移行期間においては、以下の点に留意することが重要です。
開発初期段階の製品については、可能な限り最新規格を適用することで、将来的な規格変更への対応を最小限に抑えることができます。一方、開発後期や申請準備段階の製品については、既に実施した試験の妥当性を確認し、必要に応じて追加試験やギャップ分析を実施します。
5.2 申請資料作成時の留意事項
申請資料を作成する際は、使用した規格の版を明確に記載し、評価の根拠となる情報を体系的に整理することが重要です。特に、既存製品との同等性を主張する場合は、比較対象製品の選定理由、同等性の判断根拠、相違点がある場合はその安全性への影響評価を詳細に記載する必要があります。
PMDAのホームページに公開されているSTED記載項目および審査ポイントを参照し、審査側の視点を理解した上で資料を作成することで、照会事項を減らし、承認までの期間を短縮することが可能となります。
まとめ
今回発出された医療機器の生物学的安全性評価に関するQ&A集は、実務上の疑問に対して具体的な指針を示す重要な資料です。最新規格の適用時期や規格更新時の対応方法、機能性試験と化学分析に関する規制要求の違い、既承認品との同等性評価、さらには歯科・眼科など特殊な医療機器への対応など、多岐にわたる実務的なポイントが整理されています。これらを正確に理解し、自社の品質システムや承認申請資料作成に反映することは、製品開発の効率化と審査対応の円滑化に直結します。
特に規格の移行期における対応戦略や、最新規格と旧規格のギャップ分析は、承認取得を左右する重要な要素です。計画的な準備と十分な裏付け資料の整備が成功の鍵となります。
弊社では、生物学的安全性評価や規格移行期の対応、承認申請資料作成のサポートを行っております。自社製品の評価方法に迷われている場合や、申請準備に不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な実務経験に基づき、最適な対応策をご提案いたします。