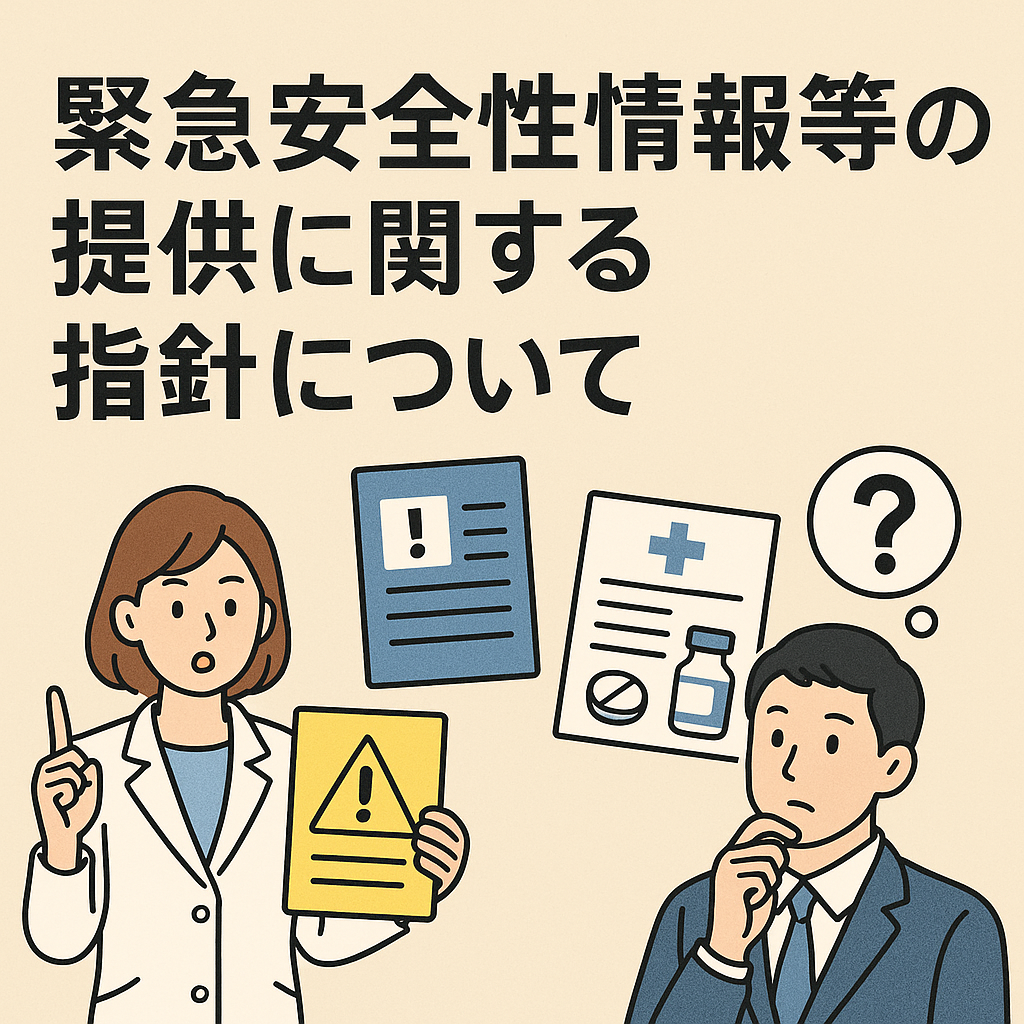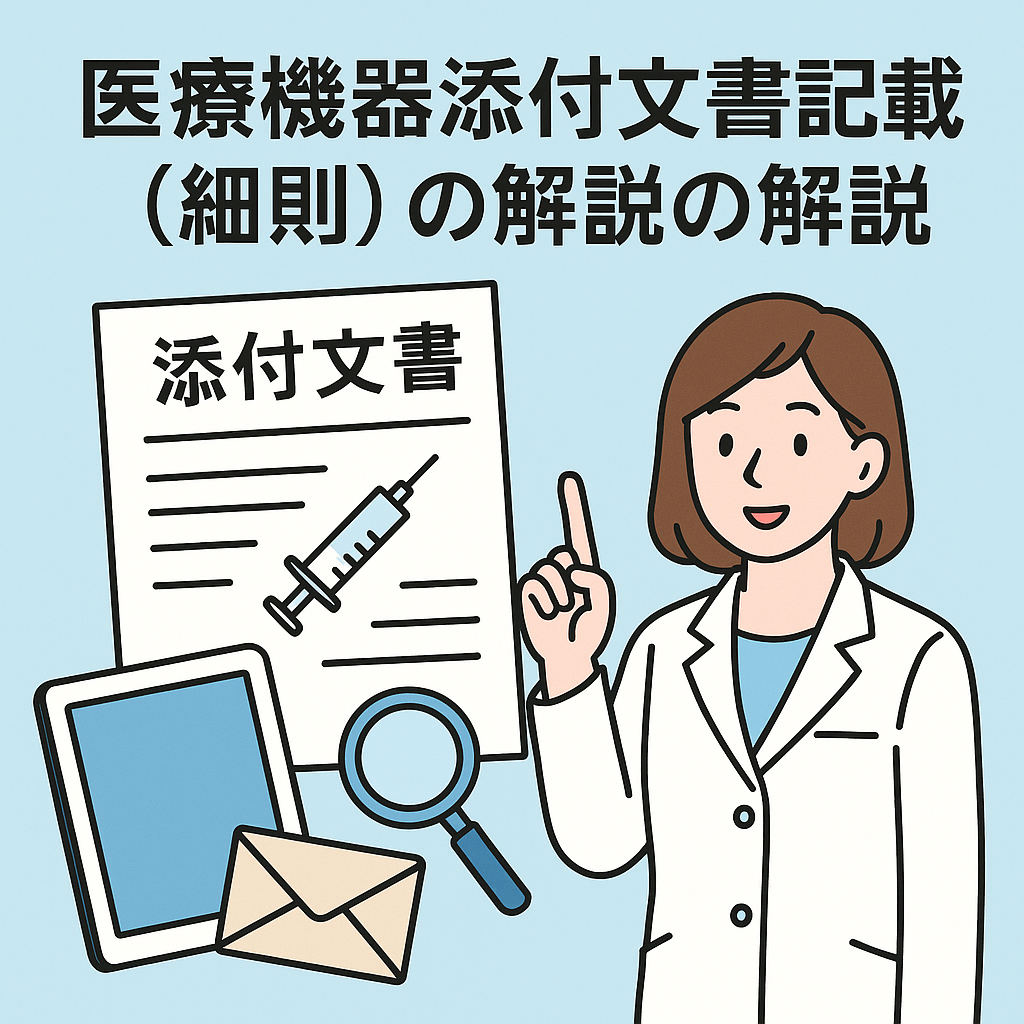概要
本指針は、医薬品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の使用による重大な健康被害の発生・拡大を防止するため、製造販売業者が行うべき緊急安全性情報(イエローレター)および安全性速報(ブルーレター)の作成基準と提供方法を定めたものです。平成26年の薬事法改正により再生医療等製品が新たに定義されたことを踏まえ、従来の指針を改訂し、情報提供の迅速性と網羅性を重視した内容となっています。また、医薬関係者だけでなく、患者や一般国民にもわかりやすい情報提供を求めており、電子媒体の活用も推進されています。
1. 緊急安全性情報(イエローレター)の作成基準と提供方法
1.1 作成基準
緊急安全性情報は、国民(患者)および医薬関係者に対して緊急かつ重大な注意喚起や使用制限が必要な状況で作成されます。具体的には以下のような場合が該当します。
法第68条の10に基づく副作用・不具合等の報告において、死亡、障害またはこれらにつながるおそれのある症例が発生した場合、未知重篤な副作用・不具合等の発現により安全性上の問題が有効性に比して顕著である場合、外国における緊急かつ重大な安全性に関する行政措置が実施された場合、などです。
これらの状況に対応して、警告欄の新設・追加、禁忌事項の新設・追加、新たな安全対策の実施を伴う使用上の注意の改訂、安全性上の理由による効能効果や用法用量の変更、回収を伴った行政措置などが実施されます。
1.2 提供方法
緊急安全性情報の提供は以下の手順で行われます。まず、医薬・生活衛生局医薬安全対策課が製造販売業者に対して書面または電磁的方法により通知を行います。製造販売業者は厚生労働省およびPMDAと協議の上、緊急安全性情報を作成します。
情報提供開始後は速やかに報道発表を行い、回収等が必要な場合は新聞の社告等への掲載も検討されます。PMDAは緊急安全性情報をホームページに掲載し、PMDAメディナビでの配信も行います。製造販売業者も自社のホームページに同様の情報を掲載することが求められます。
医療機関・薬局等への情報提供は、直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子メール等による迅速な伝達と、直接面談、オンライン面談、電話等による詳細な情報提供を組み合わせて実施されます。提供計画書の提出から1か月以内に情報が到着していることの確認も必要です。
2. 安全性速報(ブルーレター)の作成基準と提供方法
2.1 作成基準
安全性速報は、緊急安全性情報に準じて、一般的な使用上の注意の改訂情報よりも迅速な注意喚起が必要な場合に作成されます。保健衛生上の危害発生・拡大の防止のため、適正使用のための対応(注意の周知・徹底、臨床検査の実施等)の注意喚起が必要な状況が該当します。
2.2 提供方法
安全性速報の提供方法は基本的に緊急安全性情報と同様ですが、報道発表は必須ではありません。医薬・生活衛生局医薬安全対策課からの通知を受け、製造販売業者が厚生労働省およびPMDAと協議して作成します。
PMDAのホームページへの掲載とPMDAメディナビでの配信は速やかに行われ、製造販売業者も自社ホームページに掲載します。医療機関・薬局等への情報提供は緊急安全性情報と同様の方法で実施され、1か月以内の到着確認が必要です。
3. 使用上の注意等の改訂に伴う情報対応
3.1 通常の改訂対応
医薬・生活衛生局医薬安全対策課は、PMDAでの検討結果に基づき、使用上の注意等の改訂の指示・指導を課長通知として製造販売業者に通知します。PMDAはこの通知をホームページに掲載し、PMDAメディナビで配信します。
製造販売業者は改訂電子添文をPMDAに届け出て公表し、「改訂内容を明らかにした文書」を作成して情報提供を実施します。ただし、PMDAメディナビをもって情報提供に代えることも可能です。
3.2 注意事項等情報変更時の対応
法第68条の2の3の規定により注意事項等情報の届出対象となる医薬品等については、製造販売業者は改訂電子添文をPMDAに届け出て、PMDAのホームページに公表することが義務付けられています。
4. PMDAが実施する情報提供
4.1 補完的情報提供
PMDAは、リスク・コミュニケーション向上の観点から、「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「PMDA医療安全情報」、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」、「患者向医薬品ガイド」等の資材を提供しています。
これらは緊急安全性情報等による情報提供や使用上の注意を補完し、適正使用の向上に資するものです。特に「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、警告等の重大な改訂後も副作用報告が減少しない場合に作成が検討されます。
4.2 定期的情報提供
PMDAは、注意事項等情報の改訂内容を明らかにした文書として、電子版の医薬品・医療機器等安全性情報および医薬品安全対策情報(DSU)をホームページに定期的に掲載し、メディナビで配信しています。
5. 情報保存と記録管理
5.1 保存期間
製造販売業者は、厚生労働省からの命令・指示、社内各部門での連絡等に関する文書、情報提供記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用しなくなった日から原則5年間保存する必要があります。
ただし、製品の種類により保存期間は異なり、生物由来製品は10年、特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器および設置管理医療機器は15年、再生医療等製品は10年、指定再生医療等製品は30年となっています。
5.2 提供計画書と報告書
製造販売業者は、緊急安全性情報または安全性速報を提供する際、事前にPMDA安全部門と協議し、提供計画書を提出します。情報提供完了後は、提供報告書により実施結果を報告することが義務付けられています。
まとめ
本指針は、医薬品等による健康被害の発生・拡大を防止するための重要な枠組みを定めています。緊急安全性情報(イエローレター)は最も重大な安全性上の問題に対応し、安全性速報(ブルーレター)は迅速な注意喚起が必要な場合に使用されます。
情報提供においては、迅速性と網羅性のバランスを保ちながら、医薬関係者だけでなく患者・一般国民にもわかりやすい情報提供が求められています。電子媒体の活用により、PMDAメディナビやホームページを通じた即時的な情報配信が可能となり、より効果的な安全対策の実施が期待されています。
緊急安全性情報や安全性速報の作成・提供体制の整備、記録管理の具体的な方法についてお悩みの際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。弊社スタッフが御社の状況に応じて適切な支援をご提案いたします。