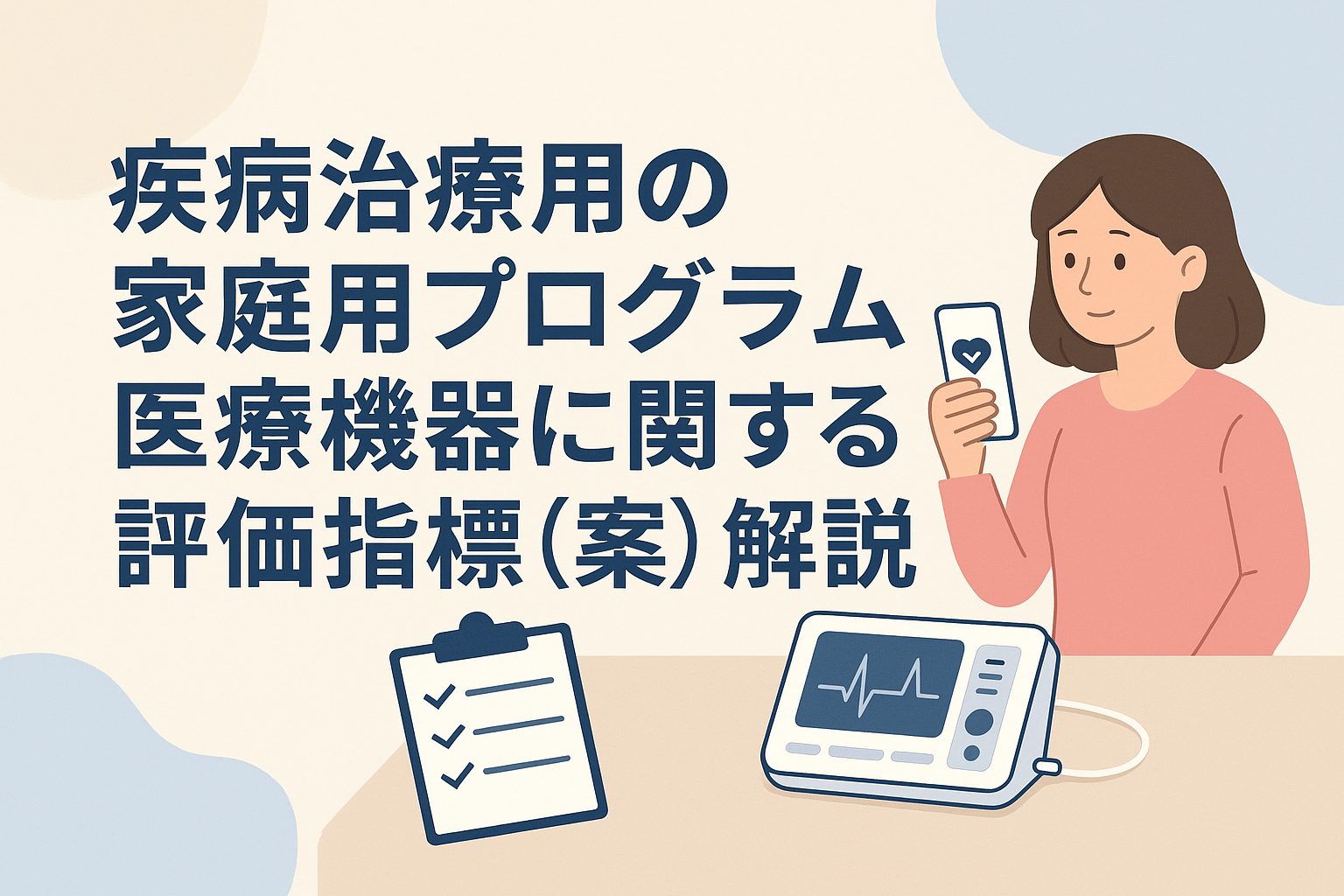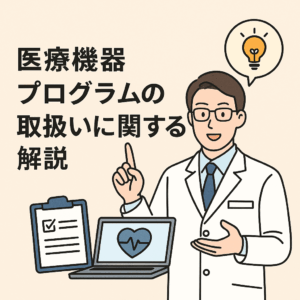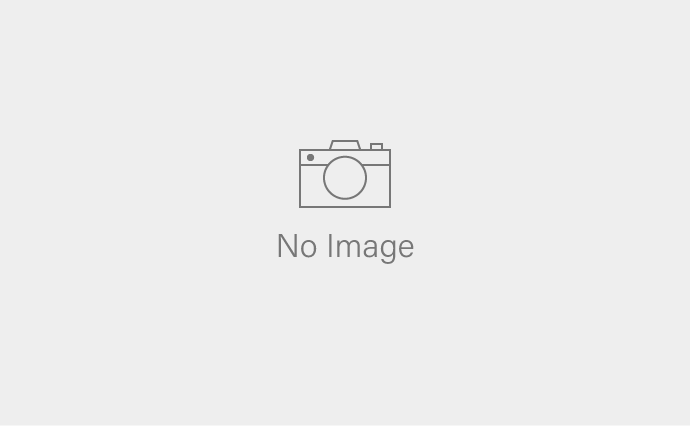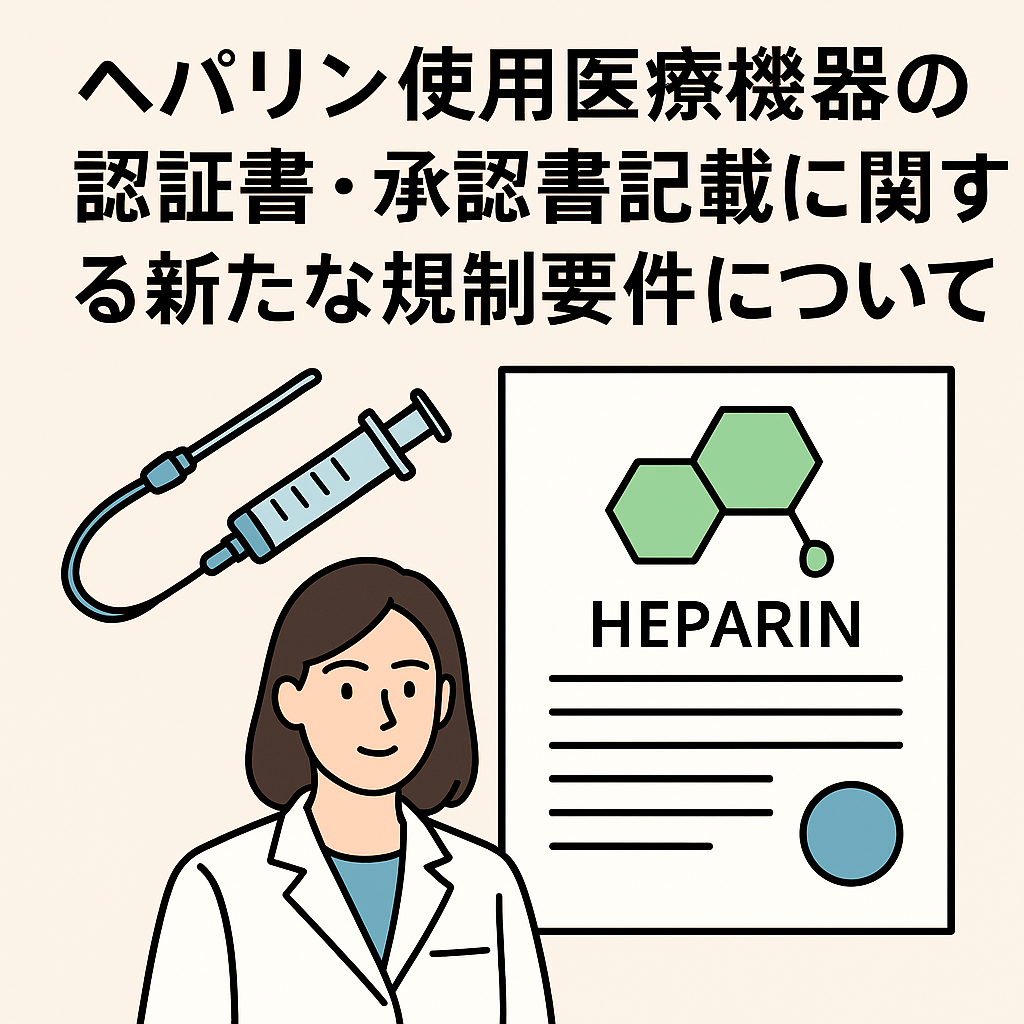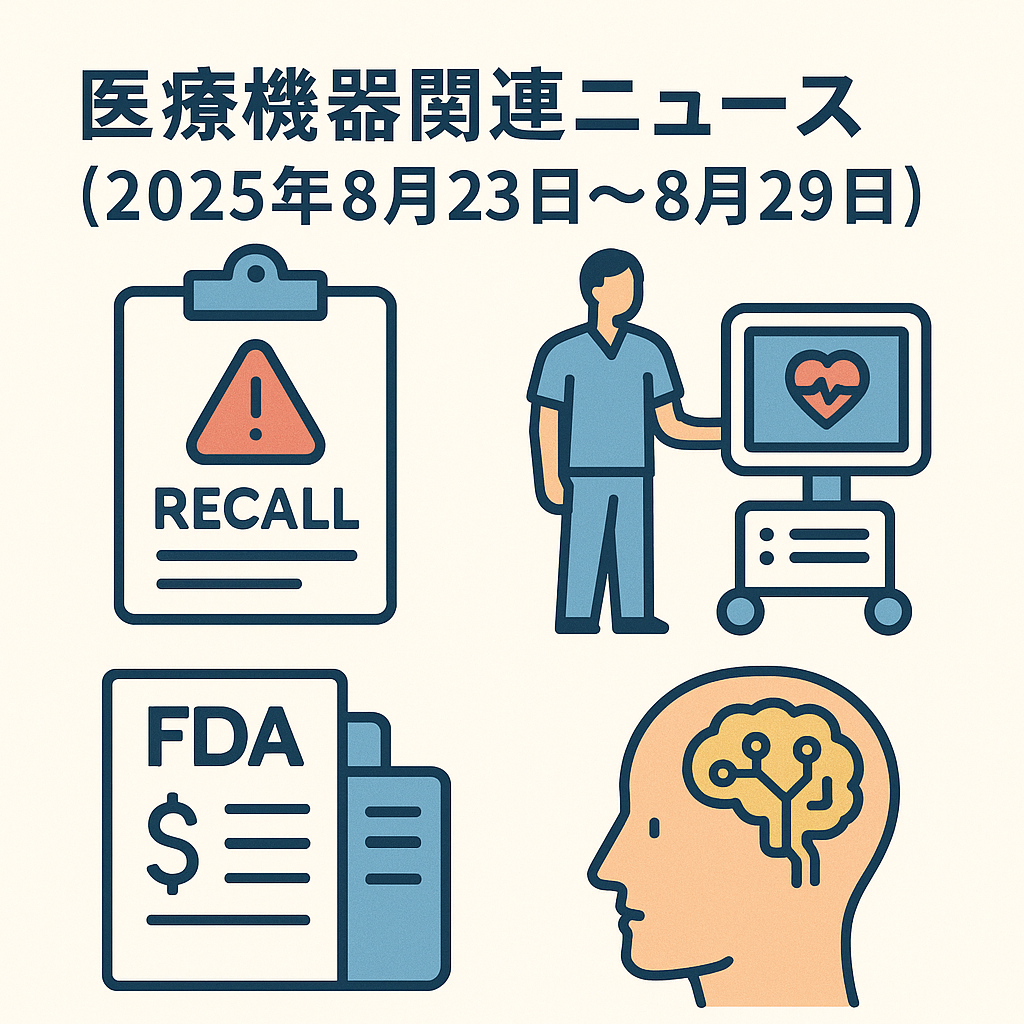概要
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課が公表した「疾病治療用の家庭用プログラム医療機器に関する評価指標(案)」は、医療現場以外の家庭で使用される疾病治療用プログラム医療機器の薬事承認を円滑化するための重要な指針です。
この評価指標は、プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略2(DASH for SaMD 2)の一環として策定され、これまで承認実績のない家庭向けの疾病治療用プログラム医療機器について、製品開発から承認申請に至るまでの考え方を体系的に整理したものです。
家庭用プログラム医療機器は、医療現場向けプログラム医療機器とは異なり、疾病や症状への対処に必要な医学的知識を持たない一般使用者が、医師の指示や処方なしに自己責任で使用するという特殊性があります。このため、より厳格な安全性の確保と使用者への適切な情報提供が求められます。
評価指標では、「スイッチ家庭用プログラム医療機器」(医療現場向けから転用)と「ダイレクト家庭用プログラム医療機器」(新規開発)という2つのカテゴリーに分けて、それぞれの特性に応じた評価方法を提示しています。
1. 家庭用プログラム医療機器の基本概念と特徴
1.1 定義と対象範囲
家庭用プログラム医療機器とは、医療機関への受診や医師の指示・処方がなくても、使用者の選択により使用が可能なプログラム医療機器を指します。これは従来の医療現場向けプログラム医療機器とは明確に区別される新しいカテゴリーです。
評価指標の対象となるのは、類別が「疾病治療用プログラム」に該当するプログラム医療機器のうち、医療機器としての目的性を有し、意図したとおりに機能しない場合に使用者の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラムです。ただし、一般医療機器(クラスⅠ)に相当するものは除外されます。
1.2 想定される使用者
家庭用プログラム医療機器は、多様な状況の使用者を想定しています。無症状又は症状が軽度である者から、過去に疾病への罹患が診断されている者、治療が完了していない者まで、幅広い使用者層が対象となります。
特に重要なのは、これらの使用者が「疾病や症状への対処に必要な医学的知識を持たない」という前提です。このため、使用者が自己責任で適切に使用できるよう、製品設計から情報提供まで、すべての段階で使用者の理解度を考慮した対応が必要となります。
1.3 家庭用プログラム医療機器のリスク
医療現場向けプログラム医療機器と比較して、家庭用プログラム医療機器には特有のリスクが存在します。最も重要なリスクは、診断や治療の遅れ、並びに医療上の観点から不適切な治療が行われることによる症状の悪化や、治療効果が得られないまま使用期間が漫然と長期化するリスクです。
また、医療者がその使用状況を把握できないため、適切な医療機関への受診タイミングを逸するリスクも考慮する必要があります。
2. 製品開発における要件と考慮事項
2.1 家庭用プログラム医療機器の基本要件
家庭用プログラム医療機器として承認を得るためには、以下の6つの基本要件を満たす必要があります。
第一に、使用者が症状から使用の可否を判断することが可能であること、または医師による診断や健康診断の結果等を受けて、使用者の判断に基づき適正に使用できることが求められます。
第二に、医療者による指導監督がなくても、使用により重篤な状態になるおそれのないことが必要です。これは家庭用プログラム医療機器の最も重要な安全性要件の一つです。
第三に、十分な医学的知識を持たない使用者による不適切な使用等があった場合でも、重大なリスクをもたらすことがないことが求められます。
第四に、人体に対する作用が著しくないものであって、長期に使用する場合においても使用者の状態やその変化に応じた医療者による調整等を必要としないことが必要です。
第五に、使用者の判断が間違っていた場合に重症化する等、医療機関への受診が遅れることによって生じるリスクについて、講じる対策によりリスクが許容可能であることが求められます。
第六に、習慣性、依存性及び耽溺性(夢中になりすぎる特性)のリスクが許容可能であることが必要です。
2.2 スイッチ型とダイレクト型の区別
評価指標では、家庭用プログラム医療機器を開発経緯によって2つのタイプに分類しています。
「スイッチ家庭用プログラム医療機器」は、製造販売承認実績がある医療現場向けプログラム医療機器の全て又はその一部の機能を転用又は改良することにより開発されたものです。この場合、既存の臨床試験成績や使用成績評価の結果を活用できる可能性があります。
一方、「ダイレクト家庭用プログラム医療機器」は、医療現場向けプログラム医療機器としての製造販売承認実績のない家庭用プログラム医療機器です。この場合、新規の臨床試験が必要となることが多く、より包括的な評価が求められます。
3. 承認申請時の必要事項と評価方法
3.1 申請時に明示すべき基本事項
製造販売承認申請時には、設計開発の経緯、品目の仕様、開発機器の原理(アルゴリズムを含む)、対象となる症状や状態、使用目的又は効果、類似品の国内外での使用状況、使用場所、使用方法等を明らかにする必要があります。
特に重要なのは、使用に適する使用者と適さない使用者の明確化です。対象とする症状や状態並びにその重篤度、使用者の要件を具体的に示すとともに、使用者が有している基礎疾患による制限も明記する必要があります。
また、開発コンセプトとして、当該製品が介入し解決する課題及びその達成手段、介入内容及び介入頻度を明確にし、症状や状態に対する現状の対応手段と当該製品との差分を説明することが求められます。
3.2 有効性及び安全性に関する評価項目
製造販売承認申請では、有効性及び安全性に影響する項目を具体的なデータ又はその他の科学的根拠等をもって明らかにする必要があります。
提示される指示等の根拠については、これまでに有効性について検証されたことのない新規手法が含まれる場合、その手法を用いることの適切性について説明することが必要です。学会等が発行するガイドラインに基づく場合であっても、サロゲートエンドポイントを使用して評価する際は、その適切性を示すことが求められます。
開発時に当該製品の機能設計・性能評価・検証等に用いられたデータについては、製品の目的に合致しない、偏った使用者、網羅性に欠ける方法で収集されたデータ等を用いた場合、汎化性に欠けるプログラムとなる可能性があることに留意が必要です。
4. 臨床評価における特別な考慮事項
4.1 臨床試験の必要性と設計
家庭用プログラム医療機器については、その有効性及び安全性を非臨床試験のみで評価することが難しいことから、想定される使用者における有効性及び安全性が確保されていることを検証的治験により確認することが必要です。
臨床試験の計画にあたって、まずは二重盲検ランダム化比較試験の実施の必要性を検討し、実施困難と判断される場合には、家庭用プログラム医療機器の有効性及び安全性を評価するために必要な試験計画について、PMDAの相談を活用することが推奨されます。
4.2 シャムアプリの活用
家庭用プログラム医療機器は、医薬品のプラセボ効果等と同様に使用者に心理的な影響を与えることによって効果をもたらす可能性が考えられます。ホーソン効果やプラセボ効果と言われるような心理的な影響のみの効果を評価する目的で、対照群においてシャムアプリの使用を考慮する必要があります。
検証的治験においてシャムアプリを使用する場合には、パイロットスタディ等でシャムアプリの盲検性や試験全体での盲検性の確保が適切に評価されていることが理想とされます。
4.3 評価項目の設定
評価項目の設定にあたっては、有効性の指標として臨床的に意義があり、かつ可能な限り広く認知された標準的な客観的指標を用いることが原則です。対象とする症状や状態等によっては、主観的な評価指標を用いざるを得ない場合がありますが、その際は評価すべき内容に応じて可能な限り信頼性や妥当性が検証されている、又は開発分野において標準的に広く受け入れられている適切な指標を選択することが必要です。
5. 市販後の安全管理と継続的評価
5.1 市販後監視の重要性
家庭用プログラム医療機器では、当該製品が対象とする症状に関連する疾患や、別疾患を有する使用者が、医療機関への受診や治療と並行して製品を使用する可能性があります。この場合、当該家庭用プログラム医療機器が提示する内容が、その疾患に対して医学・薬学・看護学・栄養学等の観点から不適切となる可能性があります。
また、家庭用プログラム医療機器を使用することで、適切な受診機会を逸するということもあり得るため、家庭用プログラム医療機器が提示する内容等について、適切な問い合わせ対応が可能となる窓口の設置が必要となります。
5.2 ガイドライン更新への対応
製造販売承認後に予見されるプログラム医療機器特有の課題として、家庭用プログラム医療機器が提示する指示等の根拠となったガイドライン等の更新が挙げられます。ガイドライン等の更新に伴い新たな臨床評価を必要とする変更を行う場合は、臨床試験(治験)の必要性の考え方及び臨床試験(治験)のデザインに準じて臨床試験を実施することが必要です。
5.3 不適切な介入に対する配慮
家庭用プログラム医療機器が不適切な介入を行う可能性に留意する必要があります。特に、メンタルヘルスの不調への不適切介入、慢性疾患に対する生活指導の不適切介入、重篤な疾病の診断遅延に関わる事例などでは、生命に関わる重篤な事態が生じる可能性があるため、対象とする症状や状態だけでなく関連する合併症等を含めて配慮する必要があります。
まとめ
「疾病治療用の家庭用プログラム医療機器に関する評価指標(案)」は、家庭向けSaMD開発の新しい指針を示す重要文書です。従来の医療現場向けプログラムと異なり、一般使用者が医師の指示なしに使用するという特性を踏まえ、厳格な安全性要件や臨床評価手法が明確化されました。
今後、この評価指標に基づく開発が進むことで、国民の健康増進や医療アクセスの多様化が期待されます。一方で、開発や薬事申請、市販後の安全管理においては高度な専門知識と経験が求められます。
弊社では、家庭用プログラム医療機器の開発支援、承認申請、PMDA相談対応、市販後管理体制の構築まで一貫してご支援しています。
本評価指標に基づく製品開発をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。