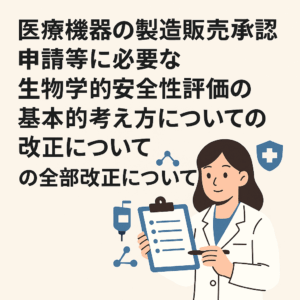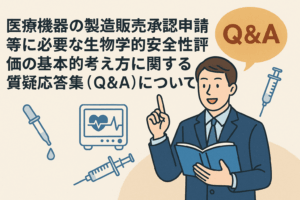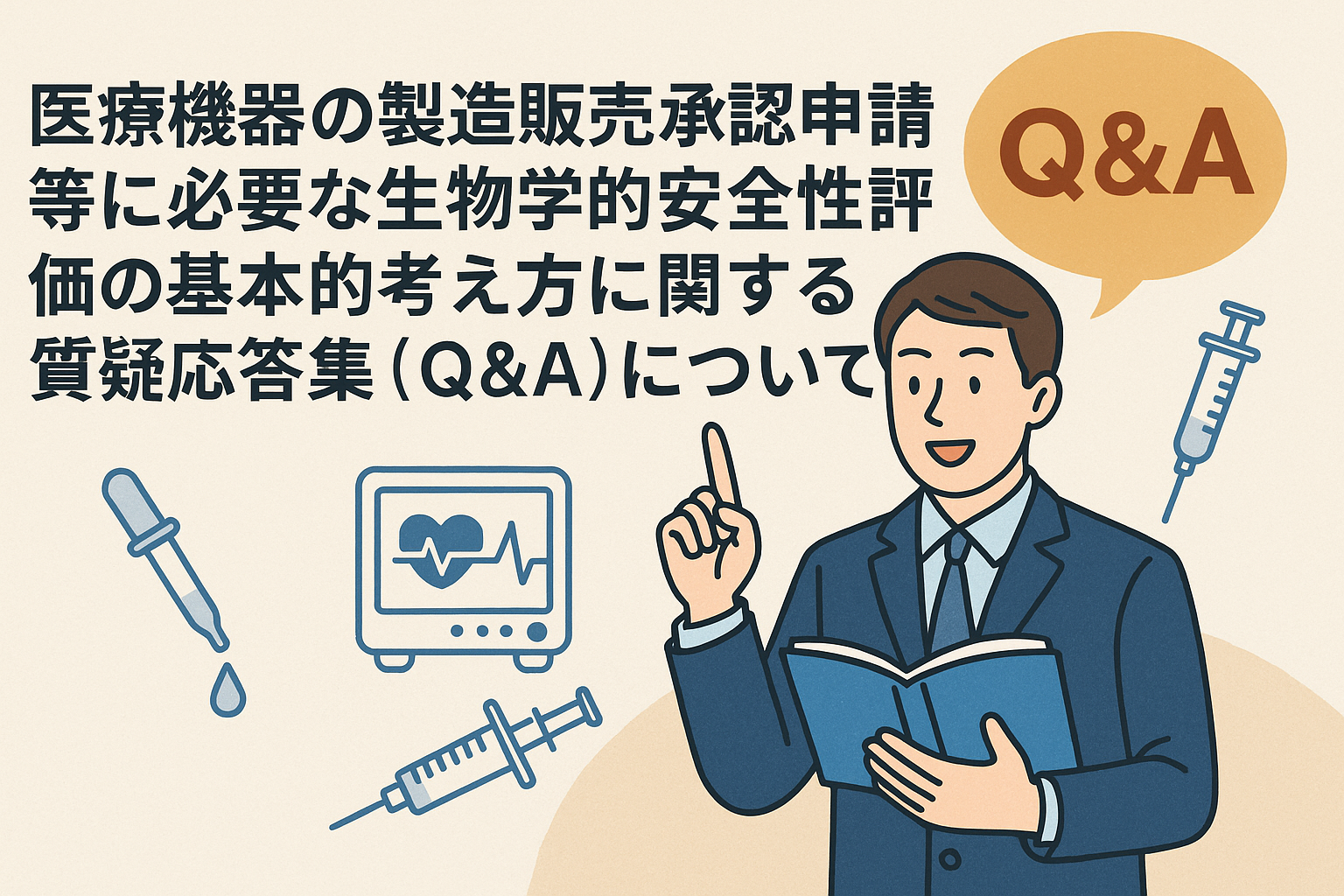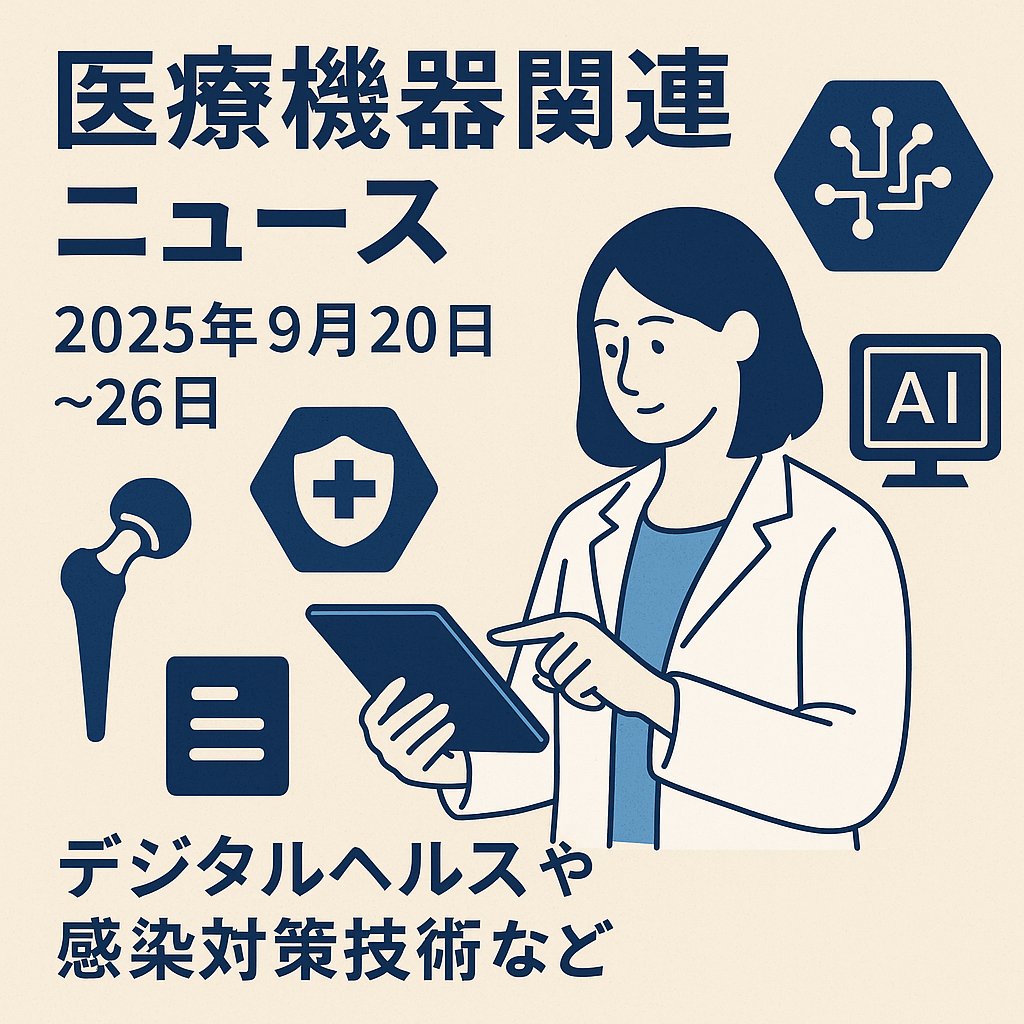概要
医薬品医療機器総合機構(PMDA)が2025年6月4日に公表した本審査ポイントは、医療機器の承認・認証申請における生物学的安全性評価の効率化と審査の迅速化を目的としています。国際規格ISO 10993-1およびJIS T 0993-1に基づき、医療機器の生物学的安全性評価に必要な評価項目や試験方法を体系的に整理した内容となっています。
本文書では、医療機器の接触リスク(接触部位、接触期間)に応じたカテゴリ分類と、それぞれに必要な生物学的安全性試験を明確化しています。また、化学的特性データを活用した毒性学的リスクアセスメントの手法についても詳細に記載されており、試験の省略が可能な条件も示されています。
1. 医療機器の接触リスクによるカテゴリ分類
1.1 接触期間による分類
医療機器は生体への接触期間により以下の3つに分類されます。
1. 一時的接触機器 24時間以内の単一または累積接触となる医療機器です。ただし、接触期間が1分未満のランセットや皮下注射針などは「一過的接触医療機器」として、原則生物学的安全性評価は不要となります。
2. 短・中期的接触 24時間を超え、30日以内の単一または累積接触となる医療機器です。
3. 長期的接触 30日を超える単一または累積接触となる医療機器です。
1.2 接触部位による分類
医療機器は接触する生体部位により、以下のカテゴリに分類されます。
非接触医療機器 :診断ソフトウェアや体外診断用医療機器など、生体と直接・間接的に接触しない機器は、原則として生物学的安全性評価は不要です。
健常な皮膚に接触する医療機器 :電極、固定テープ、血圧計カフ部などが該当します。キーボードやタッチパネルなど、リスクが明らかに少ない場合は試験実施は不要です。
健常な粘膜に接触する医療機器 :コンタクトレンズ、尿道カテーテル、気管内チューブなどが該当します。
損傷した皮膚・粘膜又は血液以外の内部組織に接触する医療機器 :ドレッシング、腹腔鏡、人工関節、ペースメーカなどが該当します。
血液に接触する医療機器 :輸液投与セット、血管内カテーテル、人工血管、心臓弁などが該当します。
2. 生物学的安全性試験の選択と実施
2.1 カテゴリ別の必要試験項目
各カテゴリに応じて、細胞毒性、感作性、刺激性、全身毒性、埋植(組織接触後の局所作用)、遺伝毒性、がん原性、血液適合性の各試験が要求されます。例えば、長期間血液に接触する医療機器では、すべての試験項目が必要となります。
試験実施の判断においては、既承認品との同等性、原材料の使用実績、製造工程の変更有無などを総合的に考慮します。新規材料を使用する場合や製造工程を大きく変更する場合は、より厳格な評価が必要となります。
2.2 個々の試験の特徴と留意点
細胞毒性試験(ISO 10993-5) 哺乳類培養細胞を用いたin vitro試験で、すべての医療機器に必要とされる基本的な試験です。コロニー形成法、XTT法、MTT法などの手法があります。
感作性試験(ISO 10993-10) 医療機器から遊離する化学物質の遅延型アレルギーリスクを確認します。陽性対照試験は少なくとも6か月に1回実施する必要があります。
全身毒性試験(ISO 10993-11) 急性、亜急性、亜慢性、慢性の4種類から、接触期間に応じて選択します。24時間以内に全身血流への大量ばく露が考えられない場合は、急性全身毒性試験を省略できる場合があります。
血液適合性試験(ISO 10993-4) 溶血性、血栓形成、補体活性化などの評価項目から、製品特性に応じて選択します。間接的な血液接触では溶血試験のみで充足する場合があります。
3. 化学的特性データを用いた評価手法
3.1 化学分析による毒性学的リスクアセスメント
ISO 10993-18に従い、医療機器から溶出される可能性のある化学物質を特定・定量し、ISO 10993-17により毒性学的評価を行うことで、一部の生物学的安全性試験を省略できます。
分析評価閾値(AET)を設定し、この値を超える物質について毒性学的評価を実施します。AETは、TTC(毒性学的懸念の閾値)などを基に算出され、その値未満であれば追加の分析は不要となります。
3.2 毒性学的評価指標の活用
TSL(毒性学的スクリーニング限界) 特定期間の累積ばく露量の閾値で、これを下回れば毒性学的リスクは無視できるレベルと判断されます。
TI(耐容摂取量) NOAEL、LOAELなどから計算される、健康に有害な影響が現れないと判断されるばく露量です。
MoS(安全マージン) TIとワーストケース推定ばく露量(EEDmax)の比で、1を超えていれば安全性が確保されていると判断されます。
4. 試験実施における実務上の留意点
4.1 試験検体の選定
最終製品を評価対象とすることが原則です。複数の構成品からなる場合は、ワーストケース評価として最も長い接触期間を適用するか、接触期間ごとに分類して評価を行います。非接触部分が含まれる場合は、接触部位のみを被検物質とします。
4.2 抽出条件の設定
ISO 10993-12に従い、極性溶媒と非極性溶媒を使用することが推奨されます。抽出温度は臨床的なワーストケースを想定しつつ、製品の変形により想定外の化学物質が溶出されないよう注意が必要です。
4.3 既承認品との同等性評価
既承認品と原材料、製造方法、滅菌方法等が同一である場合、生物学的安全性評価の一部を省略できる可能性があります。ただし、原材料の供給元変更や製造工程の変更がある場合は、新たな評価が必要となります。
5. 今後の展望と規制動向
5.1 国際規格の改定への対応
本審査ポイントは2025年5月時点のISO 10993-1/FDIS の内容を反映しています。今後も国際規格の改定に応じて、評価方法や要求事項が更新される可能性があります。
5.2 化学的特性評価の重要性
化学分析技術の進歩により、従来の生物学的安全性試験に代わる評価手法として、化学的特性データを用いた毒性学的リスクアセスメントの活用が拡大しています。これにより、より科学的で効率的な安全性評価が可能となっています。
まとめ
医療機器の生物学的安全性評価では、製品の接触リスクに応じた適切な試験選択と化学的特性データを活用した効率的な評価が求められます。本審査ポイントは、ISO 10993シリーズを基盤とした体系的な指針を示しており、申請者にとって非常に実務的な参考資料となります。
特に、新規材料の使用や製造工程の変更がある場合は、慎重かつ確実な評価が必須となります。効率的に薬事申請を進めるためには、PMDAの助言制度の活用に加え、専門的なサポートを受けることが効果的です。
弊社では、最新の審査ポイントや国際規格に基づいた生物学的安全性評価の戦略立案・資料作成支援を行っています。ご不明点や実務対応に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。