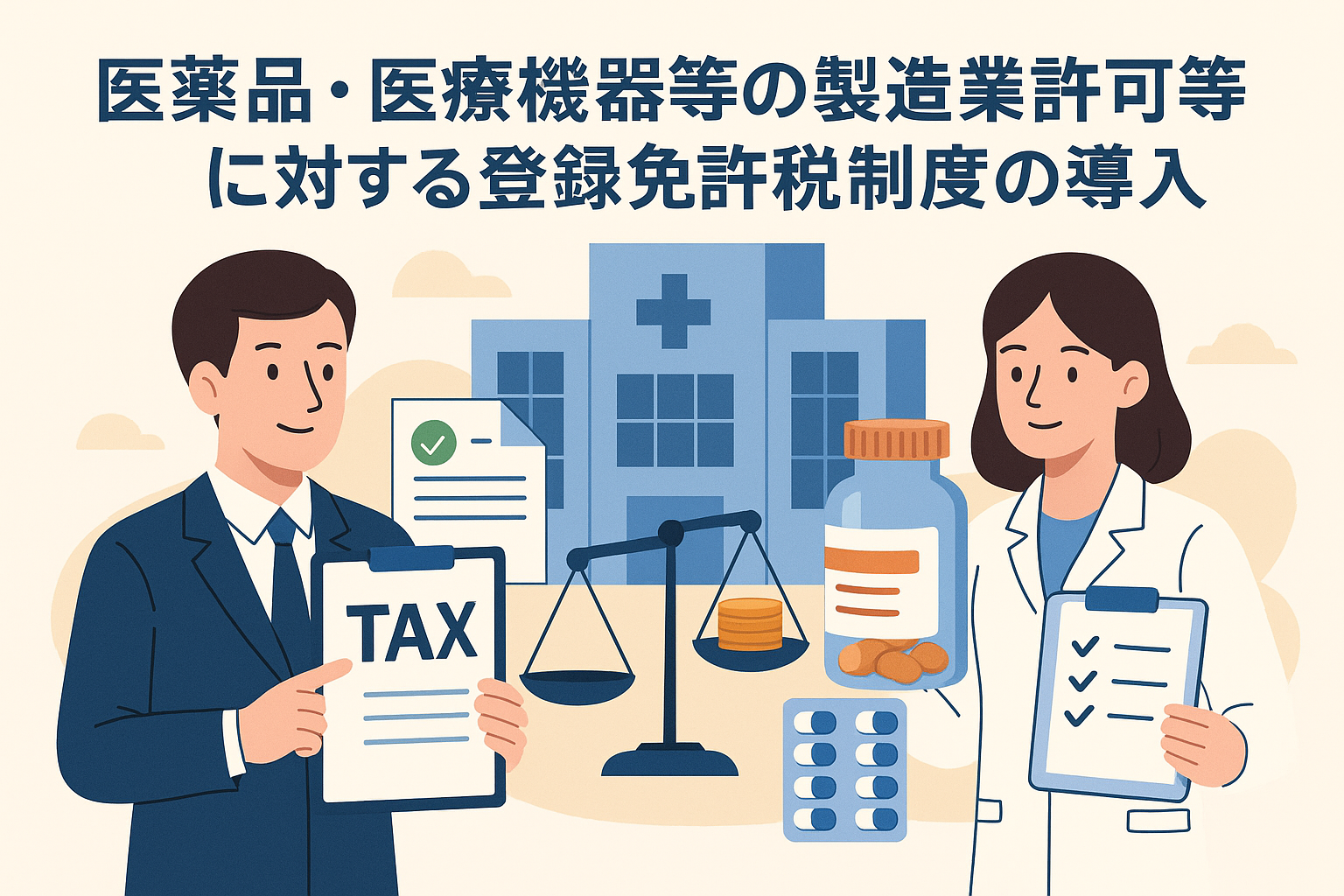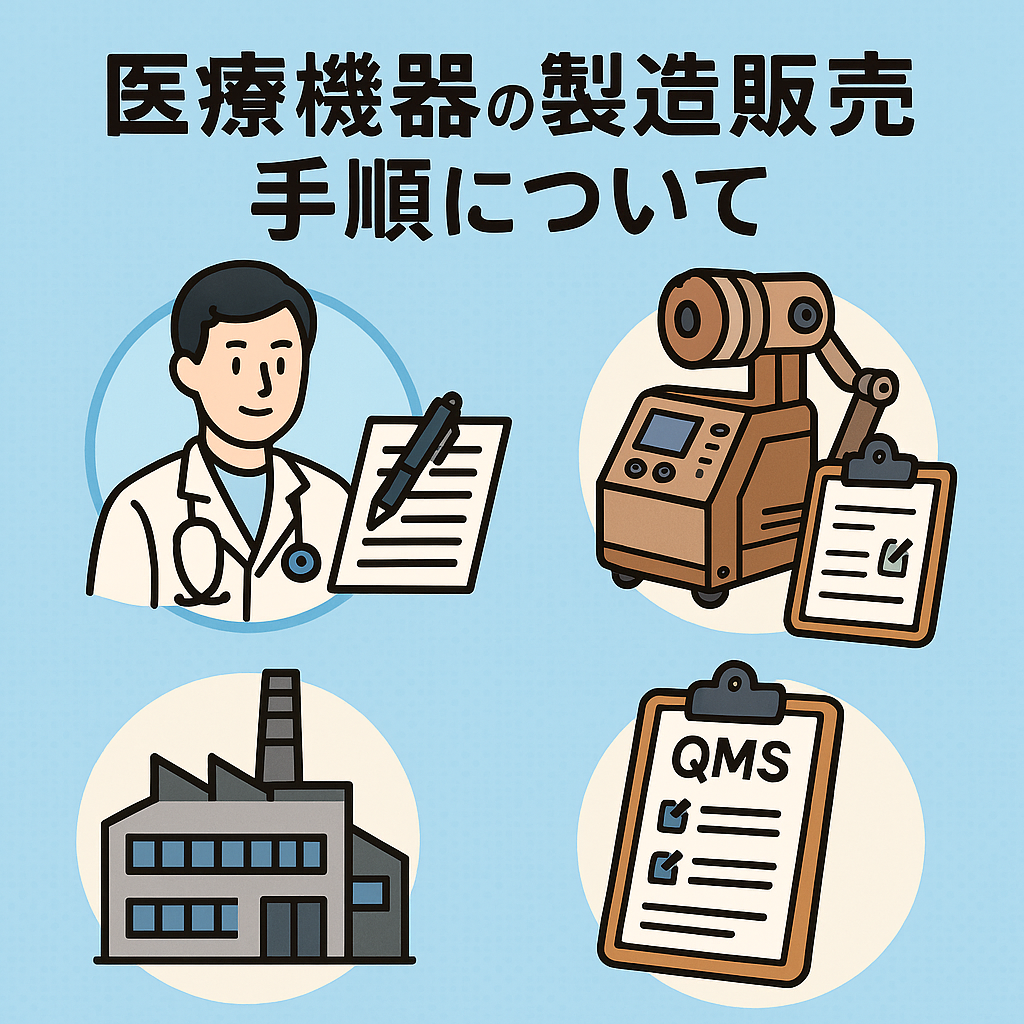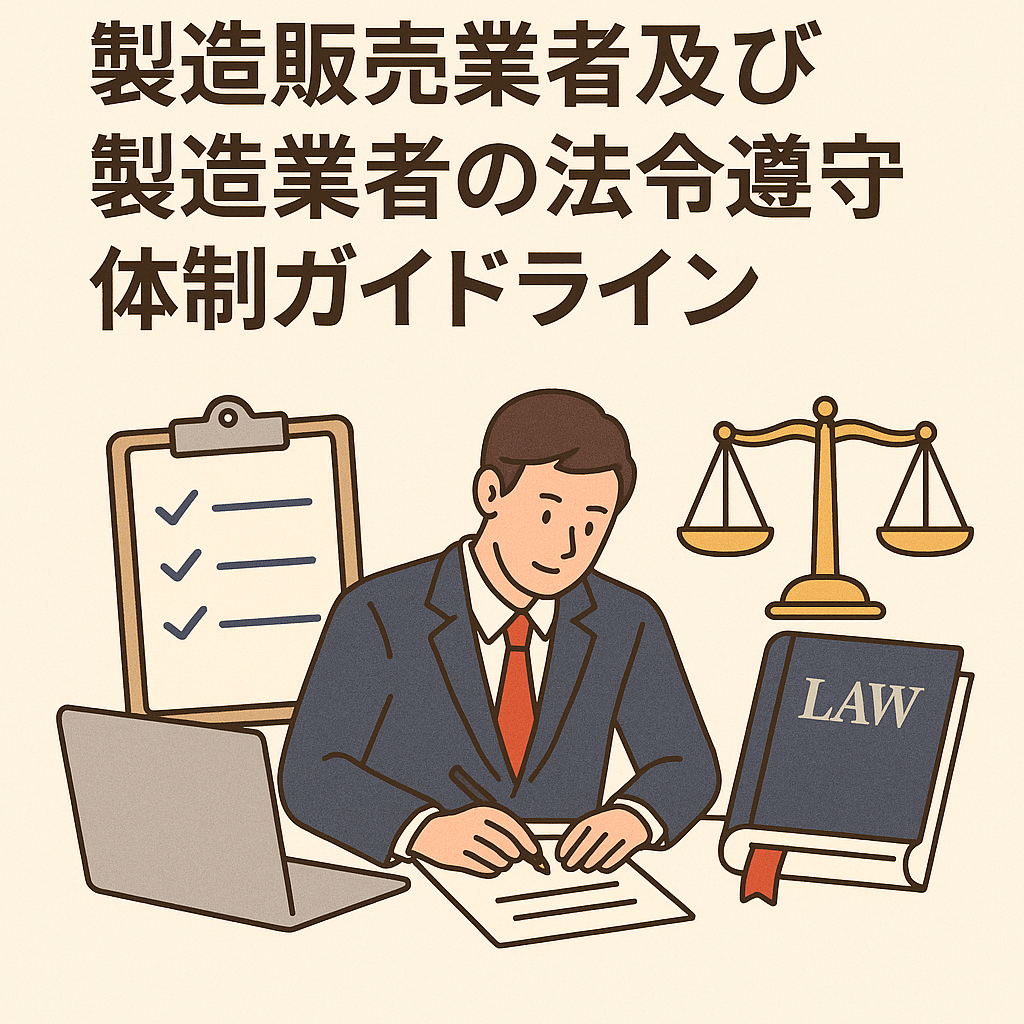概要
平成18年2月23日、厚生労働省医薬食品局審査管理課より、医薬品、医療機器等の製造業の許可等に対する登録免許税の課税について重要な事務連絡が発出されました。この通知は、薬事法に基づく各種許可申請に関する大きな制度変更を含むもので、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売業者や製造業者にとって重要な内容となっています。
今回の改正により、これまで手数料のみで処理されていた各種許可申請が、登録免許税の課税対象となることが決定されました。これは、平成18年1月17日に閣議決定された「平成18年度税制改正の要綱」に基づく改正法案の一環として実施されるもので、薬事法関係の許可等が他省庁所管の法律に基づく個人の資格又は事業の開始に係る登録、免許等と同様の取り扱いを受けることとなりました。この改正は、規制改革の流れの中で、各種許可制度の統一的な運用を図るとともに、適正な受益者負担を求めるものです。
1. 改正の背景と経緯
1.1 税制改正の要綱と改正法案
平成18年1月17日に閣議決定された「平成18年度税制改正の要綱」において、医薬品や医療機器等の製造販売業等に係る登録、免許等について、登録免許税の課税対象とすることが盛り込まれました。この決定を受けて、改正法案が国会に提出され、その中の第35条において登録免許税法の一部改正が規定されることとなりました。
この改正の背景には、他省庁所管の法律に基づく許可等についても登録免許税が課されている現状があり、薬事法関係の許可等についても同様の取り扱いとすることで、制度の整合性を図る狙いがありました。また、これに伴い、従来設定されていた手数料が新規に課税される登録免許税の税額を下回る場合には、当該手数料を廃止することとなり、手数料制度の見直しも同時に行われることとなりました。
1.2 薬事法における許可制度の位置づけ
薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特に必要性の高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。この目的を達成するため、製造販売業や製造業の許可制度が設けられており、これらの許可を取得することで初めて、医薬品等の製造や販売が可能となります。
今回の改正により、これらの許可申請に際して登録免許税が課されることとなりましたが、これは単なる負担増ではなく、許可制度の重要性を改めて認識し、適正な事業運営を促進する意味合いも持っています。
2. 登録免許税が課される許可等の詳細
2.1 対象となる許可等と課税額
改正法案第35条による改正後の登録免許税法第2条及び別表第1第77号において、以下の許可等が登録免許税の課税対象として定められました。
第一種医薬品製造販売業の許可については、1件につき15万円の課税額が設定されました。これは薬事法第12条関係の許可となります。同様に、第二種医薬品製造販売業の許可、医薬部外品製造販売業の許可、化粧品製造販売業の許可、第一種医療機器製造販売業の許可、第二種医療機器製造販売業の許可、第三種医療機器製造販売業の許可についても、それぞれ1件につき15万円の課税額が設定されています。
一方、医薬品製造業の許可、医薬部外品製造業の許可、化粧品製造業の許可については、薬事法第13条関係として、1件につき9万円の課税額となっています。また、医療機器製造業の許可についても同様に1件につき9万円、医薬品等の外国製造業者の認定及び医療機器修理業の許可についても、それぞれ薬事法第13条の3関係、薬事法第40条の2関係として、1件につき9万円の課税額が設定されました。
2.2 変更許可等の取り扱い
改正案においては、変更の許可、許可等の更新の取扱いについても明確に規定されています。許可等の更新については、登録免許税は課されないこととなっており、これは事業継続性への配慮から設けられた措置です。一方、区分の追加や変更については、それぞれの区分の変更のために申請する場合と、区分の変更のために申請する場合があり、これらについては登録免許税が課される可能性があります。
また、許可等の更新については、登録免許税は課されないものの、許可等の更新を含む変更の許可を受ける場合は、変更の許可を含むことから、課税対象となることに注意が必要です。
3. 手数料制度の改正と経過措置
3.1 手数料の廃止
登録免許税の課税に伴い、これまで設定されていた手数料の額が新規に課税される登録免許税の税額を下回ることから、当該手数料を廃止することとなりました。具体的には、改正法案附則第178条による改正後の薬事法第78条第1項並びに薬事法関係手数料令第1条、第3条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第11条第1項及び第2項関係の手数料が対象となります。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可については、これまで動物用医薬品で2万5千8日円、その他の場合で法第83条第1項において使用される場合以外においては15万円の手数料が設定されていました。また、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可については、動物用医薬品で2万7千3日円、区分の追加で2万6千2日円、その他の場合で9万円の手数料が設定されていました。
3.2 医療機器の修理業の許可
医療機器の修理業の許可については、動物用医薬品で1万9千4日円、区分の追加で1万9千4日円、その他の場合で9万円の手数料が設定されていました。また、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の外国製造業者の認定についても、動物用医薬品で2万7千3日円、区分の追加で2万6千2日円、その他の場合で9万円の手数料が設定されていました。これらの手数料は、登録免許税の導入に伴い廃止されることとなります。
3.3 施行期日及び経過措置
改正法の施行期日については、平成18年4月1日以降に許可等が行われる場合から適用されることとなりました。ただし、薬事法に規定する許可等に対し、上記第2に掲げるとおり登録免許税が課税され、手数料に関しては、改正後の薬事法関係手数料令の規定が適用される原則があります。
一方、経過措置として、平成18年1月1日より前に申請が行われ、平成18年4月1日から5月31日までの間に許可等が行われる場合は、薬事法に規定する許可等に対し、上記第2に掲げる登録免許税は課税されず、手数料に関しては、改正前の薬事法関係手数料令の規定が適用されることとなりました。この例外措置は、制度移行期における事業者への配慮として設けられたものです。
また、平成18年1月1日より前に申請が行われ、平成18年5月31日より後に許可等が行われる場合は、薬事法に規定する許可等に対し、上記第2に掲げるとおり登録免許税が課税され、手数料に関しては、改正後の薬事法関係手数料令の規定が適用されることとなりました。
4. 税制改正による事業者への影響と対応
4.1 費用負担の変化
今回の税制改正により、医薬品や医療機器等の製造販売業者及び製造業者にとって、許可申請に係る費用負担の構造が大きく変化することとなりました。従来の手数料制度から登録免許税制度への移行により、課税額が明確化され、統一的な基準での負担となることが特徴です。
製造販売業の許可については15万円、製造業や修理業の許可については9万円という課税額は、事業規模や業態によって負担感が異なることが予想されます。特に、複数の区分での許可を必要とする事業者にとっては、初期投資としての負担が増加する可能性があります。
4.2 申請手続きの留意点
新制度下での申請手続きにおいては、登録免許税の納付方法や時期について十分な理解が必要となります。税の納付が許可の要件となることから、申請準備段階での資金計画も重要となってきます。また、経過措置の適用を受ける場合には、申請時期と許可時期の関係を正確に把握し、適切な対応を取ることが求められます。
事業者においては、この制度変更を機に、許可申請に関する社内体制の見直しや、税務処理の適正化を図ることが重要です。特に、登録免許税は税法上の取り扱いとなることから、会計処理においても適切な対応が必要となります。
まとめ
平成18年度の税制改正により導入された医薬品・医療機器等の製造業許可等に対する登録免許税制度は、薬事行政における重要な制度変更となりました。この改正は、他省庁所管の許可制度との整合性を図るとともに、適正な受益者負担を実現することを目的としています。
製造販売業の許可については1件につき15万円、製造業や修理業、外国製造業者の認定については1件につき9万円という明確な課税額が設定され、従来の手数料制度は廃止されることとなりました。施行期日は平成18年4月1日からとされましたが、申請時期によって経過措置が設けられており、事業者への配慮も図られています。
医薬品や医療機器等の製造販売業者及び製造業者においては、この制度変更を正確に理解し、適切な対応を取ることが求められます。特に、新規参入を検討している事業者や、複数の許可区分を必要とする事業者にとっては、初期投資計画の見直しが必要となる可能性があります。また、税務処理の観点からも、登録免許税の適正な会計処理が求められることとなります。
今後、この制度が定着していく中で、許可制度の運用がより透明性の高いものとなり、医薬品・医療機器産業の健全な発展に寄与することが期待されます。事業者においては、制度の趣旨を理解し、コンプライアンスを重視した事業運営を心がけることが、業界全体の信頼性向上につながるものと考えられます。
弊社では、製造販売業・製造業・修理業の許可取得に関する申請支援や、登録免許税制度への対応に関するご相談を承っております。今回の制度改正に伴う具体的な影響や対応方法についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。