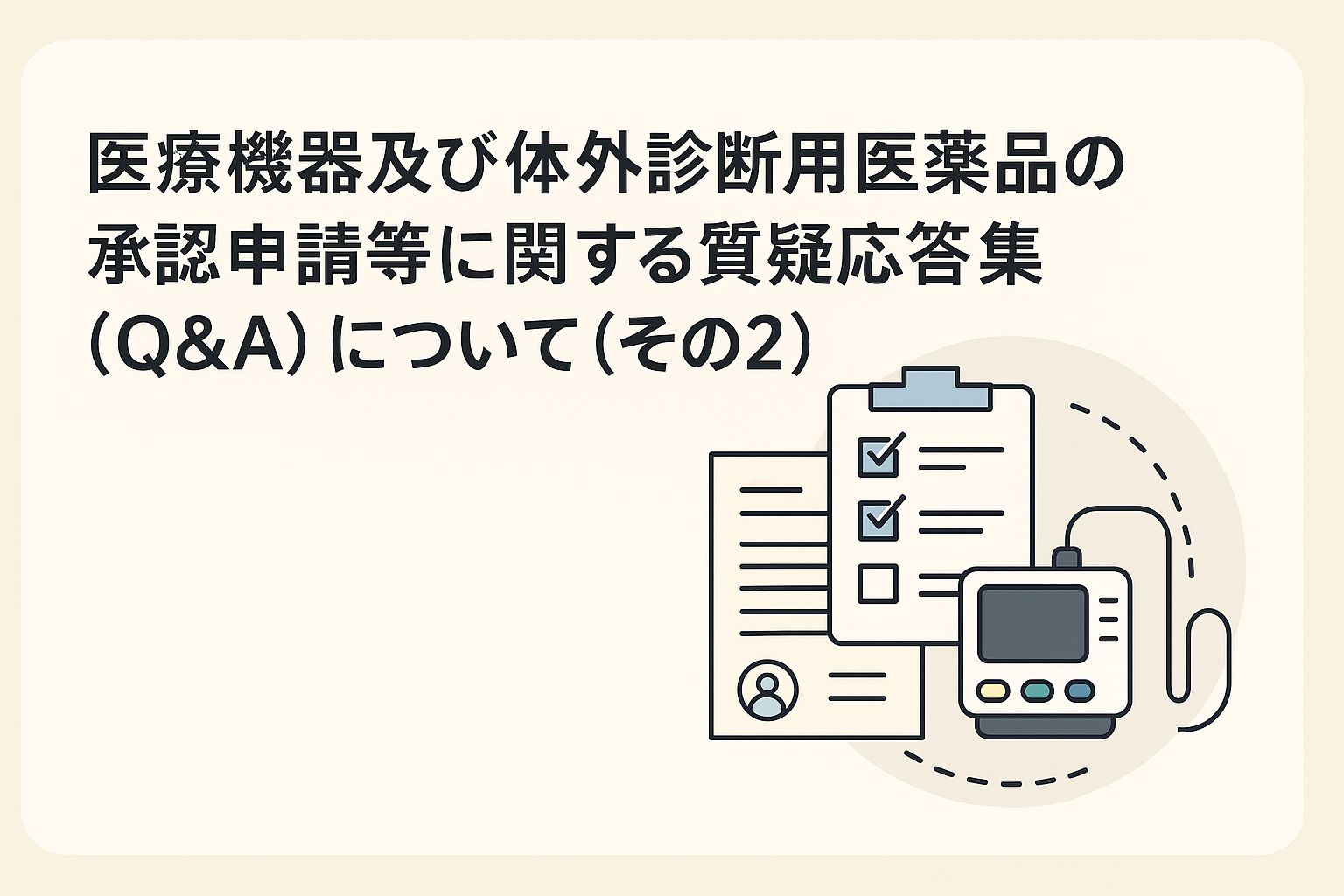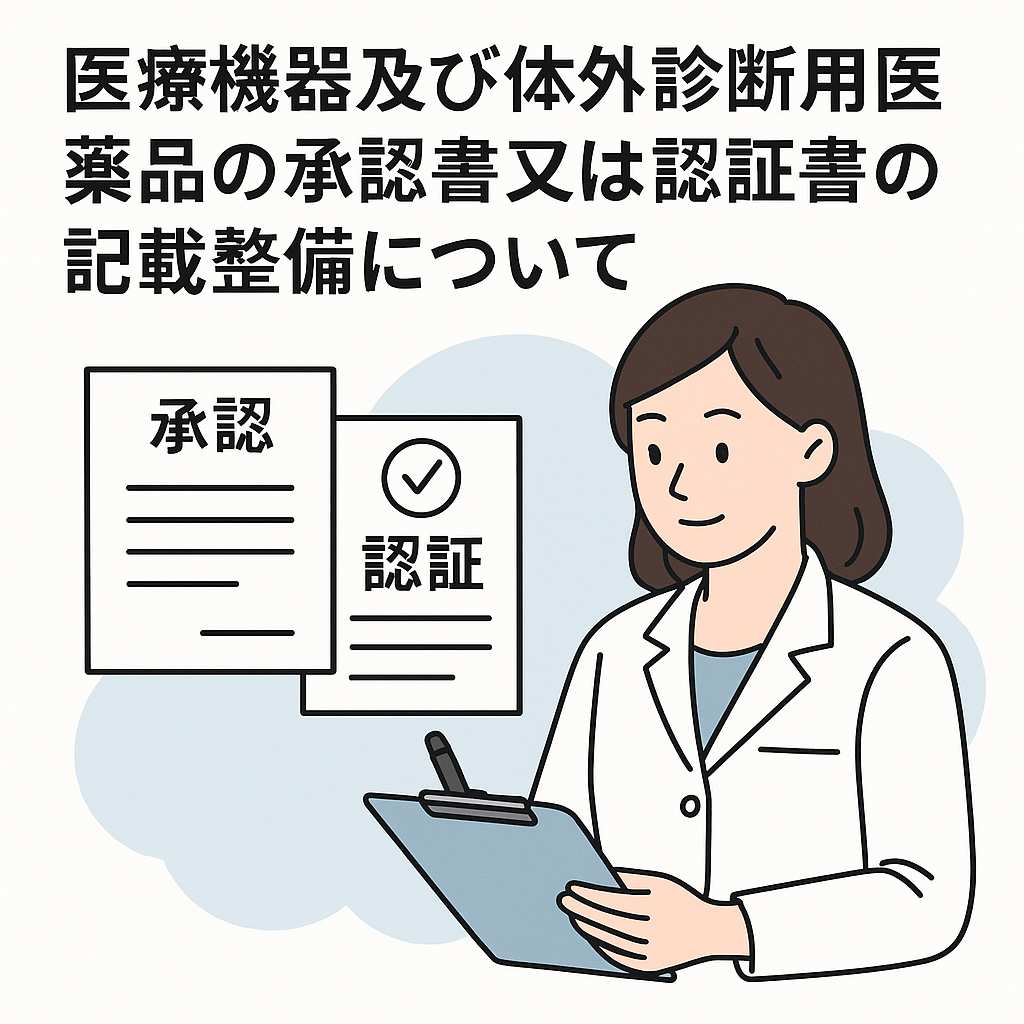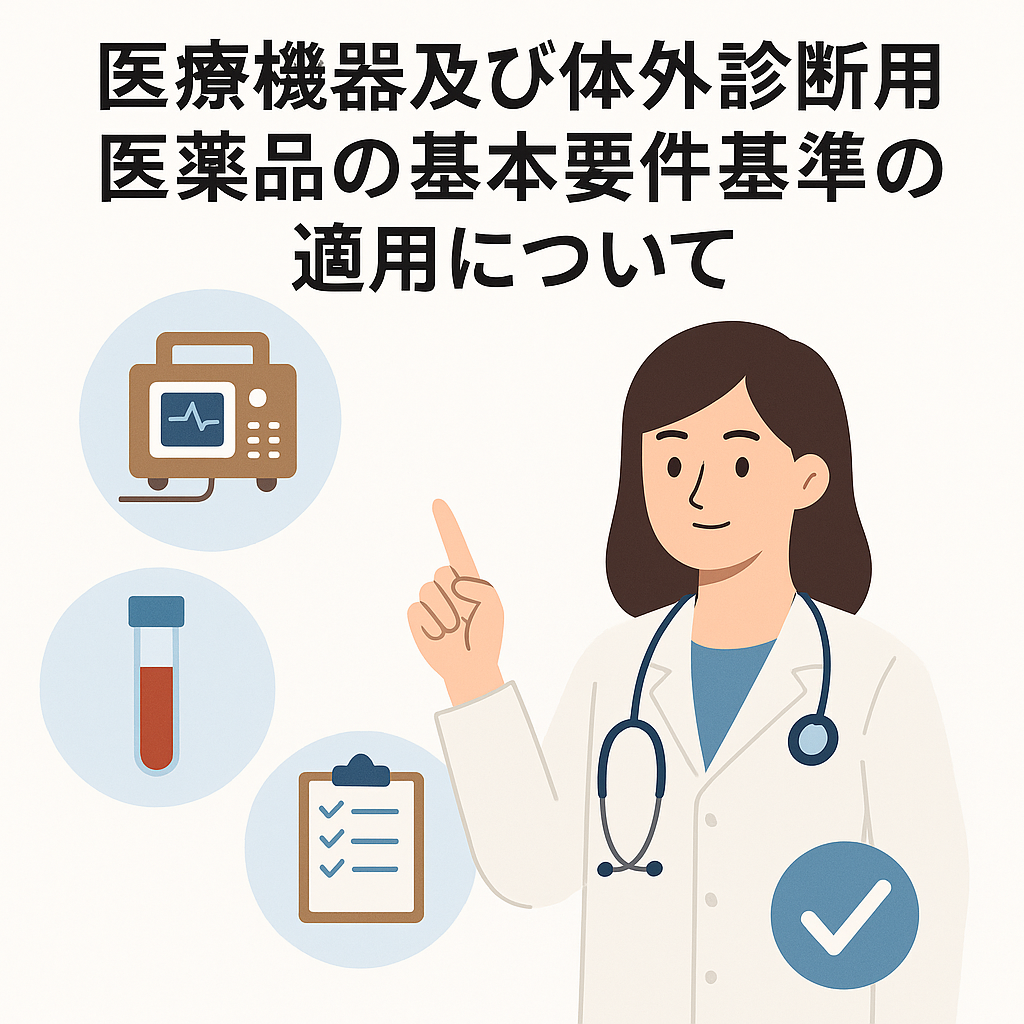概要
平成31年2月1日、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課より、医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する新たな質疑応答集が発出されました。本通知は、医薬品医療機器等法における医療機器・体外診断用医薬品の製造販売承認等の取扱いをより明確にするためのものです。
特に注目すべき点は、製造販売を終了した医療機器本体の構成部品の取扱いについて、具体的な対応方法が示されたことです。医療機器メーカーが本体の製造販売を終了した後も、補充用の構成部品を継続して供給する場合の承認書等の変更手続きが明確化されました。これにより、医療現場への部品供給の継続性が確保され、既存医療機器の保守・維持が円滑に行えることになります。
また、JIS規格等の改正への対応や、構成部品に関する変更手続きの方法についても詳細な指針が示されており、製造販売業者にとって実務上重要な内容となっています。
1. 製造販売終了後の構成部品供給に関する取扱い
1.1 記載整備による対応方法
医療機器本体の製造販売を終了しているものの、単体で医療機器に該当する構成部品のみを補充等のために継続販売する場合、承認書の製造方法欄への適切な記載が必要となります。
具体的には、承認書の製造方法欄に「本体の製造販売は終了し、医療機器たる構成品の製造販売を行う」旨を記載することで対応可能です。この手続きは軽微変更届により行うことができ、承認整理を行う必要はありません。
既に平成26年9月29日付けの通知により記載整備が完了している品目であっても、同様に軽微変更届により対応できることが明確化されました。この取扱いは承認品目だけでなく、認証品目においても同様に適用されます。
1.2 製造所欄の記載について
構成部品のみを製造販売する場合、製造所欄の記載は当該医療機器たる構成部品に係る登録製造所の組合せとすることが求められます。本体に係る製造所の記載は不要となり、製造販売業者は構成部品の製造に必要な製造所のみを管理すればよいことになります。
これにより、本体の製造に関する委託契約が終了し、製造所の登録ができない施設があっても、構成部品の供給を継続することが可能となります。医療現場において必要とされる補充部品の安定供給が確保される仕組みとなっています。
1.3 QMS適合性調査の取扱い
定期のQMS適合性調査については、当該構成部品が管理医療機器又は高度管理医療機器の場合、その一般的名称に該当する製品群区分と、製造所欄に記載した登録製造所の組合せで調査申請を行うことになります。
ただし、有効な基準適合証の交付を受けている場合は、この限りではありません。製造販売業者は、構成部品の品質管理体制を適切に維持し、必要な調査を受けることで、継続的な供給体制を確保することが求められます。
2. JIS規格等への適合性確認
2.1 本体製造販売終了後の規格改正への対応
医療機器本体の製造販売を終了し、構成部品のみを販売している場合、医療機器本体に係る承認、認証基準又は適合性確認において適合が必須とされているJIS規格等が改正されても、改正後の規格への適合性を確認する必要はないことが明確化されました。
これは、既に市場に流通している医療機器の保守・維持を目的とした構成部品供給において、過度な規制負担を避けるための措置といえます。製造販売業者は、既存の規格に基づいて製造された医療機器の構成部品を、そのまま継続して供給することが可能です。
2.2 構成部品に適用される規格の改正
一方で、構成部品に対して直接適用されるJIS規格等が改正された場合には、その適合性を確認する必要があることに留意が必要です。
構成部品そのものの品質や安全性に関わる規格については、最新の規格への適合が求められます。製造販売業者は、構成部品に適用される規格の改正情報を適切に把握し、必要に応じて適合性確認を行う体制を整備する必要があります。
3. 構成部品に係る変更手続き
3.1 変更手続きの基本的な考え方
医療機器本体の製造販売を終了し、構成部品のみを販売している場合であっても、これらの構成部品について承認書等の記載内容に変更が生じた場合には、適切な変更手続きが必要となります。
変更の内容や程度に応じて、軽微変更届または一部変更承認申請のいずれかの手続きを選択することになります。製造販売業者は、変更の影響範囲を適切に評価し、必要な手続きを遅滞なく行うことが求められます。
3.2 参照すべき通知
具体的な変更手続きについては、以下の通知を参照することが示されています。
平成29年7月31日付け薬生機審発0731第5号「医療機器の一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて」では、軽微変更手続きの具体的な取扱いが示されています。
平成20年10月23日付け薬食機発第1023001号「医療機器の一部変更に伴う手続きについて」では、一部変更承認申請が必要となる場合の手続きについて規定されています。
平成25年3月29日付け薬食機発0329第7号「医療機器の原材料の変更手続について」及び平成25年5月29日付け薬食機発0529第4号「医療機器の原材料の変更手続に関する質疑応答集(Q&A)」では、原材料変更に関する詳細な取扱いが示されています。
3.3 変更手続きにおける留意点
製造販売業者は、これらの通知に基づいて適切な変更手続きを行う必要があります。特に、構成部品の品質、有効性及び安全性に影響を与える可能性のある変更については、慎重な評価と適切な手続きが求められます。
また、変更手続きを行う際には、当該構成部品が医療機器本体の製造販売終了後も継続して供給されているものであることを明確にし、必要な情報を適切に記載することが重要です。
4. 実務上の対応ポイント
4.1 承認書等の記載整備の進め方
製造販売業者は、本通知に基づく対応を計画的に進める必要があります。まず、自社が保有する承認・認証品目のうち、本体の製造販売を終了し、構成部品のみを供給している品目を特定することから始めます。
次に、該当する品目について、承認書または認証書の製造方法欄に必要な記載を追加するための軽微変更届を準備します。この際、記載内容が適切であることを確認し、必要に応じて規制当局への事前相談を行うことも検討すべきです。
4.2 品質管理体制の見直し
構成部品のみの供給体制に移行する際には、QMS体制の見直しも必要となります。製造所の組合せの変更に伴い、品質管理監督システムの文書体系や手順書の改訂が必要となる場合があります。
また、定期的なQMS適合性調査に向けた準備も重要です。構成部品に特化した品質管理体制であることを明確にし、調査時に適切な説明ができるよう、関連文書の整備を進める必要があります。
4.3 規格改正への対応体制の構築
JIS規格等の改正情報を適時に把握し、構成部品への影響を評価する体制の構築が重要です。構成部品に直接適用される規格については、改正への対応が必須となるため、規格改正の動向を継続的に監視する仕組みが必要です。
社内に規格管理の責任者を置き、定期的な規格改正情報の確認と影響評価を行う体制を整備することが推奨されます。また、必要に応じて業界団体等からの情報収集も活用すべきです。
まとめ
本通知は、医療機器本体の製造販売終了後も構成部品の供給を継続するための具体的な取扱いを示したものであり、製造販売業者にとって極めて重要な実務上の指針です。承認書の記載整備による対応方法や、製造所欄の記載の考え方、QMS適合性調査の申請方法などが体系的に整理されており、医療機器の保守・維持を支える実務の根幹をなす内容となっています。
さらに、JIS規格改正への対応における重要な留意点として、本体に係る規格改正への適合確認が不要である一方、構成部品に適用される規格については最新基準への適合が求められる点が明確化されています。加えて、軽微変更届や一部変更承認申請などの変更手続きの具体的運用も複数の通知を参照する形で整理されており、現場での手続き実務に直結する内容です。
弊社では、このような構成部品供給に関する承認書・認証書の記載整備、JIS規格改正対応、QMS調査対応、変更手続きの判断・書類作成支援など、豊富な実務経験に基づいたサポートを提供しています。特に、製造販売業者の限られたリソースの中で効率的かつ適正に対応を進めるための戦略的な進め方のご提案も可能です。
構成部品の供給体制や承認書対応、QMS調査、規格改正対応などでお困りの際は、ぜひ弊社までご相談ください。 最新の法令・通知に基づいた実践的な支援を通じて、貴社の法令遵守と事業継続を強力にバックアップいたします。