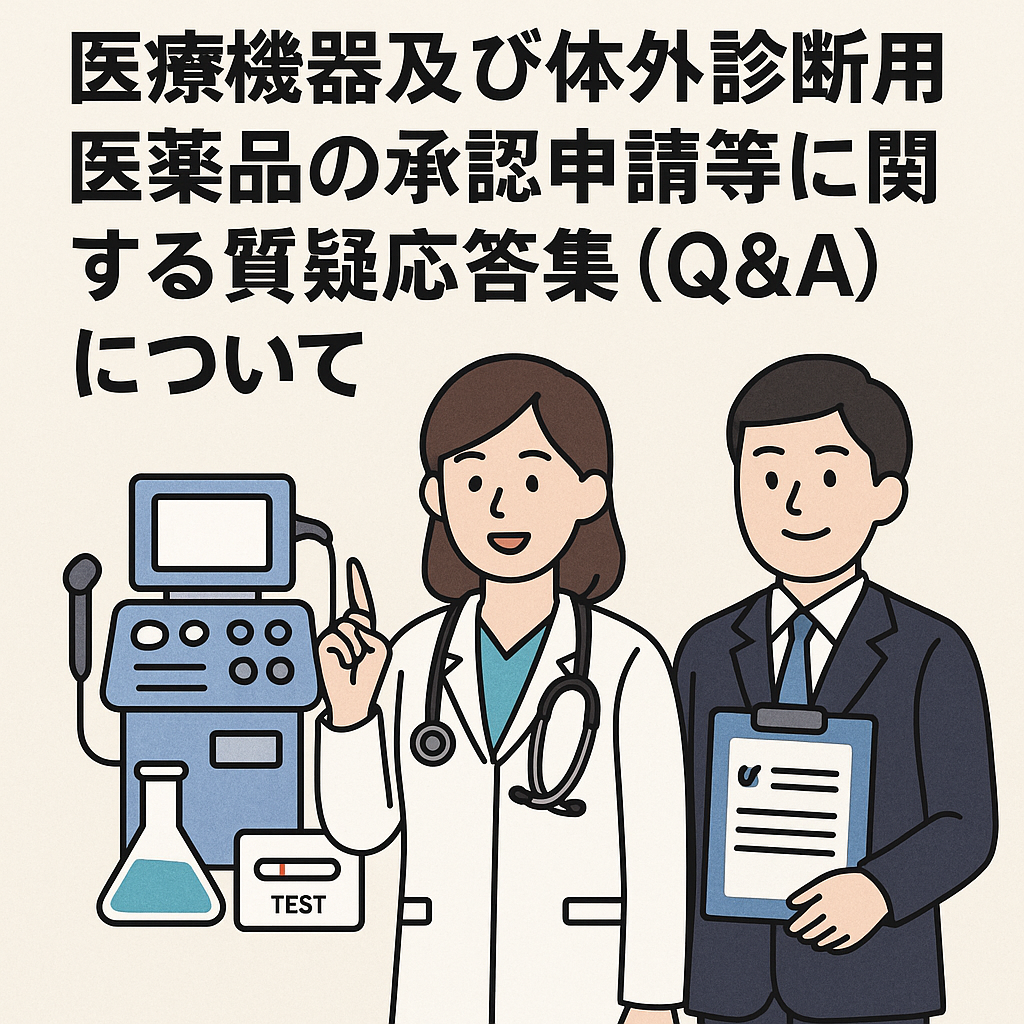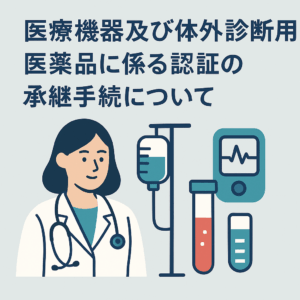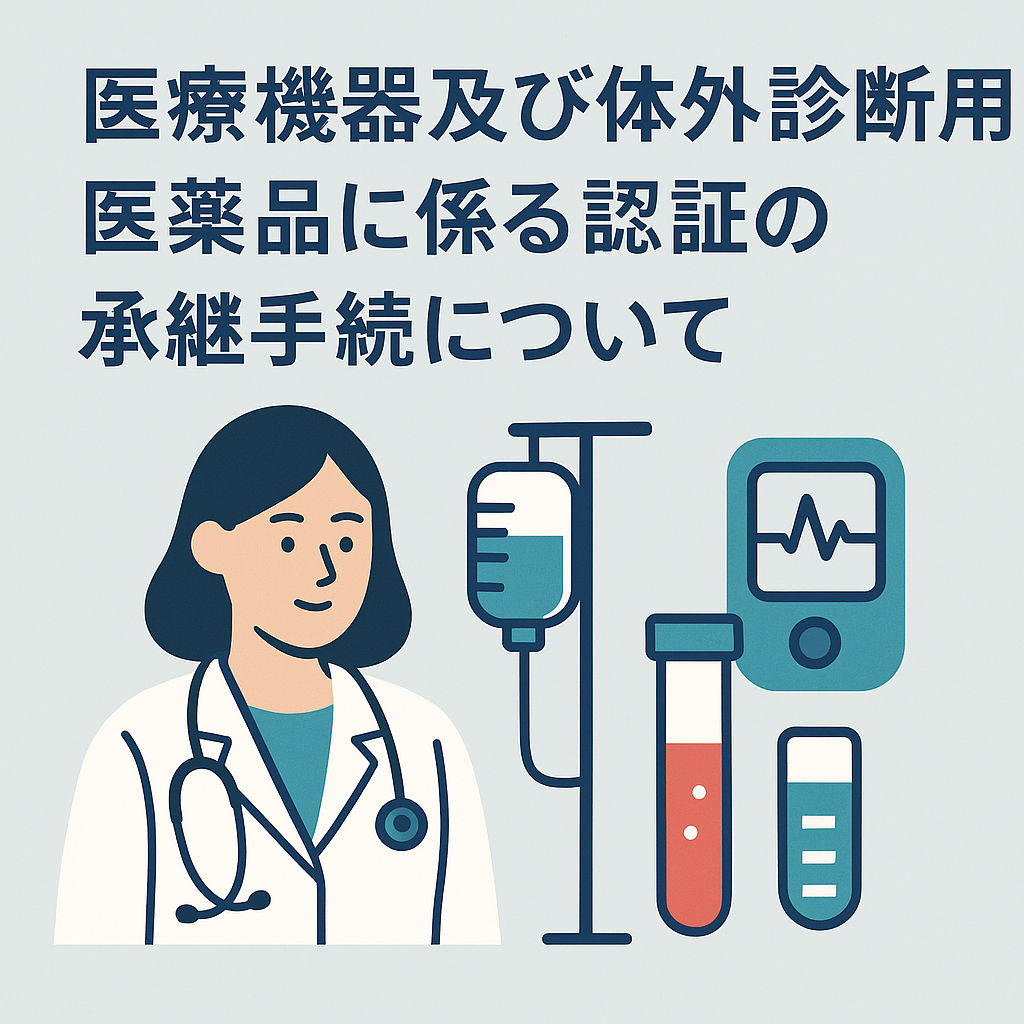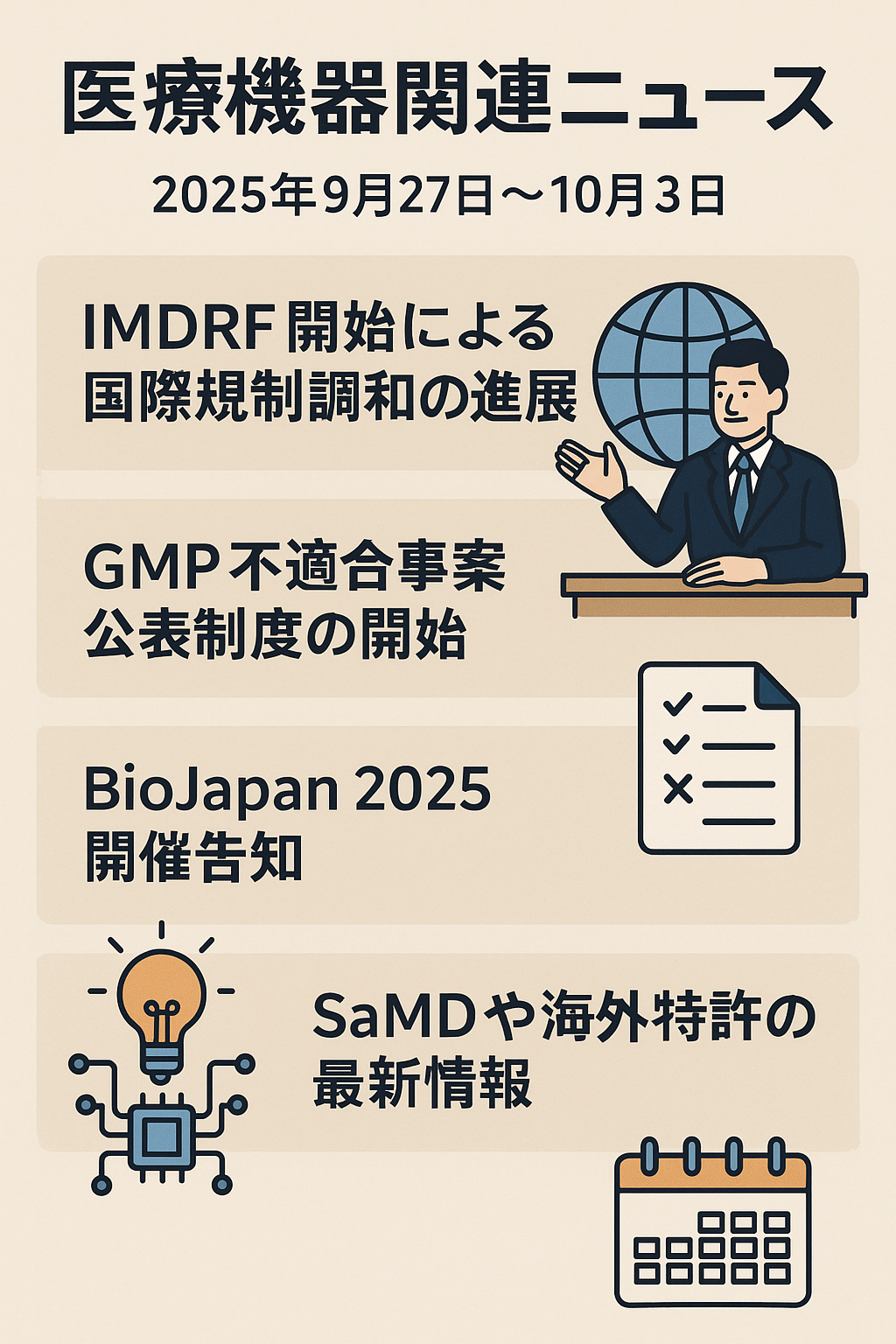概要
平成26年11月25日付けで、厚生労働省から医療機器および体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集が発出されました。これは、平成25年11月27日に公布された薬事法等の一部改正により、従来の薬事法が医薬品医療機器等法へと変更されたことを受けて作成されたものです。
今回の質疑応答集は、新法施行に伴う実務上の疑問点を明確にし、製造販売業者や製造業者が適切に対応できるよう指針を示すものとなっています。特に承認書の記載整備や製造業の登録手続きという、実務上極めて重要な事項について詳細な解説が行われています。新法への円滑な移行を図るため、各業者が押さえるべき重要なポイントが整理されています。
1. 記載整備の基本的な考え方と実務対応
1.1 経過措置対象品目における設計製造所の記載
製品群省令附則第2条第1項に規定される設計管理の適用を受けない経過措置対象品目においても、承認書または認証書の記載整備時には設計に係る製造所の記載が必要となります。QMS省令における設計開発が適用されない品目であっても、設計に係る施設は登録製造所として記載整備が求められます。
特に注意すべき点は、経過措置対象品目であっても、設計に係る施設が新法施行後に登録製造所とみなされない場合です。この場合、改正法附則第6条第1項の規定に基づき、施行日から起算して3か月を経過する日までに登録申請を行う必要があります。
1.2 みなし医療機器製造業者の登録番号と記載方法
改正法附則第4条および第7条により医療機器の製造業の登録を受けたものとみなされる者の登録番号については、改正前の許可番号または認定番号とすることとされています。FD申請様式の製造販売する品目の製造所欄の登録年月日欄には、登録製造業者としてみなされた日である平成26年11月25日を記載します。
登録更新後は、更新後の有効期間の始期を記載することになります。これは、フレキシブルディスク申請等の取扱いについての通知において、登録年月日欄には有効期間の始期を記録することとされているためです。
1.3 製造所情報の具体的な記載方法
同一の製造所で複数の製造工程を行っている場合の記載方法について、具体例が示されています。設計、主たる組立て、滅菌(EOG)、滅菌(放射線)の工程を同一製造所Aで行っている場合、製造販売する品目の製造所欄にはすべての工程を列記します。
滅菌方法が放射線またはその他である場合は、製造方法欄に滅菌方法を具体的に記載することが求められます。ガンマ線、電子線、プラズマガスなど、実際の滅菌方法を明確に記載する必要があります。
2. 製造方法欄の記載における留意事項
2.1 工程情報の記載の必要性
記載整備通知では、各工程の関係について誤認が生じない場合においては、工程ごとの記載や工程に関する情報は原則として記載しなくてもよいとされています。しかし、製造販売する品目の製造所欄で記載されている内容を補足する必要がある場合等においては、製造方法欄に工程に関する情報等が必要になる場合があります。
このような場合、表を用いて説明することが可能です。例えば、各工程に係る登録製造所が複数ある場合や、滅菌製造所ごとに滅菌方法が異なる場合、構成品の詳細を記載する必要がある場合などが該当します。
2.2 既存承認品目の取扱い
整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る承認基準に基づき承認に移行した品目について、製造方法欄の記載が従前のとおりとなっている場合、記載整備の際に新たに詳細を記載する必要はありません。ただし、製造販売する品目の製造所欄においては、記載整備通知に基づいた記載が必要です。
滅菌されない品目であって、製品の使用目的、性能等が影響を受ける製造加工条件がない場合など、製造方法欄に特に記載すべき事項がない品目においては、製造方法欄を空欄にすることも認められています。
3. 製造所の登録手続きと運用
3.1 定期QMS調査と登録更新のタイミング
旧法により承認または認証を受けている品目が定期のQMS調査を受ける前に旧法による製造所の許可または認定の有効期限を迎える場合、当該製造所が新法において登録すべき製造所に該当するときは、旧法による許可または認定の有効期限内に登録更新の手続きを行う必要があります。
製造販売業者において登録すべき製造所を検討する際に疑義がある場合は、新法による定期のQMS調査申請を行う調査実施者に照会することが推奨されています。
3.2 記載整備届出のタイミング
新法施行後であれば記載整備届出は可能ですが、登録すべき製造所の登録手続きを完了させた上で対応する必要があります。特に設計に係る製造所等については、事前の登録が必須となります。
記載整備届出時期については、定期のQMS調査によって当該品目の製造販売する品目の製造所欄に記載すべき製造所が特定できるため、新法によるQMS調査を経た後に記載整備を行うことが望ましいとされています。これにより、基準適合証の内容に一致した記載整備届出が可能となります。
3.3 既存品目の継続的管理
既に製造販売していない品目について、製造に関する委託契約が終了しているために製造所の登録ができない施設がある場合、原則として承認整理することとされています。ただし、承認整理後であっても、製造販売した品目に対する不具合報告、回収等の規定の遵守については、製造販売業者は引き続き責務を有します。
医療機器本体の製造販売を終了している品目のうち、単体で医療機器に該当する構成部品のみを補充等のために販売している場合には、特別な取扱いが定められています。この場合、承認整理等を行わず、承認書の記載整備を行い、製造方法欄に本体の製造販売は終了し、医療機器たる構成品の製造販売を行う旨を記載することになります。
4. 外国製造所の登録における特例措置
4.1 責任技術者の資格証明
新施行規則第114条の9第2項第4号の規定により、医療機器責任技術者の資格を証する書類が求められていますが、設計に係る製造所の責任技術者については、登録申請書において責任技術者の氏名等が記載されるため、別途責任技術者であることを証する書類の添付は不要とされています。
FD申請様式を利用して責任技術者の資格を選択する場合には、施行規則第114条の53第1項第4号を選択した上で、備考欄に根拠となる条項を記載する必要があります。
4.2 外国製造所の図面提出要件
外国製造所の登録申請において添付すべき資料のうち、登録を受けようとする製造所を明らかにした図面に関して、詳細な内容を記載した図面が入手できない場合があります。この場合、外国製造所に限り、敷地内の登録対象となる範囲が分かるものであれば、航空写真、建物全景の写真、敷地の外国道路名を記載した周囲の状況が分かる製造所付近の道路内の概略図でも差し支えないとされています。
4.3 情報公開
新法の施行に伴い、外国製造業者の登録に関する情報を機構のホームページで公開する予定であることが明記されています。これにより、旧法による製造所の認定を受けた外国製造所と同様に、登録番号等の情報へのアクセスが可能となります。
5. 複数施設の統合管理
5.1 同一施設における複数許可の取扱い
国内の同一の施設で複数の製造業の許可番号を有している場合、例えば医療機器一般区分と医療機器保管等区分の許可で別の許可番号を有している場合、登録更新については一つの登録製造所として行うことになります。その際の登録期限については、最も長い許可の期限となります。
みなし登録製造所のうち有効期間の短い製造業許可の取扱いについては、登録権者に相談の上、速やかに廃止届を提出することとし、その備考欄に整理の旨を記載します。登録番号については、みなし登録期限に関わらず、任意の許可番号を選択して差し支えありませんが、新法における国内の製造所の登録権者は都道府県知事であることを踏まえ、旧法の一般区分の製造業許可番号を選択することが望ましいとされています。
5.2 清浄環境における製造工程の委託
旧法により承認または認証を受けている品目で、滅菌を行う前の清浄環境における工程を主たる組立てに係る製造所で行っている場合、この清浄環境における製造工程の一部が他の製造所に委託されることになったときの取扱いが明確化されています。当該工程を委託する製造販売業者または登録製造業者のQMSにおいて当該製造所を適切に管理している場合においては、登録は不要となります。
まとめ
本質疑応答集は、薬事法から医薬品医療機器等法への移行に伴い、承認申請・記載整備・製造所登録といった実務上の重要な手続きを明確化するために作成されたものです。経過措置対象品目の設計製造所記載、製造方法欄の記載方針、外国製造所の特例措置、複数許可の統合管理など、製造販売業者・製造業者が押さえるべき実務ポイントが網羅的に整理されています。
また、定期QMS調査との連動や、記載整備届出の最適なタイミング、既存品目の承認整理の考え方など、現場で直面しやすい手続き上の課題に対する具体的な対応方針も示されています。これらを適切に理解し、承認書や登録情報を正確に整備することは、今後の行政対応や査察への円滑な備えにも直結します。
一方で、経過措置品目や外国製造所の登録対応など、個別のケースで判断に迷う実務も少なくありません。 弊社では、記載整備届出の作成支援、製造所登録手続き、複数許可の整理、外国製造所の特例対応など、新制度移行に関する幅広い実務支援を行っています。自社での対応に不安がある場合や、具体的な運用の確認を希望される場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。