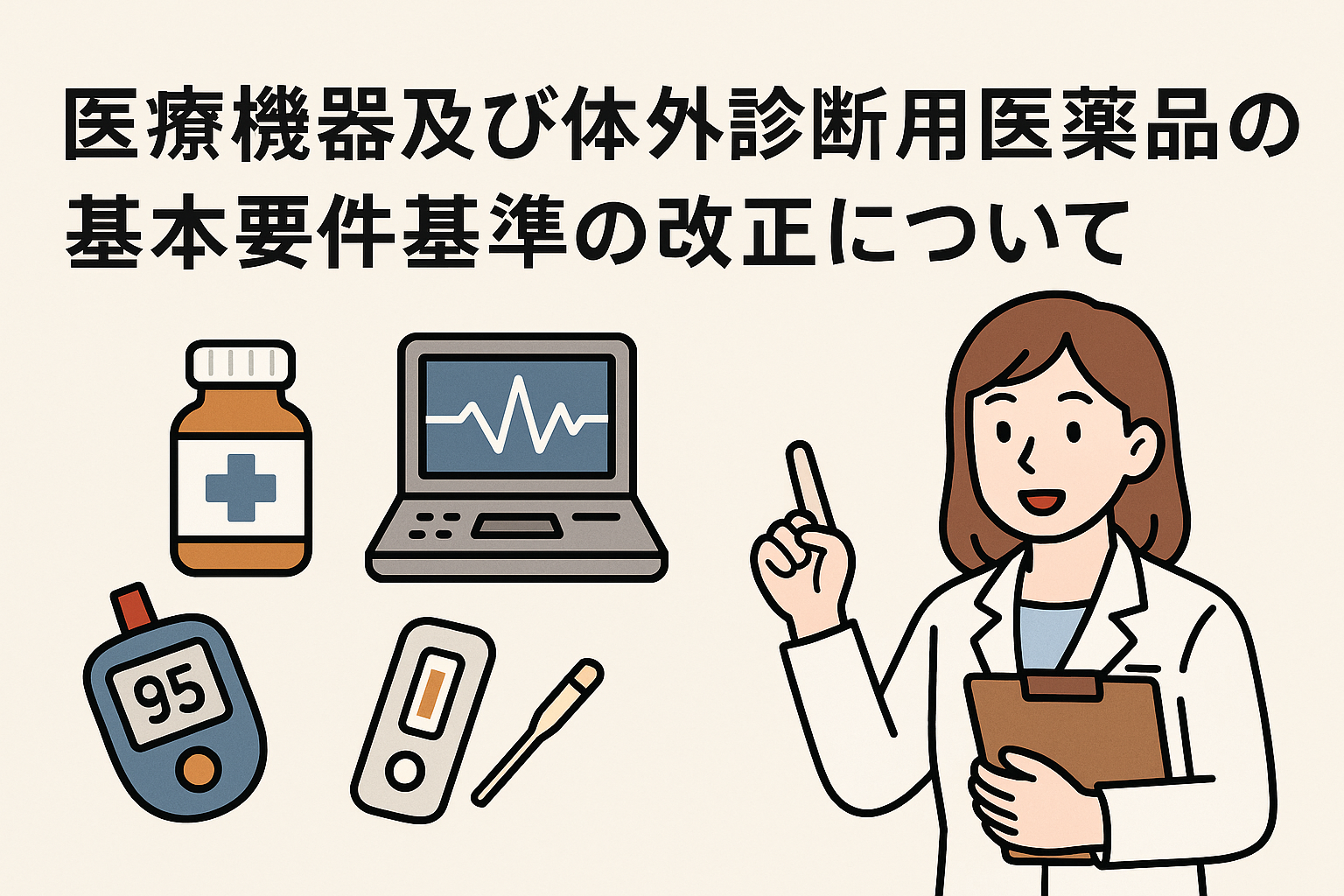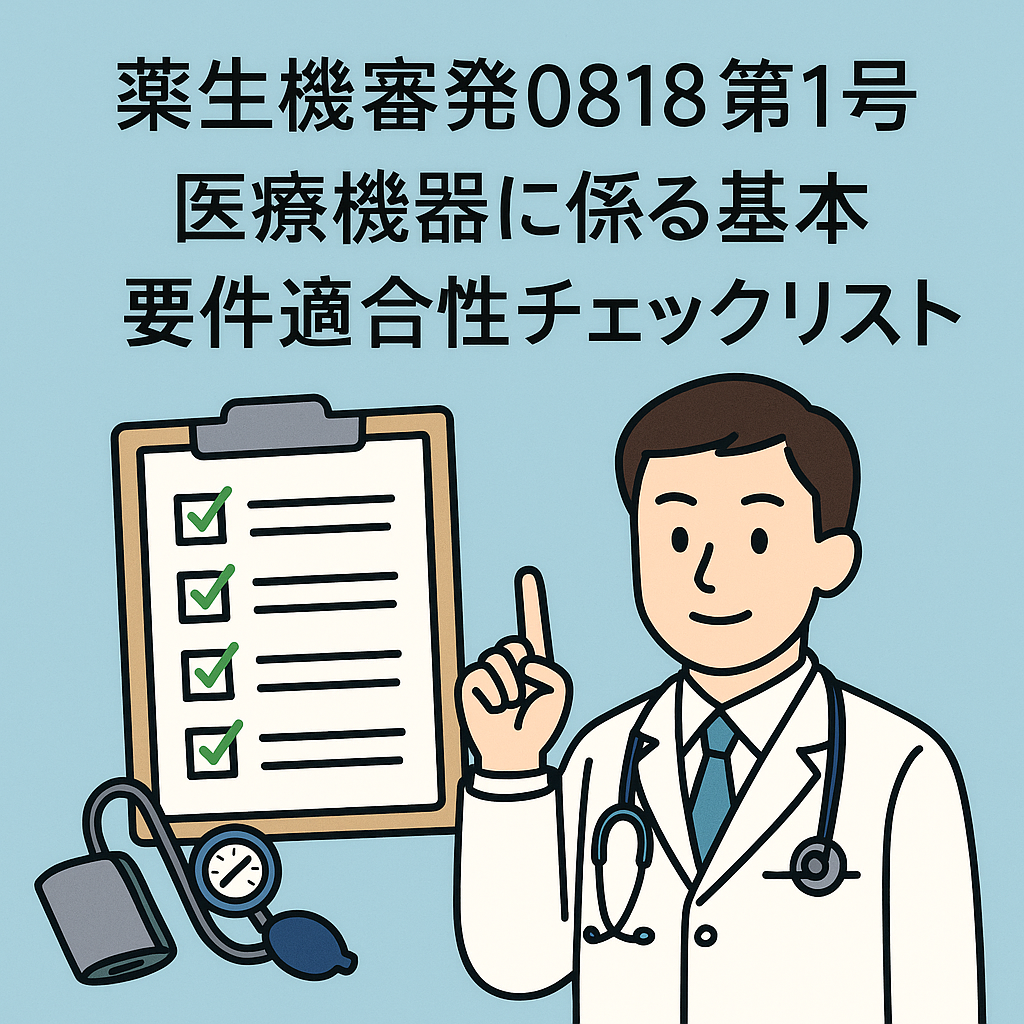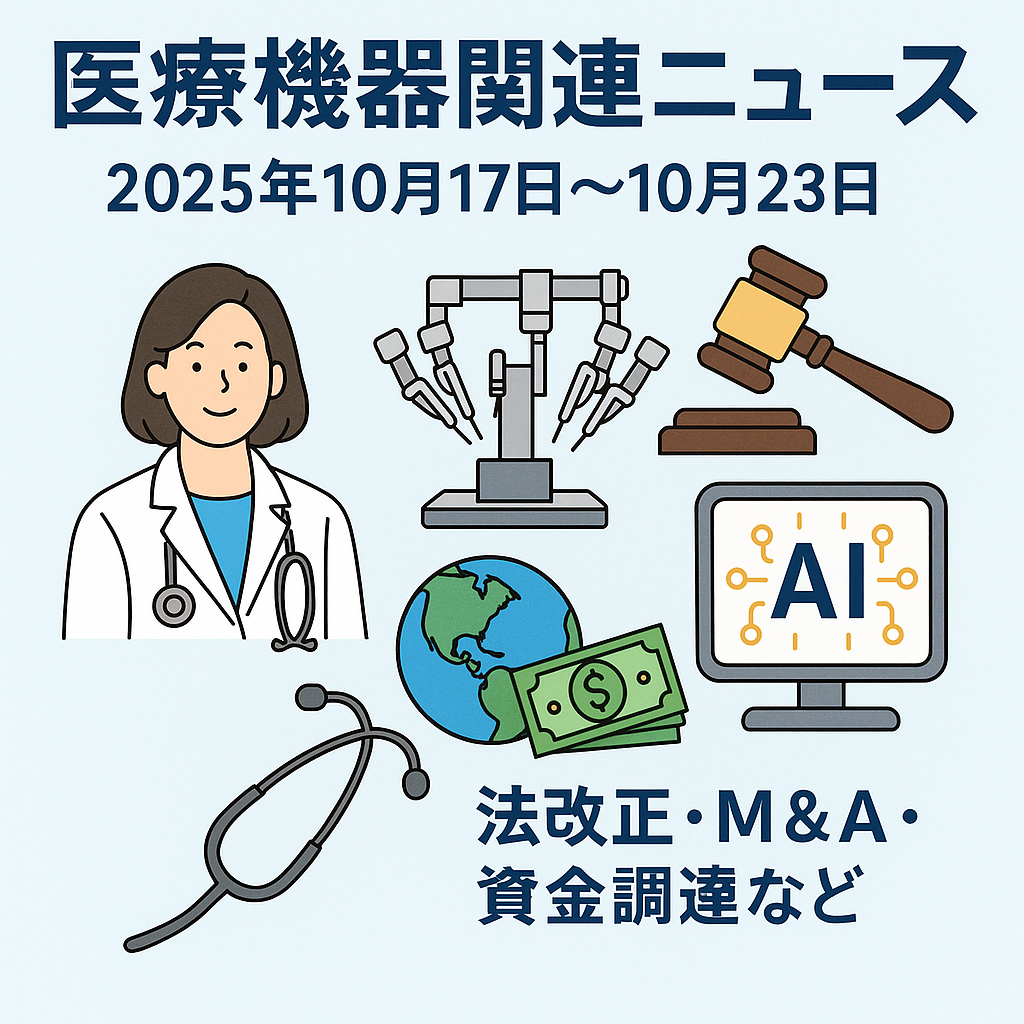概要
平成26年11月5日付けで厚生労働省から発出された「薬食機参発1105第5号」は、医療機器及び体外診断用医薬品の基本要件基準の改正に関する重要な通知です。本通知は、薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴い、医療機器と体外診断用医薬品に適用される新しい基本要件基準の取扱いを定めたものです。
この改正により、医療機器プログラムの取扱いが明確化され、一般使用者が使用する医療機器への配慮事項が追加されるなど、医療機器の安全性と有効性を確保するための要求事項が更新されました。新基本要件基準は平成26年11月25日から適用開始となり、既存の医療機器については平成29年11月24日までの経過措置期間が設けられています。
製造販売業者は、承認申請や認証申請の際に新基本要件基準への適合性を示す必要があり、各要求事項への適用または不適用を適切に判断し、その根拠を規準文書等に基づいて示すことが求められています。
1. 医療機器の新基本要件基準における主要な改正内容
1.1 設計及び製造等に係る配慮事項の明確化
医療機器の設計及び製造において、使用者の専門的知識の程度を考慮した配慮が必要となりました。特に、必ずしも専門的知識を要しない医療機器を一般使用者が使用する場合への配慮が明確化され、想定される使用者の知識レベルに応じた設計が求められています。
これは、医療機器の使用者層が医療従事者から一般使用者まで幅広くなっている現状を反映した改正であり、使用者の安全性を確保する上で重要な要素となっています。
1.2 使用環境に対する配慮の強化
医療機器が他の医療機器、体外診断用医薬品、その他の装置と併用される場合の要求事項が追加されました。具体的には、すべての装置等と安全に接続され、それぞれの性能が損なわれないようにすることが求められています。
また、接続部の設計においては、液体やガスの移送のための接続部、機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑える設計及び製造が必要です。使用上の制限事項がある場合は、医療機器の添付文書またはその容器、被包への記載が義務付けられています。
1.3 プログラムを用いた医療機器に対する配慮
医療機器プログラム及びこれを記録した記録媒体たる医療機器に関する要求事項が新設されました。システムの再現性、信頼性、性能の確保が求められ、故障発生時の危険性を適切に除去または低減する手段の実装が必要です。
さらに、最新の技術に立脚した開発ライフサイクル、リスクマネジメント、確認及び検証の方法を考慮した品質及び性能の検証が実施されなければならないことが明記されています。これにより、プログラム医療機器の品質確保がより体系的に行われることが期待されます。
2. 体外診断用医薬品の新基本要件基準の改正内容
2.1 設計及び製造における配慮
体外診断用医薬品においても、医療機器と同様に、一般使用者が使用する場合への配慮が明確化されました。使用すると想定される者の専門的知識の程度を考慮した設計及び製造が求められています。
これは、自己血糖測定器や妊娠検査薬などの一般用体外診断用医薬品が普及している現状を踏まえた改正であり、使用者の安全性確保に重要な役割を果たします。
2.2 使用環境への配慮事項
他の医療機器、体外診断用医薬品、その他の装置等と併用される場合の安全性確保が求められています。それぞれの性能が損なわれないような配慮が必要であり、使用上の制限事項がある場合は、添付文書やその容器、被包への記載が義務付けられています。
2.3 情報提供の充実
製造販売される際には、使用者の訓練及び知識の程度を考慮し、添付文書等により必要な情報を容易に理解できるように提供することが求められています。これには、製造販売業者名、安全な使用方法、性能を確認するために必要な情報が含まれます。
3. 経過措置の適用と移行期間
3.1 既存医療機器の取扱い
新基本要件基準の適用前に承認、認証を受けた医療機器、または届出された医療機器については、平成29年11月24日までの間、従前の例によることができます。ただし、新基本要件基準への適合を確認した上で変更の手続きが必要な場合は、適合性に関する資料の添付が必要です。
平成29年11月25日以降は、新基本要件基準への適合を示す資料を求めに応じて提示できるよう準備しておくことが求められています。
3.2 審査中の医療機器等の取扱い
新基本要件基準の適用の際に承認または認証審査中の医療機器については、平成29年11月24日までの間は従前の例によることができます。ただし、平成29年11月25日以降に承認または認証の処分がなされた場合は、速やかに新基本要件基準への適合性を確認し、必要に応じて変更の手続きを行う必要があります。
3.3 プログラム医療機器の特別な取扱い
プログラム医療機器については、平成26年11月25日から新基本要件基準が直ちに適用されます。これは、薬事法改正によりプログラム医療機器が新たに医療機器として位置づけられたことによるものです。
4. 基本要件基準への適合性確認における実務上の留意点
4.1 適合性評価の判断基準
基本要件基準への適合性を示す際は、各要求事項への適用または不適用を明確に判断する必要があります。適用と判断する場合は、日本国内の法令、告示、通知及び規格に基づいて根拠を示し、不適用と判断する場合は、その妥当な説明を提示する必要があります。
既に通知されている承認基準及び認証基準に係るチェックリストは、新基本要件基準への適合性判断の参考として使用可能です。
4.2 新旧基本要件基準の対応関係
通知には、医療機器及び体外診断用医薬品それぞれについて、新旧基本要件基準の対応表が別添として示されています。多くの項目では、旧基本要件基準への適合において適切な確認がされていれば、同様の判断とすることで差し支えないとされています。
ただし、プログラム医療機器に関する項目や一般使用者への配慮に関する項目など、新設された要求事項については、新たに適合性の確認が必要です。
4.3 併用に関する解釈
新基本要件基準における「併用」とは、医療機器または体外診断用医薬品の使用において、他のものと意図して組み合わせて使用することを示しています。この概念の明確化により、複数の機器や薬品を組み合わせて使用する場合の安全性確保がより具体的に求められることになりました。
まとめ
令和26年の「薬食機参発1105第5号」により、医療機器および体外診断用医薬品の基本要件基準が大幅に改正されました。今回の改正では、プログラム医療機器の取扱いが明確化され、一般使用者への配慮や使用環境の安全性確保など、実務上の対応が求められる項目が追加されています。これにより、製造販売業者や開発者は、従来よりも厳格かつ実践的な適合性評価を行う必要があります。
新しい基本要件基準への対応では、経過措置期間中の既存製品への対応方針の整理や、承認・認証申請書類の見直し、プログラム医療機器のリスクマネジメント文書整備など、具体的な準備が欠かせません。適用可否の判断や関連JIS・ISO規格との整合性を確認し、文書化して示すことが審査でのポイントとなります。これらを怠ると、承認手続や市場出荷の遅延につながる可能性があります。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、今回の改正内容に基づく基本要件チェックリスト整備、適合性評価書作成支援、QMS文書改訂支援などを専門的にサポートしています。貴社製品が新要件に該当するかの判定や、PMDA提出資料の整備に関するご相談も承ります。