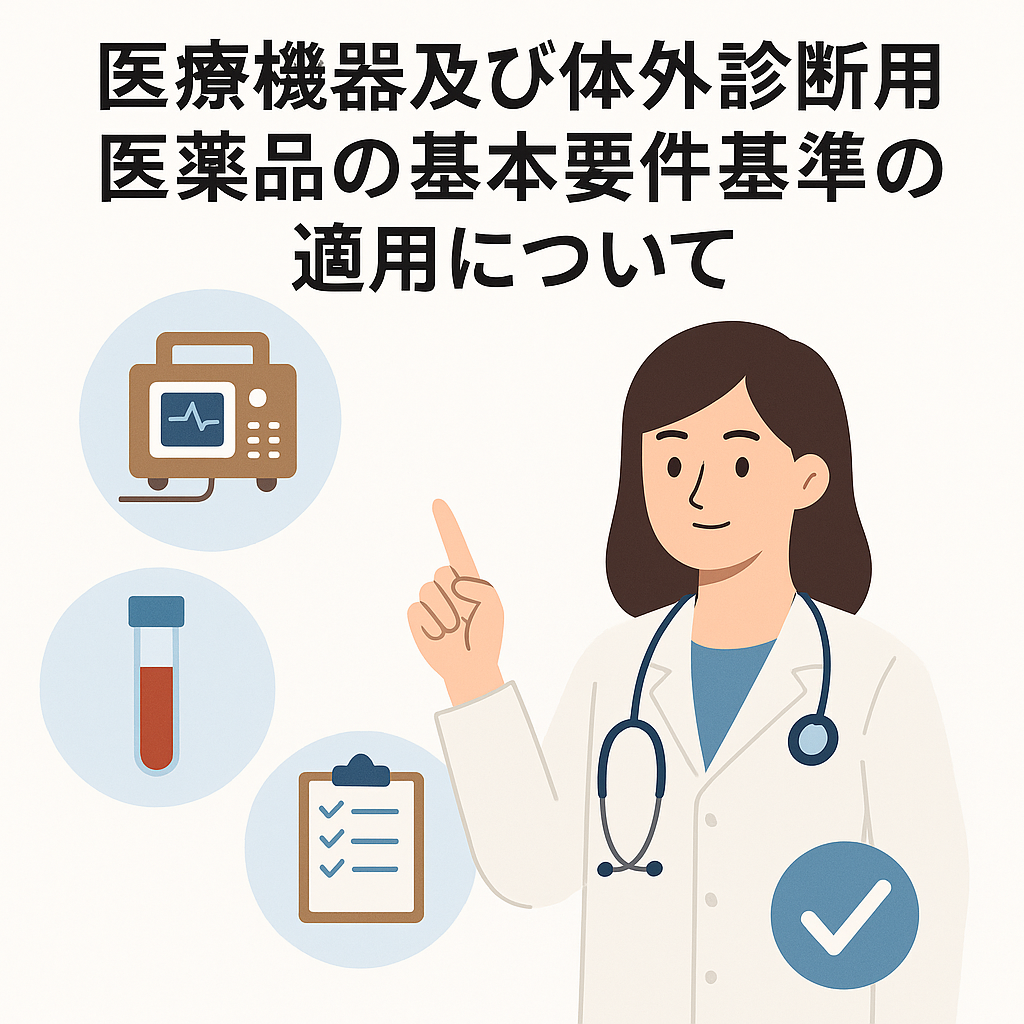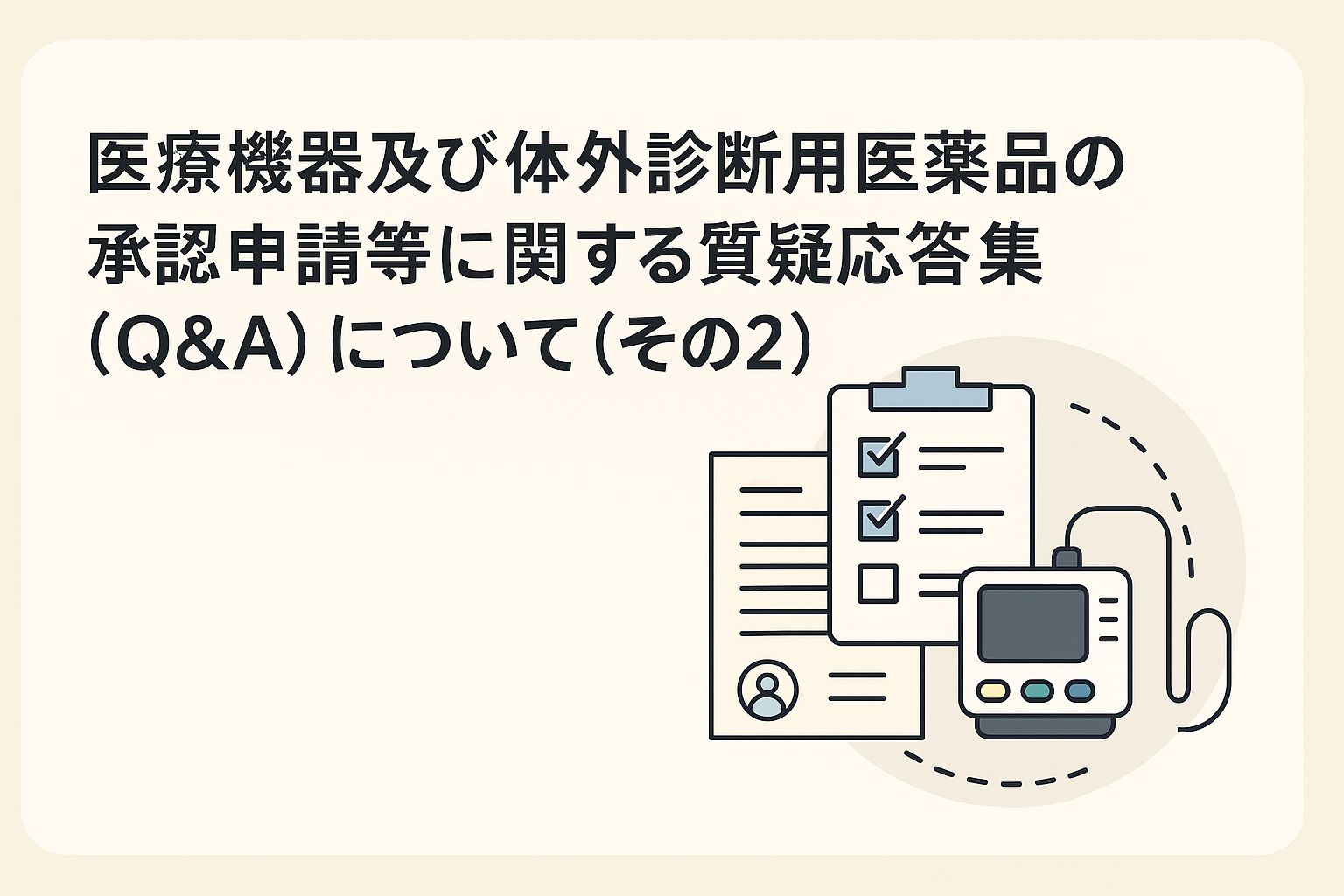概要
厚生労働省は平成20年3月28日付けで、医療機器及び体外診断用医薬品の基本要件基準の適用に関する重要な通知を発出しました。この通知は、薬事法第41条第3項に基づく医療機器の性状、品質及び性能の適正を図るための基準と、同法第42条第1項に基づく体外診断用医薬品の製法、性状、品質、貯法等の基準として定められた「薬事法第42条第1項の規定により厚生労働大臣が定める体外診断用医薬品の基準」の適用について、重要な変更を示すものです。
本通知により、平成17年4月1日から適用されていた一般的要求事項の規定が、平成20年4月1日から適用されることとなりました。これは医療機器等の品質管理と安全性確保において重要な転換点となる内容であり、製造販売業者をはじめとする関係者に周知徹底が求められています。
1. 基本要件基準の定義と重要性
1.1 基本要件基準とは
基本要件基準は、すべての医療機器及び体外診断用医薬品が具備すべき品質、有効性及び安全性に係る基本的な要件を規定したものです。これは医療機器等の設計、開発、製造、流通、使用のすべての段階において満たされるべき最低限の要求事項を定めています。
医療機器については薬事法第41条第3項、体外診断用医薬品については第42条第1項がその法的根拠となっており、これらの基準を満たすことは医療機器等の承認・認証を受けるための必須条件となっています。
1.2 基本要件基準の適合性確認の重要性
基本要件基準への適合性は、その各条項に適合することを示すための適切な規格、基準等がある場合には、当該規格、基準等を活用して示すことができます。他に合理的な方法がある場合には、必ずしも特定の規格、基準等に定められた試験検査の実施を求めるものではありません。
これにより、製造販売業者は柔軟性を持って基本要件への適合を証明することが可能となり、技術革新や新しい評価方法の導入にも対応できる仕組みとなっています。
2. 製造販売の承認及び認証における適用
2.1 承認申請における取り扱い
製造販売の承認又は認証を受けた医療機器等については、その他の法令や基準への適合等を前提に、その時点における基本要件への適合性が確認されたものとみなされます。平成20年3月31日以前に申請された医療機器等であって、製造販売の承認又は認証を受けたものについては、新たに基本要件基準の各条項への適合性を確認するため、現時点において必ずしも改めて新たな試験検査を行うことを求められるものではありません。
2.2 既承認品目の取り扱い
既に承認・認証を受けている医療機器等については、製造販売の届出の際、製造販売業者において基本要件基準への適合性を確認しており、必要があることとなっています。これは、継続的な品質管理と安全性確保の観点から重要な措置です。
3. 基本要件基準への適合性確認プロセス
3.1 適合性確認の方法
基本要件基準への適合性は、製造販売の承認もしくは認証又は製造販売の届出のときのみに確認されればよいものではなく、技術の進歩や医療環境の変化等に対応し、市販後においても継続してその適合性が確保されるべきものであることが重要です。
製造販売業者においては、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号、以下「GQP省令」という)及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号、以下「GVP省令」という)に従って品質管理及び製造販売後安全管理を実施することが求められています。
3.2 品質管理システムとの連携
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号、以下「QMS省令」という)が適用される医療機器等については、製造業者及び外国製造業者において、製造管理及び品質管理を実施することとされています。製造販売業者、製造業者及び外国製造業者は、GQP省令、GVP省令及びQMS省令の遵守を通じ、自ら製造販売又は製造する医療機器等の基本要件基準への適合性が常に確保される体制を構築すべきです。
4. 継続的な適合性確保の要件
4.1 市販後の品質管理体制
基本要件基準への適合状況については、継続的かつ計画的に確認し、外部の求めに応じ説明できるようにしておくことが重要です。これは単に初回の承認・認証時のみの要件ではなく、製品のライフサイクル全体を通じて維持されるべき要件です。
4.2 技術進歩への対応
医療技術の進歩や新たな科学的知見の蓄積により、基本要件基準への適合性を評価する方法や基準自体も変化する可能性があります。製造販売業者は、これらの変化に適切に対応し、常に最新の技術水準に基づいた品質管理を実施する必要があります。
4.3 文書管理と記録の保持
基本要件基準への適合性を示す文書や記録は、適切に管理され、必要に応じて速やかに提示できる状態で保管されている必要があります。これには、設計開発記録、検証・妥当性確認記録、リスクマネジメント文書などが含まれます。
5. 今後の展望と課題
5.1 規制の国際整合化
医療機器規制の国際整合化が進む中で、基本要件基準についても国際的な規格や基準との調和が図られています。ISO 13485やISO 14971などの国際規格への準拠は、基本要件基準への適合性を示す有効な手段となっています。
5.2 新技術への対応
AI・機械学習を活用した医療機器、デジタルセラピューティクス、遠隔医療機器など、新しいタイプの医療機器の登場により、基本要件基準の適用にも新たな課題が生じています。これらの新技術に対応した評価方法の確立と、基本要件基準の適切な適用が今後の重要な課題となっています。
まとめ
医療機器および体外診断用医薬品の「基本要件基準」は、製品の品質・有効性・安全性を確保するための中核的な制度です。平成20年の厚生労働省通知によって、承認・認証時のみならず、製品ライフサイクル全体を通じた適合性確保が求められるようになり、製造販売業者にはGQP省令・GVP省令・QMS省令を踏まえた包括的な品質管理体制の構築が必須となりました。また、ISO 13485やISO 14971といった国際規格との整合も進んでおり、グローバル展開を視野に入れる企業にとっても重要な要素となっています。
近年では、AI・機械学習を活用したSaMD(プログラム医療機器)やデジタルセラピューティクス、遠隔医療機器といった新しい技術・製品形態への対応が求められており、従来の枠組みでは対応しきれない事例も増加しています。こうした背景から、基本要件基準の正確な理解と柔軟な適用、リスクマネジメント文書や技術文書の適切な整備が、承認・認証申請および市販後管理の両面で重要な鍵となっています。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、基本要件基準への適合性確認や申請書類整備、ISO 13485やISO 14971との整合性評価、QMS体制構築支援など、規制対応と実務を両立した専門的な薬事コンサルティングを提供しています。これから医療機器・体外診断用医薬品の申請を予定している企業様や、既承認品目の見直し・国際展開を検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。豊富な実務経験に基づき、貴社の製品開発と薬事対応を力強くサポートいたします。