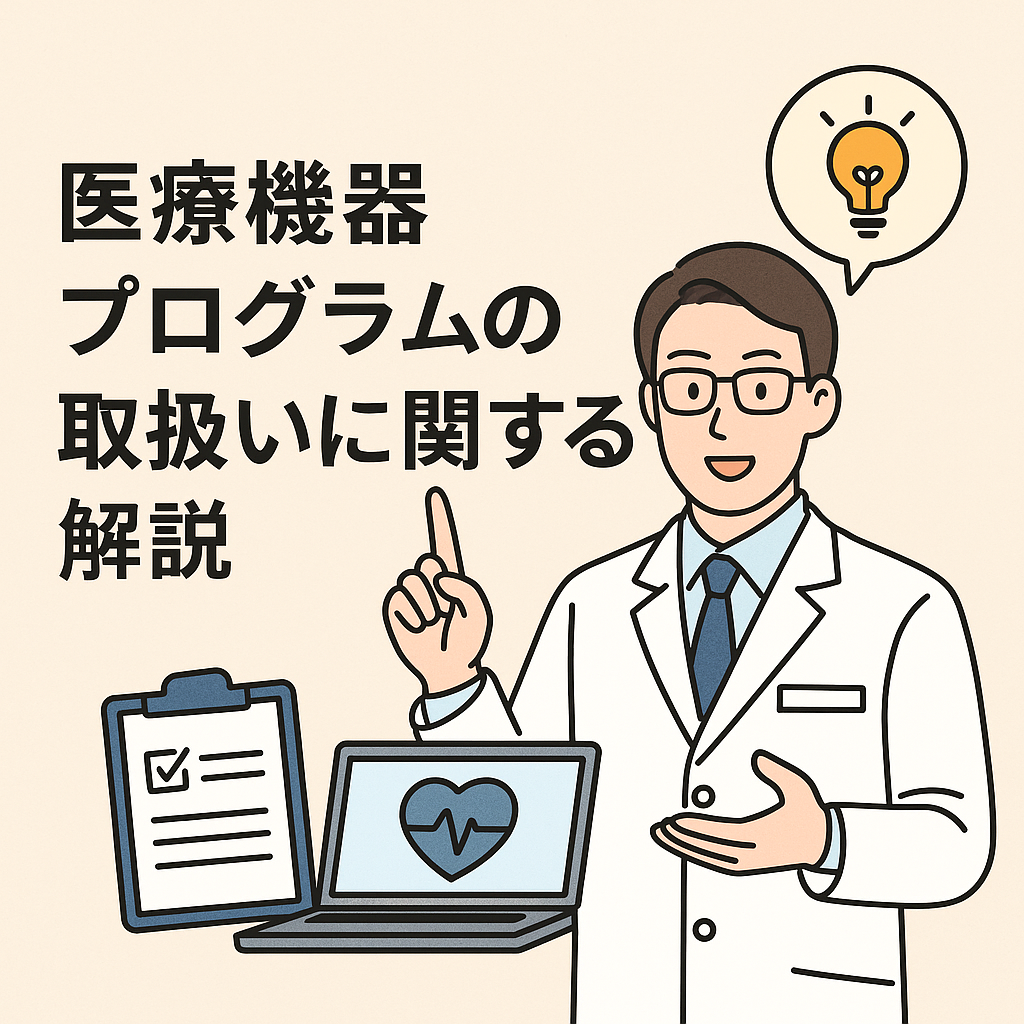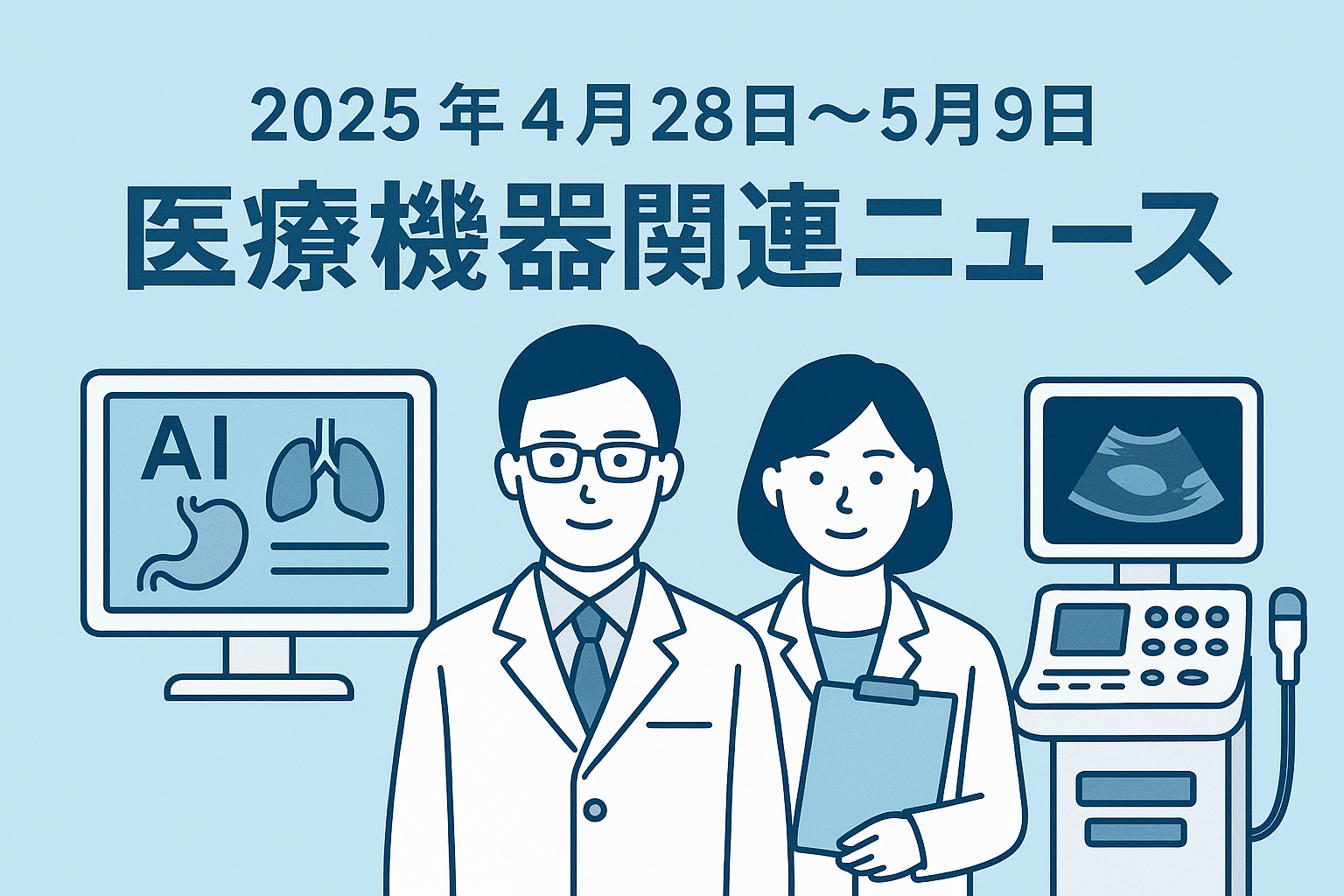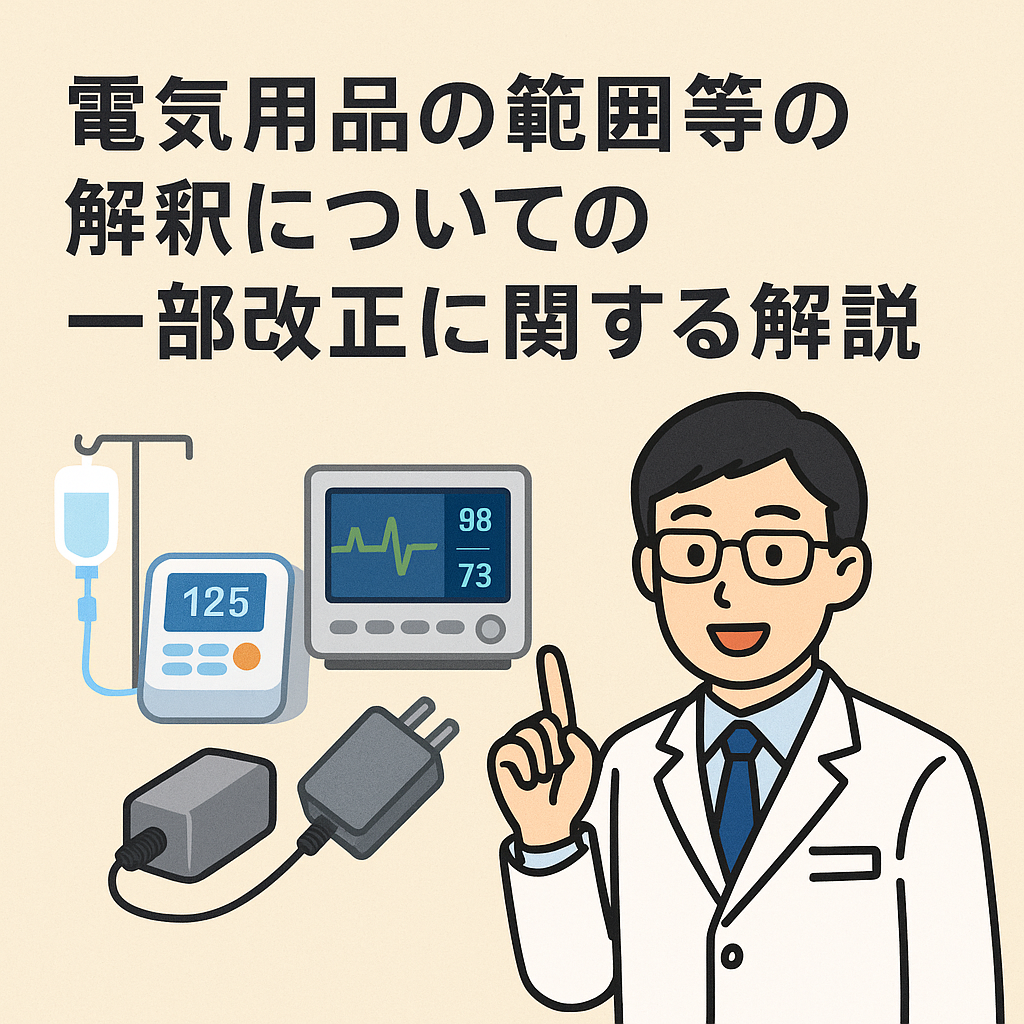概要
平成26年11月21日付けの厚生労働省通知「医療機器プログラムの取扱いについて」は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)によって、医療機器の定義に「プログラム及びこれを記録した記録媒体」が加えられたことに伴い、その具体的な取扱いを明確化したものです。本通知では、医療機器プログラムの該当性の判断基準、製造販売業・製造業の許可・登録要件、承認申請の方法、販売業や貸与業の規制、法定表示や添付文書の取扱い等について詳細に規定されています。この通知は平成26年11月25日から適用され、医療機器プログラムを取り扱う関係者に適切な指導を行うことを目的としています。
1. 医療機器プログラムの概要と定義
1.1 適用範囲
本通知は、法第2条第4項に規定する「医療機器」の定義に該当するプログラムを対象としており、それ以外の医療機器に該当しないプログラムは対象外となります。医療機器プログラムの該当性は、施行令別表第一に基づいて判断されます。
1.2 用語の定義
通知では以下の用語が定義されています。
- プログラム:電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
- 医療機器プログラム:医療機器のうちプログラムであるもの
- 記録媒体:磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリなどのデータを記録するもの
- 電気通信回線:インターネットなどの電気通信網(両方向からの通信を伝送する有線または無線のもの。一方向にしか情報を送信できない放送は含まない)
1.3 医療機器プログラムの該当性
プログラムが医療機器に該当するかどうかは、施行令別表第一に示すプログラムに該当するかどうかにより判断されます。具体的には以下のような区分となります。
- 疾病診断用プログラム
- 疾病治療用プログラム
- 疾病予防用プログラム
ただし、いずれの場合も「副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの」は医療機器から除外されています。
2. 医療機器プログラムの提供方法と分類
2.1 電気通信回線を通じたプログラムの提供
医療機器プログラムは、記録媒体を通じての提供だけでなく、電気通信回線(インターネット等)を通じても提供することができます。電気通信回線を通じた提供には以下の形態が含まれます。
- ダウンロード販売
- 所有権は移転せずに使用権を認める形態
なお、利用者から提供されたデータを使用して診断等を行うサービスは、利用者がデータの提供のみを行い医療機器プログラムを使用しない場合、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供とは解されません。ただし、電気通信回線を通じて利用者が医療機器プログラムを操作し、利用者が提供するデータから自動的に診断等の結果が提供される場合は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供と解される場合があります。
2.2 一般的名称とクラス分類
医療機器プログラムに関する一般的名称は、これまでの一般的名称とは別に、クラス分類告示において新設されています。クラス分類は、クラス分類通知等で示されているクラス分類ルールに基づき判断され、医療機器プログラムについては原則として能動型機器に関するクラス分類ルールが適用されます。
ただし、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に与えるおそれがほとんどないプログラム及びこれを記録した記録媒体は医療機器の範囲から除外されるため、一般医療機器に該当する医療機器プログラムの一般的名称は規定されていません。
3. 製造販売業と製造業に関する要件
3.1 製造販売業の許可
医療機器プログラム等を製造販売するためには、以下の区分に応じた許可が必要です。
- 高度管理医療機器に該当する医療機器プログラム等:第一種医療機器製造販売業許可
- 管理医療機器に該当する医療機器プログラム等:第二種医療機器製造販売業許可
3.2 製造業の登録
医療機器プログラム等を製造する場合、以下の種類に応じて製造業の登録が必要です。
医療機器プログラムの場合。
- 設計の工程について登録が必要
医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器の場合。
- 設計の工程について登録が必要
- 国内における最終製品の保管の工程について登録が必要
4. 承認申請と規制対応
4.1 製造販売承認申請の取扱い
医療機器プログラム等の承認申請書の各欄の記載事項は以下のとおりです。
- 類別欄:施行令別表第1に従って記載
- 一般的名称欄:クラス分類通知の別添に記載される一般的名称の定義に基づき記載
- 販売名欄:誤解を与え保健衛生上の危害を発生するおそれがなく、医療機器としての品位を保つもの
- 使用目的又は効果欄:医療機器の特性に応じ、適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する結果などを適切に記載
- 形状、構造及び原理欄:提供形態、動作原理、プラットフォームの要件、併用機器等について具体的に記載
- 性能及び安全性に関する規格欄:品質、安全性及び有効性の観点から設計仕様を記載
- 使用方法欄:インストール方法から順を追って分かりやすく記載
4.2 QMS調査について
医療機器プログラム等についても、他の医療機器と同様にQMS調査(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令への適合状況調査)が必要となります。ただし、プログラムの区分について基準適合証の交付を受けている場合、当該基準適合証に記載の登録製造所と同一の登録製造所で製造される医療機器プログラム等については、基準適合証の有効期間内においてQMS調査を受ける必要はありません。
4.3 基本要件への適合
医療機器プログラム等についても、他の医療機器と同様に基本要件基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準)への適合性が求められます。
5. 販売・表示・安全対策
5.1 販売業及び貸与業について
医療機器プログラム等を販売、授与、貸与、またはそれらの目的で陳列、あるいは電気通信回線を通じて提供する場合、高度管理医療機器たる医療機器プログラム等にあっては販売業又は貸与業の許可が、管理医療機器たる医療機器プログラム等にあっては販売業等の届出が必要となります。
電気通信回線を通じて医療機器プログラムを提供する場合は販売業の対象となり、貸与業は当該行為の対象となりません。インターネットモール事業者は販売業の対象ではありませんが、販売業者がインターネットモールを通じて医療機器プログラムを提供する場合には、当該ホームページに販売業者の情報等を表示する必要があります。
5.2 法定表示について
記録媒体を通じて提供する場合と電気通信回線を通じて提供する場合で、法定表示の方法が異なります。
記録媒体を通じて提供する場合。
- 記録媒体やその容器・被包に法定表示を記載すること
- 使用者が容易に閲覧できる方法で電磁的記録として法定表示を提供すること
電気通信回線を通じて提供する場合。
- 提供を受ける前に法定表示の情報を提供すること
- 使用者が容易に閲覧できる方法で電磁的記録として法定表示を提供すること
5.3 添付文書と不具合報告
医療機器プログラムの添付文書等記載事項については、他の医療機器と同様の記載要領に従いますが、医療機器プログラムの特性に鑑みて必要な項目のみ記載することで差し支えありません。添付文書は電磁的記録として提供することも可能です。
医療機器プログラム等の不具合等の報告や回収については、他の医療機器と同様に関連通知に従って対応する必要があります。
まとめ
医療機器プログラムは、薬事法改正により新たに医療機器として定義され、その取扱いには特有の規制が適用されることになりました。医療機器プログラムに該当するかどうかは、疾病の診断・治療・予防への使用目的と、人の生命・健康への影響度合いによって判断されます。
医療機器プログラムを製造販売するためには、リスクに応じた製造販売業の許可と製造業の登録が必要であり、承認申請においてはプログラムの特性に応じた記載が求められます。また、提供形態(記録媒体または電気通信回線)によって、販売業・貸与業の規制や法定表示・添付文書の取扱いが異なる点に注意が必要です。
これらの規制枠組みを正しく理解し、開発から販売まで適切に対応することが、医療機器プログラムビジネス成功の鍵となります。
弊社では、医療機器プログラムに関する該当性判断、承認申請支援、各種規制対応のコンサルティングを承っております。ご相談やご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。