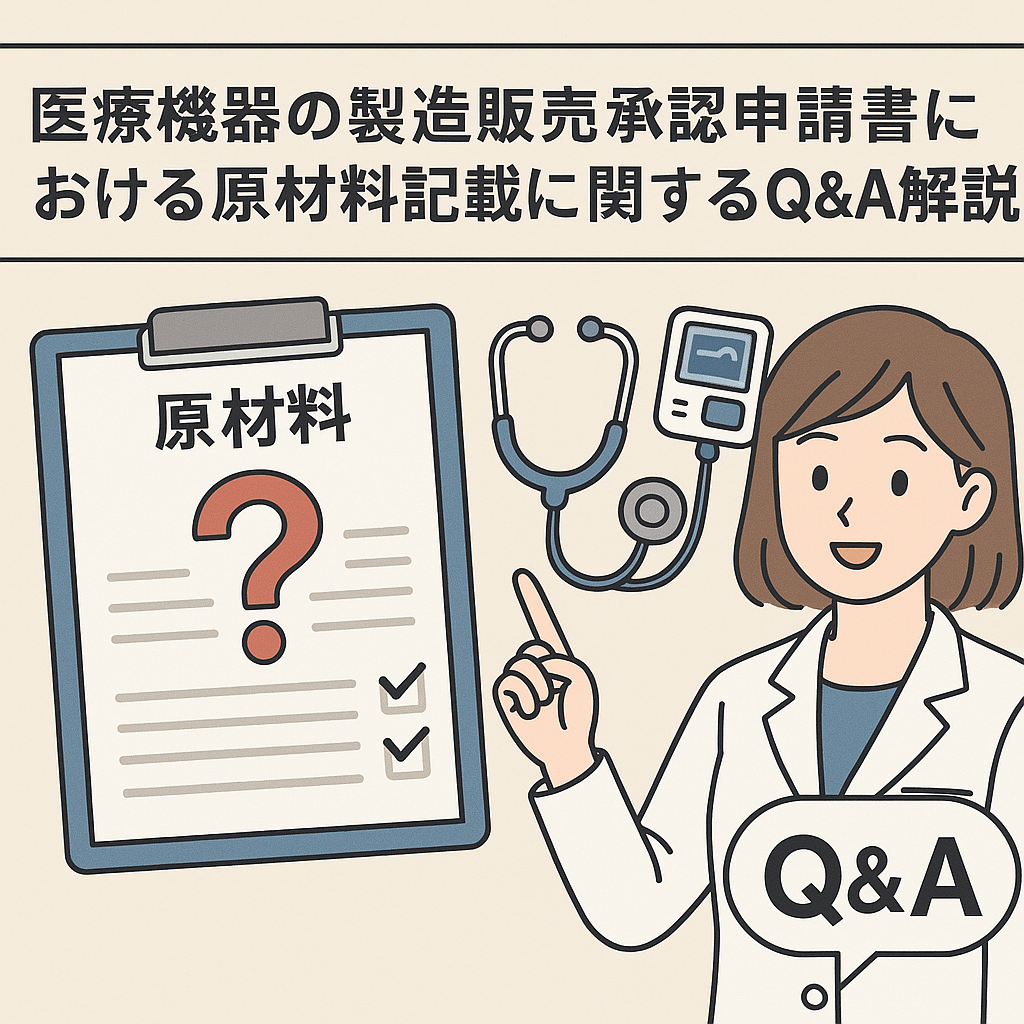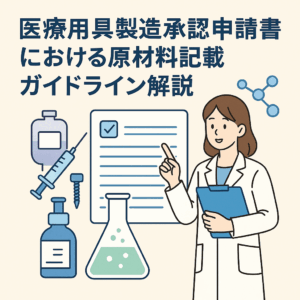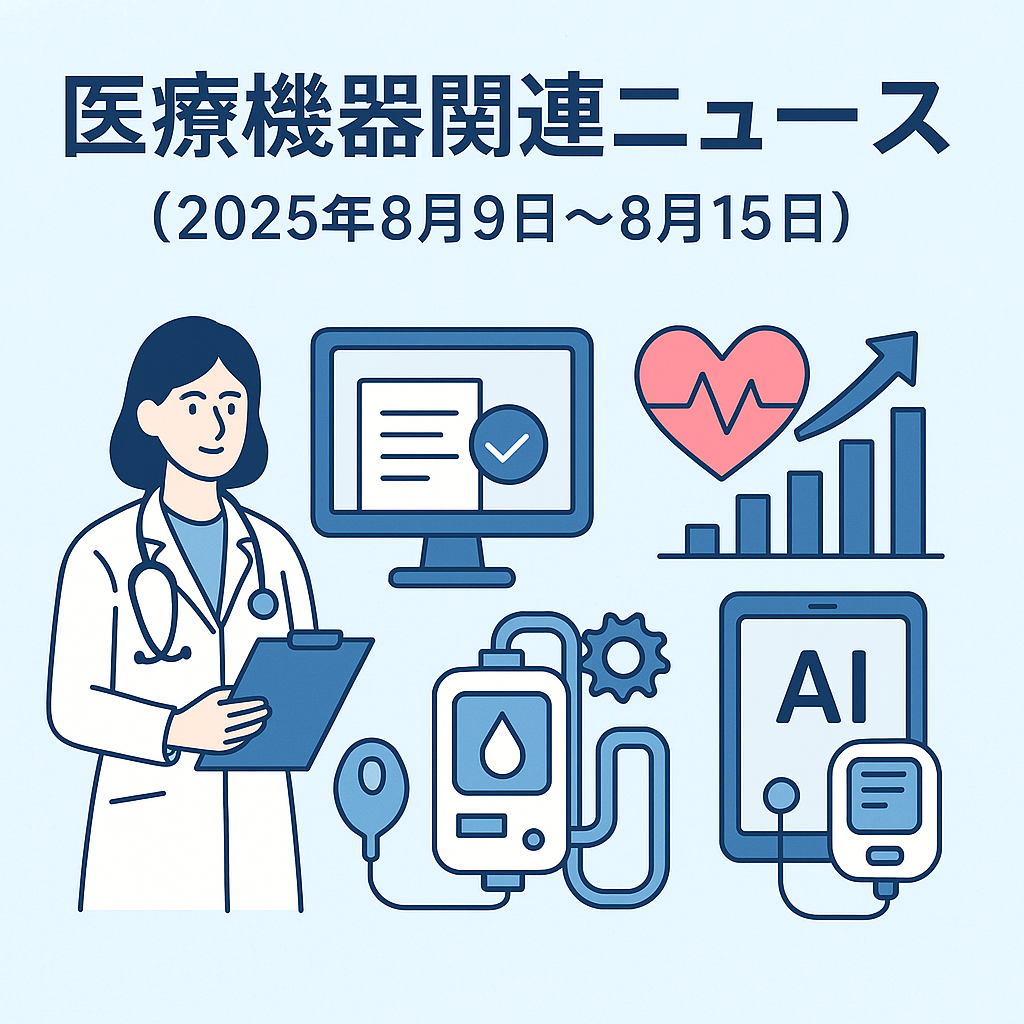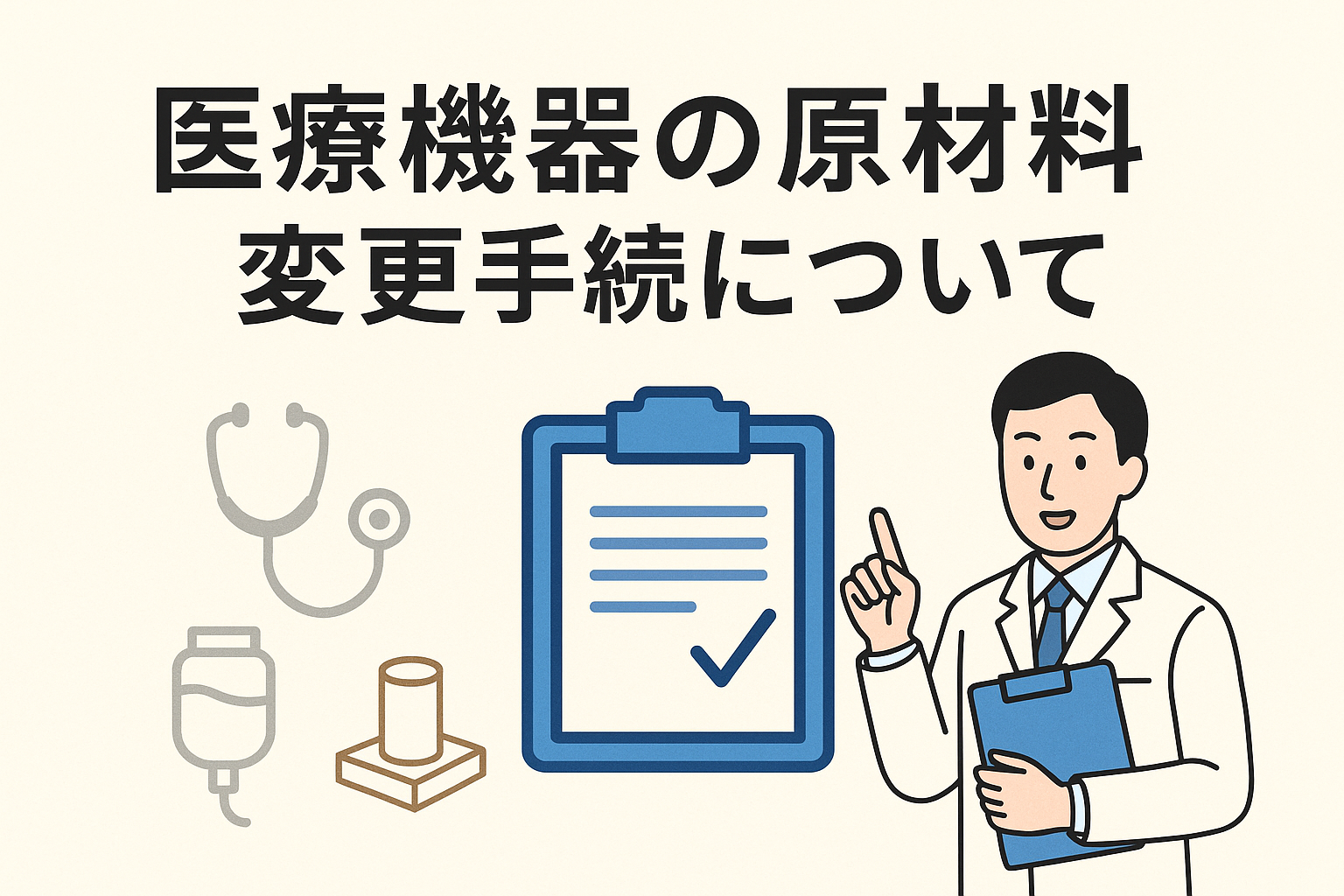概要
本記事では、平成19年8月15日に厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室から発出された「医療機器の製造販売承認申請書における原材料記載に関するQ&A」について解説します。
この事務連絡は、平成16年11月15日に発出された医療機器審査No.19事務連絡に関する実務的な疑問に答える形で作成されたものです。医療機器の製造販売承認申請書における原材料記載の適切な方法について、具体的な事例を通じて明確化を図っています。
事務連絡はあくまで参考であり法的拘束力はありませんが、承認申請における原材料記載の実務において重要な指針となっています。現行法下においても原材料欄の記載にあたって参考にされており、医療機器業界における標準的な考え方を示しています。
1. 事務連絡の位置付けと適用範囲
1.1 法的拘束力と適用性
事務連絡に記載されている原材料記載の方法は、あくまで参考であり、法的拘束力や強制力のあるものではありません。平成16年の旧法下で発出された事務連絡は現在でも廃止されておらず、現行法(改正薬事法)下においても原材料欄の記載にあたって参考にすることが推奨されています。
1.2 適用対象となる原材料
事務連絡の別添報告書は、申請品目の有効性、安全性及び品質を担保する上で必要となる材料特定のためのガイダンスです。適合することを求めるものではなく、製品の有効性及び安全性に影響するものについて記載が必要とされています。
接着剤については、接着強度や生物学的安全性が有効性及び安全性に影響があると考えられることから、使用されている部分のリスクを勘案した上で、原則として詳細な記載が求められます。ただし、製造工程でのみ使用し、最終製品に残らないものについては記載不要です。
2. リスクレベルに応じた記載要件
2.1 医療機器のクラス分類に応じた記載
医療機器の人体への侵襲の度合い、接触期間等のリスクに応じた適切な記載が求められます。長期留置やインプラントの原材料については詳細な記載が必要ですが、24時間以内の一時的接触の医療機器については、インプラントほどの詳細な記載は不要とされています。
クラスⅣの製品であっても、製品の部位によってリスクが異なることがあり、それぞれのリスクと有効性への影響を考えて適切な記載とすることが認められています。
2.2 接触部位による記載の差異化
血液、体液等に接触しない部品であって、原材料の特性等が性能、有効性、安全性に重要な影響をもたらす可能性がないものについては、一般名並びに化学名及び/又はCAS番号での記載が可能です。簡略記載はできても空欄では十分ではなく、一般電気部品等についてはその旨記載することで差し支えありません。
3. 原材料メーカーからの情報入手が困難な場合の対応
3.1 添加剤情報が得られない場合の対処法
原材料メーカーから添加剤の成分及び配合量について企業秘密を理由に開示されない場合があります。このような場合には、添加剤の情報なしでも原材料を適切に特定できる方法を検討する必要があります。
具体的な方法として、原材料製造業者名、製品名(又は商品名)、製造番号あるいは記号、原材料規格及び製品仕様で規定した上で、この規定の範囲において添加剤を含め原材料が変わらない旨の契約等で説明する方法が例示されています。
3.2 情報開示されない場合の記載方法
「開示されない」「開示できない」は申請書に記載すべき内容として適切ではありません。開示されない場合には、その情報がなくても原材料が特定できるとする妥当な説明が必要です。事務連絡の別添報告書中の各部の記載要領に規定されている他の選択肢や、原材料が変わらないこと等の契約書を示す方法等を検討する必要があります。
3.3 QMS情報の活用
原材料製造業者との取り決め事項等については、原材料の特定のための情報として利用できる可能性があります。ただし、原材料特定の方法が形状、外観等による原材料の識別のために行っている場合のように、事務連絡の別添報告書に示された記載要領の基本的考え方と大きく違う場合には、それらの情報は参考にはなってもその情報のみでは不十分な場合もあります。
4. 部品の原材料記載と特定方法
4.1 構成部品の原材料記載
チューブやシート等の仕掛品を受け入れる場合、どの段階で受け入れているのか等多くの事例があり得るため、一概に受入れ規格又は仕掛品発注時の仕様書をもって十分であるとは判断できません。個別に状況を勘案し、判断する必要があります。
基本的考え方は、構成部品の原材料をどのように特定するかであるので、記載された情報で構成部品の原材料が特定できることを説明することが重要です。
4.2 色素マーカー等を含む部品の取り扱い
色素マーカーをつけた部品や色素・添加物が既に配合されたチューブなどを購入する場合、詳細情報の入手が困難な場合があります。このような場合、製造業者名、製品番号で特定は十分であると考えられますが、物が変わった場合にタイプテストとして生物学的安全性試験を行う場合は、生物学的安全性に影響を及ぼす可能性のある変更があったことを意味します。
5. 承認前例と生物学的安全性試験の取り扱い
5.1 原材料記載と生物学的安全性試験の関係
原材料記載の目的は原材料を特定することであり、生物学的安全性は特定された原材料の安全性を担保するものです。原材料を特定できない場合には、特定できない範囲での製品の有効性・安全性の評価が必要になり、生物学的安全性は必要な要素ではありますが十分条件ではありません。
5.2 MSDS情報の活用
MSDSは原材料の安全性に関する情報ですが、安全性情報は必ずしも物を特定する情報の全てではありません。原材料記載の趣旨を理解の上、物を特定するのに必要な情報を検討する必要があります。MSDSの中の情報で物を特定するのに必要な情報があればこれを使用することは可能です。
5.3 承認前例との同一性証明
生物学的安全性については、平成15年2月13日医薬審発第0213001号審査管理課長通知において、生物学的安全性評価を改めて行う必要がある場合が記載されています。製造業者名、製品番号の特定により、生物学的安全性を確認するような変更は含まれないとの前提であれば可能です。
まとめ
本Q&Aは、医療機器の製造販売承認申請書における原材料記載について、実務上の様々な課題に対する具体的な解決方法を示しています。事務連絡はあくまで参考ですが、原材料の適切な特定という基本的な目的を達成するための実用的なガイダンスとして機能しています。
重要なポイントは、原材料メーカーから詳細情報が得られない場合でも、適切な特定方法を検討し、妥当な説明を提供することで承認申請が可能であることです。また、医療機器のリスクレベルや接触部位に応じて記載の詳細度を調整できる柔軟性も示されています。
自社製品の申請や原材料記載方法について不明点やお困りごとがある場合は、ぜひ弊社までお問い合わせください。