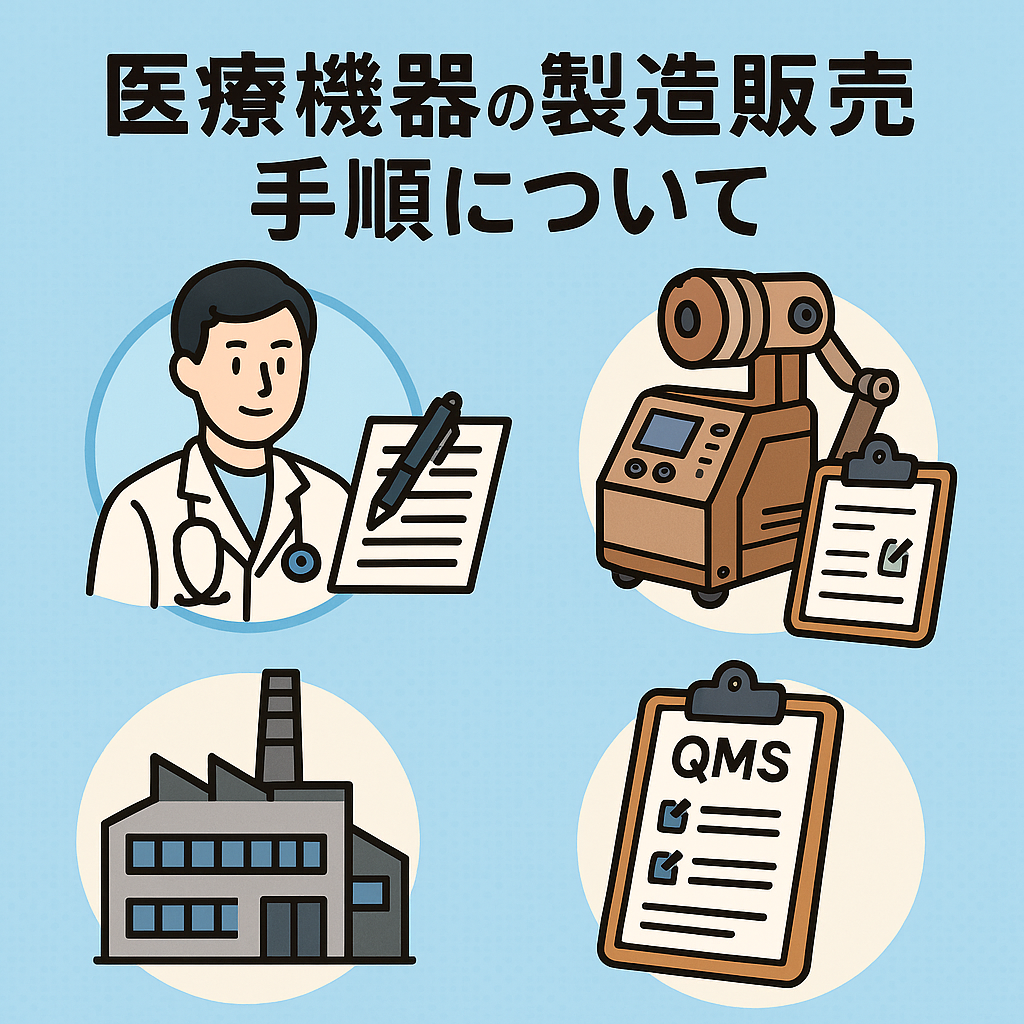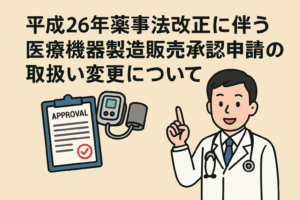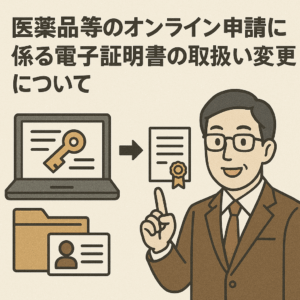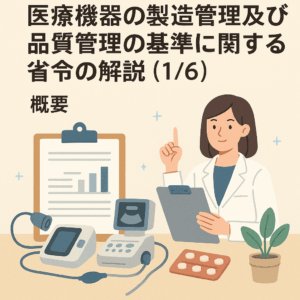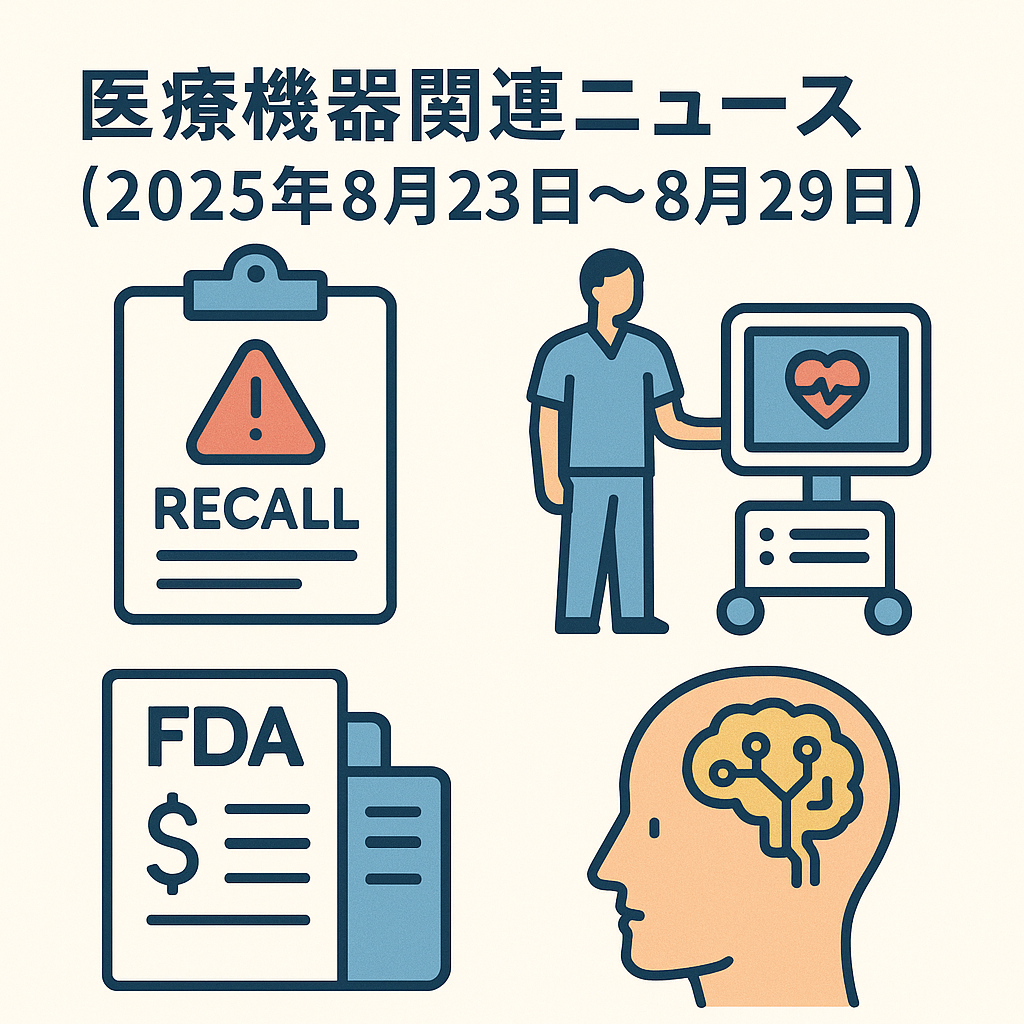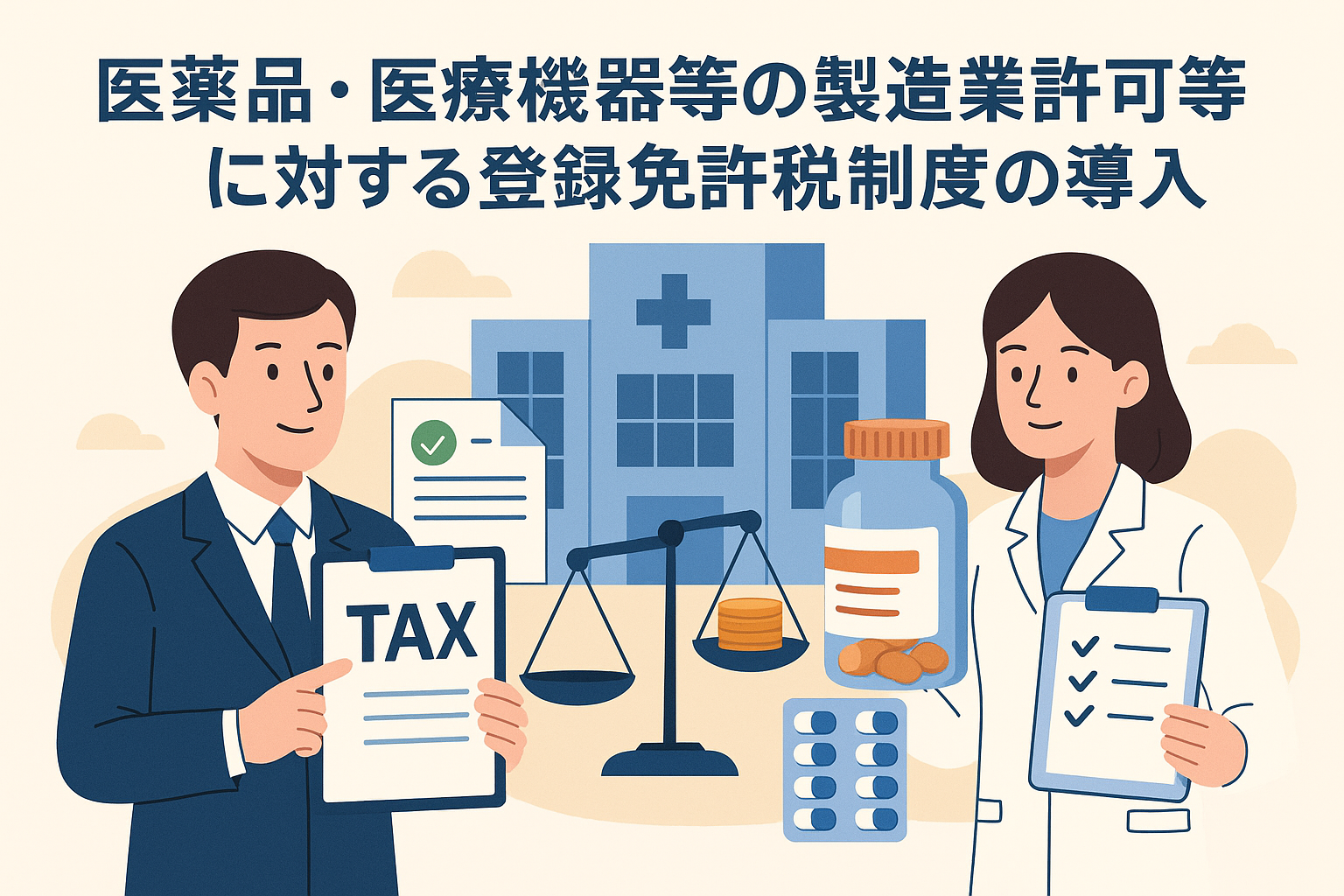概要
日本において医療機器を市場へ出荷(製造販売)するためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)による規制を受けており、事業者は規制当局である厚生労働省及び各都道府県から必要な許可、登録、承認を取得しなければなりません。
医療機器の製造販売を開始するまでには、大きく3つの側面から審査を受ける必要があります。第一に企業としての責任体制の審査、第二に製品そのものの有効性と安全性等の審査、第三に製品の生産方法と管理体制の審査です。これらの審査をすべてクリアして初めて、医療機器を市場へ流通させることが可能となります。
本記事では、医療機器の製造販売を行うために必要な手続きの全体像と、各申請の詳細について体系的に整理します。医療機器ビジネスに新規参入を検討している企業や、既存事業者で新たな製品開発を行う方々にとって、規制要件を理解し、適切な手続きを進めるための指針となることを目的としています。
1. 製造販売業許可申請
1.1 申請の目的と意義
製造販売業許可は、医療機器を市場に対して最終的な責任を負う企業が取得すべき許可です。この許可を取得することで、企業は品質保証業務責任と安全管理業務責任を担う能力を有していることが公的に認められます。製造販売業者は、製品の市場出荷から市販後の安全管理まで、一貫した責任を負うことになります。
1.2 申請先と審査権限
製造販売業許可の審査権限は各都道府県知事にあります。申請書は事業所が所在する都道府県の薬務主管課窓口に提出します。都道府県によって審査基準や手続きの詳細が若干異なる場合があるため、事前に管轄の都道府県担当部署に確認することが重要です。
1.3 申請に必要な要件
申請にあたっては、総括製造販売責任者の設置が必須となります。医療機器の製造販売業においては、総括製造販売責任者は第85条第1項及び第2項、第114条の49第1項及び第2項、または第137条の50第1項の各号のいずれかに該当する資格を有する必要があります。また、申請者に欠格条項がないことも確認されます。欠格条項には、過去の許可取消歴、禁錮以上の刑の履歴、薬事関連法令違反歴などが含まれます。
1.4 電子申請の推進
現在、製造販売業許可申請はFD(フレキシブルディスク)申請システムを使用した電子的な申請が推奨されています。電子申請により、申請書類の作成効率が向上し、審査期間の短縮にもつながります。手数料については各都道府県のホームページ等で確認する必要があります。
2. 製造販売承認申請
2.1 承認申請の重要性
製造販売承認は、個々の医療機器製品に対して、その性能、安全性等の面で問題がないことを確認するための制度です。この承認は厚生労働大臣により付与され、申請書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の窓口に提出します。承認を取得することで、初めてその医療機器を市場に流通させることが可能となります。
2.2 申請書類の種類
国内で製造される医療機器については「医療機器製造販売承認申請書」を、外国で製造される医療機器については「外国製造医療機器製造販売承認申請書」を提出します。申請書には、製品の一般的名称、販売名、使用目的又は効果、形状・構造及び原理、原材料、性能及び安全性に関する規格、使用方法、保管方法及び有効期間、製造方法など、詳細な情報を記載する必要があります。
2.3 審査プロセス
承認審査はPMDAが実施し、製品のリスククラスに応じて審査の深度が異なります。高リスクの医療機器ほど、より詳細な臨床試験データや安全性データの提出が求められます。審査期間も製品のリスククラスによって異なり、新医療機器の場合は通常12か月程度、改良医療機器の場合は6~9か月程度を要することが一般的です。
2.4 申請システム
製造販売承認申請においても、FD申請またはDWAP(医薬品医療機器申請・審査システム)を使用した電子申請が推奨されています。これらのシステムを利用することで、申請書類の作成から提出、審査の進捗確認まで、一連のプロセスを効率的に管理することができます。手数料は国と総合機構それぞれに支払う必要があり、製品のクラスや申請区分によって金額が異なります。
3. 製造業者登録申請
3.1 国内製造業者の登録
国内で医療機器を製造する事業者は、製造所ごとに都道府県知事による登録を受ける必要があります。この登録により、製造所が医療機器の製造に必要な構造設備を有し、適切な製造管理を行う能力があることが確認されます。申請書は製造所が所在する都道府県の窓口に提出します。
3.2 外国製造業者の登録
外国の製造業者が日本向けに医療機器を製造する場合は、厚生労働大臣による登録が必要です。申請書はPMDAの窓口に提出します。外国製造業者登録においては、申請書類を邦文と外国文の両方で作成する必要があり、また、日本国内に選任製造販売業者を置く必要があります。
3.3 登録の要件と管理者
製造業登録にあたっては、管理者または責任技術者の設置が必要です。管理者が薬剤師である場合はその薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者の場合は第114条の53第1項から第3項までの各号のいずれに該当するかを明記する必要があります。設計の業務のみを行う製造所の場合は、備考欄に「設計」と記載します。
4. QMS適合性調査申請
4.1 QMS調査の目的
QMS(Quality Management System)適合性調査は、医療機器の製造管理及び品質管理の基準(QMS省令)に適合していることを確認するための調査です。この調査により、製造所が一貫した品質の医療機器を製造する能力を有していることが証明されます。調査はPMDA等により実施されます。
4.2 調査の種類と頻度
QMS適合性調査には、承認前の適合性調査と定期的な適合性調査があります。承認前調査は製造販売承認申請と同時期に実施され、定期調査は原則として5年ごとに実施されます。調査は書面審査と実地審査の組み合わせで行われ、製品のリスククラスや製造所の過去の調査結果等を考慮して、調査の深度が決定されます。
4.3 調査申請の手続き
QMS適合性調査申請書には、製造販売業の許可番号、申請品目の情報、製造所の情報などを記載します。複数の製造所が関与する場合は、それぞれの製造所について記載が必要です。申請はFDまたはDWAPシステムを使用した電子申請が可能で、手数料はPMDAに支払います。
5. その他の重要な手続き
5.1 業者コードの取得
製造販売業許可申請や製造業登録申請を行う前に、業者コードの取得が必要です。業者コードは9桁の数字で構成され、申請者の業者コード(下3桁が000)と製造所等の業者コード(製造所固有の番号)があります。国内事業者は都道府県を経由して、外国製造業者はPMDAを経由して厚生労働省に登録票を提出します。
5.2 認証品目と届出品目
すべての医療機器が承認を必要とするわけではありません。リスクの低い一部の医療機器は、登録認証機関による認証(認証品目)や、PMDAへの届出のみ(届出品目)で製造販売が可能です。認証品目は第三者認証機関が基準適合性を確認し、届出品目は製造販売業者の自己責任において市場出荷されます。
5.3 市販後の責任
製造販売開始後も、製造販売業者には継続的な責任があります。不具合情報の収集と報告、回収の実施、安全性情報の提供など、市販後安全管理業務を適切に実施する必要があります。また、定期的なQMS調査を受け、継続的に品質管理体制を維持することが求められます。
まとめ
医療機器の製造販売を行うためには、製造販売業許可、製造販売承認、製造業登録、QMS適合性調査といった複数の重要な手続きを適切に進める必要があります。これらの制度は、医療機器の品質・有効性・安全性を確保するために設けられており、企業の責任体制から製品ごとの安全性確認、製造所の管理能力、品質管理システムの適合性まで幅広く審査されます。
新規参入や新製品開発を検討されている企業にとっては、どのような申請が必要になるのか、自社の状況に応じた最適な手続きを理解することが極めて重要です。しかし、制度の改正や電子申請システムの活用など、最新の情報を常に把握していくのは容易ではありません。
弊社では、医療機器の薬事申請やQMS対応に関するご相談を承っております。実務的な申請サポートから戦略的な薬事対応まで、経験豊富な専門家が企業様を支援いたします。
医療機器の製造販売に関する具体的なご質問やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。