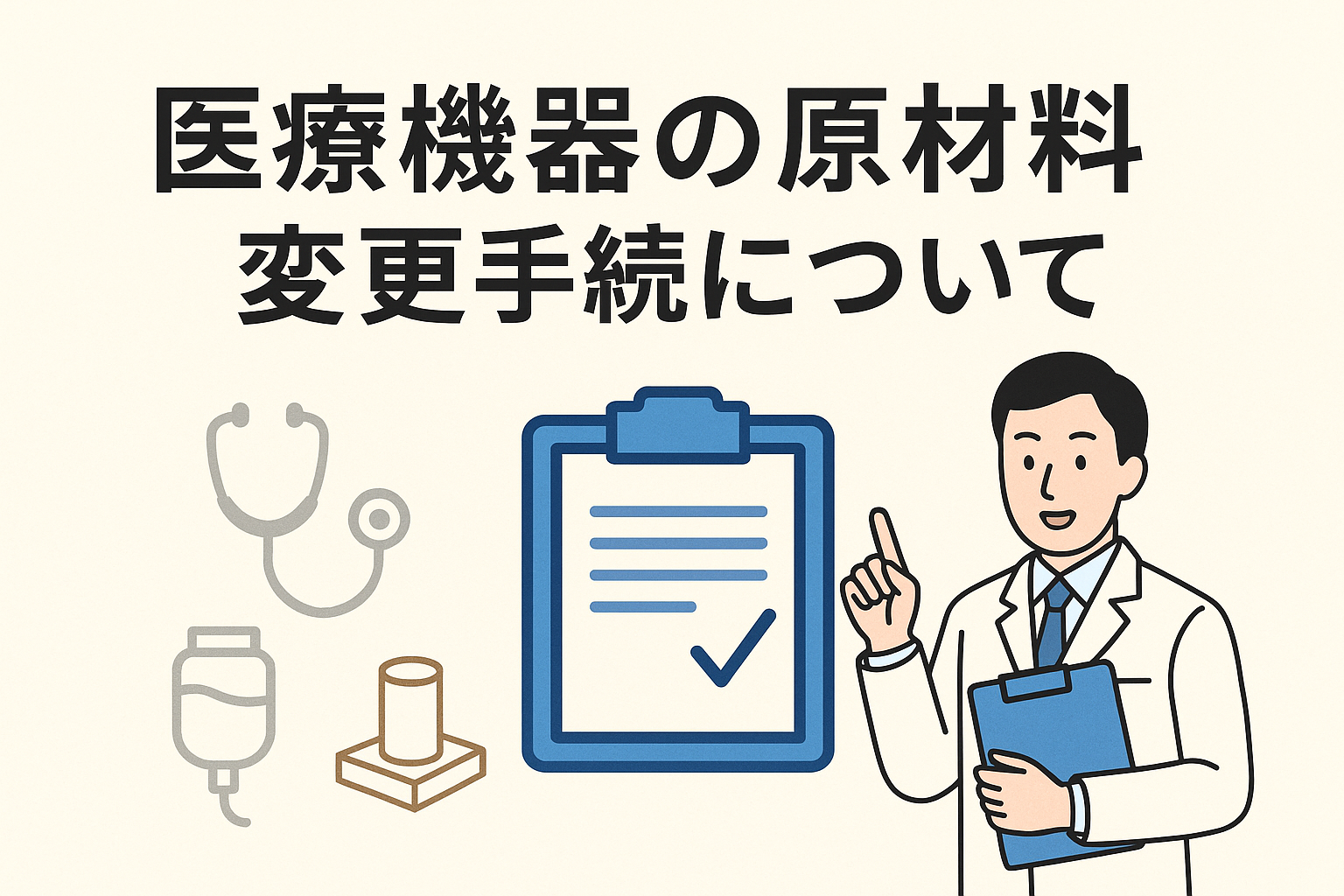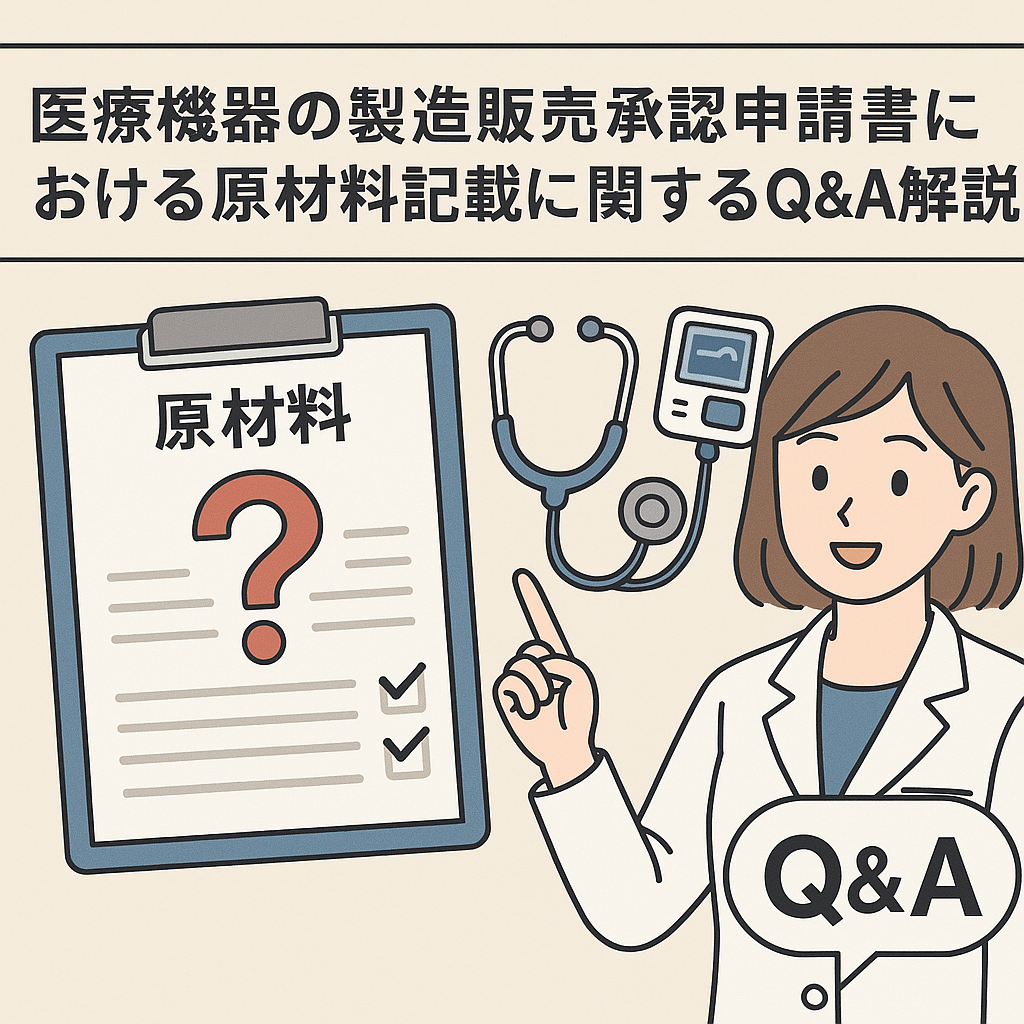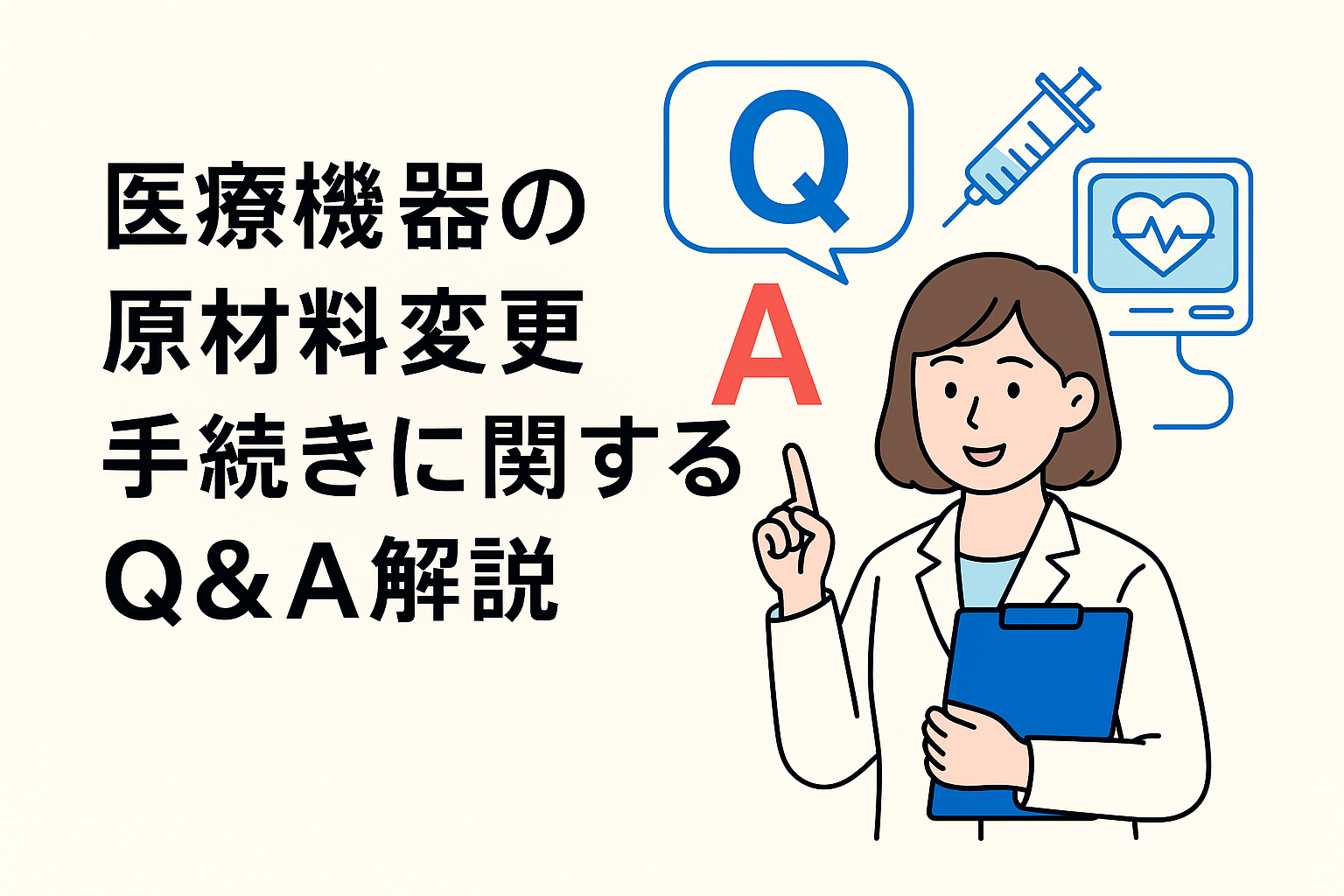概要
平成25年3月29日に厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長から発出された「医療機器の原材料の変更手続について」(薬食機発0329第7号)は、医療機器の原材料変更に関する手続きの合理化を図った重要な通知です。
この通知は、医療機器規制制度タスクフォースでの検討結果を踏まえ、血液、体液、粘膜等に接触する医療機器において、性能及び機能の変更を目的としない原材料の変更について、「使用前例」という概念を導入することで軽微変更届による変更を可能にしました。従来は承認事項一部変更承認申請が必要であった多くの原材料変更が、より迅速かつ合理的な手続きで実施できるようになった画期的な制度改正です。
特に注目すべきは、別添として示された原材料リストです。このリストには熱可塑性樹脂、ゴム、その他の高分子系材料、金属、セラミック、その他の6カテゴリーに分類された100種類以上の原材料が掲載されており、これらの原材料については使用前例として扱われる可能性が高いことを示しています。
1. 通知発出の背景と目的
1.1 医療機器規制制度タスクフォースの設立
厚生労働省は平成24年2月に「医療機器規制制度タスクフォース」を立ち上げました。このタスクフォースは、医療機器の特性を踏まえた、より合理的な規制制度の構築と運用を実現することを目的としており、医療機器業界との建設的な意見交換を通じて解決すべき課題について検討を行いました。
1.2 制度改正の必要性
従来の制度では、医療機器の原材料変更について画一的な取り扱いがなされており、性能や安全性に実質的な影響を与えない軽微な変更であっても、承認事項一部変更承認申請が必要とされる場合が多くありました。これにより、企業の開発効率や製品の市場投入スピードに影響を与えていたため、より合理的な制度設計が求められていました。
1.3 実施可能なものからの速やかな運用改善
本通知は、タスクフォースで得られた結論について、実施可能なものから速やかに実務的に運用を改善するという方針に基づいて発出されました。これにより、医療機器業界の実情に即した、より実用的な規制運用が実現されることになりました。
2. 適用範囲と基本要件
2.1 適用対象となる医療機器
本通知が適用される医療機器は、血液、体液、粘膜等に接触する医療機器に限定されています。接触の形態については、直接接触か間接接触かを問わないとされており、幅広い医療機器が対象となります。
2.2 適用される原材料変更の条件
適用される原材料変更には、以下の条件があります。まず、性能及び機能の変更を目的としない原材料の変更であることが必要です。また、生物由来原材料は除外されており、対象は非生物由来の原材料に限定されます。さらに、承認申請書または認証申請書の「原材料又は構成部品」欄のみを変更する場合に適用されます。
2.3 他の通知との関係
本通知以外の通知、事務連絡等により原材料を変更する際の手続きが別途示されているものについては、当該通知等による取り扱いも可能とされています。これにより、既存の制度との整合性が保たれ、企業は最も適切な手続きを選択することができます。
3. 原材料変更の具体的手続き
3.1 一般名レベルで異なる原材料の変更
変更する原材料が一般名レベルで異なる場合であっても、「使用前例」に該当する範囲であり、医療機器の性能、機能及び安全性が原材料の変更後も同等であることが新たな試験を実施しなくても説明できる場合には、軽微変更届による変更が可能です。ただし、体内植込み医療機器については除外されており、従来通りの承認事項一部変更承認申請が必要です。
3.2 規格が異なる原材料の変更
変更する原材料の一般名は同一であるが、原材料の規格が異なる場合についても、使用前例に該当し、同等性が説明できる場合には軽微変更届による変更が可能です。特に注目すべきは、「原材料又は構成部品」欄の原材料の規格の変更を伴わない変更であれば、承認書または認証書の変更手続きが不要であることです。これにより、企業の事務負担が大幅に軽減されます。
3.3 軽微変更届の記載要件
軽微変更届を提出する際には、備考欄に「平成25年3月29日付け薬食機発0329第7号通知に基づく原材料の変更」と記載することが必要です。また、適切な変更管理を行った上で対応したことがわかる自己宣言書を添付することも求められています。
4. 使用前例の判定基準
4.1 基本的な使用前例の考え方
使用前例として認められるためには、変更しようとする原材料が既に承認又は認証されている医療機器で使用実績があることが前提となります。その上で、原材料の規格・仕様、添加剤成分の種類及び配合量などが変わらないこと、身体への接触程度が同等又はそれ以上のリスクが高い部位での使用実績があること、身体への接触時間が同等又はそれ以上での使用実績があることという3つの条件をすべて満たす必要があります。
4.2 生物学的安全性評価との関係
身体への接触程度及び接触時間の判定については、「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について」等の通知に基づく医療機器のカテゴリ及び接触部位、接触時間の分類が用いられます。これにより、科学的根拠に基づいた合理的な判定が可能となります。
4.3 別添リストの活用
本通知には別添として原材料リストが添付されており、このリストに掲載された原材料については、医療機器の血液、体液、粘膜等の接触部位での使用実績が多く、生物学的安全性の評価がある程度確定している物質として位置づけられています。ただし、このリストは必要に応じて更新される予定であり、安全性に疑義が生じるような事案があった場合には、個別に必要な措置の指導が行われる可能性があります。
4.4 外国での承認実績の考慮
国内での使用実績がない場合でも、別添に該当する原材料であって、製造販売届出されている医療機器、法改正により承認不要品目から承認品目へ移行した医療機器、または外国(本邦と同等の水準にあると認められる承認制度を有している国)で承認等されている医療機器で十分な使用実績がある場合には、使用前例として取り扱われる可能性があります。
5. 留意事項と運用上の注意点
5.1 製造販売業者の責任
製造販売業者は、原材料の変更を行う場合には、その変更が当該医療機器の品質、有効性及び安全性に与える影響について適切に検証、評価しなければなりません。また、その結果については、GQP調査等の際に調査権者等の求めがあった場合には適切な説明ができるようにしておく必要があります。これは、軽微変更届による手続きが可能になったとしても、製造販売業者の品質管理責任が軽減されるものではないことを示しています。
5.2 安全性確保の前提条件
使用前例の考え方については、当該原材料の品質不良等が原因となる回収等の安全性に関する問題が生じていないことが前提とされています。当該原材料を用いた医療機器の使用実績があり、変更時点においても安全性が確保されていることは製造販売業者において十分確認しておく必要があります。
5.3 同一品目の範囲の制限
本通知による取り扱いは、原材料の変更が同一品目の範囲を超える場合には適用されません。そのような変更については従来どおり別品目として承認申請または認証申請が必要となります。これにより、製品の基本的な特性を変更するような大幅な原材料変更については、従来通り厳格な審査が行われることが担保されています。
5.4 個別指導の可能性
安全性に関して疑義が生じるような事案があった場合には、使用前例の条件に該当していても承認事項一部変更承認申請による手続きが必要となる場合があります。また、別添のリストに掲げる成分に関して安全性に疑義が生じるような事案があった場合には、リストの更新にかかわらず、個別に必要な措置の指導を行うことがあるとされています。
まとめ
本通知は、医療機器の原材料変更手続きを大幅に合理化した重要な制度改正です。使用前例という概念の導入により、安全性が十分に確立された原材料の変更については軽微変更届による手続きが可能となり、企業の開発効率向上と患者への医療機器の迅速な提供が実現されました。
一方で、製造販売業者には適切な変更管理と安全性確保の責任が引き続き求められます。本通知の内容を正しく理解し、自社製品にどのように適用できるかを判断することが重要です。
弊社では、原材料変更手続きの具体的な運用やPMDA対応に関するご相談を承っております。制度の活用や申請に関してご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。