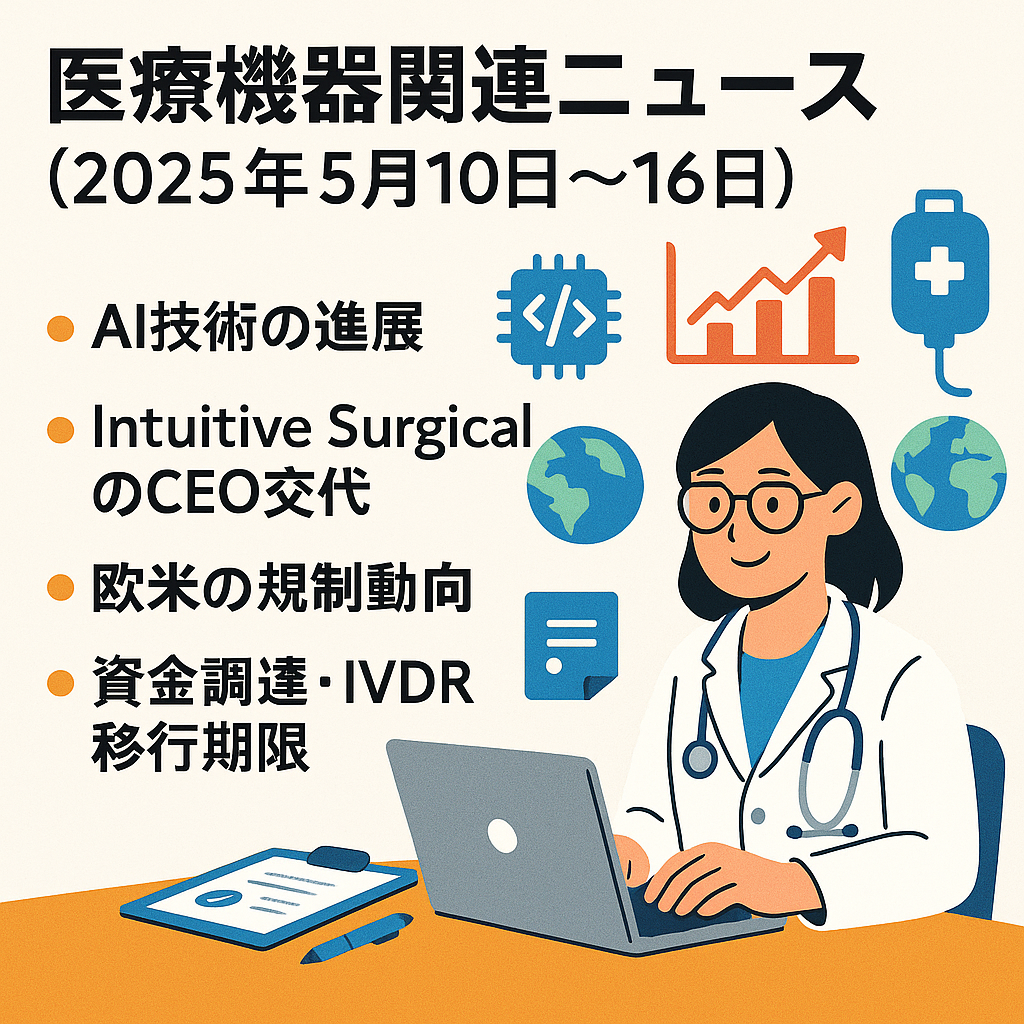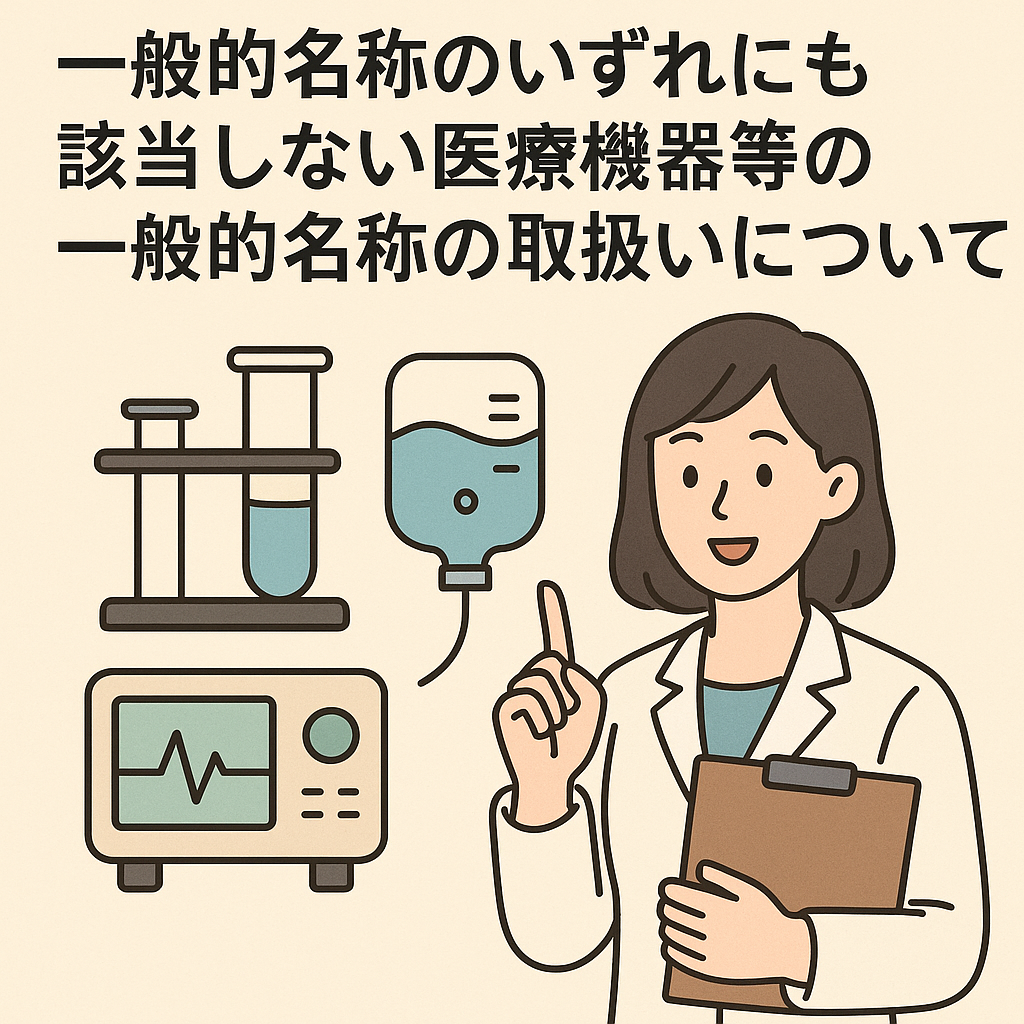概要
医療機器の規制は国や地域によって異なりますが、国際的な整合化の動きが進んでいます。その中心となったのが医療機器規制国際整合化会議(GHTF: Global Harmonization Task Force)です。本記事では、GHTFが策定した医療機器のクラス分類ルールを中心に、その背景や目的、具体的な内容、そして現在の規制への影響について解説します。国際調和の流れを理解することで、医療機器の開発・製造・流通に関わる方々の規制対応の一助となれば幸いです。
1. GHTFの概要と設立背景
1.1 GHTFとは
GHTF(医療機器規制国際整合化会議)は、1992年に設立された医療機器の規制に関する国際的な任意グループです。アメリカ、EU、カナダ、オーストラリア、日本の規制当局と産業界の代表者によって構成されていました。GHTFの主な目的は、医療機器の規制に関する国際的な整合化を促進し、安全で効果的な医療機器へのアクセスを確保しつつ、不必要な規制上の障壁を減らすことでした。
1.2 設立の背景と目的
1990年代初頭、医療機器の国際貿易が増加する中で、各国・地域の規制の違いが製品の国際展開の障壁となっていました。同じ製品でも国によって異なる申請手続きや評価基準が適用されることで、メーカーの負担が増大し、医療機器の市場投入が遅れるという問題がありました。
GHTFは、これらの問題を解決するため、以下の目的を掲げて活動を開始しました。
- 医療機器の安全性と有効性を確保するための規制の調和
- 技術革新を促進し、医療機器へのアクセスを向上させるための規制の効率化
- 規制当局間の情報交換と協力体制の構築
- 規制に関するガイダンス文書の作成と普及
1.3 現在のIMDRFへの移行
GHTFは2011年までに活動を終了し、その役割はIMDRF(International Medical Device Regulators Forum:国際医療機器規制当局フォーラム)に引き継がれました。IMDRFはGHTFの成果を引き継ぎながら、より広範な国際的枠組みで規制の調和を進めています。
2. GHTFクラス分類ルールの基本概念
2.1 リスクに基づく分類の考え方
GHTFのクラス分類ルールの根幹は「リスクに基づく分類」という考え方です。これは医療機器を、その使用に伴うリスクの程度に応じて分類するという原則です。リスクが高い医療機器ほど、より厳格な規制管理の対象となります。
GHTFは医療機器のリスクを評価する際、以下の要素を考慮することを推奨しています。
- 使用目的と機器の使用方法
- 人体との接触の程度と特性(非侵襲的、侵襲的、植込み型など)
- 使用部位(中枢神経系、心臓、血管系など)
- 使用期間(一時的、短期的、長期的)
- エネルギー供給の有無と特性(能動型、非能動型)
- 生物学的影響の有無(生体適合性、吸収性など)
2.2 4段階のクラス分類システム
GHTFは医療機器を4つのクラスに分類する枠組みを提案しました。
- クラスA(日本のクラスⅠに相当):低リスク 例:包帯、診察用具、再使用可能な手術器具など
- クラスB(日本のクラスⅡに相当):中~低リスク 例:注射針、吸引カテーテル、短期使用の接触レンズなど
- クラスC(日本のクラスⅢに相当):中~高リスク 例:人工関節、人工透析装置、埋め込み型神経刺激装置など
- クラスD(日本のクラスⅣに相当):高リスク 例:心臓ペースメーカー、植込み型除細動器、人工心臓弁など
この4段階の分類は、各国の規制システムの基盤となっています。日本では薬機法(医薬品医療機器等法)に基づき、一般医療機器(クラスⅠ)、管理医療機器(クラスⅡ)、高度管理医療機器(クラスⅢ・Ⅳ)として規制されています。
3. GHTFクラス分類ルールの詳細
GHTFのクラス分類ルールは大きく分けて以下の分類に従っています。
3.1 非侵襲型医療機器に関するルール
非侵襲型医療機器とは、身体に侵入しない医療機器を指します。GHTFでは以下のルールを設けています。
- 基本的に非侵襲型機器はクラスAに分類される
- 体液や組織の保存・輸送に使用される非侵襲型機器はクラスBに分類される
- 体液や組織の生物学的・化学的性質を変化させることを目的とした非侵襲型機器はクラスCに分類される
- 損傷した皮膚に接触する非侵襲型機器はその使用目的に応じてクラスB~Cに分類される
3.2 侵襲型医療機器に関するルール
侵襲型医療機器とは、身体の表面を通して体内に侵入する医療機器を指します。侵襲型機器は使用部位、使用期間、使用方法などによってさらに詳細に分類されます。
- 体腔に侵入する非外科的侵襲型機器は、使用期間と接触部位に応じてクラスA~Cに分類される
- 一時的使用(24時間未満)の外科的侵襲型機器は基本的にクラスBだが、例外事項がある
- 短期的使用(30日未満)の外科的侵襲型機器はクラスBだが、特定の部位に使用する場合は上位クラスになる
- 長期的使用(30日以上)の侵襲型機器や植込み型機器は基本的にクラスCだが、心臓や中枢神経系に使用する場合はクラスDになる
3.3 能動型医療機器に関するルール
能動型医療機器とは、電気エネルギーなどの動力源を必要とする医療機器を指します。
- 診断用能動型機器は基本的にクラスBだが、生命維持に関わる重要なパラメータを監視する場合はクラスCになる
- エネルギーを人体に供給する能動型治療機器は基本的にクラスBだが、エネルギーの特性や使用部位によってはクラスC、Dになる
- 医薬品や体液を人体に投与・除去する能動型機器は、その使用方法によりクラスB~Cに分類される
3.4 特別ルール
以下のような特別な特性を持つ医療機器については、追加のルールが設けられています。
- 医薬品を含有する医療機器はクラスCまたはDに分類される
- 動物由来の組織を含む医療機器はクラスC~Dに分類される
- 医療機器の消毒・滅菌に使用される機器はクラスBに分類される
4. 分析機器に関するGHTFルール
4.1 体外診断用医療機器(IVD)の特殊性
体外診断用医療機器(IVD)は、患者から採取した検体を体外で分析する機器です。直接患者の体に接触しないため、一般的な医療機器とは異なるリスク評価が必要です。IVDのリスクは主に「誤った検査結果が与える影響の大きさ」に基づいて評価されます。
4.2 IVDのクラス分類
GHTFは体外診断用医療機器を以下のように分類することを推奨しています。
- クラスA:個人及び公衆衛生上のリスクが低い、または存在しないIVD 例:臨床検査用試薬、バッファー溶液など
- クラスB:個人へのリスクは中程度、公衆衛生上のリスクは低いIVD 例:妊娠検査薬、尿検査機器など
- クラスC:個人へのリスクが高い、または公衆衛生上のリスクが中程度のIVD 例:血液型判定機器、感染症検査機器など
- クラスD:個人及び公衆衛生上のリスクが高いIVD 例:HIV検査機器、HBV検査機器など
特に、自己検査用診断機器については、専門知識を持たない一般の方が使用することを考慮し、より厳格な分類となる傾向があります。
5. GHTFルールの各国規制への影響
5.1 日本の医療機器規制への反映
日本では、薬機法(医薬品医療機器等法)において、GHTFのクラス分類の考え方を取り入れた医療機器のクラス分類制度を採用しています。
- クラスⅠ(一般医療機器):GHTFのクラスAに相当
- クラスⅡ(管理医療機器):GHTFのクラスBに相当
- クラスⅢ・Ⅳ(高度管理医療機器):GHTFのクラスC・Dに相当
このクラス分類に応じて、承認・認証・届出などの規制プロセスが定められています。
5.2 国際的な規制の調和状況
現在、多くの国がGHTF(現IMDRF)の枠組みを取り入れた規制システムを採用しています。各国・地域の主な規制状況は以下の通りです。
- EU:医療機器規則(MDR)、体外診断用医療機器規則(IVDR)
- 米国:FDA医療機器規制
- カナダ:医療機器規則
- オーストラリア:医療機器規制
- 日本:医薬品医療機器等法
- 中国:医療機器監督管理条例
- ブラジル:ANVISA医療機器規制
これらの国々では、基本的なクラス分類の考え方はGHTFに準拠していますが、詳細な運用や解釈には国ごとの違いが残っています。
5.3 国際認証制度(MDSAP)
医療機器単一監査プログラム(MDSAP: Medical Device Single Audit Program)は、IMDRFの取り組みの一つで、参加国(米国、カナダ、ブラジル、オーストラリア、日本)の規制要件を一度の監査で評価できるプログラムです。GHTFが推進した規制調和の考え方をさらに進めたもので、製造業者の負担軽減と規制の効率化を目指しています。
6. 製造業者のためのGHTFルール活用ガイド
6.1 初期開発段階での考慮事項
医療機器の開発初期段階から、GHTFクラス分類ルールを考慮することが重要です。製品の使用目的、使用方法、対象患者、使用期間などを明確にし、想定されるクラス分類を検討します。クラス分類は必要となる規制対応を左右するため、開発計画や市場投入戦略に大きな影響を与えます。
6.2 国際展開を見据えた規制戦略
グローバル市場を目指す医療機器メーカーは、GHTF/IMDRFの枠組みを活用した規制戦略を立てることが効果的です。各国の規制要件の共通点を特定し、最も効率的な申請順序や必要となるデータパッケージを計画することで、国際展開のスピードアップと費用削減が可能になります。
6.3 ボーダーラインケースの対応
医療機器と医薬品の境界や、複数のクラス分類ルールが適用可能なケースなど、分類が曖昧な「ボーダーライン製品」については、早期から規制当局に相談することが推奨されます。日本では、PMDAの相談制度を活用することで、適切なクラス分類と規制要件を確認できます。
7. 今後の展望
7.1 IMDRFによる更なる規制調和
IMDRFは、GHTFの成果を基盤としつつ、より広範な規制調和を目指しています。特に、ソフトウェア医療機器(SaMD)、人工知能/機械学習を活用した医療機器、サイバーセキュリティなど、新たな技術分野における規制の整備が進められています。
7.2 技術革新に対応する規制の進化
医療機器の技術革新のスピードは加速しており、既存のクラス分類ルールでは評価が難しい製品も登場しています。IMDRFでは、このような革新的技術に対応するための規制の枠組みの見直しや拡張が議論されています。
7.3 規制科学の発展
医療機器の安全性と有効性を科学的に評価するための「規制科学」の発展も重要な課題です。リアルワールドデータの活用やデジタルヘルス技術の評価方法など、革新的な規制アプローチが模索されています。
まとめ
GHTFが構築した医療機器のクラス分類ルールは、国際的な医療機器規制の基盤となっています。リスクに基づく分類という基本原則のもと、医療機器の特性(侵襲性、使用期間、使用部位など)を考慮した体系的なルールが策定され、世界各国の規制に反映されています。
日本の医療機器におきましても、GHTFルールに基づいたクラス分類がなされているものの、海外とのクラス分類が異なるケースも見受けられます。
日本の規制当局へ申請するにあたっては、海外のクラス分類を参考にしつつ、本邦においてどのような医療機器のクラス分類になるのかを正しく把握する必要があります。
弊社では、医療機器の輸入や薬事申請に関する相談まで幅広くサポートしています。国際展開や規制対応でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。