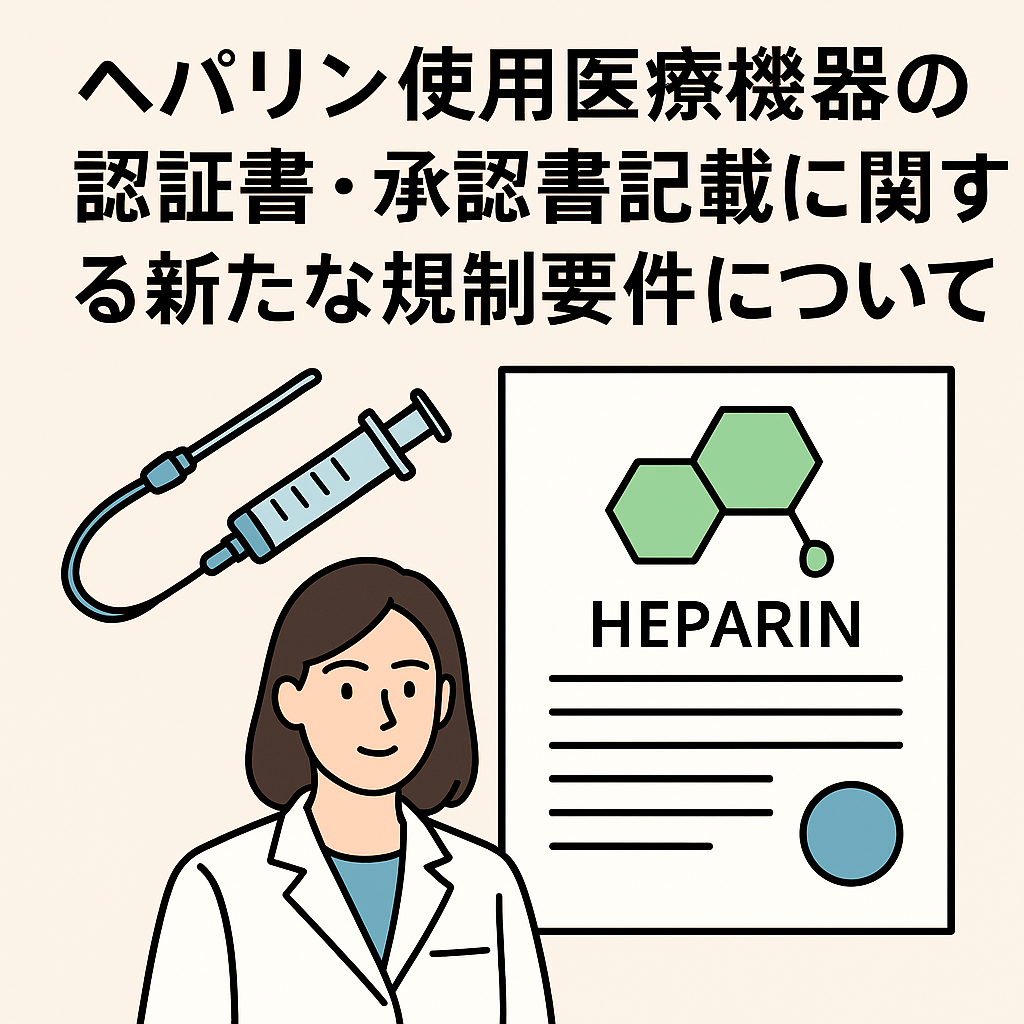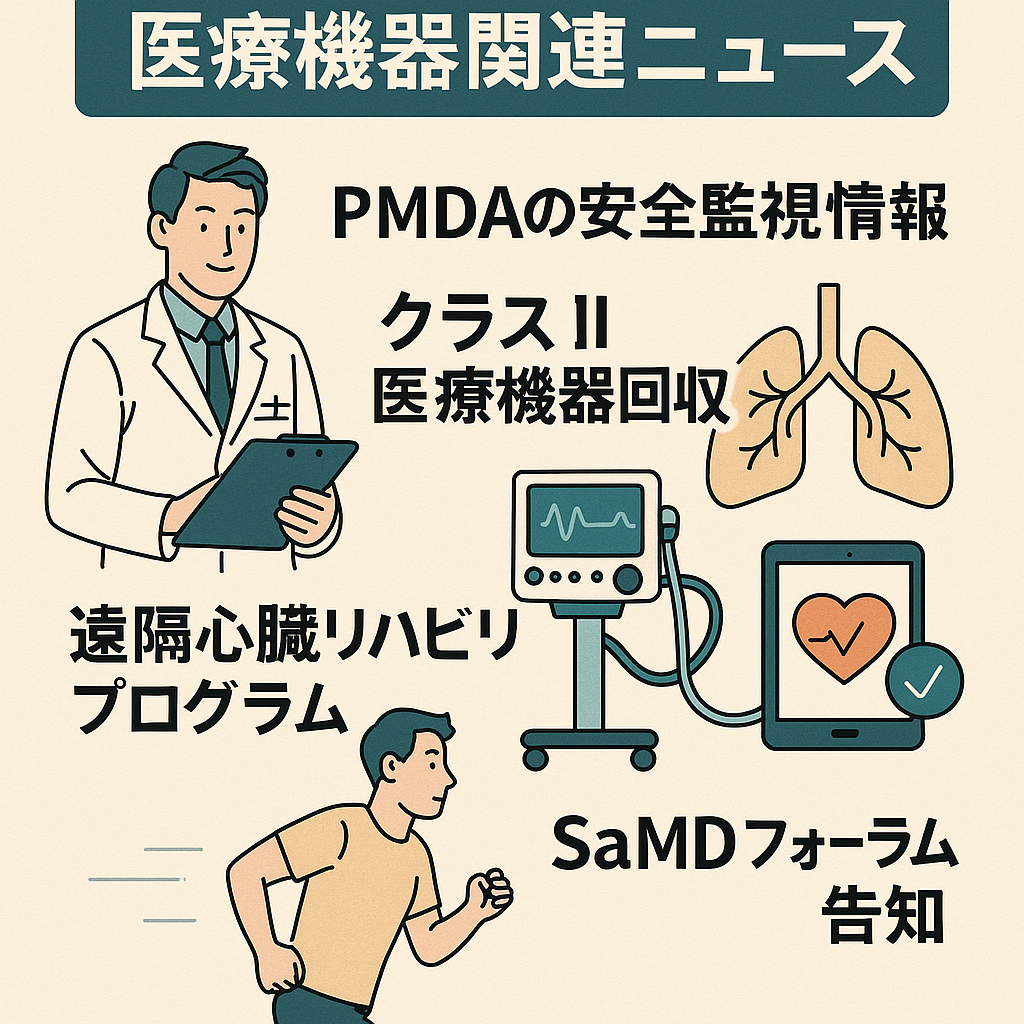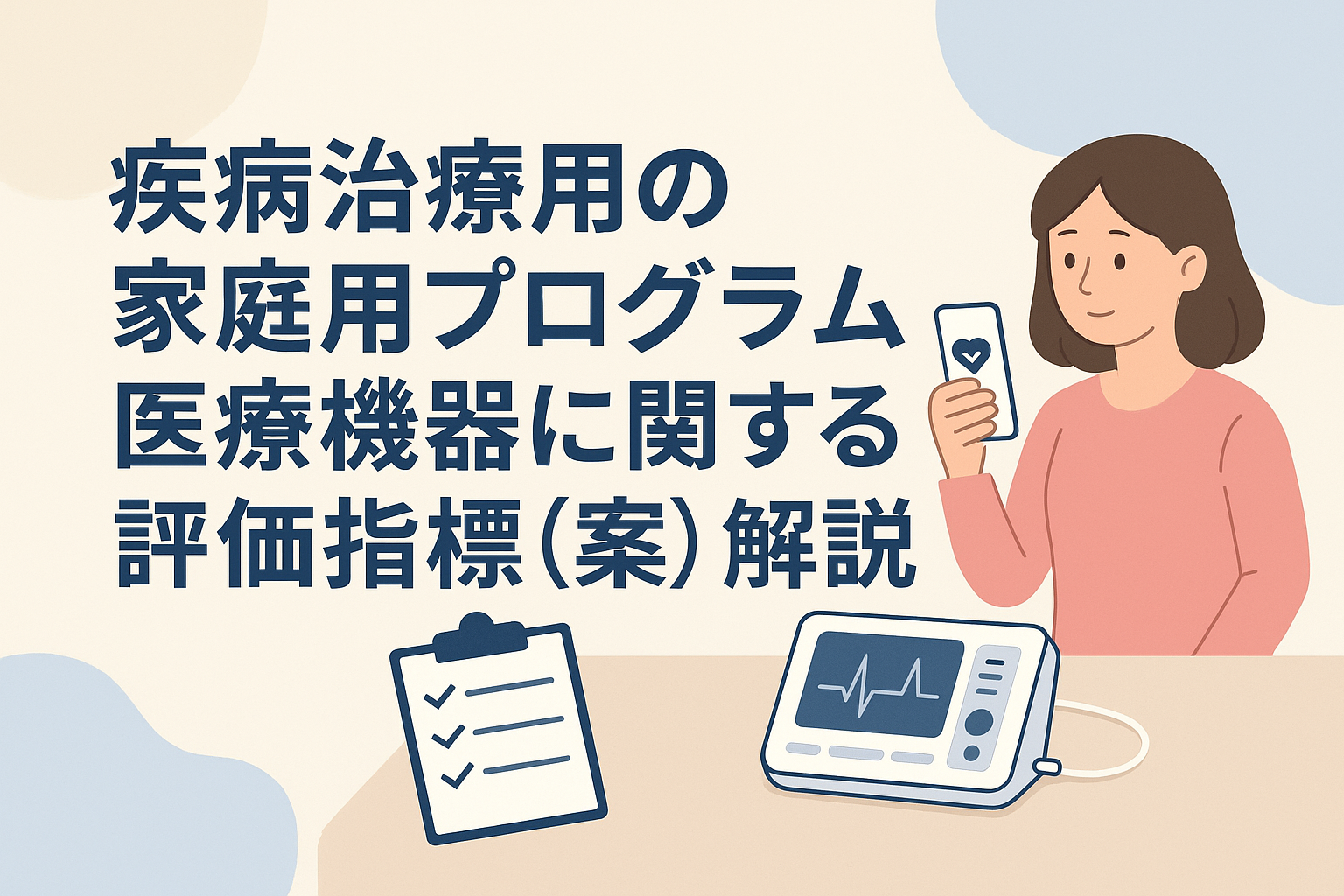概要
平成27年2月24日に発出された厚生労働省の通知「ヘパリンを使用した医療機器の取扱いについて」は、医療機器業界にとって重要な規制変更を示しています。この通知は、薬事法改正を背景に、ヘパリンを使用した医療機器の品質確保を強化するため、認証書および承認書におけるヘパリンの規格設定に関する新たな要件を定めたものです。
本通知の主なポイントは、ヘパリン様物質の混入防止対策の強化、薬局方準拠の試験方法の採用、既存承認書への規格追加義務、そして明確な実施スケジュールの設定です。これらの措置により、ヘパリン使用医療機器の安全性がより一層確保されることになります。
1. 通知発出の背景と意義
1.1 ヘパリン汚染事件を受けた安全対策の歴史
ヘパリンを使用した医療機器に対する規制強化は、過去に発生したヘパリン汚染事件への対応策として始まりました。平成20年に発生したヘパリン製剤への不純物混入事例では、国際的にアレルギー反応や重篤な副作用が報告され、医療安全の観点から緊急の対策が求められました。
これを受けて厚生労働省は、平成20年4月14日付けで「ヘパリン使用医薬品・医療機器の品質の確保の徹底等について」という事務連絡を発出し、出荷前におけるヘパリン様物質の混入確認を義務付けました。この事務連絡により、すべてのヘパリン使用製品について、適切な試験検査による品質確認が求められるようになりました。
1.2 薬事法改正に伴う規制体系の整備
平成25年に成立した薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、医療機器の規制体系が大幅に見直されました。この改正では、医療機器の特性に応じたより適切な規制の実現を目指し、承認・認証制度の整備や品質管理システムの強化が図られました。
本通知は、この法改正の趣旨を踏まえ、ヘパリン使用医療機器について、認証書・承認書への規格記載を体系的に整理することで、品質確保の実効性を高めることを目的としています。特に生物由来製品としてのヘパリン使用医療機器について、より厳格な品質管理体制の構築が求められています。
2. 認証書におけるヘパリン規格設定の要件
2.1 薬局方準拠の試験方法の採用
認証申請を行うヘパリン使用医療機器(生物由来製品)については、認証書においてヘパリンの規格を適切に設定することが義務付けられました。具体的には、日本薬局方、米国薬局方(USP)、または欧州薬局方(EP)の試験方法を引用することが求められています。
これらの薬局方は、国際的に認められた医薬品・医療機器の品質基準であり、科学的根拠に基づいた試験方法が規定されています。薬局方準拠の試験方法を採用することで、ヘパリンの品質が国際標準に適合していることを客観的に証明できます。
2.2 認証基準への影響
認証制度は、比較的リスクの低い医療機器について、第三者認証機関による迅速な審査を可能とする制度です。ヘパリン使用医療機器の認証においては、今後、ヘパリンの規格設定が認証基準の重要な要素となります。
認証申請者は、使用するヘパリンが適切な品質基準を満たしていることを、薬局方準拠の試験方法により立証する必要があります。これにより、認証機関は統一された基準でヘパリンの品質を評価でき、審査の透明性と予測可能性が向上します。
3. 承認書への規格追加に関する詳細規定
3.1 既存承認書への規格追加義務
すでに承認を取得しているヘパリン使用医療機器のうち、ヘパリン様物質に関する試験検査項目が承認書に記載されていないものについては、承認書記載事項の変更が必要となります。具体的には、承認書の原材料欄等に、現在実施しているヘパリンの試験検査内容を記載しなければなりません。
この措置により、既存の承認製品についても、現在の品質管理実態が承認書に適切に反映されることになります。薬局方に適合するヘパリンを使用している場合は、その旨を記載することで要件を満たすことができます。
3.2 追加的試験検査の承認書反映
平成20年の事務連絡発出以降、ヘパリン様物質に関する試験検査を追加的に実施している事業者については、これらの追加試験検査項目を承認書に追記することが求められています。これは、実際の品質管理体制と承認書記載内容の整合性を確保するための措置です。
追加試験の承認書への反映により、承認時点では想定されていなかった品質管理強化措置が正式に承認内容に組み込まれ、法的な位置付けが明確になります。
3.3 変更手続きの簡素化措置
承認書記載事項の変更手続きについては、手続きの負担軽減を図るため、一定の条件下で軽微変更届出による対応が認められています。具体的には、単に規格または試験方法の追加を行う場合、または薬局方適合の記載追加を行う場合については、軽微変更届出で対応可能です。
一方、これら以外の変更については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)との事前相談が必要となります。この区分により、事業者は適切な手続きを選択でき、規制当局も効率的な審査が可能となります。
4. 実施スケジュールと移行措置
4.1 実施期限の設定
承認書への規格追加に関する手続きは、平成28年3月1日までに完了することが義務付けられています。この期限設定により、すべてのヘパリン使用医療機器について、統一的なスケジュールで品質管理体制の強化が図られることになります。
実施期限の設定は、事業者に対して十分な準備期間を提供する一方で、安全対策の実効性を確保するための必要な措置です。事業者は、この期限に向けて計画的に対応を進める必要があります。
4.2 認証基準対象製品への特別措置
認証基準が作成された、または作成予定のあるヘパリン使用医療機器については、特別な配慮が設けられています。これらの製品については、通知発出日以降、速やかに承認書記載事項の変更手続きを行うことが望ましいとされています。
この措置は、認証制度への移行を円滑に進めるための配慮であり、認証基準の整備と承認書の記載内容を整合させることで、将来的な制度運用の効率化を図っています。
5. 医療機器業界への影響と今後の展望
5.1 品質管理体制への影響
本通知により、ヘパリン使用医療機器の製造販売業者は、品質管理体制の見直しと強化が必要となります。特に、試験検査体制の整備、薬局方準拠の試験方法の導入、品質文書の整備などが重要な課題となります。
また、承認書と実際の品質管理実態の整合性確保により、GMPの観点からも、より一層の品質保証体制の充実が求められます。これは短期的には事業者の負担となりますが、長期的には製品の信頼性向上と市場競争力の強化につながります。
5.2 国際調和への貢献
薬局方準拠の試験方法採用により、ヘパリン使用医療機器の品質評価が国際標準に合致することになります。これは、日本の医療機器の国際展開において重要な意味を持ちます。
国際的に認められた品質基準への準拠により、海外での承認取得や市場参入が円滑になる可能性があります。また、海外から輸入される医療機器についても、同様の品質基準が適用されることで、国内市場における公平な競争環境が整備されます。
5.3 将来的な規制動向
本通知は、医療機器の安全性確保に向けた継続的な取り組みの一環として位置付けられます。今後も、科学技術の進歩や国際的な規制動向を踏まえ、より効果的な安全対策が検討されることが予想されます。
特に、生物由来製品としての医療機器については、原材料の安全性確保がますます重要となることから、関連する規制要件の更なる整備が進む可能性があります。事業者は、こうした規制動向を注視し、継続的な対応体制の整備が求められます。
まとめ
平成27年2月24日付け厚生労働省通知「ヘパリンを使用した医療機器の取扱いについて」は、ヘパリン使用医療機器の品質確保を目的とした重要な規制措置です。薬事法改正を背景に、認証書・承認書におけるヘパリン規格の適切な設定と既存承認書への規格追加が義務付けられています。
特に、認証申請においては薬局方準拠の試験方法の採用が求められ、既存承認製品については平成28年3月1日までに承認書記載事項の変更が必要となります。さらに、軽微変更届出で対応可能な場合もあるため、実務上の判断が重要です。
弊社では、これらの通知対応や承認書・認証書の記載整備に関するご相談を承っております。
「自社の手続きが軽微変更で対応可能か判断したい」「承認書の記載整備を効率的に進めたい」といった具体的なご質問がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。