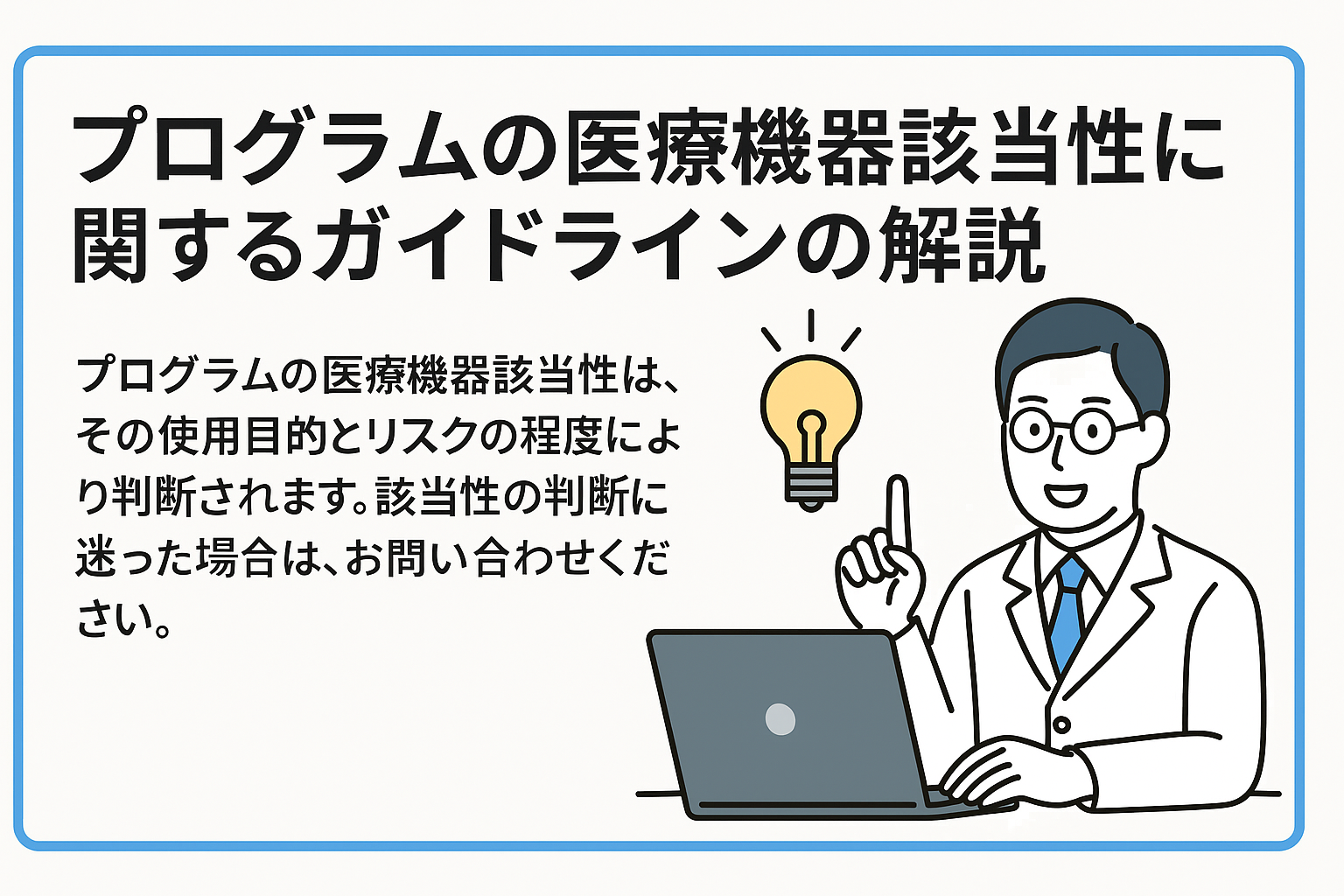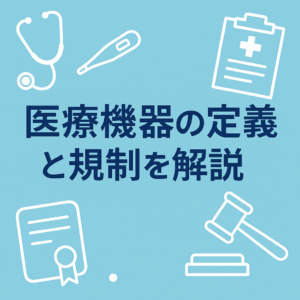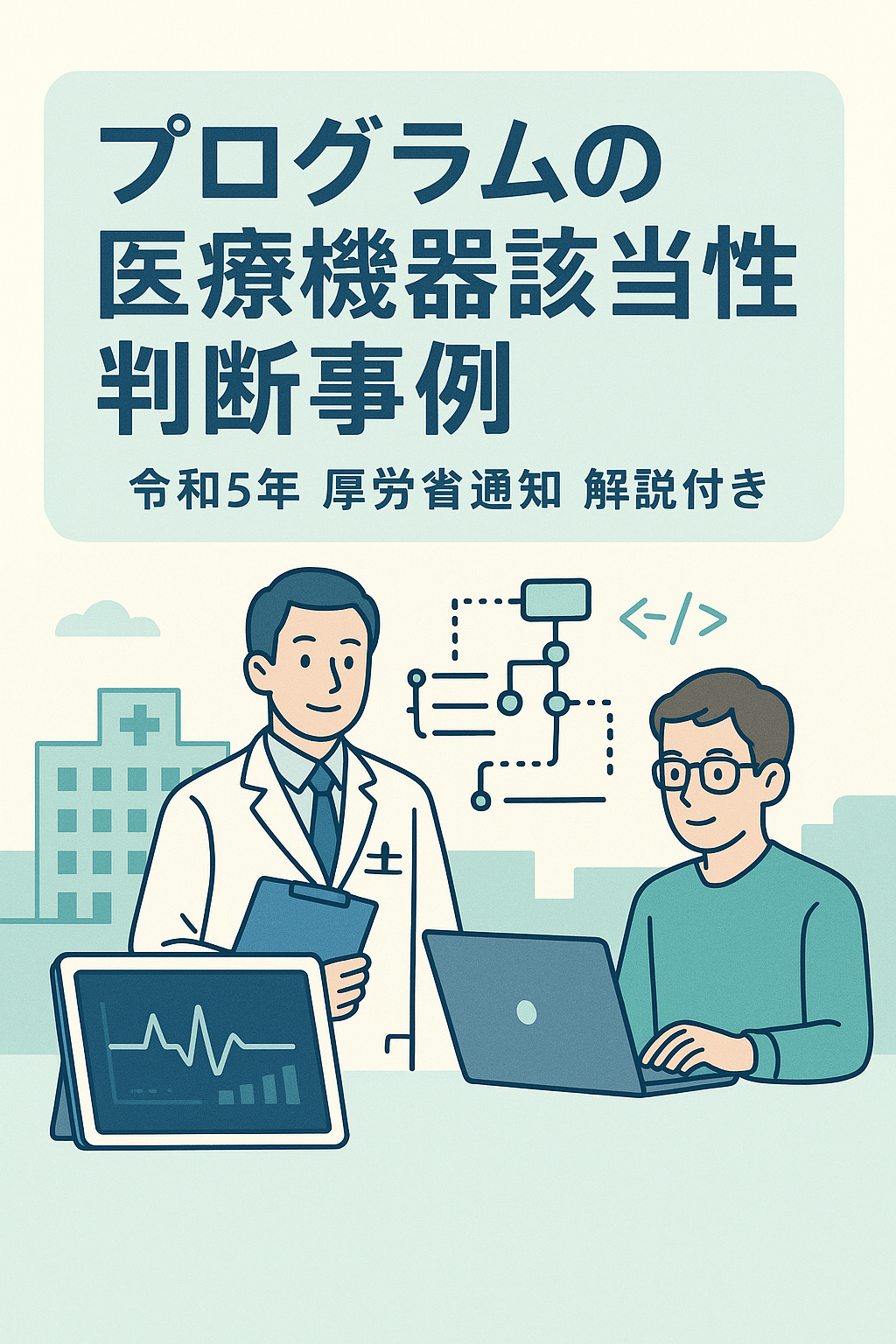概要
近年の科学技術の発展により、様々な新しいプログラムが医療分野で活用されるようになってきました。このような背景から、平成25年の医薬品医療機器等法の改正により、単体プログラムも医療機器として規制対象となりました。厚生労働省は令和3年3月31日に「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」を策定し、令和5年3月31日に一部改正を行いました。
このガイドラインは、医療機器プログラムの開発者に対して医薬品医療機器等法における規制の基本的要素と判断の参考となる情報を提供することを目的としています。医療機器プログラムとは、医療機器としての目的性を有し、意図したとおりに機能しない場合に患者または使用者の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラムを指します。ただし、生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの(一般医療機器に相当するもの)は除外されます。
本記事では、プログラムの医療機器該当性の判断基準や典型的な事例について解説し、開発者が適切に対応できるようにします。
1. 医療機器プログラムの基本的考え方
1.1 医療機器プログラムの定義と範囲
医薬品医療機器等法第2条第4項では、医療機器は「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されています。また、医薬品医療機器等法施行令別表第一において、疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム及び疾病予防用プログラム(プログラムを記録した記録媒体も同様)が医療機器として定められています。
ただし、各プログラムの定義においては「副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く」と規定されており、一般医療機器(クラスⅠ医療機器)に相当するプログラムは医療機器の範囲から除外されます。
1.2 医療機器プログラムの特徴
医療機器プログラムは、デスクトップパソコンやスマートフォンなどの汎用コンピュータにインストールすることで医療機器としての機能を与えるもの、または既存の医療機器にインストールすることで医療機器としての更なる機能を付与するものです。汎用コンピュータを利用して医療機器を操作するプログラムは、原則として操作対象の医療機器に含めたものとして取り扱われます。
本ガイドラインでは、プログラム単体またはプログラムを記録した記録媒体として流通するプログラムの医療機器該当性を対象としています。有体物と一体として流通するプログラムは、有体物部分も含めて一体の製品として医療機器該当性を判断します。
2. 医療機器該当性の判断基準
2.1 該当性の基本的考え方
特定のプログラムが医療機器に該当するか否かは、製造販売業者等による製品の表示、説明資料、広告等に基づき、当該プログラムの使用目的及びリスクの程度が医療機器の定義に該当するかにより判断されます。同じ機能を有するプログラムであっても、使用目的が異なれば医療機器該当性の判断が異なる可能性があります。
複数の機能を有するプログラムの場合、少なくとも1つの機能が医療機器プログラムの定義を満たす場合、全体として医療機器としての流通規制を受けることになります。また、汎用コンピュータ等のセンサと連動して医療機器としての機能を発揮するプログラムは、汎用センサ等を含めた一体の製品として見たときに医療機器の定義を満たすか否かにより判断されます。
2.2 医療機器に該当しない典型的な事例
以下の目的を持つプログラムは、医療機器に該当しません:
- 患者説明を目的とするプログラム
- 医療関係者が患者や家族に治療方法等を理解してもらうための患者説明用プログラム
- 院内業務支援、メンテナンスを目的とするプログラム
- 医療関係者が患者の健康記録等を閲覧等するプログラム
- 診療予約や受付、会計業務等の院内業務支援プログラム
- 医療機関に医療機器の保守点検や消耗品の交換時期等を伝達するメンテナンス用プログラム
- 使用者(患者や健康な人)が自らの医療・健康情報を閲覧等することを目的とするプログラム
- 個人の健康記録を保存、管理、表示するプログラム
- スポーツのトレーニング管理等の医療・健康以外を目的とするプログラム
- 生命及び健康に影響を与えるリスクが低いと考えられるプログラム
- 有体物の一般医療機器と同等の処理を行うプログラム
3. 該当性判断の手順
3.1 事前準備(使用目的、処理方法などの明確化)
プログラムの医療機器該当性の判断にあたっては、以下の項目を明確にする必要があります:
- プログラムの構成、提供方法
- プログラムの使用者(医療関係者、患者、健康な人など)
- プログラムの使用目的または効果
- プログラムが行う処理方法
- 処理のアルゴリズム
3.2 該当性判断のフローチャート
該当性判断は、別紙1「医療機器該当性に係るフローチャート」に従って行います。また、入力情報を基に疾病候補、個人または集団における疾病発症リスクを表示するプログラムについては、別紙2「医療機器該当性に係るフローチャート(疾病リスクを表示するもの)」を参照することもできます。
判断の流れは次のとおりです:
- プログラムの形態の確認(有体物と一体か、単体か)
- 医療機器を制御するプログラムかどうかの確認
- 疾病の診断・治療・予防に使用されることを目的としているかの確認
- 同一の処理を行う医療機器の有無の確認
- GHTFクラス分類ルールに基づくリスク判定
3.3 人の生命及び健康に影響を与えるリスクの程度
医療機器は患者へのリスクの高さに応じてクラスⅠからクラスⅣに分類されます。医療機器プログラムのクラス分類も、有体物にインストールされて使用可能な状態としたものを想定した上で、同様の考え方でリスクの程度を判定します。
リスクの程度の判断には、次の2点を考慮します:
- 医療機器プログラムにより得られた結果の重要性に鑑みて疾病の治療、診断等にどの程度寄与するのか
- 医療機器プログラムの機能の障害等が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれを含めた総合的なリスクの蓋然性
4. 臨床研究等における取扱い
医師または歯科医師が主体的に実施する妥当な臨床研究において用いられる医療機器の提供については、医薬品医療機器等法が適用されない場合があります。取扱いについては「臨床研究において使用される未承認の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の提供等に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用について」(平成30年4月6日付け薬生発0406第3号)を参照するとよいでしょう。
5. その他留意事項
5.1 医療機器に該当しないプログラムの標ぼうに関する留意点
医療機器ではないプログラム(一般医療機器相当のプログラムを含む)については、利用者による誤解を防ぐために「当該プログラムは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的としていない」または「当該プログラムは医療機器ではない」旨の記載、表示を行うことが望ましいとされています。
一般医療機器相当のプログラムは、有体物として一般医療機器が存在する医療機器と同等の性能等、または個別の判断により一般医療機器相当の性能等を標ぼうすることができますが、医療機器であるという誤解が生じないよう留意する必要があります。
5.2 適正使用のための周知啓発
プログラムの利用者が事業者(開発者)の想定外の目的で使用しないよう、使用対象者や適切な使用目的について十分な周知啓発を行うことが重要です。周知啓発の方法(自己学習、オンライントレーニング、対面研修等)はプログラムのリスクに応じて決定することが望ましいとされています。
まとめ
プログラムの医療機器該当性は、その使用目的とリスクの程度により判断されます。医療機器プログラムは、医療機器としての目的性を有し、意図したとおりに機能しない場合に患者または使用者の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるものを指します。
医療機器に該当するプログラムの開発者は、医薬品医療機器等法に基づく規制に従う必要があります。一方、医療機器に該当しないプログラムであっても、利用者による誤解を防ぐための表示や適正使用のための周知啓発を行うことが重要です。
医療機器プログラムの開発にあたっては、本ガイドラインを参考に、適切な対応を行いましょう。
開発中または提供中のプログラムが医療機器に該当するかどうか、判断に迷われる場合は、お気軽に弊社までご連絡ください。弊社では、医療機器プログラムに関する該当性判断のサポートから、各種申請・法規対応までをサポートいたします。