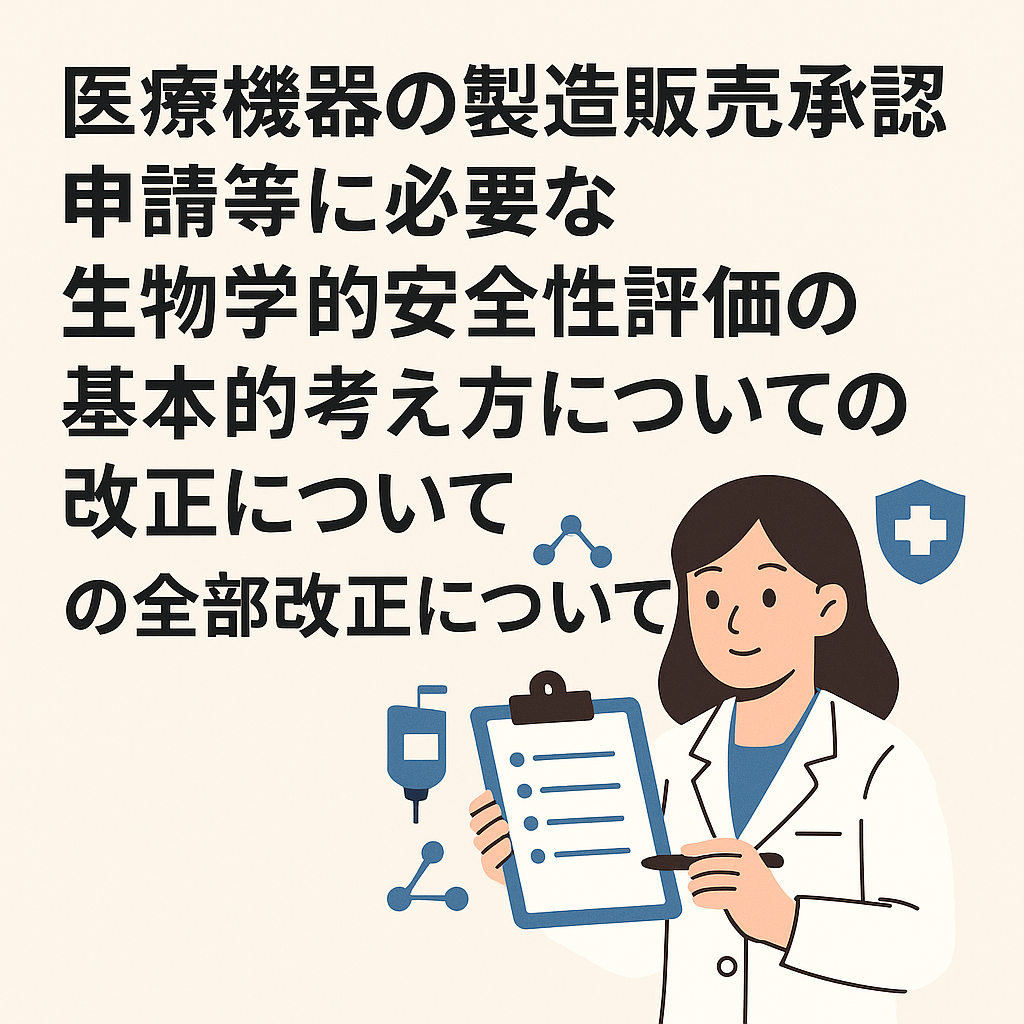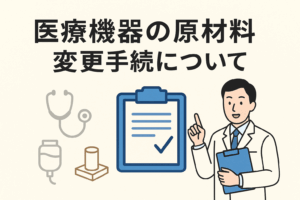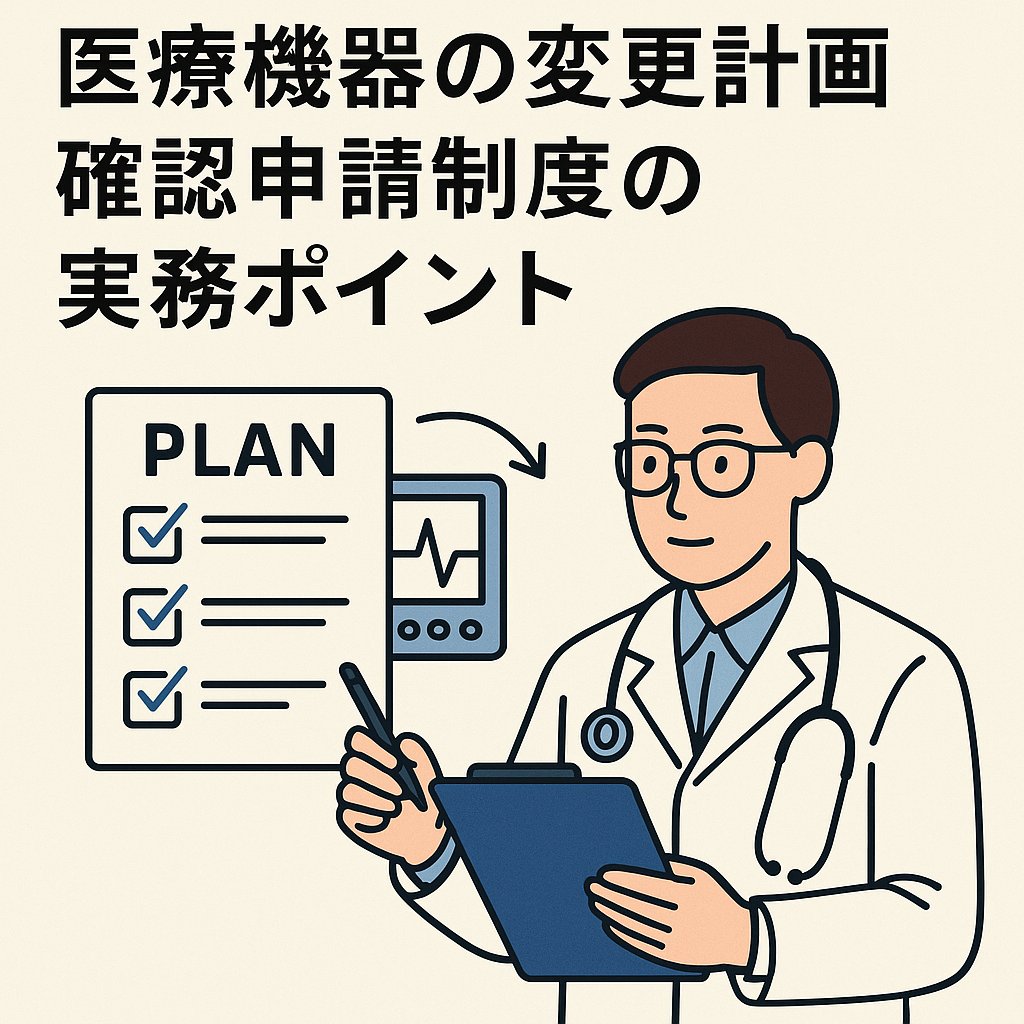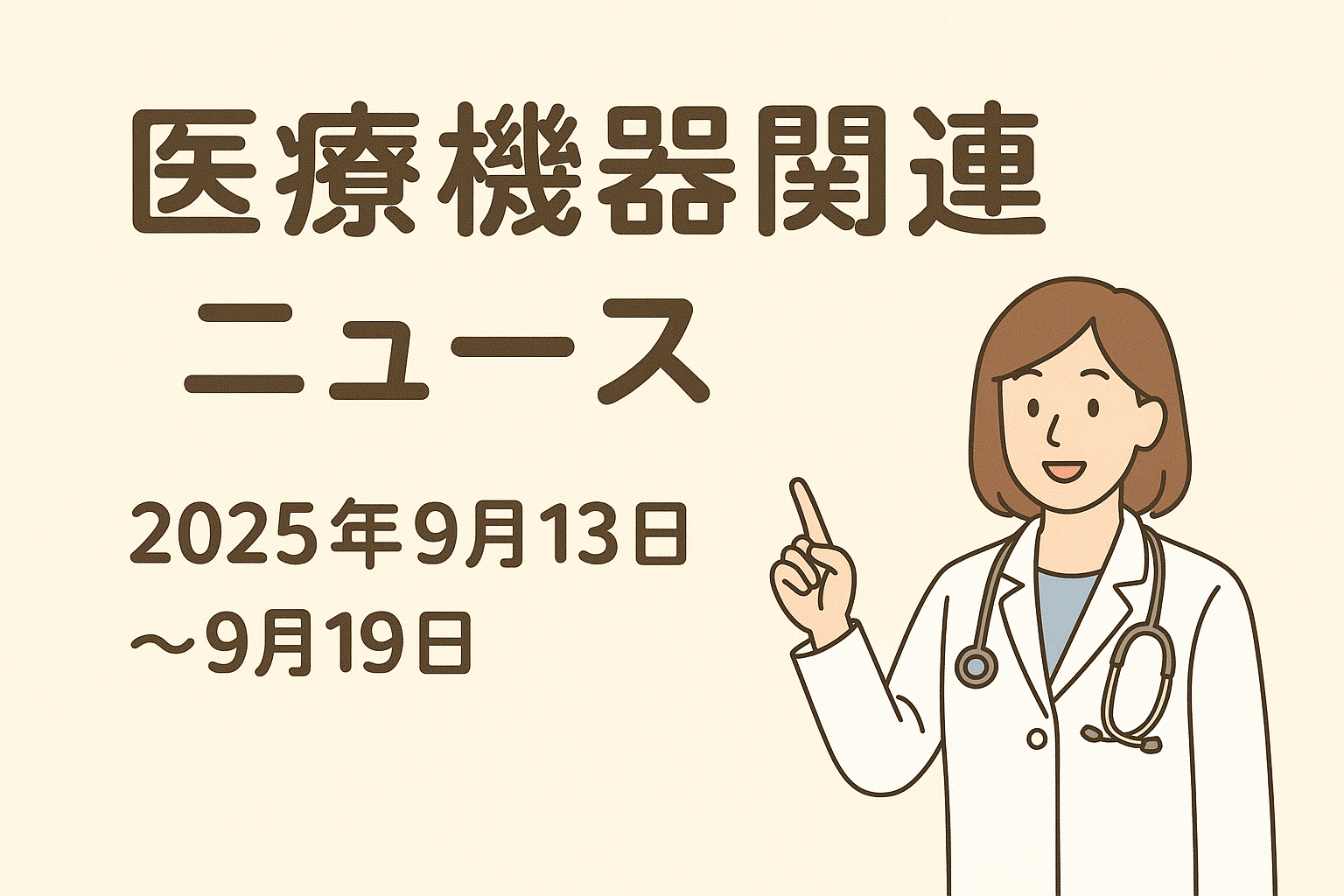概要
令和7年3月11日、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課から、医療機器の生物学的安全性評価に関する重要な通知が発出されました。本通知は、従来の令和2年1月6日付け通知を全面的に改正したもので、医療機器の製造販売承認申請等における生物学的安全性評価の基本的考え方を、製造販売業者がより実践的に活用できるよう再構成したものです。
主要な変更点として、国際規格ISO 10993-1およびJIS T 0993-1に基づくリスクマネジメントプロセスの一環としての生物学的安全性評価の位置づけが明確化され、評価手順がより体系的に整理されています。また、動物実験の3R原則への配慮、GLP準拠要件の明確化、そして評価結果の申請書添付資料(STED)への記載方法についても詳細に規定されました。
1. 生物学的安全性評価の基本的枠組み
1.1 評価対象と基本原則
生物学的安全性評価は、直接的または間接的に人体に接触する医療機器およびその構成材料を対象とします。評価においては、最終製品に対して実施することが原則となります。この際、単に原材料だけでなく、製造過程で使用される加工助剤、添加物、滅菌後の残留物なども考慮する必要があります。
評価の目的は、医療機器が生体適合性を有していることの確認と、臨床使用時に許容できない生物学的リスクが存在しないことを確認することです。重要な点として、生物学的リスクが認められた場合でも、直ちにその医療機器を不適格と判断するのではなく、ISO 14971およびJIS T 14971に従った総合的なリスクアセスメントを実施し、適切なリスクコントロールを行うことが求められています。
1.2 リスクマネジメントプロセスとの統合
本通知では、生物学的安全性評価をISO 14971のリスクマネジメントプロセスの一環として位置づけることが強調されています。まずリスクアセスメントを行い、その情報をもってリスク評価を実施するという段階的アプローチが採用されています。この統合的アプローチにより、生物学的リスクを医療機器全体のリスク管理の中で適切に位置づけ、バランスの取れた評価が可能となります。
2. 医療機器のカテゴリ分類とエンドポイント
2.1 接触期間によるカテゴリ分類
医療機器は接触期間により3つのカテゴリに分類されます。累積的な総接触時間が24時間以内の「一時的接触」、24時間を超え30日以内の「短・中期的接触」、そして30日を超える「長期的接触」です。この分類は、生体への暴露期間に応じたリスク評価を可能にし、必要な試験項目の選定の基準となります。
2.2 接触部位によるカテゴリ分類
接触部位による分類では、組織、粘膜、血液等への接触部位ごとに医療機器が分類されます。体内での接触部位の違いは、必要とされる生物学的安全性評価の項目と深度に直接影響を与えるため、正確な分類が重要となります。
2.3 生物学的安全性エンドポイント
必要な評価項目として、細胞毒性、感作性、刺激性、全身毒性(急性、亜急性、亜慢性、慢性)、埋植、遺伝毒性、発がん性、血液適合性が規定されています。さらに、医療機器の臨床使用実態に応じて、材料由来の発熱性、生体内分解性、生殖発生毒性をエンドポイントに含めることも検討が必要です。これらのエンドポイントは、医療機器のカテゴリ分類に応じて選択的に評価されます。
3. 試験実施における重要事項
3.1 動物実験における倫理的配慮
動物実験を実施する際は、動物の愛護及び管理に関する法律、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、厚生労働省の基本指針、およびISO 10993-2に従うことが義務付けられています。特に重要なのは、動物実験代替法の3R原則の遵守です。Replacement(実験動物の置き換え)、Reduction(実験動物数の削減)、Refinement(実験方法の改善による動物の苦痛の軽減)の各原則を適切に適用し、動物の福祉に最大限配慮することが求められています。
3.2 GLP準拠要件
生物学的安全性評価を目的とした試験は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(GLP省令)に従って実施することが必要です。ただし、重要な例外として、製品の機能性や有効性を評価する試験で安全性評価が副次的な目的である場合や、指定管理医療機器の場合はGLP準拠が必須ではありません。この区別を正確に理解し、適切に適用することが規制対応において重要となります。
4. 申請書添付資料への記載方法
4.1 評価手順の体系化
申請書添付資料(STED)への記載は、以下の4つの手順に沿って体系的に行います。
手順1では、生物学的安全性リスクアセスメントを実施します。これには、評価対象の有無の確認、臨床使用情報および物理学的・化学的情報の収集、既承認品等との生物学的同等性情報の収集が含まれます。
手順2では、評価対象の医療機器カテゴリと要求エンドポイントを確認します。ISO 10993-1またはJIS T 0993-1の分類表を参照し、適切なカテゴリと必要な評価項目を特定します。
手順3では、試験実施の要否を確認し、不足している試験があれば実施します。既存データの活用可能性も含めて検討し、効率的な評価戦略を立案します。
手順4では、総合的な生物学的安全性のリスク評価を行います。個別の試験結果を統合し、医療機器全体としての生物学的安全性を評価します。
4.2 記載事例の活用
医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトには、STED記載事例が公開されています。これらの事例は作成の参考となりますが、あくまで一例であり、各医療機器の特性に応じた適切な記載が必要です。関連する通知に従い、十分な説明がなされていれば、必ずしも事例通りの記載でなくても問題ありません。
5. 関連公的規格の活用
5.1 ISO 10993シリーズの重要性
本通知では、ISO 10993シリーズ全体が生物学的安全性評価の基準として位置づけられています。特に重要な規格として、ISO 10993-3(遺伝毒性、がん原性及び生殖発生毒性)、ISO 10993-4(血液適合性)、ISO 10993-5(細胞毒性)、ISO 10993-6(埋植)、ISO 10993-10(感作性)、ISO 10993-11(全身毒性)、ISO/TS 10993-20(免疫毒性)、ISO 10993-23(刺激性)が挙げられています。
5.2 補完的な規格の活用
ISO 10993シリーズ以外にも、ISO/TS 21726(毒性学的懸念の閾値の適用)、ISO 18562シリーズ(呼吸ガス経路の生体適合性評価)、ISO 14971(リスクマネジメント)、ISO 9394(眼用光学機器の生体適合性)などの関連規格が参考として示されています。これらの規格を適切に活用することで、より包括的で科学的根拠に基づいた評価が可能となります。
まとめ
今回の改正通知は、従来の考え方を全面的に見直し、ISO 10993シリーズやJIS T 0993-1に基づくリスクベースアプローチを中心に据えた内容へと刷新されました。接触期間や接触部位に応じた分類の明確化、必要なエンドポイントの整理、GLP準拠要件や3R原則の徹底など、製造販売業者が実務で直面する評価プロセスが具体的に示されています。
これにより、製造販売承認申請においては、単なる試験実施ではなく、総合的なリスクアセスメントと体系的なSTED記載が求められます。規制当局も科学的根拠に基づいた評価を重視しているため、各社は自社の品質マネジメントシステムに新たな要件を的確に組み込み、効率的かつ確実な対応を進める必要があります。
弊社では、本改正内容を踏まえた生物学的安全性評価の戦略立案、試験計画・リスクアセスメントの妥当性確認、申請資料作成支援まで幅広くサポートしております。規制対応に関するご不安や、効率的な評価戦略の構築についてお悩みがございましたら、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせください。