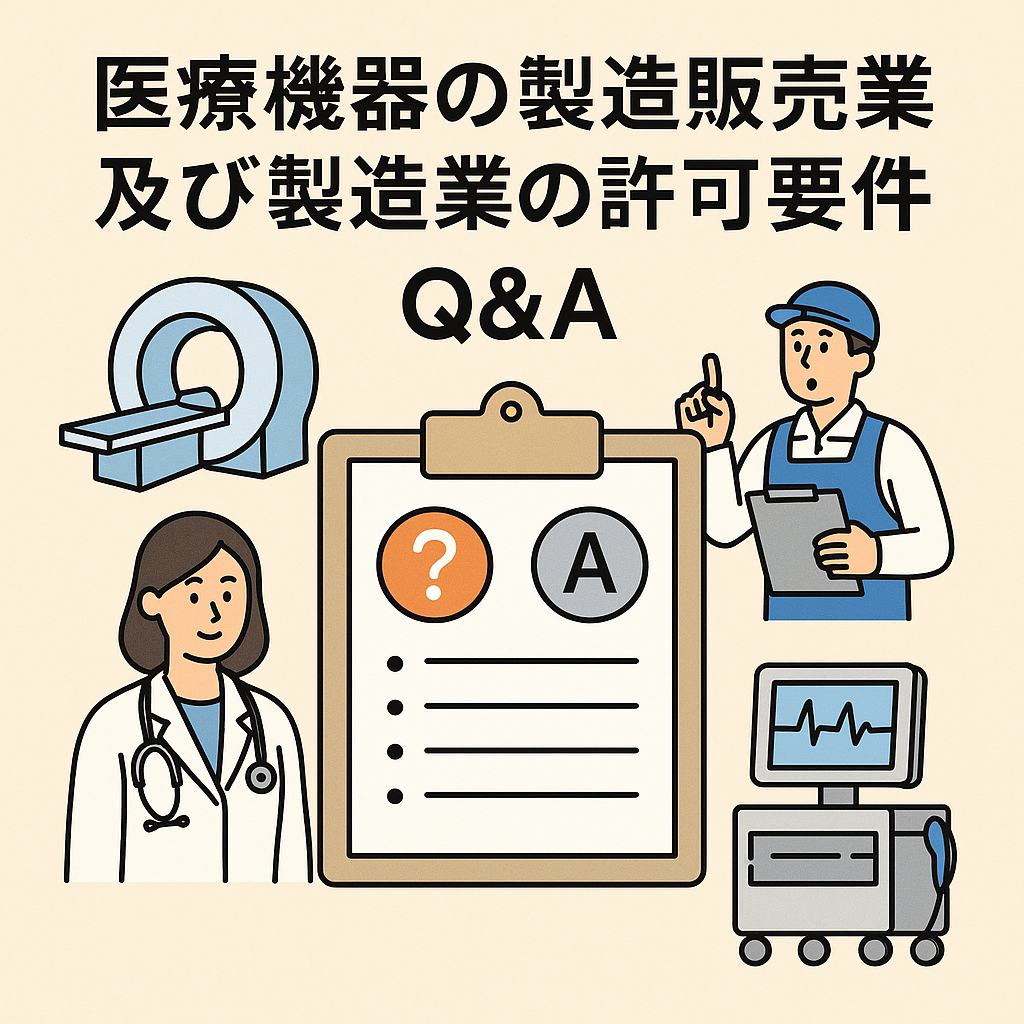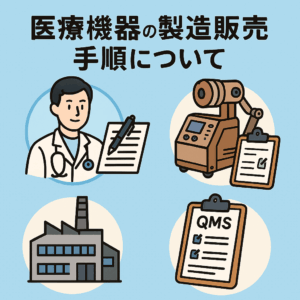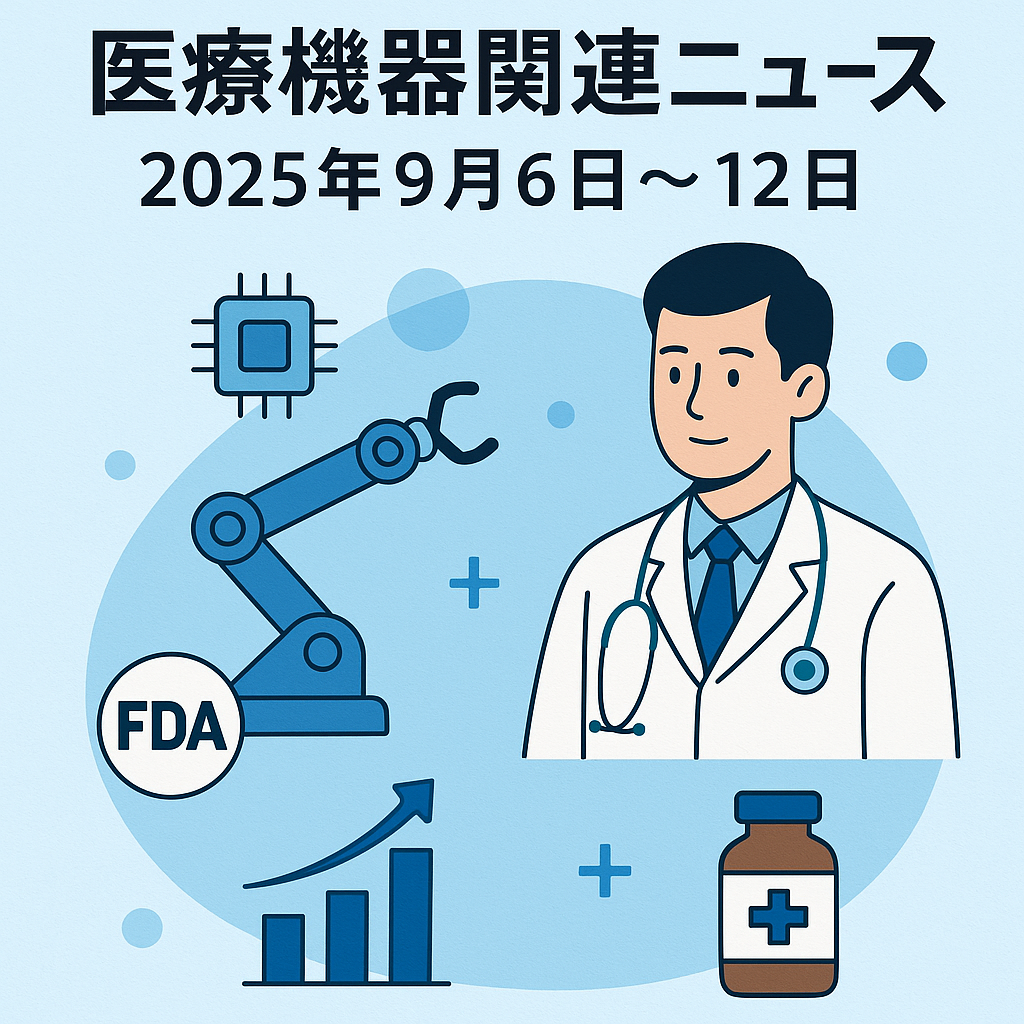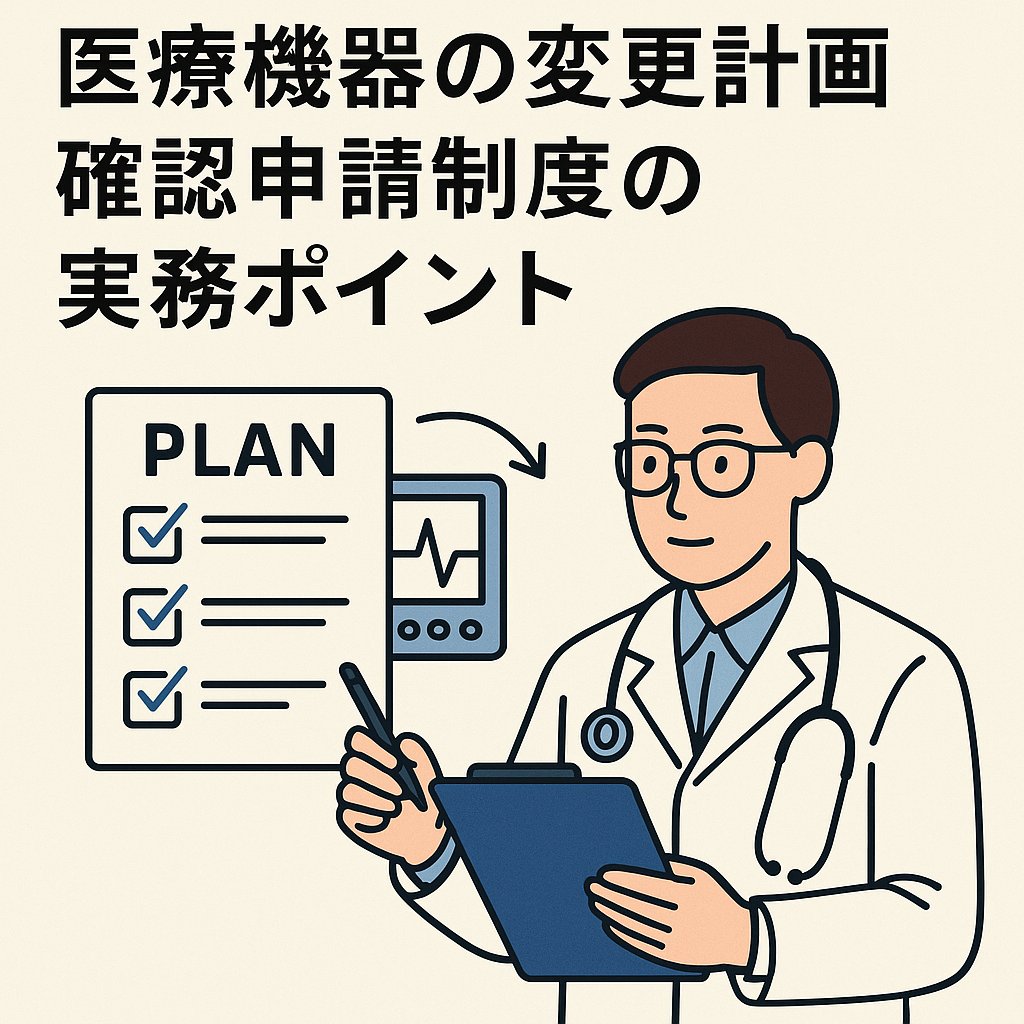概要
平成24年8月30日に薬事法施行規則の一部を改正する省令が公布され、医療機器の製造販売業及び製造業における総括製造販売責任者や責任技術者の資格要件が変更されました。本記事では、この改正に伴い厚生労働省から発出された質疑応答集(平成25年1月11日付)の内容を基に、実務上重要となるポイントを整理します。
医療機器業界では、品質管理と安全管理の要となる総括製造販売責任者や責任技術者の適切な配置が求められています。今回の改正では、これらの責任者の資格要件について、学歴要件の追加や単位取得の明確化など、重要な変更が加えられました。本記事では、現場で実際に生じる疑問に対する具体的な回答を示しながら、改正内容の理解を深めていきます。
1. 総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件(改正事項)
1.1 情報学分野の専門課程への追加
薬事法施行規則の改正により、総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件として認められる専門分野に、新たに「情報学」が追加されました。規則第85条第3項第1号及び第91条第3項第1号において、従来の農学、園芸学、水産学及び畜産学に加えて、コンピュータや情報ネットワークを専門とする課程も含まれることになりました。
これは情報学に関連する分野として、コンピュータ、情報ネットワーク等の情報機器類を専門に取り扱う課程を意味します。医療機器の高度化・デジタル化が進む中で、情報技術の専門知識を持つ人材の重要性が認識された結果といえます。
1.2 生物学系分野の追加と判断基準
改正により、規則第85条第3項第1号及び第91条第3項第1号に「生物学」が新たに追加されました。この生物学には、バイオテクノロジー、遺伝子工学のように生物工学技術を応用した分野が含まれます。具体的には、農作物の栽培技術、森林科学、水産学関連の加工技術、漁業学、畜産関連の加工機械技術学、品種学等を講義内容とする科目も生物学に含まれると解釈されています。
ただし、講義内容を確認の上判断する必要があることから、単にバイオテクノロジー学科や遺伝子工学科といった学科名だけでは判断できません。実際の講義内容を精査し、生物学に該当するかを個別に判断する必要があります。
1.3 医療機器分野に関連する技術と工学の解釈
規則第85条第3項第1号及び第91条第3項第1号における「専門の課程に工学が追加されたが、学科名等では工学と名が付いているものの、社会工学、教育工学など医療機器分野とは全く異なる分野と融合したような学科を卒業している場合、工学に該当すると判断して差し支えないか」という問いに対して、医療機器分野に関連する技術に関する工学と考えられる場合には学科名等で判断することで差し支えないとされています。
社会工学、教育工学など医療機器の安全管理、品質管理の責任者として備えるべき知識を学んでさえいれば、講義内容等を検討した上でその該当性を判断することが必要です。
2. 総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件(単位)
2.1 単位取得証明の具体的要件
医療機器の総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件について、当該者は高等学校普通科を卒業し、単位取得証明により理科Iの単位を取得している場合、本事例は薬事法施行規則第85条第4項第2号又は第91条第4項第2号の資格要件を満たすと判断して差し支えないとされています。
理科Iや理科総合A、Bなどの理科系科目は高等学校教育における物理、化学、生物及び地学の基礎的な概念を学ぶものであり、これらの科目を修得したときも同様に取り扱うことができます。
2.2 解剖生理学等の専門科目の取り扱い
医療機器の総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件について、当該者が短期大学衛生技術学科を卒業し、単位取得証明により解剖生理学、解剖組織学、生化学、病理学、電子工学、血液学、血清学、臨床生理学、放射化学等で合計31単位を取得している場合も資格要件を満たします。
これらの科目は薬事法施行規則第85条第3項第1号又は第91条第3項第1号の資格要件を満たすと判断して差し支えありません。解剖生理学、解剖組織学、病理学、血液学、血清学及び臨床生理学は医学として、生化学及び放射化学は化学として、電子工学は工学として認められます。学部・学科名等で資格要件の該当性が判断できない場合は、単位取得状況や講義内容等を総合的に検討し判断する必要があります。本事例では、医学・化学・工学に該当すると思料される科目を30単位以上取得しており、同号の資格を有すると判断して差し支えありません。
3. 総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件(学歴)
3.1 海外の大学における機械学、工学修得の取り扱い
医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者の資格要件について、当該者がアメリカ合衆国の大学の機械工学科を卒業している場合、単位取得状況等を総合的に検討し、本事例は規則第85条第3項第4号又は第91条第3項第4号の資格要件を満たすと判断して差し支えありません。
海外の大学において機械学、工学を修得した場合については、薬事法施行規則の一部を改正する省令及び薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について(平成24年8月30日付け薬食審査発0830第10号及び薬食安発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び厚生労働省医薬食品局安全対策課長連名通知)に基づき、日本の教育制度における大学と同等の専門内容で、同等の単位・時間数等で修得していれば、資格要件を満たすものと判断して差し支えありません。
日本の大学と同等程度の確認を行うには、例えば大学の単位互換などについて国際的に用いられている「学位等の認証に関するユネスコ地域条約」や、海外の大学が日本の基準とほぼ同一授業単位であるセメスター制度か否かなどを参考にできます。また、品質管理に関する業務の責任者及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者との相互の密接な連携を図ることができるよう、コミュニケーションに問題がないかなど、当該者が業務を行う上で支障がないことを念のため確認することも重要です。
3.2 大学卒業と同等以上の学歴の判断
医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者の資格要件について、当該者がたとえば大学で工学に関する専門科目を30単位以上取得しているが、当該大学を卒業していない場合、本事例は規則第85条第3項第1号又は第91条第3項第1号の資格要件を満たさないと判断して差し支えありません。
規則第85条第3項第1号又は第91条第3項第1号では「専門の課程を修了した者」としており、単位を取得しただけで大学を卒業していない場合には「専門の課程を修了した者」とは言えないため、資格者として認めることはできません。
3.3 学歴要件における従事経験の考慮
医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者の資格要件について、当該者が規則第85条第3項第2号又は第91条第3項第2号に定める従事経験を経た後、同号に定める学歴を備えた場合、本事例は規則第85条第3項第2号又は第91条第3項第2号の資格要件を満たすと判断して差し支えありません。
法令上では「(前略)専門の課程を修了した後、(中略)業務に三年以上従事した者」と明記しており、必要な学歴を備えた後に三年以上の従事経験を必要としています。学術的知識を持った上の従事経験とそうでない場合とでは当該業務の理解や質が異なると考えられるため、資格要件を満たすためには正しい順序が必要です。
4. 総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件(従事経験)
4.1 従事経験として認められる業務の範囲
医療機器の総括製造販売責任者の従事経験について、薬局において品質管理業務を行っていた者(薬局製造販売医薬品製造業の管理者及び薬局製造販売医薬品製造販売業の総括製造販売責任者も含む)は、規則第85条第3項第2号及び第3号に定める従事経験を満たすと判断して差し支えありません。
総括製造販売責任者に求められる業務は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号、以下「GQP省令」という。)及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号、以下「GVP省令」という。)の遵守を含め市場出荷の最終判断責任者としての責任を伴うものです。薬局製造販売医薬品についてはGQP省令及びGVP省令が適用されないため、薬局における従事経験をもって有資格者と認めることはできません。
4.2 品質確保業務の具体的内容
医療機器の総括製造販売責任者の従事経験における資格要件のうち、医療機器販売業者で品質確保業務に従事していた者は、規則第85条第3項第2号及び第3号に定める従事経験を満たすと判断して差し支えありません。
規則第165条で規定する販売業者等の行うべき「品質確保」と薬事法(昭和35年法律第145号)第18条第1項で規定する製造販売業者の行うべき「品質管理」は明確に異なります。医療機器販売業者の品質確保業務の従事経験をもって、規則第85条第3項第2号及び第3号に定める総括製造販売責任者の従事経験を満たすとは考え難いため、資格要件を満たすとは言えません。
4.3 医薬品分野での経験の活用
医療機器の総括製造販売責任者の従事経験における資格要件のうち、薬事法の平成17年改正以降、医療機器製造業者において品質管理業務を行っていた者は、規則第85条第3項第2号及び第3号に定める「医薬品又は医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務」を満たすと判断して差し支えありません。
「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の品質管理の基準に関する省令の施行について」(平成16年9月22日薬食発第0922001号医薬食品局長通知)第2の2の(5)において、製造業における製造管理又は品質管理に係る業務は品質管理業務に類する業務とされているので、製造販売業における実質的な品質管理理の責任者である品質保証責任者の要件に準じて、総括製造販売責任者の資格要件においても、製造業における品質管理業務を「医薬品又は医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務」と判断して差し支えありません。
4.4 動物用医薬品分野での経験
医療機器の総括製造販売責任者の従事経験における資格要件について、動物用医薬品の製造販売業者における品質管理又は製造に関する従事経験がある場合、規則第85条第3項第2号及び第3号に定める資格要件を満たすと判断して差し支えありません。
動物用医薬品製造販売業と医療機器製造販売業とでは品質管理及び製造販売後安全管理の基準が別で定められており、動物用医薬品の製造販売業における品質保証・安全管理業務や製造業における業務の従事経験をもって、人のための医療機器に関する同業務を経験したことにはならないため、資格要件を満たすとは言えません。
4.5 研究開発部門での従事経験
医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者の従事経験のうち、研究開発等で製品の研究開発業務に従事していた場合、規則第85条第3項第2号及び第3号又は第91条第3項第2号及び第3号に定める資格要件を満たすと判断して差し支えないとされています。
一般的に製品の開発段階における業務については、品質管理に関わるものと考えにくいため、原則として規則第85条第3項第2号及び第3号又は第91条第3項第2号及び第3号に定める資格要件を満たすとは言えません。
4.6 一般医療機器の取扱いに関する経験
一般医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者の資格要件について、医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務又は医療機器の製造に関する業務に5年以上従事していた者は、規則第85条第4項第3号又は第91条第4項第3号に該当すると判断して差し支えありません。
「医療用具の取扱について」(昭和36年7月8日付け薬発第281号薬務局長通知)第2の3の(3)において、旧薬事法における責任技術者の資格要件(厚生大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認めた者)として当該医療用具の製造の実務又は研究に少なくとも「5年以上の従事している者」を例示しています。このため、一般医療機器の製造販売業における総括製造販売責任者及び製造業における責任技術者についても、同通知に従い、医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に5年以上従事していた者は、規則第85条第4項第3号該当する者として、また医療機器の製造に関する業務に5年以上従事していた者は、第91条第4項第3号に該当する者として取り扱って差し支えありません。
なお、資格要件とは別に、新規に一般医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者となった者は講習会等への積極的に参加することが望まれます。
5. 兼務について
5.1 製造販売業者と卸売販売業者との兼務
第1種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者と医薬品卸売販売業の管理薬剤師との兼務は可として差し支えありません。
薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について(平成16年7月9日付け薬食発第0709004号厚生労働省医薬食品局長通知、以下「薬食発第0709004号通知」という。)の第26の1(7)において、第1種医薬品製造販売業者の総括製造販売責任者と卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務はできないものとされていますが、第1種医療機器製造販売業については、その保健衛生上の危害の発生のおそれを勘案すれば、同様に兼務はできません。
5.2 異なる企業間での兼務
第2種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者と医療機器販売業の管理者との兼務について、業務を行う場所が同一所在地であれば兼務は可として差し支えありません。
薬食発第0709004号通知の第26の1(7)において、医薬品における第2種製造販売業の総括製造販売責任者と卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務については、それぞれの業務に支障を来さない場合等の合理性がある範囲において認められるため、同様に、本事案に関しても同一所在地で兼務することに合理性が認められれば兼務できるとして差し支えありません。
5.3 品質保証責任者と安全管理責任者の兼務
第1種医療機器製造販売業の品質保証責任者及び安全管理責任者と製造業の責任技術者との兼務(事業所が同一所在地の場合)について、品質保証責任者と責任技術者は可能、安全管理責任者と責任技術者は兼務不可として差し支えありません。
品質保証責任者と責任技術者の兼務は可能ですが、安全管理責任者と責任技術者の兼務は不可として差し支えません。薬食発第0709004号通知の第26の1(3)において、同一法人において同一施設内での品質保証責任者と製造業の責任技術者との兼務は認められており、安全管理責任者と製造業の責任技術者との兼務は認められていません。これは、一般に製造業の責任技術者の業務には製造販売後安全管理に関する業務は含まれておらず、安全管理責任者と製造業の責任技術者が兼務することは合理的とは言えないからです。
5.4 GQP省令における品質保証責任者の資格要件
医療機器の総括製造販売責任者又は責任技術者として薬事法施行規則第85条第3項第1号又は第91条第3項第1号によって認められる者は従事経験を有していないこともありえますが、当該者が品質保証責任者を兼務することは可能です。
GQP省令において品質保証責任者の資格要件が定められており、品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事している必要があります。このため、各責任者の資格要件を満たす者でなければ兼務はできません。
6. 認定講習会について
6.1 認定講習機関の実施体制
連名通知の2の(1)における都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)の趣旨を説明されたいとの質問に対して、全ての都道府県で実施する必要があるのかという点について説明します。
総括製造販売責任者及び責任技術者の3年間の実務経験の要件について、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の活用により、専門学校などで実施する医療機器開発に必要な薬事法等の法的知識、医療機器に求められる品質とそれを達成する製造技術を持った技術者を養成する人材育成プログラムなどを県の関与の下実施することにより代替することができないかという要請がありました。
これを踏まえ、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号、以下「復興特区法」という。)において、県知事の認定する講習の受講により実務経験を代替する措置を執っていることから、この制度を参考に、全国で適用可能な方法により、通知したものです。ただし、緊急的に実施されている復興特区法に基づくものとは講習の時間等の要件等は異なっています。
このような経緯のため、認定講習は、特区などの指定により自治体が積極的な関与を行っている場合などを想定しているので、本講習を都道府県で一律に実施するよう求めるものではありません。
6.2 自己実施講習の取り扱い
連名通知の2の(1)における都道府県知事の認定する講習については、自ら実施する講習を含むのかという質問に対しては、都道府県知事が自ら実施することを妨げるものではありません。
6.3 特定認定機関の複数県での活動
連名通知の2の(1)において、規則第85条第3項第4号及び規則第91条第3項第4号又は規則第85条第4項第3号及び規則第91条第4項第3号に該当する者として当該事業者が所在している都道府県が行う講習の修了者となっているが、例えば特定の認定機関を複数の都道府県が認定することは可能です。
特定の認定機関を複数の都道府県が認定し、講習を実施しても差し支えありません。
6.4 都道府県間での講習認定の連携
A県で認定された認定講習機関がB県で講習を実施できるかという質問に対して、A県で認定された認定講習機関により、A県内で実施されている講習をB県の医療機器製造販売業者が受講できます。
ある団体をA県が講習機関に認定する際、講習の開催場所としてB県での開催が認められた場合は、B県での講習を実施できます。ただし、当該講習の修了者として認められるのは、A県内の製造販売業者に限られます。
また、A県とB県が同時にある団体を認定し、それぞれの県内(又はそれ以外の場所)で行われる講習を認めることも可能です。
まとめ
医療機器の製造販売業及び製造業における総括製造販売責任者や責任技術者の資格要件は、平成24年の薬事法施行規則改正を受けて大きく見直されました。情報学や生物学分野の追加、単位取得要件の具体化、従事経験の範囲や兼務の可否など、実務に直結する重要な変更点が整理されています。
これらの要件は、企業における責任者配置や人材育成に直結するため、誤解なく正確に理解し、適切に対応することが求められます。特に、海外大学卒業者の取り扱いや従事経験の解釈などは個別判断が必要な場合も多く、専門的な知見が不可欠です。
弊社では、最新の通知・Q&Aを踏まえた資格要件の確認や責任者配置に関するご相談を承っております。自社の体制整備や人材要件に不安がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。