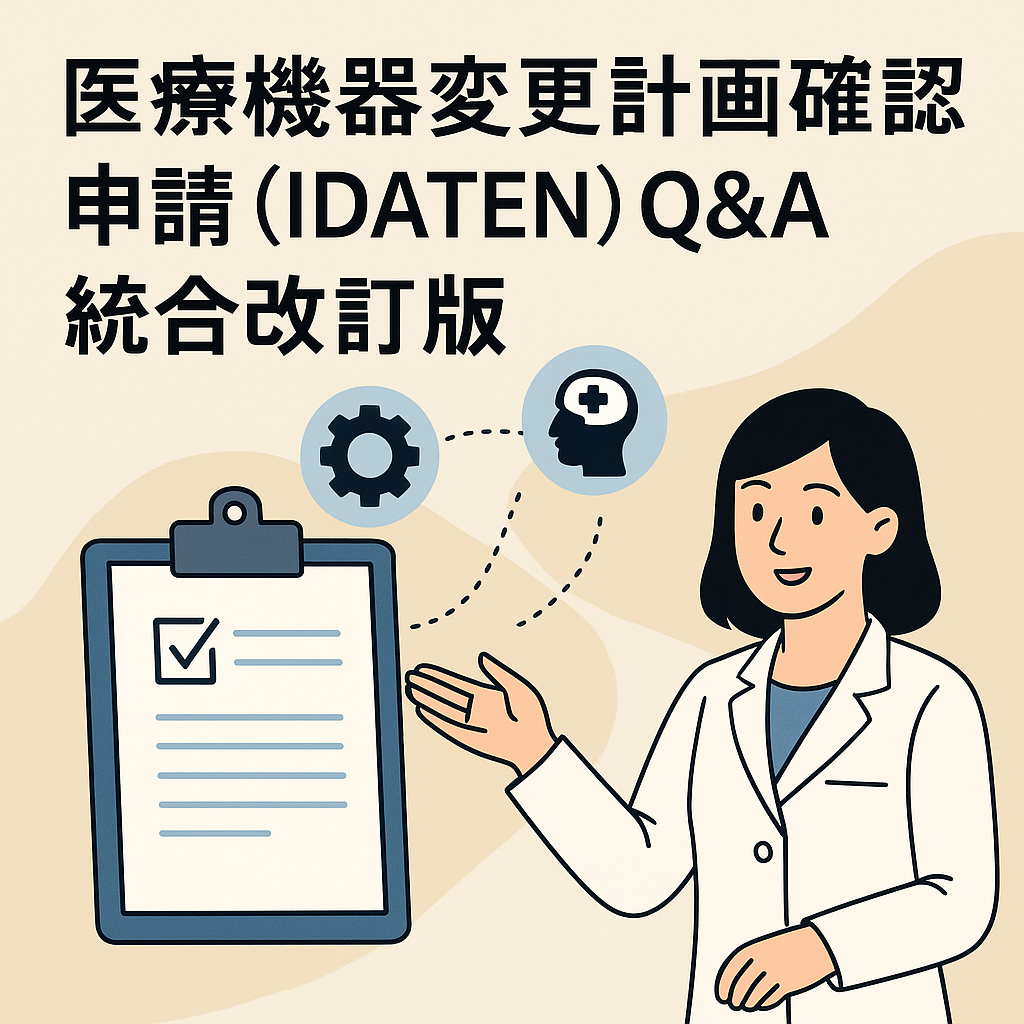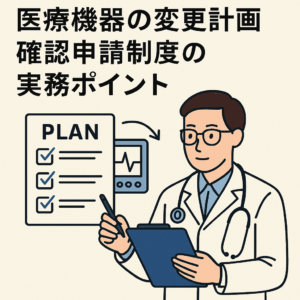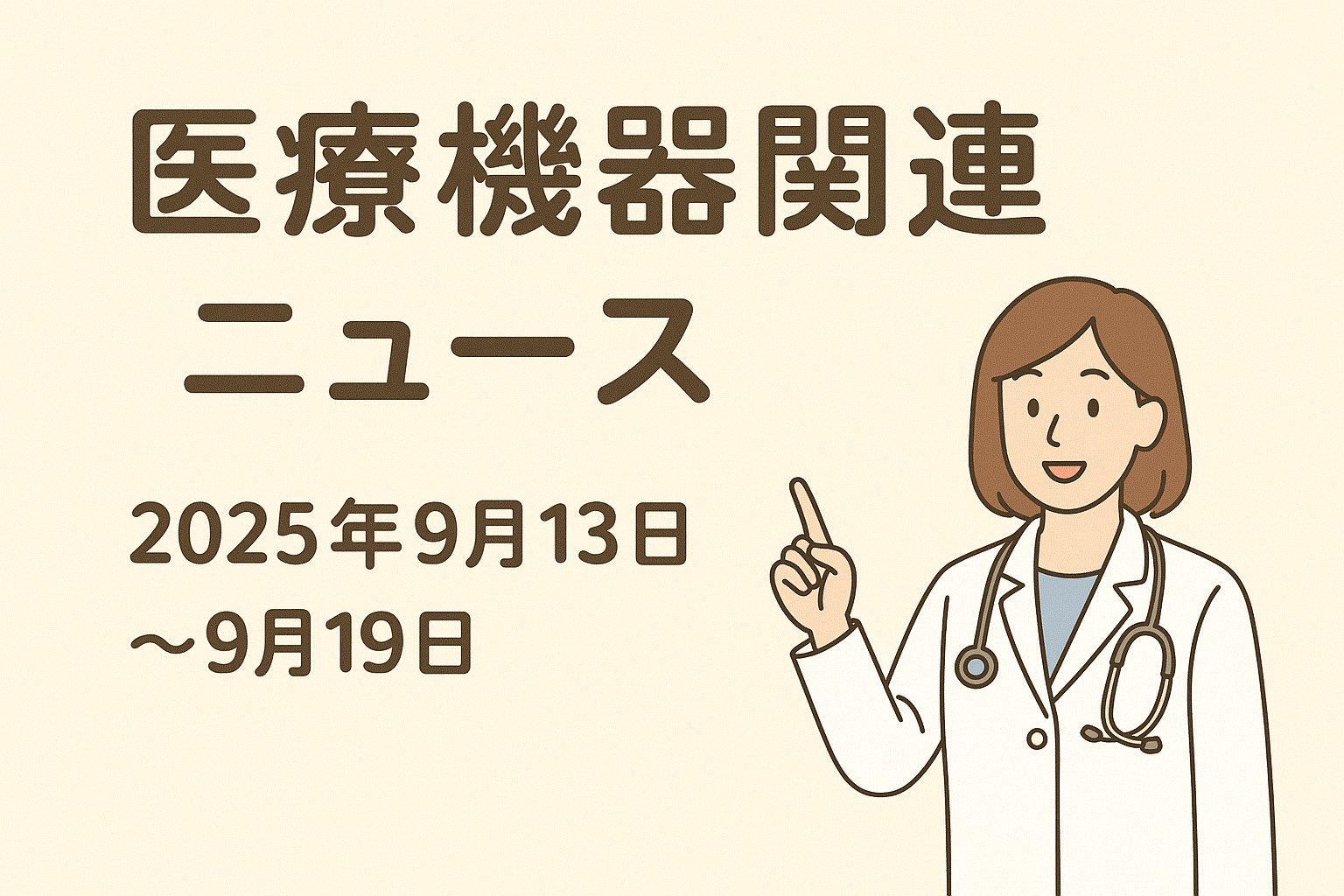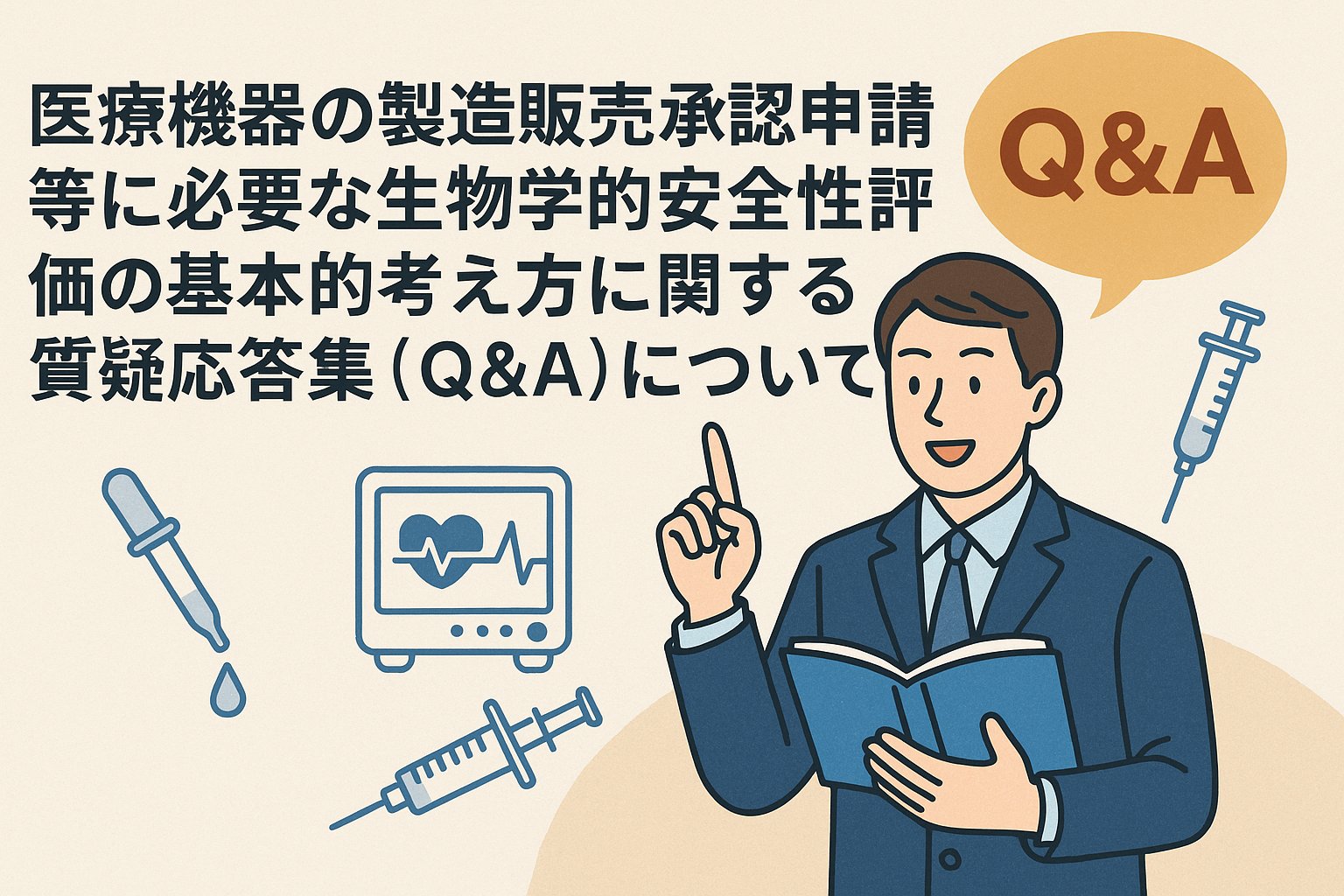概要
令和5年12月22日、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課より、医療機器の変更計画確認申請(IDATEN)に関する質疑応答集の統合・改訂版が発出されました。この事務連絡は、規制改革実施計画に基づき、これまで個別に発出されていた3つのQ&Aを統合し、スタートアップ企業などのニーズを踏まえて内容を充実させたものです。
IDATEN制度は、医療機器の承認事項の変更を計画的に実施できる制度であり、特に人工知能(AI)関連技術を活用した医療機器やプログラム医療機器の継続的な改良を可能にする重要な仕組みです。今回の改訂により、制度の利用がより明確化され、医療機器開発企業にとって活用しやすいものとなりました。
1. IDATEN制度の基本構造と改訂の背景
1.1 変更計画確認申請制度の位置づけ
医療機器の変更計画確認申請制度は、医療機器の承認後に行う変更について、事前に変更計画を立案し、その計画について厚生労働大臣の確認を受けることで、計画に従った変更を届出により実施できる制度です。従来は承認事項の変更には一部変更承認申請が必要でしたが、本制度により、確認を受けた変更計画に従った変更については届出による対応が可能となります。
この制度は特に、継続的な改良が必要な医療機器、例えばAI技術を活用した医療機器やプログラム医療機器において重要な意味を持ちます。市販後も性能向上のための学習や改良を継続的に行うことが求められるこれらの医療機器にとって、迅速な変更手続きは競争力の維持に不可欠です。
1.2 今回の改訂の経緯
令和5年6月16日に閣議決定された規制改革実施計画において、「変更計画確認手続制度(IDATEN)の効果を向上させる観点から、必要な変更計画書について、様式の具体的な記載例及び医療機器の開発経験の乏しいスタートアップなどのニーズを踏まえたQ&Aを充実させる」ことが示されました。
これを受けて、既存の3つのQ&A文書を統合し、一部改正を行いました。既存Q&Aは以下のとおりです。
- 令和2年10月30日付け「医療機器の変更計画の確認申請に関する質疑応答集(Q&A)について」
- 令和3年10月20日付け「医療機器の変更計画の確認申請に関する質疑応答集(Q&A)(その2)について」
- 令和4年3月31日付け「人工知能関連技術を活用した医療機器の変更計画の確認申請に関する質疑応答集(Q&A)について」
2. 変更計画確認申請の実務的な流れと要点
2.1 申請前の相談プロセス
変更計画確認申請を行う前に、医療機器開発前相談を活用することが推奨されています。この相談では、提出予定の変更計画が本制度の対象となるかどうかについて事前に助言を受けることができます。ただし、同一申請者による複数の変更計画確認申請事例の経験が蓄積された場合には、この相談を省略することも可能です。
相談を希望する場合には、まず全般相談を申し込み、医療機器開発前相談に必要な資料の充足性や相談までのスケジュールを確認することが望ましいとされています。また、試験プロトコルに関する相談を希望する場合には、医療機器プロトコル相談を申し込むことができます。
2.2 申請のタイミングと変更計画の内容
承認申請中の医療機器についても、変更計画の確認申請に必要な情報が得られた時点で申請が可能です。この際、医療機器の承認申請時にPMDAにより附されるシステム受付番号が必要となります。ただし、変更前の承認事項が不明確である場合には、確認申請に対する議論が進められない可能性があることに留意が必要です。
変更計画には複数の変更内容を含めることができます。この場合、各変更内容の関係性を明確にし、変更実施時期が異なることが明確となるよう、「変更①」「変更②」等を付記する必要があります。また、変更計画の確認申請後に変更計画の内容に変更が生じないよう、申請前に十分な検討が必要です。
2.3 届出による変更実施
変更計画の確認を受けた後、変更計画に従った変更を実施する際は、変更日の30日前までに届書を提出します。届出前相談の申し込みに特段の期限は設定されていませんが、円滑な届出を実施するため早めの相談が推奨されています。
届書提出の際には、変更計画確認申請時に添付した資料に対し、追記した内容の概要を示した資料を添付することが望ましいとされています。また、製造販売業者において機構受理日から承認事項の変更年月日まで30日以上の余裕を持った日程設定が可能です。
3. 申請書類作成における具体的な留意事項
3.1 申請書の記載方法
変更計画確認申請書の作成にあたっては、承認事項のうち変更予定のない欄については「変更なし」と記載します。オンライン申請(DWAP)を利用する場合には、変更予定のない欄は空欄とし、経過表等はその他の備考欄に別紙として提出することができます。
新旧対照表の作成では、複数の変更内容を含める場合、多段階の比較表として作成します。変更計画に含まれる複数の変更内容が別々の届出により変更される場合には、比較表は変更内容と変更計画に従った変更に係る届出における変更事項との間で対比させる必要があります。
3.2 添付資料の構成と内容
課長通知の別表1に示された添付資料として、以下の資料が必要です。
- 変更計画に関する資料(開発の経緯、国内外における使用状況を含む)
- 設計及び開発の検証方法に関する資料
- 試験計画書又は試験報告書(試験報告書が既に作成されている場合)
適合宣言書や滅菌バリデーションに関する宣言書については、変更計画確認申請時には案の添付までは求められませんが、変更計画の実施後に宣言することとなる基準について説明する必要があります。
3.3 経過表の記載における注意点
変更計画確認申請においては、一部変更承認及び軽微変更届とは別の記号を用いて変更箇所を記載します。例えば、従前「〇」印を使用していた場合には、変更計画確認申請での変更箇所については「●」印を使用し、区別します。
経過表は薬事手続きの履歴であることから、変更計画の中止又は廃止等に関わらず作成する必要があります。また、多段階の変更内容を含む場合には、変更実施時期が異なることが明確となるよう付記が必要です。
4. AI関連技術とプログラム医療機器への特別な対応
4.1 人工知能関連技術を活用した医療機器の定義と対象
人工知能関連技術を活用した医療機器とは、深層学習を含む機械学習等により構築されたプログラムを主な機能として利用する医療機器を指します。ハードウェアを含む有体物である医療機器でも、人工知能関連技術を活用して機能を実現しているものは対象となります。
設計又は製造に人工知能関連技術を用いたものの、プログラム自体を医療機器に搭載していないものは対象外です。また、変更内容が人工知能関連技術に関係しない場合は、通常の変更計画確認申請の手続きに従います。
4.2 AI医療機器特有の提出資料
人工知能関連技術を活用した医療機器では、以下の特有の資料提出が求められます。
- 変更計画の作成及び実施に関する責任及び権限を記載した資料(組織図等)
- 変更計画の作成、照査、検証、妥当性確認及び変更計画の変更を実施するための手順
- 変更計画で示されたとおりの変更が実施されていることを確認するための手順
- 市販後に性能が変化することが想定される医療機器における性能管理手順
これらの資料は、AI医療機器が開発段階と同様に追加学習において連続的に設計、検証、改良、妥当性確認のサイクルが実施されることを考慮したものです。
4.3 プログラム医療機器の変更計画
プログラム医療機器については、複数の機能を有する場合、機能ごとに複数の変更内容を記載することが可能です。ただし、各変更内容の関係性が明確となるよう資料をまとめる必要があります。
変更計画の確認完了を待たずに試験を実施することも、医療機器製造販売業者の責任において可能です。ただし、確認申請の結果、プロトコルに変更が生じた場合には、再試験を含む適切な手続きが必要となります。
まとめ
今回のQ&A統合・改訂により、医療機器の変更計画確認申請制度(IDATEN)の運用は一層明確化され、特にスタートアップや新規参入企業でも取り組みやすい内容となりました。実務上は、申請前の適切な相談の活用、複数の変更を整理したわかりやすい計画立案、さらにAI・プログラム医療機器に特有の追加要件への対応が重要なポイントとなります。
本制度を活用することで、医療機器の継続的な性能向上と市場投入の迅速化が可能となり、競争力を維持しながら最先端の技術を患者へ届けることができます。一方で、申請書類の作成や資料の整理には専門的な知識が必要となり、特にAI技術を組み込んだ製品では従来以上に丁寧な対応が求められます。
弊社では、IDATEN制度の活用を検討される企業様に向けて、制度適用の可否判断から具体的な申請書作成、相談対応まで包括的なサポートを提供しています。
自社での対応に不安をお持ちの方や、実際の運用方法を詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。