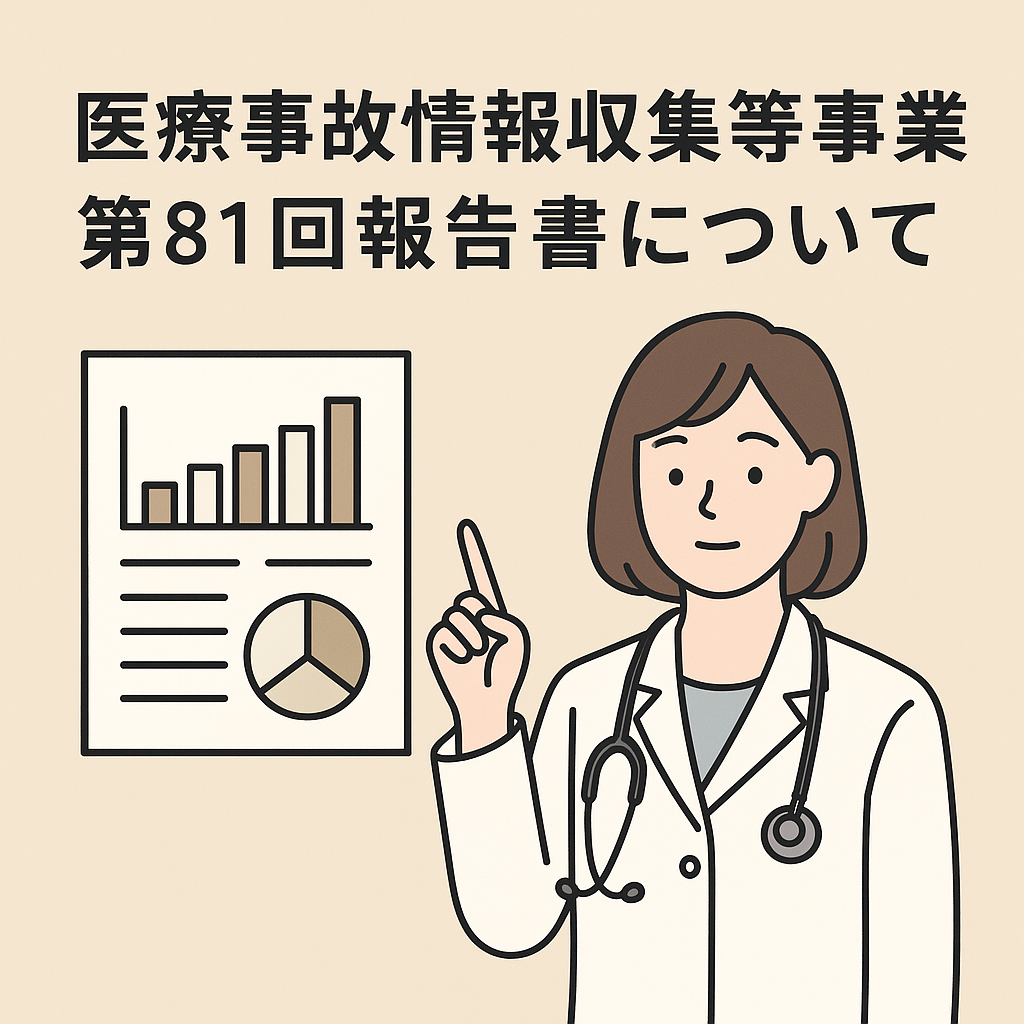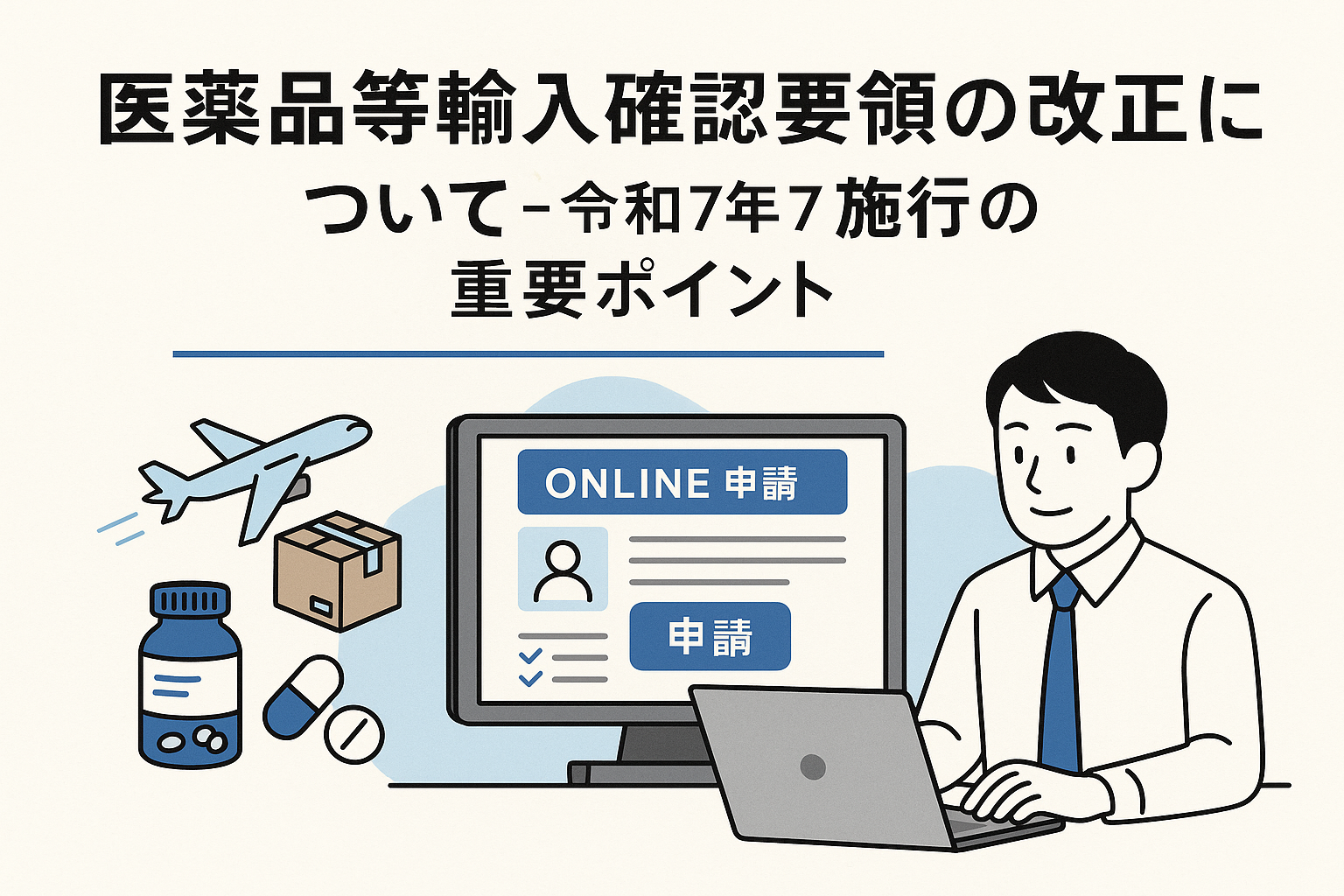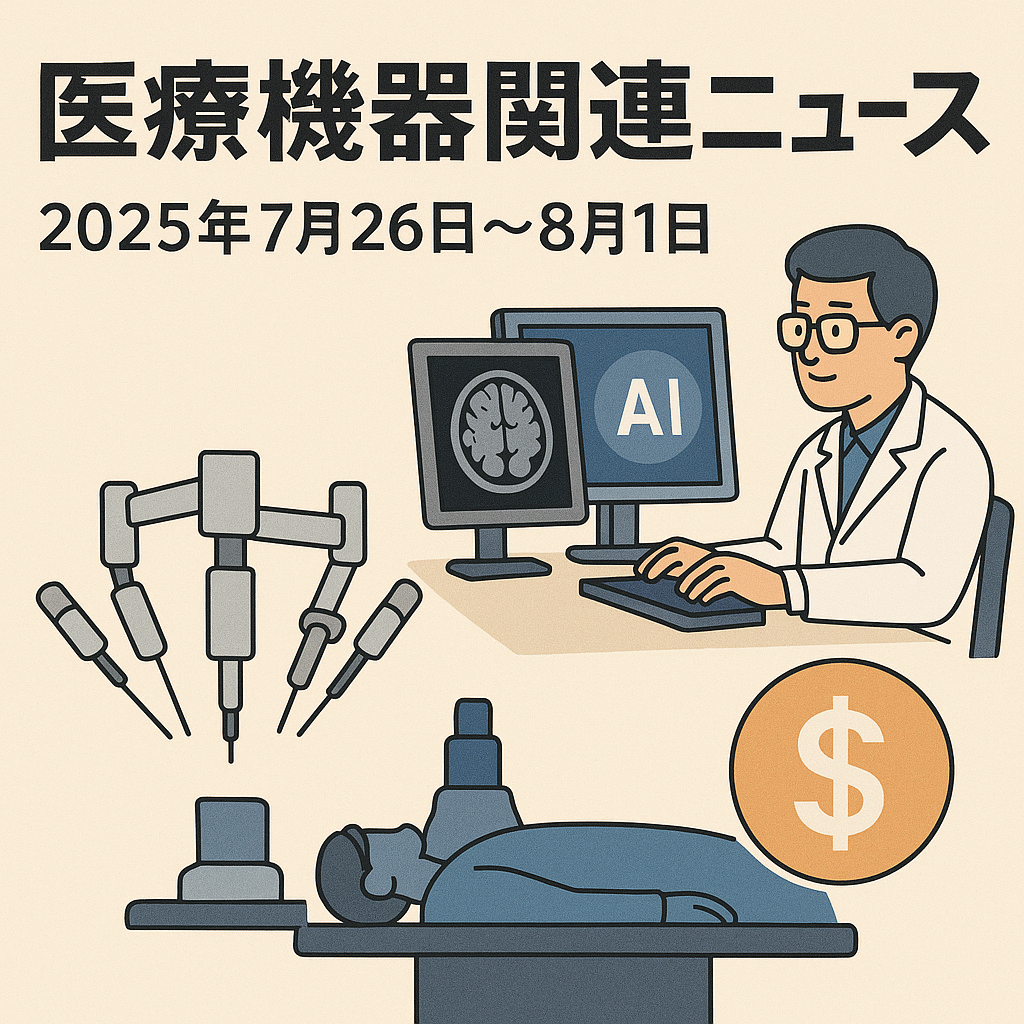概要
厚生労働省は令和7年6月25日、医療事故情報収集等事業の第81回報告書が公益財団法人日本医療機能評価機構より公表されたことを通知しました。本事業は平成16年10月から実施されており、医療機関から報告された医療事故情報等を収集、分析し提供することで、医療安全対策の推進を図ることを目的としています。今回の報告書では、2025年1月から3月に発生した医療事故について詳細な分析が行われており、医療機器産業に携わる関係者にとって重要な情報が含まれています。
本報告書では、報告された医療事故1,256件について、薬剤、治療・処置、医療機器等、療養上の世話など事故の概要別に分類・分析されています。また、「胃瘻・腸瘻の造設・カテーテル交換や管理に関連した事例」と「院外で粉砕調剤された持参薬の与薬に関連した事例」を分析テーマとして取り上げ、さらに「誤った患者への輸血」について再発・類似事例の詳細な分析が行われています。
1. 医療事故情報の集計結果
1.1 報告件数と医療機関数
2025年1月から3月の期間において、報告義務対象医療機関からは合計1,256件の医療事故が報告されました。内訳は1月406件、2月408件、3月442件となっており、月を追うごとに報告件数が増加している傾向が見られます。参加登録申請医療機関からは同期間に149件(1月57件、2月44件、3月48件)の報告がありました。
報告義務対象医療機関数は270施設で変動はありませんでしたが、参加登録申請医療機関数は1月の3,760施設から3月には3,906施設へと増加しており、医療安全への意識の高まりが伺えます。
1.2 事故の概要別分類
報告された1,256件の医療事故を概要別に分類すると、最も多かったのは「治療・処置」で428件(34.1%)、次いで「療養上の世話」が385件(30.7%)となっています。医療機器等に関連した事故は45件(3.6%)、ドレーン・チューブ関連が87件(6.9%)でした。薬剤関連は94件(7.5%)、検査関連は66件(5.3%)、輸血関連は4件(0.3%)と比較的少数でしたが、重篤な結果につながる可能性があるため注意が必要です。
1.3 ヒヤリ・ハット事例の収集状況
ヒヤリ・ハット事例収集には1,405の医療機関が参加しており、発生件数情報として279,961件、事例情報として6,466件が報告されました。これらの事例は重大事故の予防につながる貴重な情報源となっています。
2. 分析テーマの詳細
2.1 胃瘻・腸瘻の造設・カテーテル交換や管理に関連した事例
胃瘻・腸瘻は経腸栄養法の一つとして広く用いられていますが、カテーテルの交換や管理において様々なリスクが存在します。報告書では、カテーテル交換時の手技的な問題、管理中の偶発的な抜去、感染症の発生など、多岐にわたる事例が分析されています。
これらの事例から、定期的な交換時期の管理、適切な固定方法の選択、患者・家族への教育の重要性が改めて確認されました。特に在宅医療への移行が進む中、医療機器メーカーとしては、より安全で管理しやすい製品の開発が求められています。
2.2 院外で粉砕調剤された持参薬の与薬に関連した事例
高齢化に伴い、嚥下困難な患者への粉砕調剤のニーズが増加していますが、薬剤の特性を考慮せずに粉砕することで、効果の減弱や副作用のリスクが生じる可能性があります。報告書では、腸溶性製剤や徐放性製剤を不適切に粉砕した事例などが取り上げられています。
医療機器メーカーの観点からは、服薬支援デバイスの開発や、粉砕可否の判断を支援するシステムの構築など、技術的なソリューションの提供が期待されます。
3. 再発・類似事例の分析「誤った患者への輸血」
3.1 事例の発生状況
医療安全情報No.11(2007年10月)および第2報No.110(2016年1月)で注意喚起された「誤った患者への輸血」について、2025年1月から3月の期間に1件の類似事例が報告されました。2019年10月以降の累計では15件となっており、依然として発生が続いている状況です。
これらの事例の多くは異型輸血(14件)であり、患者に重篤な影響を与える可能性が高い事故です。発生時間帯を見ると、22時から翌1時59分の深夜帯に4件と最も多く、次いで10時から11時59分、12時から13時59分、16時から17時59分にそれぞれ2件発生しています。
3.2 事例の分類と要因分析
報告された15件の事例は、「血液製剤間違い」(12件)と「患者間違い」(3件)に分類されます。血液製剤間違いの事例では、輸血部門から払い出す際(2件)、部署の保冷庫から取り出す際(9件)、ベッドサイドでワゴンから手に取る際(1件)に発生していました。
特に部署の保冷庫から取り出す際の間違いが多く、複数患者の輸血用血液製剤が保管されている状況下で、思い込みや確認不足により誤った製剤を取り出してしまう事例が目立ちました。背景要因として、緊急時の焦り、多忙な状況、コミュニケーション不足、知識・経験不足などが挙げられています。
3.3 認証システムの使用状況と課題
輸血実施時の認証システムについて、設置されていたが使用しなかった事例が4件、使用したが手順に不備があった事例が1件、設置されていなかった事例が1件報告されています。大量輸血時や緊急時には認証作業が間に合わないという理由で省略されるケースがあり、システムの運用面での課題が浮き彫りになっています。
医療機器メーカーとしては、緊急時でも確実に使用できる認証システムの開発、より迅速で簡便な照合方法の提案など、現場のニーズに応じた製品開発が求められます。
4. 医療安全向上への提言
4.1 システム面での改善
報告書から読み取れる課題として、認証システムの普及は進んでいるものの、その適切な使用が徹底されていない現状があります。医療機器メーカーは、単に機器を提供するだけでなく、運用方法の教育や継続的なサポートを行うことが重要です。
また、部門システムと基幹システムの連携不足により、認証の目的が不明確になっている事例も見られました。システム間の相互運用性を高め、シームレスな情報連携を実現することが求められます。
4.2 製品開発への示唆
今回の報告書から、以下のような製品開発のニーズが示唆されます。
まず、輸血用血液製剤の保管・管理システムについて、保冷庫内の製剤を視覚的に識別しやすくする工夫や、取り出し時の二重チェック機能の実装などが考えられます。
次に、小児用の分割バッグにおける認証の課題に対しては、分割後も確実に認証できる仕組みの開発が必要です。
さらに、緊急時や多忙時でも確実に使用できる簡便な認証システムの開発も重要な課題です。
4.3 教育・啓発活動の重要性
医療機器メーカーは製品の提供だけでなく、医療従事者への教育・啓発活動にも積極的に関与すべきです。特に、新しいシステムや機器を導入する際には、その目的や正しい使用方法について十分な研修を行い、定期的なフォローアップを実施することが重要です。
5. まとめ
医療事故情報収集等事業第81回報告書は、現場で実際に発生した医療事故の分析結果を通じて、医療機器メーカーにとって重要な示唆を与える内容となっています。特に、輸血ミスに関する認証システムの運用課題や、胃瘻・腸瘻カテーテル管理、粉砕調剤に関する事例分析は、今後の製品開発や安全対策に直結する貴重な情報です。
弊社では、こうした医療安全に関する情報を踏まえ、医療機器メーカー様や関係機関向けに薬事戦略やリスク対策のご提案を行っております。
報告書の具体的な内容の解釈や、自社製品への活用方法などについてご相談を希望される方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。