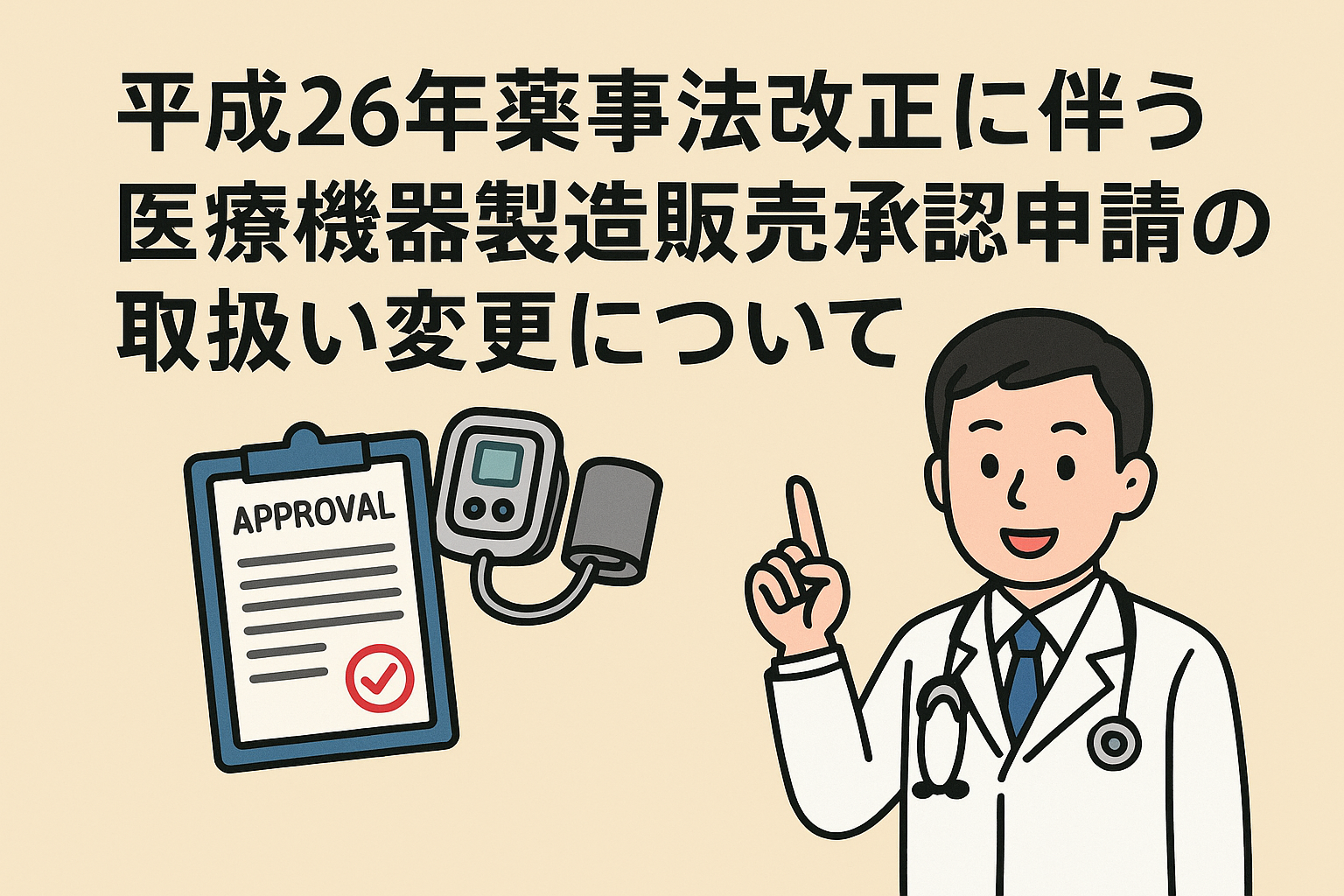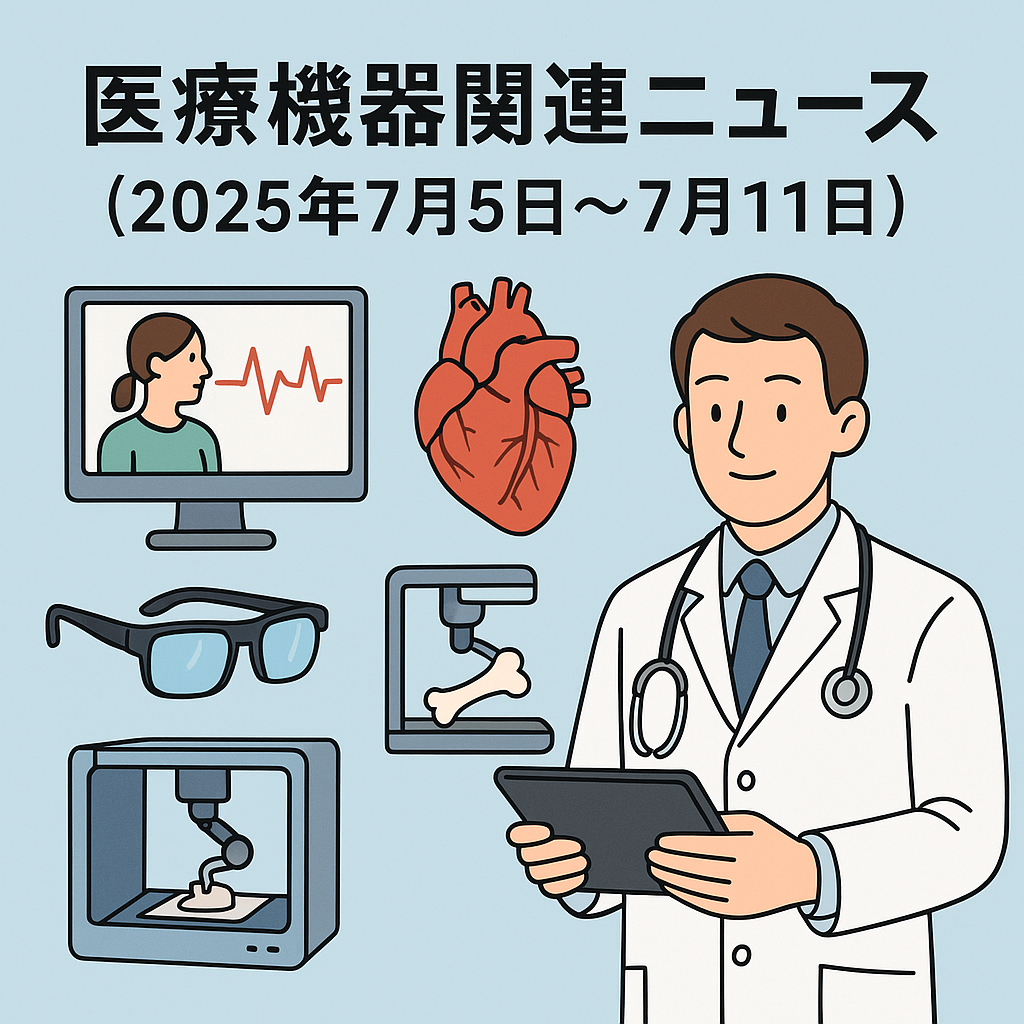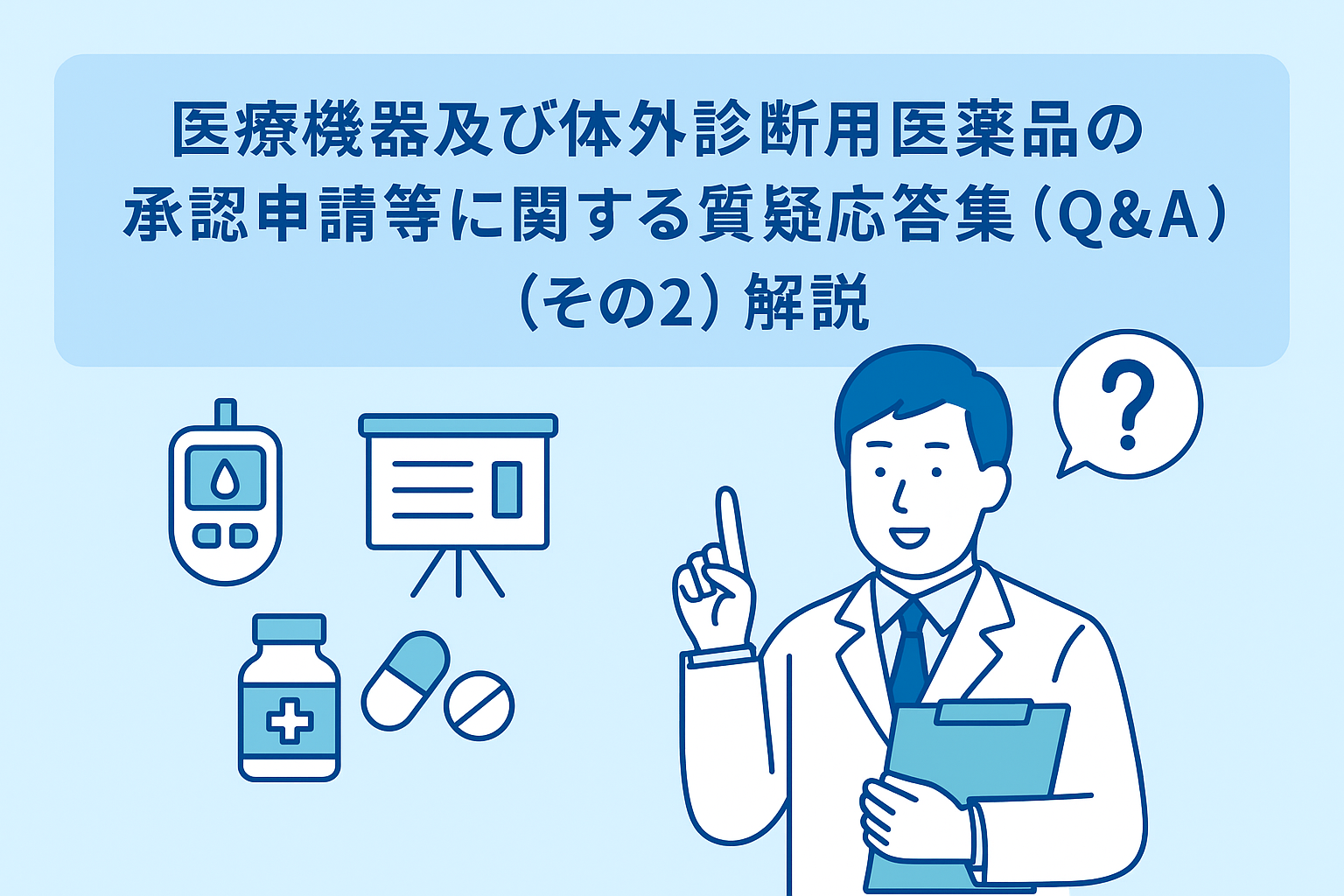概要
平成26年11月20日に厚生労働省医薬食品局長から発出された「医療機器の製造販売承認申請について」(薬食発1120第5号)は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行に伴い、医療機器の製造販売承認申請の取扱いを大幅に見直した重要な通知です。
この通知では、平成26年11月25日から施行された改正法に対応し、医療機器の分類体系の整理、申請書様式の変更、添付資料の範囲見直しなど、承認申請制度の包括的な改革が行われました。特に、新医療機器、改良医療機器、後発医療機器の定義が明確化され、それぞれの区分に応じた適切な審査体制が構築されています。
また、併せて発出された「医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」(薬食機参発1120第1号)により、申請書記載の詳細な留意点も示されており、申請者にとって実務上の指針が明確化されました。
1. 薬事法改正の背景と基本方針
1.1 改正法の施行体制
薬事法等の一部を改正する法律は、平成25年11月27日に公布され、関連政令・省令とともに平成26年11月25日から施行されました。この改正により、医療機器の規制体系が大幅に見直され、医薬品とは独立した承認・認証制度が確立されています。
改正の主な目的は、医療機器の特性に応じた適切な規制の実現と、国際調和の促進でした。従来の医薬品と一体的な規制から脱却し、医療機器固有のリスクに基づく分類体系と審査体制を構築することで、より効率的で科学的な承認プロセスの実現を目指しています。
1.2 医療機器分類の明確化
改正により、医療機器は以下の3つのカテゴリーに分類されることになりました。
新医療機器:既に製造販売の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なる医療機器を指します。これらは最も厳格な審査が求められ、臨床試験データの提出が原則として必要です。
改良医療機器:新医療機器と後発医療機器のいずれにも該当しないものを指し、既承認機器からの一定の改良が認められるものの、同一性は維持されている機器が対象となります。
後発医療機器:既承認医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が実質的に同等であると認められる医療機器で、最も簡素化された審査プロセスが適用されます。
2. 製造販売承認申請書の変更点
2.1 申請書様式の改正
申請書の各欄について、医療機器の特性に応じた記載方法が明確化されました。特に重要な変更点として、類別欄では医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令別表第1に従った記載が求められ、各類別への該当性についてはクラス分類通知を参考に判断することとされました。
名称欄では、一般的名称についてクラス分類通知の別添に記載される定義に基づいた記載が必要となり、該当する一般的名称がない場合の手続きも明確化されています。販売名については、医療機器としての品位を保ち、他の用途を想定させるような名称は認められないことが明示されました。
2.2 使用目的・効果欄の記載方針
使用目的については、医療機器の特性に応じて適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する結果等を適切に記載することが求められています。この記載により、当該医療機器の医療現場での位置づけと期待される医療効果が明確になります。
2.3 製造方法欄の詳細化
製造方法欄では、各製造工程に係る登録製造所の関係について分かりやすい記載が求められ、特に組合せ医療機器については構成品の滅菌状況等の確認が必要なため、工程フロー図等の記載が必要とされています。
滅菌医療機器については滅菌方法と引用する滅菌バリデーション基準の記載が必須となり、ヒト及び動物由来原料を使用する場合は製造工程中の不活化・除去処理の方法等の記載が求められます。
3. 添付資料の範囲と要件
3.1 添付資料の分類と内容
新しい制度では、添付資料が8つのカテゴリーに整理されました。開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料(イ)、設計及び開発に関する資料(ロ)、基本要件基準への適合性に関する資料(ハ)、リスクマネジメントに関する資料(ニ)、製造方法に関する資料(ホ)、臨床試験成績等に関する資料(へ)、製造販売後調査等の計画に関する資料(ト)、添付文書等記載事項に関する資料(チ)となっています。
これらの資料は、申請する医療機器の区分(新医療機器、改良医療機器、後発医療機器)に応じて、添付の要否が別表2で明確に定められています。
3.2 承認基準対応機器の取扱い
承認基準への適合性を確認することにより承認審査を行う医療機器については、臨床試験成績に関する資料の添付が不要の範囲で基準が定められており、効率的な審査プロセスが実現されています。
3.3 資料作成における品質要件
添付資料を作成するための試験は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準(医療機器GLP)及び医療機器の臨床試験の実施の基準(医療機器GCP)を遵守する必要があります。また、その時点における医学、薬学、工学等の学問水準に基づき、適正に実施されたものでなければなりません。
4. 申請区分別の要件と審査プロセス
4.1 新医療機器の審査要件
新医療機器については、最も包括的な資料提出が求められます。臨床試験の試験成績又は臨床評価に関する資料の提出が原則として必要であり、製造販売後調査等の計画についても詳細な検討が求められます。
使用成績評価の対象として指定される可能性がある場合には、承認時から市販後の安全性情報収集体制の構築が必要となります。
4.2 改良医療機器の取扱い
改良医療機器は、臨床試験の実施の有無により要求される資料の範囲が異なります。臨床試験を実施する場合は新医療機器に準じた資料が必要ですが、臨床試験を実施しない場合は簡素化された資料での申請が可能です。
承認基準が設定されていない改良医療機器については、個別の科学的評価に基づく審査が行われます。
4.3 後発医療機器の効率的審査
後発医療機器については、既承認医療機器との同等性の立証に重点が置かれ、臨床試験成績に関する資料は原則として不要とされています。承認基準が設定されている場合は、基準への適合性の確認により迅速な審査が可能となります。
5. 経過措置と実務への影響
5.1 施行前後の申請の取扱い
法施行前に製造販売承認申請された品目については、従前の申請書及び添付資料に基づく審査が行われますが、使用成績評価対象品目や添付文書届出対象品目については、改正後の要件に対応する資料の追加提出が必要となります。
法施行後の申請については、平成27年3月31日までに受け付けた申請に限り、添付資料は従前の資料として扱うことが可能でした。
5.2 実務運用における配慮事項
新制度への移行期間中は、申請者の混乱を避けるため、段階的な運用が図られました。特に、製造所の登録更新や品質管理体制の移行については、十分な準備期間が設けられています。
審査用資料の編集方法についても詳細な指針が示され、申請者が適切な資料準備を行えるよう配慮されています。
まとめ
平成26年の薬事法改正により、医療機器の製造販売承認申請制度は大きく刷新され、リスクに応じた合理的な審査体制が構築されました。新医療機器・改良医療機器・後発医療機器の区分や、それぞれに求められる申請書・添付資料の要件を正確に把握することは、効率的な承認取得の鍵となります。
制度変更により、申請業務の複雑化や準備資料の整備に不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか。
弊社では、申請書作成や添付資料整備の支援、分類判断、承認基準の適用可否の助言など、医療機器の薬事申請に関するご相談を幅広く承っております。
お気軽にお問い合わせいただき、貴社の製品開発・市場投入を薬事面からサポートいたします。