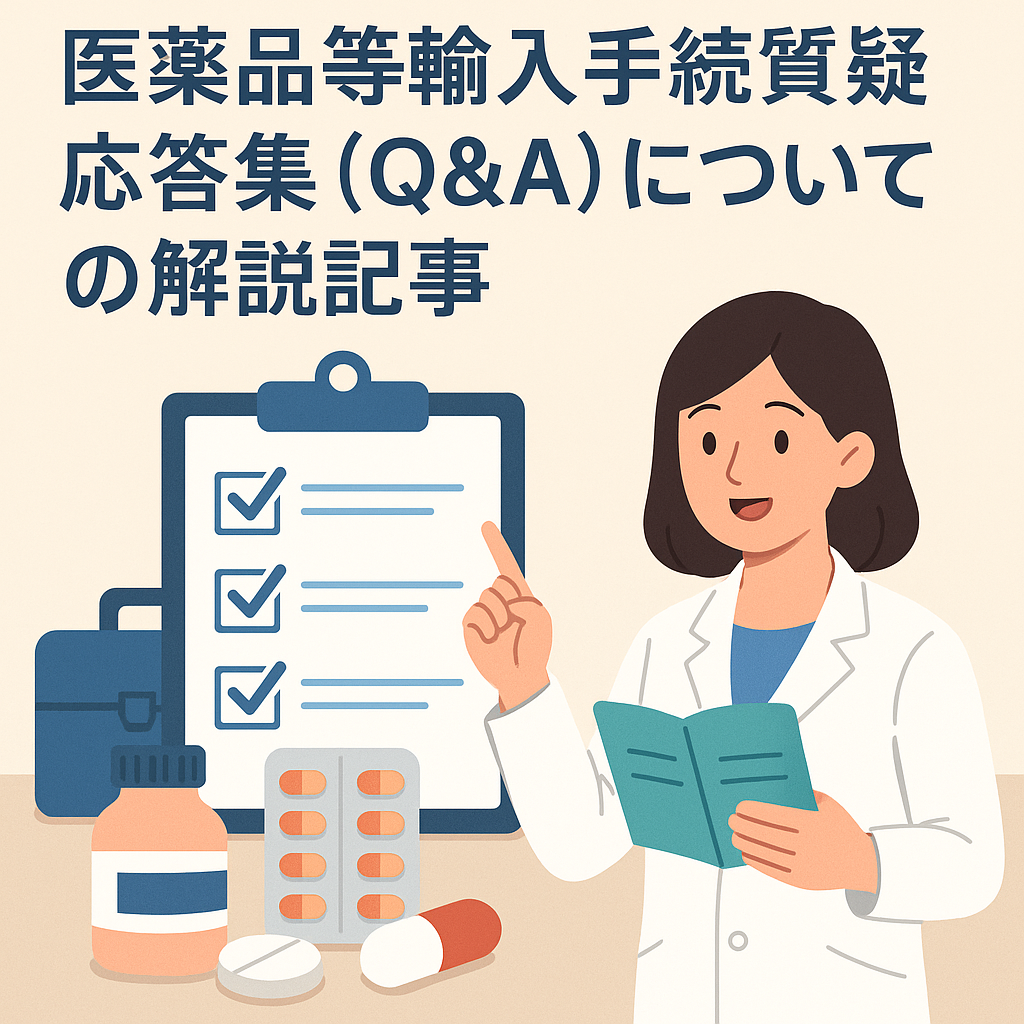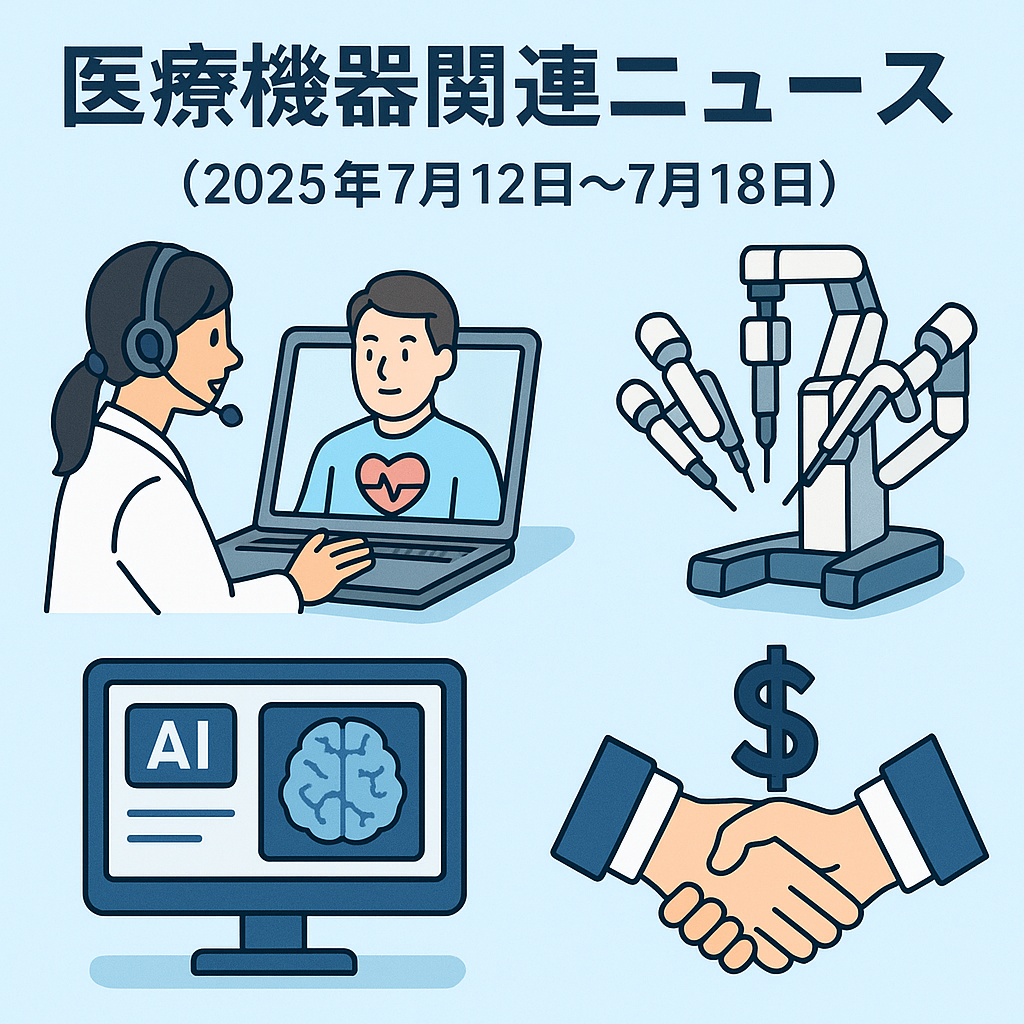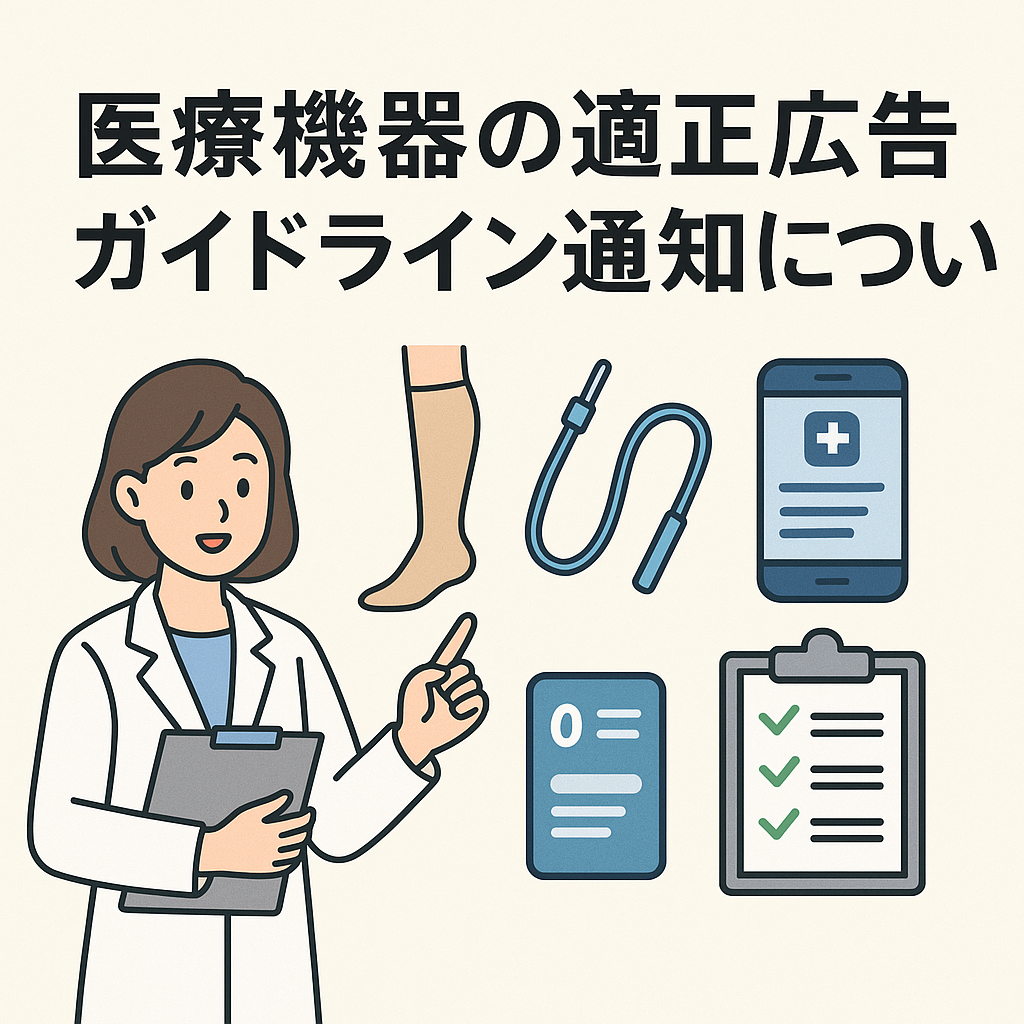概要
令和7年6月30日、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)」が発出されました。本通知は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の輸入手続について、実務上の疑問点を解決するための質疑応答集となっています。
この質疑応答集は、業として医薬品等を輸入する場合と、個人輸入等の業以外を目的とした輸入の両方について、具体的な手続方法を網羅的に解説しています。特に、輸入通関時に必要となる書類の提示方法、輸入確認証の取得要否、個人輸入可能な数量など、実務に直結する内容が詳細に記載されています。
なお、本事務連絡の発出により、令和6年3月26日付けの旧版は廃止されており、今後は本質疑応答集に基づいて輸入手続を行う必要があります。
1. 業としての医薬品等の輸入
1.1 必要な許可と承認
医薬品等を業として輸入し、製造販売又は製造するためには、以下の許可等が必要となります。
製造販売業の許可(法第12条、第23条の2、第23条の20)又は製造業の許可若しくは登録(法第13条、第13条の2の2、第23条の2の3、第23条の22)が必要です。さらに、品目ごとの製造販売承認等(法第14条、第19条の2、第23条の2の5、第23条の2の17、第23条の25若しくは第23条の37の承認若しくは第23条の2の23の認証)、届出(法第14条の9、第23条の2の12)又は登録(法第80条の6)等も必要となります。
商社等が他の業者へ販売する目的で医薬品等を輸入する場合にも、商社等は法に基づく上記の許可等、承認等を得るなどの手続を行う必要があります。
1.2 輸入通関時の手続
業として医薬品等を輸入する場合、輸入通関時に税関に対して以下の書類を提示する必要があります。
- 業許可証等(製造販売業許可証、製造業許可証又は製造業登録証)の写し
- 製造販売承認書等の写し
- 承認や認証を受けている医薬品等の場合:医薬品等製造販売承認書(写)、同製造販売届書(写)又は同製造販売認証書(写)
- 承認や認証を受けるための申請を行っている医薬品等の場合:医薬品等製造販売承認申請書(写)又は同製造販売認証申請書(写)
届書(写)や申請書(写)については、提出先である独立行政法人医薬品医療機器総合機構、認証機関又は行政機関が申請書等を受理した旨を証明できる資料(受付印が押印された当該申請・届書等の写し[控え]や、「受付票」及び「当該届出の内容を確認できる資料」等)を提示してください。
これらの輸入申告に係る通関関係書類については、NACCSの申告添付登録業務(MSX業務)を利用することにより、PDFファイル等の電磁的記録による提出が可能です。
1.3 提示すべき資料の範囲
税関に提示すべき資料について、以下の部分(頁)の写しを提示することが必要です。
業許可証等については全ての部分(頁)の写しを提示してください。製造販売承認書等については、「品目の名称」、「製造販売業者名」がわかる部分(頁)のみを抜粋した写しを提示してください。
国内の製造業者が医薬品等を輸入する場合には、製造販売承認書等にて、輸入しようとする品目の製造業者であることを証明する必要があるため、製造販売承認書等の製造所名称に係る記載のうち当該製造業者が確認できる部分(頁)(「製造所名」)の写しについても税関に提示してください。
1.4 変更が生じた場合の取扱い
税関に提示すべき項目のうち輸入者となる製造販売業者や製造業者の名称が変更になった場合は、以下の取扱いとなります。
業許可証(又は業登録証)の税関への提示については、原則として、変更内容が反映された書換え交付後の業許可証(又は業登録証)の写し及び業許可(又は業登録)の変更に係る変更届書の写しも提示してください。
輸入通関時点で、書き換え交付後の業許可証(又は業登録証)を用意できない場合には、変更前の業許可証(又は登録証)の写しに併せて、業許可変更に係る変更届書(写)も提示してください。
製造販売承認書等の税関への提示については、製造業者による輸入の場合は、製造販売承認書等に記載される「製造所名」の提示が必要となりますが、製造業者名が変更となった場合には、製造販売承認書等の変更手続に基づき、変更後の製造業者名が確認できる各種変更書類の該当部分を提示してください。
2. 業以外を目的とした医薬品等の輸入
2.1 輸入確認制度の概要
個人輸入等の業にあたらない医薬品等の輸入をするにあたっては、原則として、地方厚生局に輸入確認申請書等を提出して、当該輸入が「販売・貸与・授与」を目的としたものではないことの確認を受ける必要があります(「輸入確認証」を取得)。
ただし、個人輸入で一定の数量以下の場合等、輸入確認を受けずに、税関限りの確認で輸入をすることができる場合があります。
2.2 輸入確認申請の手続
輸入確認申請書の送付先は、貨物が到着した空港・港等の所在地ごとに以下のとおりです。
- 関東信越厚生局:函館税関、東京税関及び横浜税関の管轄区域内で輸入されるもの
- 近畿厚生局:名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関の管轄区域内で輸入されるもの
原則として、貨物が本邦に到着した時点、あるいは未到着であっても航空運送状(AWB)又は船荷証券(B/L)が発行された時点等、必要となる書類がそろった時点で申請が可能になります。
申請内容に不備等がない場合、地方厚生局に輸入確認申請書が到着してから3~4営業日程度で輸入確認証が発行されます。なお、令和5年2月1日から運用が開始された「医薬品等輸入確認情報システム」による申請の場合、2~3営業日程度で輸入確認証が発行され、郵送等による書類の配送期間の短縮にもつながります。
2.3 税関限りで輸入可能な医薬品等の数量
輸入確認証を取得せずに個人輸入が可能な医薬品の数量は以下のとおりです。
- 毒薬、劇薬及び処方箋医薬品については、用法及び用量からみて1か月分まで
- 毒薬、劇薬及び処方箋医薬品以外の医薬品については、用法及び用量からみて2か月分まで
- 外用剤(毒薬、劇薬、処方箋医薬品、トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、坐剤、膣剤、膣用坐剤及びバッカル錠を除く)については、24個まで
化粧品については、標準サイズの製品は1品目につき24個以内、少量の製品(内容量が60g又は60ml以下の製品)は1品目につき120個以内となります。
医療機器については、家庭用医療機器の数量は1セット(最小単位)です。ただし、使い捨て医療機器については反復して使用することができないことから、2か月分までの数量を最小単位とします。
3. 特別な取扱いが必要な製品
3.1 電子たばこの取扱い
電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの)は医薬品に該当します。税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1か月分(タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml)とし、1か月分を超えてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、輸入確認証の取得が必要です。
電子たばこ用のカートリッジやリキッドを霧化させることを目的とする装置は医療機器に該当します。これらを輸入する場合、1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)までを税関限りの確認で通関可能とします。
3.2 医療従事者個人用の取扱い
医療従事者個人用として輸入確認申請の対象となるのは、治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない医薬品等を、自己の責任のもと、自己の患者の治療等に供することを目的とした場合です。
医師免許、歯科医師免許、獣医師免許を持つ者に加えて、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許及び柔道整復師免許を持つ者も医療従事者の範囲に含まれます。
3.3 臨床試験用医薬品等の取扱い
臨床試験目的として輸入確認申請書等を作成の上、所管の地方厚生局から輸入確認証の交付を受けてください。治験計画届書を提出した時点及び当該治験の中止又は終了の時点で、速やかに地方厚生局に報告を行ってください。
臨床試験用に医薬品等を輸入する際、輸入が複数回に分かれる場合は、輸入確認申請書に輸入経過表を添付してください。分割輸入の予定が予め分かっていれば、複数回分まとめて輸入確認申請書を出すことも可能です。
4. 最新の改正内容
4.1 医薬品等輸入確認情報システムの利用原則化
令和7年6月30日付けの改正により、医薬品等輸入確認情報システムの利用対象となっている輸入目的の申請については、当該システムでの申請が原則とされました。
紙申請を受け付けないとするものではありませんが、政府の方針として行政手続のデジタル化・ペーパーレス化が進められていることから、特段の理由がない場合は原則として当該システムを利用してください。当該システムの利用により、申請書及び輸入確認証の郵送にかかる費用や期間がなくなり、紛失等のリスクもない等、申請者にも大きなメリットがあります。
当該システムにおいて輸入者本人以外の者(代行者)が申請手続を行うことも可能ですが、その場合、当該システム内で輸入者本人が申請内容を承認するか、代行者に対して申請手続を代わりに行うための権限を設定する必要があります。
まとめ
本質疑応答集は、医薬品等の輸入に関わる事業者・個人にとって、手続上の疑問や実務対応を明確化する上で非常に有用な資料です。業として輸入を行う際の許可や承認、通関時の必要書類の取り扱いから、個人輸入・臨床試験用医薬品等の特例まで、幅広いケースに対応する内容となっています。
特に今回の改正により、「医薬品等輸入確認情報システム」の活用が原則化されたことから、従来の申請方法との違いや、代行申請時の注意点など、実務対応において不明点が生じる可能性があります。
弊社では、医薬品・医療機器・化粧品・再生医療等製品の輸入に関する申請支援や法令対応のご相談を承っております。
輸入手続きに不安がある方や、最新の運用に確実に対応したい方は、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。