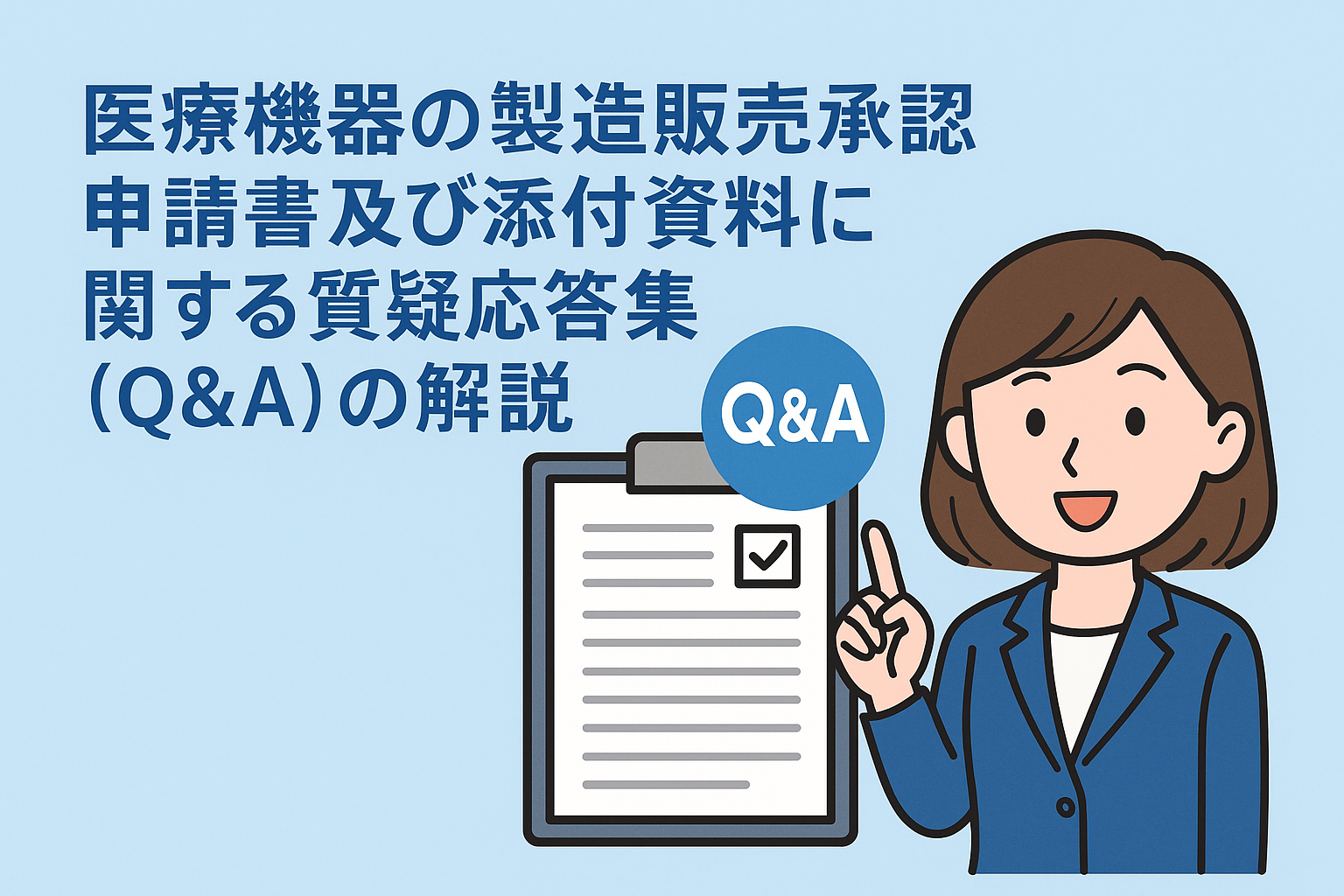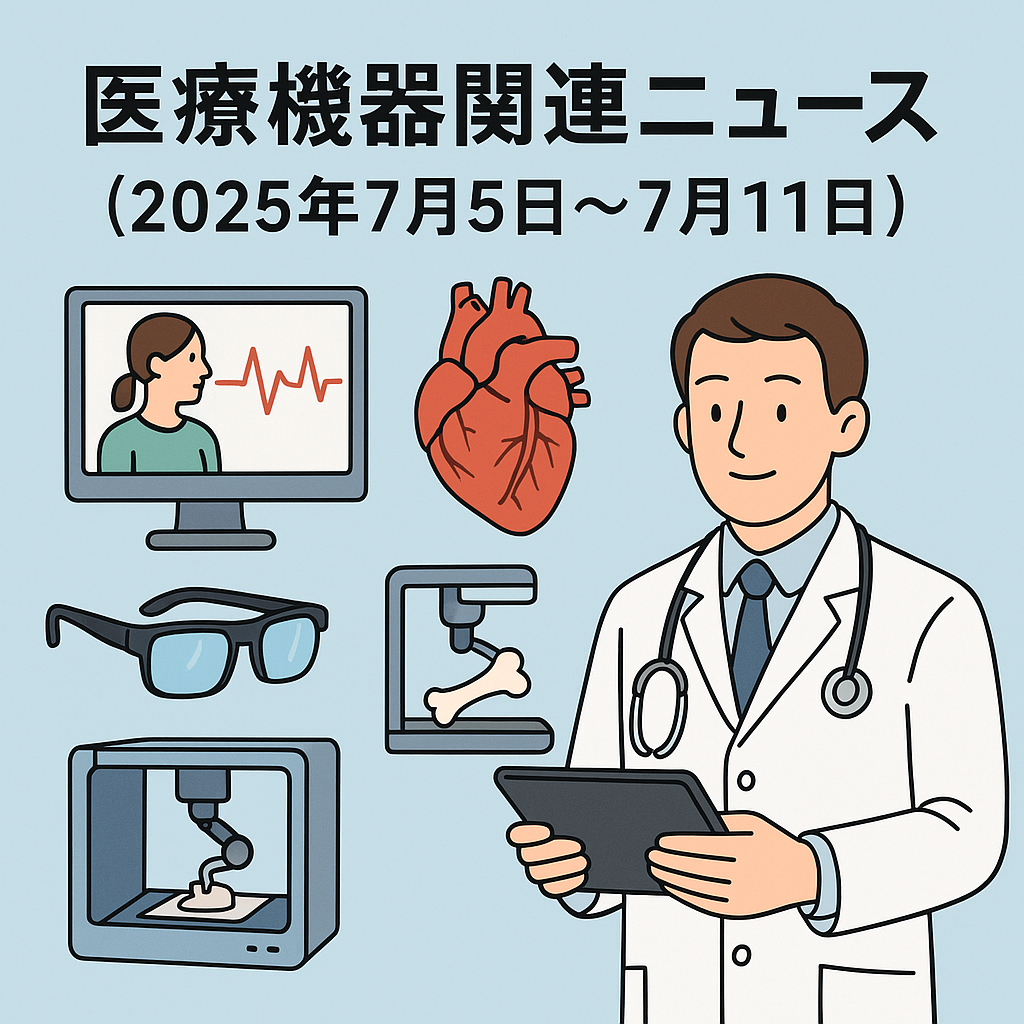概要
平成27年6月1日、厚生労働省から「医療機器の製造販売承認申請書及び添付資料に関する質疑応答集(Q&A)について」が発出されました。この通知は、医療機器の製造販売承認申請書及び添付資料の作成に関する留意事項について、実務上の疑問点を質疑応答形式でまとめたものです。
この質疑応答集は、平成26年11月20日付けの「医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」及び平成27年1月20日付けの「医療機器の製造販売承認申請書添付資料の作成に際し留意すべき事項について」の通知を補完する重要な文書となっています。
本質疑応答集では、承認申請書の記載に関する36項目の質疑応答が収録されており、申請実務における具体的な疑問点について明確な指針が示されています。
1. 承認申請書留意事項通知に関する主要なポイント
1.1 形状、構造及び原理欄の記載について
承認申請書の「形状、構造及び原理」欄における記載については、申請品目の特性に応じた合理的な判断が求められます。
特に注目すべき点として、申請品目の使用目的、形状、使用方法等の情報から原理が容易に推測される場合には、原理に関する記載項目を省略することが可能です。具体例として、チューブ形状のカニューレや非吸収性縫合糸などが挙げられています。一方で、医用電気機器については、その複雑性から必ず原理の記載が必要とされています。
医用電気機器のブロック図については、電気的安全性に関する公的規格への適合を承認事項に含める場合、ブロック図を承認事項として記載する必要はありません。ただし、申請品目の原理等を説明するために必要な場合は、系統図等を用いた記載が求められます。
1.2 原材料欄の取扱い
原材料欄の記載については、実用性を重視した取扱いが示されています。滅菌品の滅菌包装材料に関する記載は原則不要とされていますが、コンタクトレンズの一次容器など、充填液を介して血液、体液、粘膜等に間接接触となる包装材料については記載が必要です。
医療機器プログラム及びこれを記録した記録媒体などでは、特に記載を要する原材料がない場合があり、このような品目では空欄とすることが認められています。また、医用電気機器の外装や操作パネル等(患者装着部を除く)で、原材料が使用目的、性能及び安全性に直接的な影響を及ぼさないものについては記載を要しません。
1.3 製造方法欄における工程記載の合理化
製造方法欄では、滅菌品と製造専用の未滅菌品の双方で供給する製品について、登録製造所が単一であり各工程の関係について誤認が生じない場合は、工程フロー図等の記載を省略できることが明確化されました。ただし、製造専用の未滅菌品で供給する品目がある旨の記載は必要です。
薬剤コーティングなど、工程の製造条件によって製品の使用目的、性能等が影響を受ける工程については、登録製造所以外の施設が行う工程であっても、その製造条件の記載が必要とされています。この場合、製造条件や加工条件を表現するために、フロー図等を用いることが推奨されています。
2. 性能及び安全性に関する規格欄の柔軟な対応
2.1 規格項目設定の妥当性
「性能及び安全性に関する規格」欄に設定する項目については、類似医療機器において設定している項目と必ずしも同一である必要はなく、開発プロセスに応じて異なる項目が設定される場合があることが明確化されました。重要なのは、設定する項目の妥当性について添付資料1項で適切に説明することです。
この柔軟な対応は、医療機器の多様性と技術革新に配慮したものであり、申請者が科学的根拠に基づいて適切な規格項目を設定できる環境を整備しています。
2.2 組合せ医療機器の取扱い
複数の医療機器を組み合わせた医療機器については、既に承認又は認証を受けた医療機器等との組み合わせである場合、当該既承認医療機器等について「形状、構造及び原理」欄及び「製造方法」欄のみに記載することで差し支えないとされています。これにより、組合せ医療機器の申請時における記載負担が軽減されています。
3. 添付資料に関する実務的な取扱い
3.1 審査用資料の提出部数
審査用資料の提出部数については、申請区分に応じて明確に区分されています。改良医療機器(臨床なし)及び後発医療機器の申請区分においては審査用資料を2部提出する必要がありますが、その他の申請区分においては1部の提出で足ります。ただし、申請後に追加で提出をお願いする場合があることも明記されています。
3.2 記載整備に関する取扱い
旧通知に従い承認書を記載している品目について、一部変更承認申請又は軽微変更届を提出する際、記載整備通知で示されている範囲については、当該変更申請等の際に変更又は削除することが可能とされています。これにより、承認書の記載内容を最新の基準に合わせることができます。
3.3 添付資料作成時の一般的留意事項
添付資料の作成においては、申請した医療機器の特性に応じ、添付が不要な項目を除いて作成することが基本とされています。項目を削除する方法でも、項目を残して該当しない旨を記載する方法でも差し支えありません。
試験成績書が原本でない場合には、添付する写しが原本と相違ない旨の陳述書をあわせて添付する必要があります。この陳述書の署名者は、試験成績書の執筆者又は承認者、品質管理の責任者、品質保証の責任者、原本の写しを作成した部門の責任者など、写しが原本と相違ないことを証することができる者であれば問題ありません。
4. 臨床試験に関する記載要件
4.1 臨床試験成績の記載
臨床試験成績を添付しない場合には、その理由について説明する必要があります。これには、臨床試験を実施しなくとも文献等による臨床評価にて評価可能であると判断した理由の記載も含まれます。
症例一覧表においては、症例報告書から収集した全ての情報を含める必要はなく、申請品目の評価に必要な項目を選択して記載することで十分とされています。
4.2 総括報告書の作成
総括報告書の作成に際しては、ISO14155付属書Dを参照することが求められており、臨床試験の概要の記載に際してもISO14155付属書Dを参照することが可能です。申請品目の評価に必要な項目を選択して記載することとし、必ずしも通知に示す項目、順序でなくても差し支えありません。
5. 添付文書及び製造に関する情報
5.1 添付文書の取扱い
添付文書の届出対象とされていない品目においては、添付文書(案)は備考欄に添付し、添付資料5項にて設定根拠等の説明をすることで十分とされています。添付文書の届出対象とされている品目の場合は、添付資料チの別添として添付文書(案)を添付し、添付資料5項に設定根拠等を記載する必要があります。
5.2 製造に関する情報の記載
製造に関する情報については、「性能及び安全性に関する規格」の全項目について項目名を列記することが求められています。製造工程中にて確認していない事項については、「設計検証により検証済み」と記載することで対応可能です。
医療機器プログラム等において製造工程中にて確認している項目がない場合は、その旨を記載することで別紙様式2に示す表形式の記載を省略することができます。
まとめ
本質疑応答集は、医療機器の製造販売承認申請における実務上の疑問点について、具体的かつ実用的な指針を提供する重要な文書です。申請書の記載から添付資料の作成まで、幅広い項目について明確な取扱いが示されており、申請実務の効率化と適正化に大きく寄与しています。
特に、申請品目の特性に応じた柔軟な対応が認められている点は、実務負担を軽減しつつ、必要な安全性・有効性を確保できる仕組みとして注目すべきポイントです。形状、構造及び原理欄の記載省略、原材料欄の合理的な記載範囲の設定、製造方法欄の工程フロー図の省略など、申請内容に応じて適切に対応することが重要です。
また、組合せ医療機器や医療機器プログラムなど、新たな形態の医療機器に対応する取扱いも明確化されています。
本記事でご紹介した内容は一部であり、実際の申請にあたっては、品目や状況により対応が異なる場合があります。
医療機器の承認申請や添付資料の作成、PMDA対応について具体的なご相談やサポートが必要な場合は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。弊社スタッフが丁寧にサポートいたします。