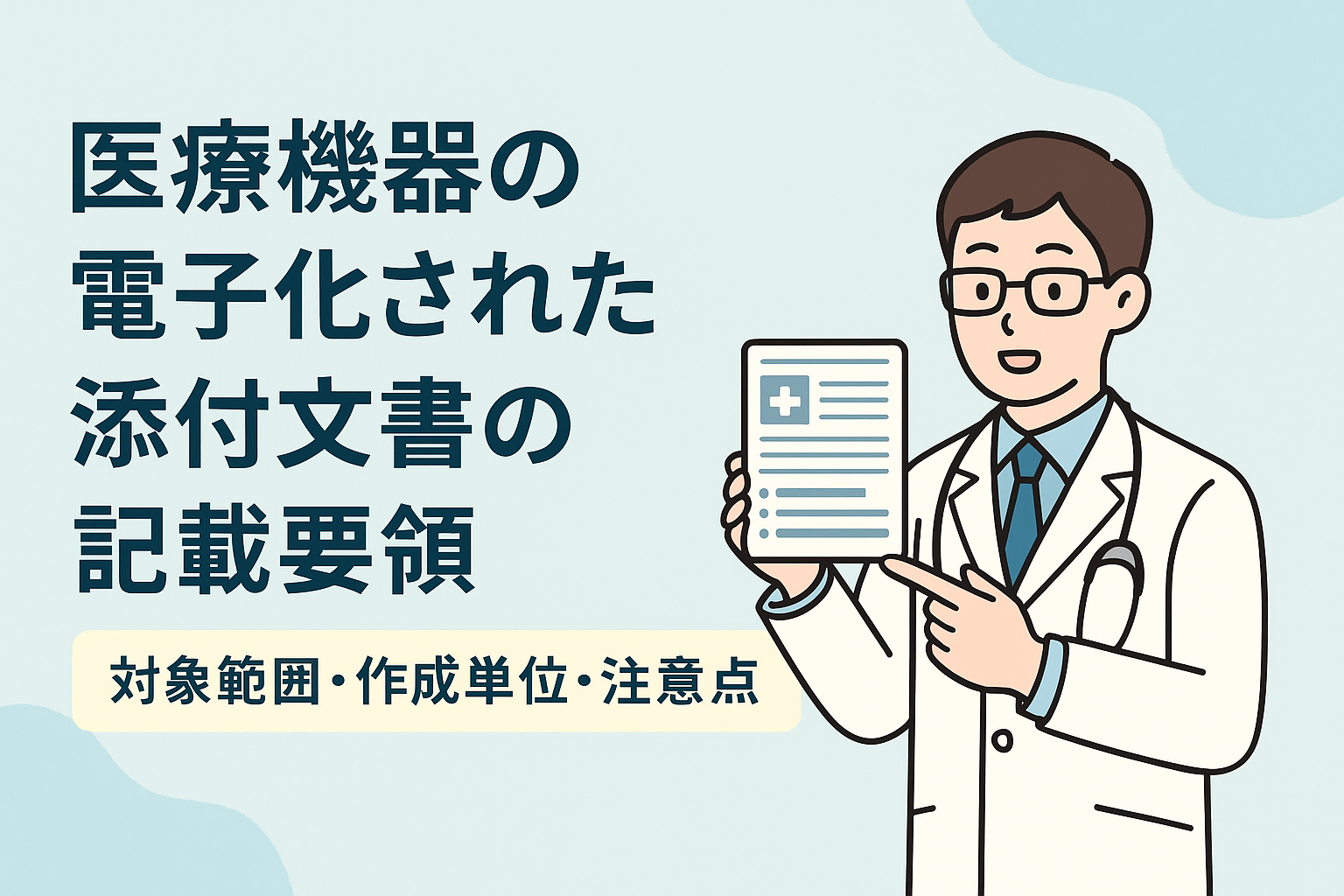概要
医療機器の添付文書は、これまで製品に物理的に添付することが義務付けられていました。しかし、令和元年の医薬品医療機器等法の改正により、令和3年8月1日から、医療機器の使用及び取扱い上の必要な注意等(注意事項等情報)については、主として一般消費者向けの医療機器を除き、添付文書への記載義務が廃止されました。
代わりに、製造販売業者は容器又は被包に符号等を記載し、その注意事項等情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページに掲載する「電子化された添付文書(電子添文)」制度が導入されました。この制度改正は、最新情報への迅速な更新、紙資源の削減、医療現場での情報アクセスの向上を目的としています。
本通知は、この新たな電子添文制度における記載要領を定めたもので、医療機器の製造販売業者が電子添文を作成する際の具体的な指針を示しています。適切な電子添文の作成は、医療機器の安全かつ効果的な使用に不可欠であり、医療従事者への正確な情報提供を通じて患者の安全確保に重要な通知となります。
1. 法改正による制度変更の要点
1.1 添付文書から電子添文への移行
医薬品医療機器等法の改正により、医療機器の使用上の注意等は「注意事項等情報」として新たに定義されました。この情報は、従来の紙の添付文書ではなく、PMDAのホームページ上で公表されることになりました。ただし、主として一般消費者が使用する医療機器については、引き続き添付文書への記載が必要です。
製造販売業者は、製品の容器や被包に、注意事項等情報を入手するための符号(GS1バーコード等)を記載する必要があります。医療従事者は、この符号を読み取ることで、PMDAのホームページから最新の電子添文にアクセスできます。
1.2 電子添文の位置づけと略称
PMDAのホームページに掲載される注意事項等情報等が記載された文書は「電子化された添付文書」と呼称され、その略称は「電子添文」とされました。これは従来の紙の添付文書に代わるものですが、法的には同等の重要性を持ちます。
電子添文は、医療機器の適正使用のために医療従事者に必要な情報を提供することを目的としており、最新の知見に基づいて作成され、随時改訂される必要があります。
2. 電子添文の適用範囲と作成単位
2.1 適用範囲の詳細
電子添文の記載要領は、原則として全ての医療機器に適用されます。ただし、以下のような区分に応じて適用方法が異なります。
医家向け医療機器については、本記載要領をそのまま適用します。一方、主として一般消費者向けの医療機器の添付文書は、本記載要領に準拠しつつも、義務教育修了程度の学力で理解できる表現とする必要があります。
家庭で使用される医家向け医療機器については、医療機関向けの電子添文に加えて、患者や介護者向けの電子添文も別途作成することが求められます。生物由来製品については、本通知に加えて別途定められた記載事項も含める必要があります。
2.2 作成単位の原則と例外
電子添文は原則として、一つの承認品目、認証品目、または届出品目につき一種類作成します。しかし、製品の特性により、以下のような例外が認められています。
人工関節のような一連の製品群については、使用者の理解しやすさを考慮し、複数の品目を一つの電子添文にまとめることができます。また、複数の製品の組み合わせで機能する医療機器の場合も、個別に作成すると誤解を招く恐れがあるため、まとめて記載することが認められています。
付属品については、本体と同一承認等であっても単独で流通する場合は、別途電子添文を作成する必要があります。ただし、組み合わせる本体を明示することで、一部の記載を簡略化することができます。
3. 電子添文の記載項目と記載順序
3.1 必須記載項目の構成
電子添文には、以下の17項目を記載する必要があります。記載順序は原則として定められた順番に従います。
- 作成又は改訂年月
- 承認番号等(承認・認証・届出番号等)
- 類別及び一般的名称等(JMDNコードや医療機器クラス分類)
- 販売名
- 警告
- 禁忌・禁止
- 形状・構造及び原理等
- 使用目的又は効果
- 使用方法等
- 使用上の注意
- 臨床成績
- 保管方法及び有効期間等
- 取扱い上の注意
- 保守・点検に係る事項
- 承認条件
- 主要文献及び文献請求先
- 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等
1から4の項目(作成又は改訂年月、承認番号等、類別及び一般的名称等、販売名)は電子添文の上部に配置し、5以降の項目を本文として記載します。複数頁にわたる場合でも、これらの基本情報は1枚目にのみ記載します。
3.2 各記載項目の詳細
作成又は改訂年月には、電子添文の作成または改訂の年月と版数を記載し、改訂履歴の継続性を担保します。承認番号等の欄には、該当する番号に加え、単回使用医療機器の場合は「再使用禁止」の記載が必要です。
警告欄には、使用範囲内で特に危険を伴う注意事項を記載します。禁忌・禁止欄には、設計限界や不適正使用等、責任範囲を超える対象及び使用方法を明記します。これらの項目は、適用対象(患者)、併用医療機器、使用方法の観点から小項目を設けて記載します。
3.3 形状・構造及び原理等の記載
医療機器の全体的構造が容易に理解できるよう、イラスト図、写真、ブロック図等を用いて視覚的に示します。また、原材料、構成品等の情報とともに、当該医療機器が機能を発揮する原理やメカニズムを簡潔に説明します。
使用目的又は効果については、承認・認証を受けた内容を正確に記載します。届出品目の場合は、クラス分類告示の一般的名称の定義範囲内で記載する必要があります。
4. 特定生物由来製品及び生物由来製品の特別な記載事項
4.1 生物由来製品の表示と警告
特定生物由来製品及び生物由来製品については、販売名欄にその旨を明記します。遺伝子組み換え技術を応用して製造される場合も、その旨の記載が必要です。
ヒトその他の生物由来成分が使用されている旨、感染症伝播リスクを完全に排除できない旨、実施している安全対策の概要、使用を最小限とすべき旨を、本文冒頭の「警告」の前に記載します。これらの情報は、医療従事者が製品選択時に最初に確認すべき重要事項として位置づけられています。
4.2 原材料情報の詳細記載
生物由来成分の名称、原材料となる生物の部位等の名称は、形状・構造及び原理等の項に詳細に記載します。ヒト血液由来製品の場合は、採血国名と採血方法(献血・非献血の別)の記載も必要です。
特定生物由来製品については、医療関係者による使用対象者の記録保存義務、使用対象者への説明義務についても記載する必要があります。これらは法的義務であり、適正使用の観点から極めて重要な情報です。
5. 実施時期と既存通知の取扱い
5.1 実施時期
本記載要領は令和3年8月1日から適用されました。この日以降に作成・改訂される電子添文は、すべて本記載要領に従う必要があります。
5.2 既存通知の改廃
旧局長通知(平成26年10月2日付け薬食発第1002第8号)は廃止され、本通知の内容に置き換えられました。ただし、課長通知(平成26年10月2日付け薬食安発1002第1号)については引き続き参照することとされ、改正法による条項や字句の変更に応じて適切に読み替えて適用します。
まとめ
医療機器の添付文書が電子化されたことにより、製造販売業者には最新情報の適切な提供体制が強く求められるようになりました。電子添文は、単なる紙媒体の代替ではなく、医療従事者が迅速かつ正確に情報へアクセスするためのインフラです。
とりわけ、生物由来製品や家庭用医療機器を取り扱う企業では、対象製品ごとの記載方法や作成単位、対象ユーザーに応じた表現の使い分けなど、個別対応が不可欠です。また、PMDAへの電子添文公開、GS1コードの整備、法令改正への対応など、実務レベルでの課題も多岐にわたります。
弊社では、電子添文の新規作成から記載内容のチェック、PMDA提出支援、関係法令への対応まで、トータルでの支援を提供しています。
制度対応でお困りのことがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。