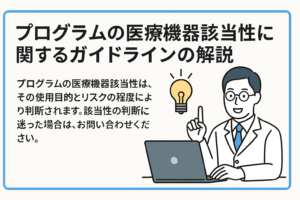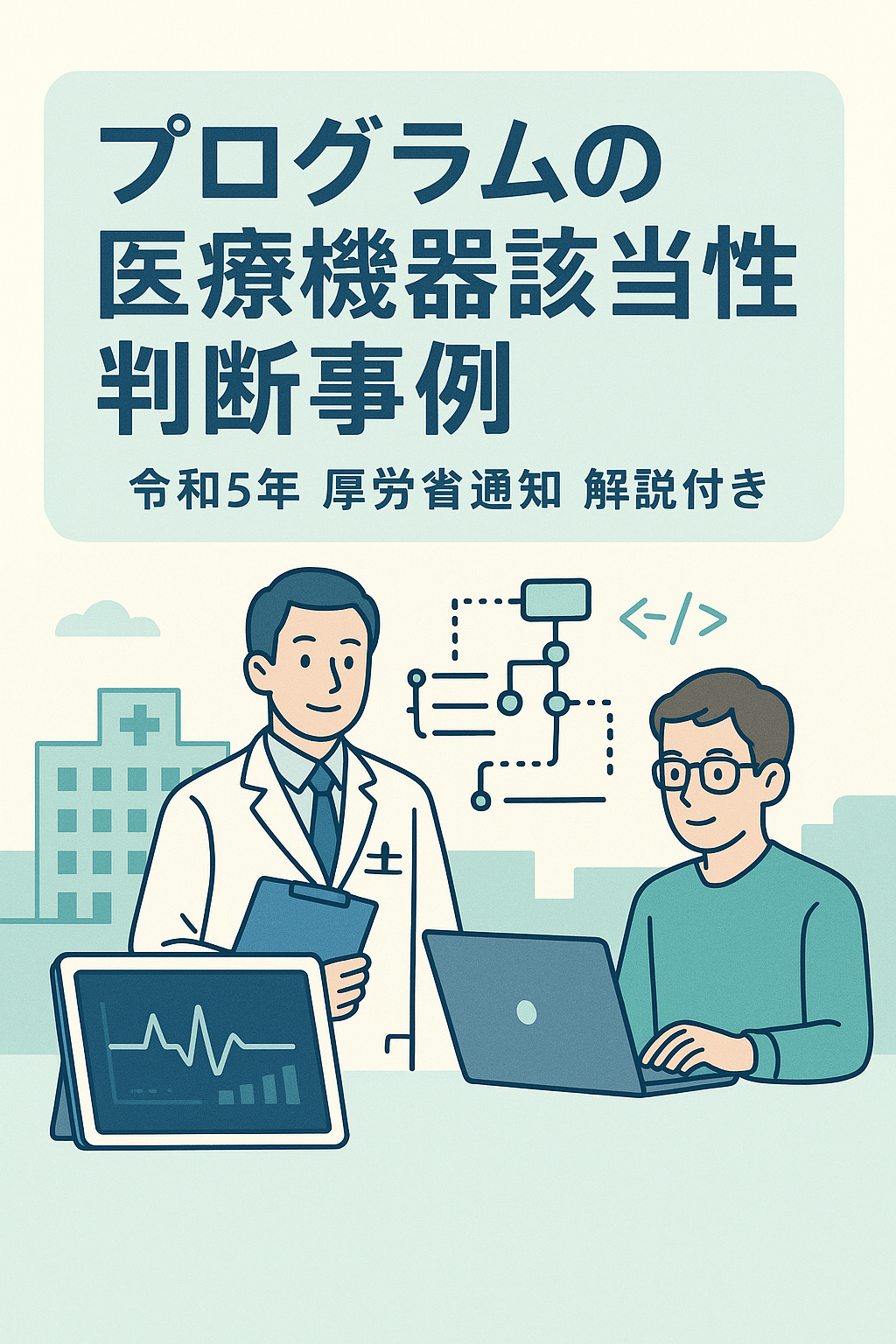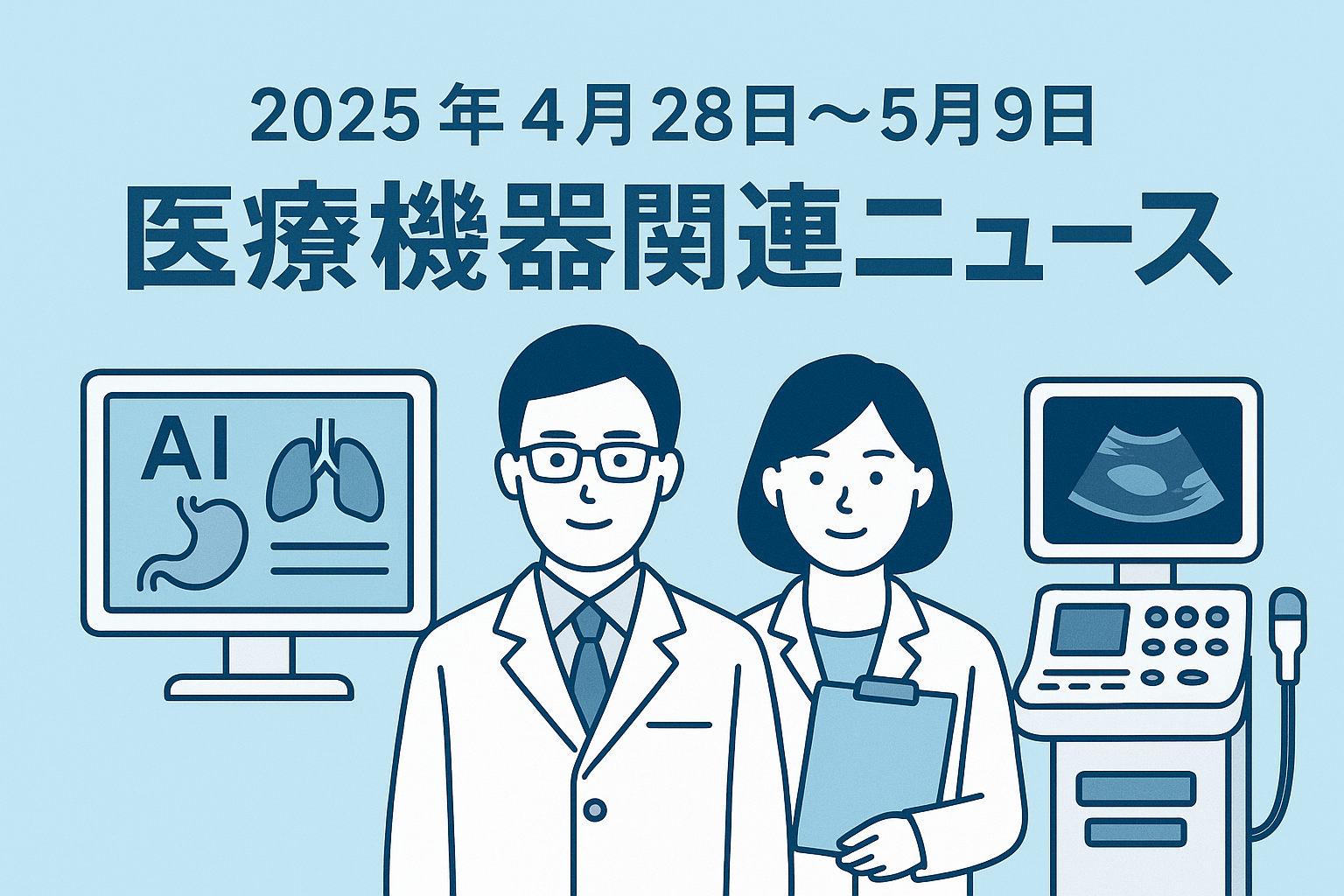概要
厚生労働省は、プログラム医療機器の該当性判断を標準化するため、相談窓口を設置しています。これまで自治体が個別に行っていた相談業務を、令和3年4月1日から厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課に一元化しました。この窓口では、開発中のプログラムが医療機器に該当するかどうかの判断について専門的な相談を受け付けています。相談は原則メールで実施され、提出された資料は必要に応じて厚生労働省や医薬品医療機器総合機構の関係部局と共有されます。本記事では、相談手続きの流れや必要書類、注意点について詳しく解説します。
1. プログラム医療機器該当性相談窓口の設置背景と目的
1.1 設置の経緯
プログラム医療機器該当性の相談は、従来各自治体が対応していましたが、令和2年10月に開催された規制改革推進会議第1回医療・介護ワーキンググループ会合において、プログラム医療機器該当性判断の標準化を図ることなどの要望が提出されました。これを受け、厚生労働省は令和3年3月31日付けの事務連絡において、プログラム医療機器該当性の相談を厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課で一元的に行うことを発表しました。令和3年4月1日から相談窓口が開設され、相談の受付が開始されています。
1.2 相談窓口の目的
この相談窓口の主な目的は、プログラム医療機器の該当性判断を標準化し、開発事業者が抱える疑問に対して一貫した回答を提供することです。医療機器プログラムの開発が活発化する中、どのようなプログラムが医療機器として規制対象になるのか明確にすることで、イノベーションを促進しつつも患者の安全を確保するバランスを取ることを目指しています。また、判断事例はデータベース化され、厚生労働省のホームページで公表されることで、業界全体の理解促進にも貢献しています。
2. 相談手続きの流れと必要書類
2.1 相談前の準備
相談を行う前に、「プログラム医療機器該当性に関するガイドライン」(令和3年3月31日付け薬生機審発0331第1号・薬生監麻発0331第15号)を確認することが重要です。このガイドラインには、プログラム医療機器の該当性判断のためのフローチャートやQ&Aが含まれており、自社製品が医療機器に該当するかどうかの予備的な判断が可能です。ガイドラインを確認した上で、疑問点や判断に迷う点を整理しておくことで、効率的な相談が可能になります。
2.2 提出書類の準備
相談を行う際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 相談様式(個人が使用するプログラムの場合は様式1、医療関係者が使用するプログラムの場合は様式2)
- 製品が有する機能についての説明資料
- 結果の算出アルゴリズムに関する資料
- 製品表示画面の画像
- 製品の広告等に関する資料
なお、会社概要については提出資料を最小限にするため添付しないよう指示されています。また、同一のプログラムであっても、機能ごとに相談様式を作成する必要があります。例えば、心電図測定機能、健康記録機能、食事記録機能を持つプログラムの場合、各機能について別々の相談様式を提出します。
2.3 相談様式の記入方法
相談様式の記入においては、ガイドラインの「判断フローチャートに係るQ&A」を参考にすることが推奨されています。様式には、企業情報や製品情報のほか、プログラムの目的や使用対象者などの基本情報を記入します。また、プログラムが「疾病の診断・治療・予防を意図しているか」などの質問に答える形で、医療機器該当性の判断に必要な情報を提供します。
3. 相談実施における注意点
3.1 相談の実施方法
相談は原則としてメールにより実施されます。メールアドレスは「samd-gaitousei@mhlw.go.jp」です。メールによる質問や回答のやり取りを通じて、プログラムの医療機器該当性について検討されます。監視指導・麻薬対策課は、必要に応じて相談者に追加資料の提出を依頼することがあります。
3.2 相談終了の条件
相談開始後、監視指導・麻薬対策課からの照会に一定期間(概ね1ヶ月)経過しても相談者からの回答が得られない場合、相談は終了として取り扱われる場合があります。その際、提出された資料は廃棄されるため、適時の回答が重要です。
3.3 判断事例の公表
相談窓口での判断事例は、概要をデータベースにまとめ、厚生労働省ホームページにおいて原則公表されます。公表されるのは相談内容の概要のみであり、提出いただいた資料そのものは公表されません。ただし、企業からの申し入れがあった場合は非公表とすることも可能です。公表を希望しない場合は、相談様式の「相談概要の公表の可否」欄に「公表不可」と記載し、その理由を記入します。
4. プログラム医療機器該当性判断の考え方
4.1 個人向けプログラムと医療関係者向けプログラムの区分
プログラム医療機器の該当性判断においては、使用対象者が「個人・家庭向け」か「医療関係者向け」かによって判断基準が異なります。個人・家庭向けのプログラムとは、一般の個人が自宅などで使用するプログラムを指します。一方、医療関係者向けプログラムとは、医師や看護師など医療従事者が使用するプログラム、および個人が医療関係者の管理下で使用するプログラムを指します。
4.2 医療機器該当性判断の主要な観点
医療機器該当性を判断する主な観点として、以下の点が挙げられます。
- プログラムが疾病の診断・治療・予防を意図しているか
- 同一の処理を行う医療機器が存在する場合、その機器のクラス分類
- GHTFルールに基づく判断(クラスⅡ以上に相当するか)
- データの表示・保管・転送のみを行うプログラムか
- 医学的判断に使用される情報を提供するか
- 診断・治療ガイドライン等に従った処理のみを行うか
- 入力情報を基に疾病候補や疾病リスクを表示するか
これらの観点に基づいて、相談窓口がプログラムの医療機器該当性を判断します。
まとめ
厚生労働省のプログラム医療機器該当性相談窓口は、プログラム医療機器の該当性判断を標準化するために設置されました。相談は原則メールで行われ、適切な様式と必要資料を提出することが求められます。相談は個人向けプログラムと医療関係者向けプログラムで異なる様式を使用し、それぞれの機能ごとに別の相談様式を作成する必要があります。判断事例は原則として公表されますが、企業からの申し入れにより非公表とすることも可能です。
開発中のプログラムが医療機器に該当するかを事前に把握し、適切な開発・申請戦略を立てることは、スムーズな事業推進に不可欠です。
弊社では、プログラム医療機器に関する該当性相談のサポートや、申請戦略の策定支援を行っております。ご不明点やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。